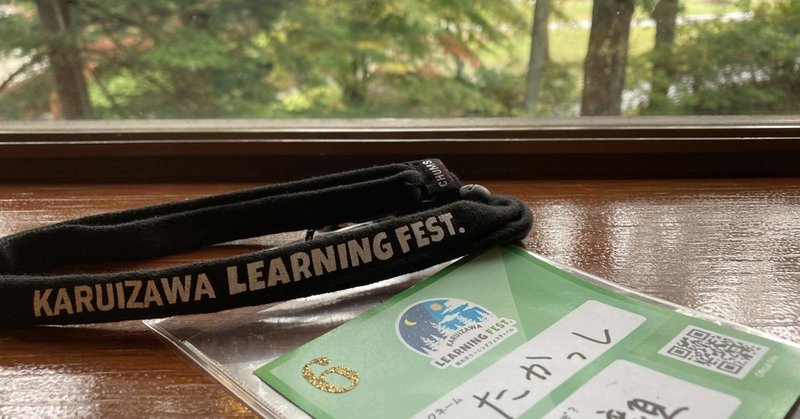
"リアル" x "自然" で学ぶことの価値
東京を離れ、会社を離れ、大自然の中で自分とは何か?ビジネスとは何か?について学び合う_。こんな体験を私はこれまでしてきたことがあっただろうか?40歳を間近に迎え、人生初の体験がそこにはあった。
私は、2020年10月9日、10日の2日間、軽井沢で開催されたラーニングフェスティバル2020に現地で参加した。
今年はコロナ禍でかつ台風が接近する中での開催となった。普段から少し肌寒い軽井沢の初秋だが、今年は初冬のような寒さ。普段なら自然の豊かさ・素晴らしさの中で自分を見つめなおす時間になるのだろうが、今年は自然の厳しさの中で自分の生命と向き合い、周囲とこの厳しい状況を支え合う、そんな時間が流れていたように感じる。
リモートワーク時代における"リアル"の価値
2020年はCOVID-19によりリモートワークが一気に広がった、いわばリモートワーク元年とも言える年だ。多くの社内外のミーティング、講演会、研修などがオンライン化され、オンラインであっても十分に代替え可能だということが証明されつつある。
私も、リモートでのミーティングや研修、講演会を開催・参加する中で、それを身を持って理解し、また本来なら参加できなかったであろうイベントにも参加できるようになった。これは子育て中の我が家においては有難い限りである。
正直、Before Coronaに"リアル"に実施されていた多くのこれらイベント事は、もはやオンライン提供でよいのではないか?とさえ感じている。
では、"リアル"でイベントを行う価値とは、いったいどこにあるのだろうか?
"リアル"でしかできないことについて考えてみた。
- 場の「空気」を参加メンバーで共有する
- 場・人の熱量を「肌」で感じる
- 全身像から来る「真の人となり」を理解する
こんなことが頭に浮かんだ。やはりオンラインでは何か大事なものが抜け落ちてしまうところもあるようだ。五感でいえば、主に「嗅覚」「味覚」「触覚」の3つが多いだろうか?また、情報にしても、その臭い、その情景といったコンテクストと共に記憶されることもある。
つまり、大切に思うモノほど、熱狂的になれるモノほど、"リアル"であることにより意味合いが強いように感じる。
腹を割って話せる仲間との会合、大好きなアーティストのコンサート、大事にしている趣味や習い事など、これらは簡単にオンラインに代替えできるものではない。

"自然"と対峙する価値
東京に住んでいると、たとえ近くにそこそこ広めの公園があったとしても、360°森林に囲まれたような場所に身を置くことはそう多くない。またそもそも本当の大自然の中では、都会で私たちが享受しているような「安定した暮らし」を確立できることは少ないように思う。自然災害とも常に意識して対峙しなければならない。
つまり、自然と向き合うことは、「私たちの日常の安定をいったん捨てる」ということ、とも言えるだろう。
私たちは今や情報に満ち溢れた世界に住んでいる。現代人が1日に触れる情報量は、江戸時代の人が1年間に触れる量に等しいともいわれるほどだ。情報量を食事量で例えると、飽食の時代どころか、消化しきれず大量廃棄という状況ではないだろうか?
そんな日常に生きているからこそ、あえてそこから抜け出して、「日常を捨てる」べきなのではないだろうか?私たちが「安定している」と思っている都会での生活は、実は情報過多により消化不良を起こした状態で、実際には返って不安定な、不健康な生活とも考えられるかもしれない。
自然は、私たち人間のちっぽけさを教えてくれる。日々悩んでいることが、大自然を前にするとほんのささいなことのように思える。都会の生活に対し、時にリセットボタンを押すことが出来れば、自分のありたい姿が自然と見えて来るのではないだろうか?

"リアル" x "自然"が私に与えたもの
便利な時代を生きるからこそ、オンラインが当たり前の時代になった時代だからこそ、昔は日常だった"リアル" x "自然"が、私にあるがままであることの素晴らしさを与えてくれたと感じる。
私にとってもはや非日常となってしまった"リアル" x "自然"は、五感を整え、大切なものを見つめ直し、ありたい自分に近づくためのきっかけを提供してくれた。今回のイベントを通して改めてそう感じた。
人と繋がる大切さ、食べる喜び、心地良い空気、人々の笑顔。振り返ってみれば、そもそも当たり前だったことに大きな価値がある事を改めて認識できた体験だった。便利性、効率性を追い求めてしまいがちな昨今の時代において、人間として生きるために、またここに戻って来よう。そう感じた雨上がりの日曜の昼下がりであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
