
【考察】「春ゆきてレトロチカ」から考える、実写ゲームの行方
「春ゆきてレトロチカ」は、スクエアエニックスより発売された推理アドベンチャーである。
数年ぶりに国内ハードから実写作品が出たとして、注目を集めた。
本作は、「推理アドベンチャー」という文脈と、「実写ゲーム」という文脈の2点から分析することができる。
推理アドベンチャーは、サスペンスなどのドラマを中心としながらも、証拠を集めて突き付ける面白さを追求したジャンルだ。
歴史を考えると、「オホーツクに消ゆ」や「ポートピア連続殺人事件」を起点として、「逆転裁判」や「ダンガンロンパ」に続く。
実写ゲームは、実写の写真や動画などを用いて、ゲームを演出する表現技法だ。
これも歴史を見ると、「学校であった怖い話」「街」などを起点として、「428」や「Her Story」などに続く。
この2点の歴史的文脈から、本作の立ち位置を考えたい。
しかし、この2点だけではレトロチカそのものの強みを説明できない。
「レトロチカ」は、ストーリーラインの説明が非常に重要になる。
ストーリーラインを説明するなら推理ゲームの扱いとしてもまとめられるが、今回は意図的に「ミステリーとしてのレトロチカ」として、分離させて説明する。
推理ゲームとしてシステム面を、ミステリーとしてストーリーを扱う、といった流れだ。
本記事では、以上の三つの観点を他ゲームや他ジャンルと分析しながら、「レトロチカの立ち位置」を検討する。
とりわけ、本作は数年ぶりに出た実写ゲームでもあるので、「実写ゲームとしての意義」を中心に検討していく。
本作は推理ゲームある以上、推理ゲームとしての立ち位置やミステリーとしての面白さも検討するが、主題は「実写ゲームとしてどれだけの重要性があったのか」という点になっていることを、念頭に置いていただきたい。
1.推理ゲームとしてのレトロチカ
まず、「推理ゲームとしてのレトロチカ」だが、シンプルに言ってしまえば「オールドスタイル」である。
本作は、証拠を集め、仮説を考え、それをもとに考えを突きつけながら犯人を捜していく。
証拠を集めるシーンは、実写ムービーを見ながら証拠になる発言が出たときにボタンを押して集めていく。
実写ムービーを見ることがメインとなるので、この点の詳細は「実写ゲームとしてのレトロチカ」で確認する。
ただ、一つだけ言うとこのシーンに「ゲーム性はほとんどない」。

続いて、仮説を考えるシーン、「推理編」だ。
仮説を生み出すシーンは、パズルのように証拠と疑問を組みあわせ、「こうじゃないの?」といった憶測を広げていく。
風呂敷を広げる面白さもあり、中々ハマる要素である。
しかし、この仮説を並べるパズルはあまりにも陳腐だ。
仮説のための証拠があっても、パズルを解くための配置のヒントがそれぞれに付いているので、ある程度総当たりでどうにかなってしまう。
そのため、パズルを解くのは面白いが、自分で考えている感覚が薄い。
ちゃんと事件に向き合えば面白くなっていくが、「あれ?これ入らないの?」と、自分の選んだ選択肢が間違ってた時の違和感は大きい。
事件を自分で解いている感覚が少ないのは微妙だった。

そして、この仮説が解決編でも問題になる。
解決編では手に入れた仮説を用いて事件の謎を追っていくのだが、仮説の説明があまりにも雑だったり、仮説の量が多すぎたりと、流れを読みにくい。
推理編で考えた仮説は、「おそらくこうだろう」といった形式で説明がされることが大半であるため、証拠との繋がりがかなり分かりにくい。
そこを繋げるための「仮説外の証拠」を、自分自身で思い出していく必要がある。
さらに、仮説の中には非現実的である種おバカな選択肢も多数盛り込まれており、推理中にげんなりすることもあるし、解決編で邪魔してきて面倒になることもある。
結果的に、かなり適当かつ多い選択肢の中から核心を突かないといけないため、解決編で非常に苦戦した。
このアイテムがこうで…と証拠をモノとしても突き出せる「逆転裁判」は、改めて遊びやすいと感じた。

本作は、謎解きの流れもかなりオールドではある。
ファンタジーな要素もありつつ、トリックを解くために証拠を集めて回答していく流れは、ファミコンにあった推理ゲームとあまり差がない。
謎の基本は「時間」「アリバイ」「犯行道具」など、推理モノとしてはシンプルでわかりやすい。
ファミコンから始まった推理ゲームと、謎解きの基礎はほぼ変わっていない。
事件のために証拠を集めなくなった「トワイライトシンドローム」などのアドベンチャーゲームとは違い、推理ゲームらしさを追求している。
ただ、それらよりも多少整理され分かりやすくなったとはいえ、謎を解いている感覚が少ないパズルは問題点であろう。

このように、推理ゲームとしての本作は「レトロ」であり、これは公式が意図したとおりである。
この作品は歴史的文脈としては非常に重要で、推理アドベンチャーの伝統を受け継ぐタイトルとしては理想的だが、どうしても「陳腐」という言葉がこびりつく。
同時期に推理アドベンチャーとして発売された「パラノマサイト」は、オールドな推理要素を持ちつつも、メタフィクションなどを多分に用いたストーリーを扱って、プレイヤーを驚かせた。
そこには、PS1期にあったオカルティズムを用い、ジャンルをサイコホラーやミステリーなど柔軟に切り替えていくことで、推理アドベンチャーの陳腐さをかき消した。
何より、オムニバス的にキャラクターを動かしたことで、複数視点から丁寧に物語を紡いでおり、ジャンルの違いを見せプレイヤーを飽きさせないことに成功している。
本作は、各章で話の切り替わりが起こることで、頭をリセットできる点は、推理ゲームを遊ぶ上で親切である。
一個の事件を追い続けていて、先が見えない不安感がなく、適度に「今やっている事件の切れ目がある」と見せている点は、時間的な感覚もつかみやすく遊びやすい。
しかし、推理やトリックの本質的面白さはファミコンから一切変わっておらず、手を変え品を変えジャンルを操作しなかったこともあって、手堅い推理ゲームにはなっているものの、新鮮さは薄い。
推理ゲームは「ダンガンロンパ」や「逆転裁判」などが証拠提示を起点としてしまっているだけあって変化に乏しい面があるが、歴史的文脈に依存しすぎているだけでは、陳腐であるとして飽きられる危険性があるのではないか、と思う。
もっとも、レトロチカはそうした側面も含めて敢えて「レトロ」に表現しているのだろうが…。
2.ミステリーとしてのレトロチカ
さて、続いて「ミステリー」として、本作のストーリーラインを追いながら、作品の特徴を掴んでいく。
本作をミステリー的側面から見ると、「ミスリードを活かした特別さが光る面白さ」があり、非常に良い。
本作は、時代を超える作品でありながら、敢えて同じ役者に違う役割を与えることで、「同じ役者=同じ役割か親族」という印象を無意識にプレイヤーに植え付けている。
実際、本作は四十間家の先祖問題を扱うため、現代のキャラの先祖がさも当然のように現れる。
そして、それを見て「親族なんだろうな」と思ったプレイヤーが、最後に強烈なミスリードを食らうように出来ている。
また、そのミスリードの裏付けに「小説を読んでいる設定」が付け加えられていることで、信用出来ない語り手の構図ができており、辻褄もバッチリ合っている。

そして、そのミスリードが役者を用いたものであり、演技を使って「実写でしかできない技法」にしている点は見事だ。
同じ役者を扱いながら、様々な設定と物語を用意し、役回りを固定しないストーリーラインを組み立てているのはとても良い。
役者の演技の違いを楽しめるだけでなく、それがストーリーラインの「実はあなただったのか」という驚きとリンクするのも良い。
役者の演技も非常に上手く、別キャラで同じ役者でありながらも、全く違った雰囲気をまとっている点は、役者自身の表現の違いを感じる。
各キャラごとの特徴が、同じ役者でもスッと入ってくるのは、ひとえに役者の演技技法の魅せる技だろう。

特に最終章は、ゲーム全体を通じた大きすぎるミスリードが明かされ、プレイヤーの想起していた関係図が一気に塗り変わる。
そこにある感動は計り知れないものである。
本作のラストシーンは、ありがちな展開を真相とともに別のテーマに塗り替えることで、意味付けを大きくしている。
変わった先もアリがちなテーマだが、切り替わるという新鮮さには舌を巻いた。
それに、そこにある辻褄として「不老」というテーマ付けと「トキジク」というアイテムがある。
多少ファンタジーではあるが、序盤で不老があることが証明されている以上、理屈としては成立していて、違和感を感じることもない。
私は、このゲームが最初からファンタジーなテーマを選んだ理由が分からなかったが、最後まで遊ぶことでようやく理解ができた。
役者の顔を活かしてミスリードを呼び、時を超えて判明する真の人間関係は、驚きと感動を与える要素としては完璧だ。

3.実写ゲームとしてのレトロチカ
このように、本作はミステリーとして、素晴らしいほどのストーリーラインを展開している。
ここは評価すべきであり、従来の推理ゲームにあった「犯人はお前だった」という驚きを超える仕組みがあるとして、新しい試みであったといえる。
しかし、実写ゲームとしてはどうなのか。
実写ゲームの課題などを見ながら考えていく。

実写ゲームの課題とは何か。
率直に言ってしまえば、それは「映画など映像媒体との比較、差異」だ。
実写を扱うわけだから、当然のようにほかの映画などと比較される。
映画を見るようなゲームなら「ゲームである必要は無い」。
実写ゲームは、常にゲームらしさを求められている。
割り切って映画を見せるゲーム、例えば「Quantum Break」などがあるが、これらのゲームのジャンルはアクションである。
「Quantum Break」は映画を見せることでストーリーの裏の展開を見せながら、アクションゲームとしての楽しさをプレイヤーに提供している。
実写はあくまでストーリーの補完であり、ゲームのメインではない。
一方、「レトロチカ」のようなアドベンチャーは、操作できる部分がアクションと比べて少ないため、映画を見せて終わるような展開になりかねない。
そのため、ゲームらしさが必然的に求められる。

では、そのゲームらしさとは何か。
それは「ゲーム的能動性」である。
ゲームをする時、プレイヤーはコントローラーを握る。
その際、知恵や操作テクニックを使い、ゲームの中に能動的に介入すること、つまりゲームの攻略を楽しむ。
それはゲーム的能動性であり、ストーリーをなぞって、画面を見続けているだけの映画とは決定的に違う点だ。
つまり、実写ゲームは能動性を担保するために、そのコントローラーや知恵を絞り、ゲームを「攻略する」時間が求められている。
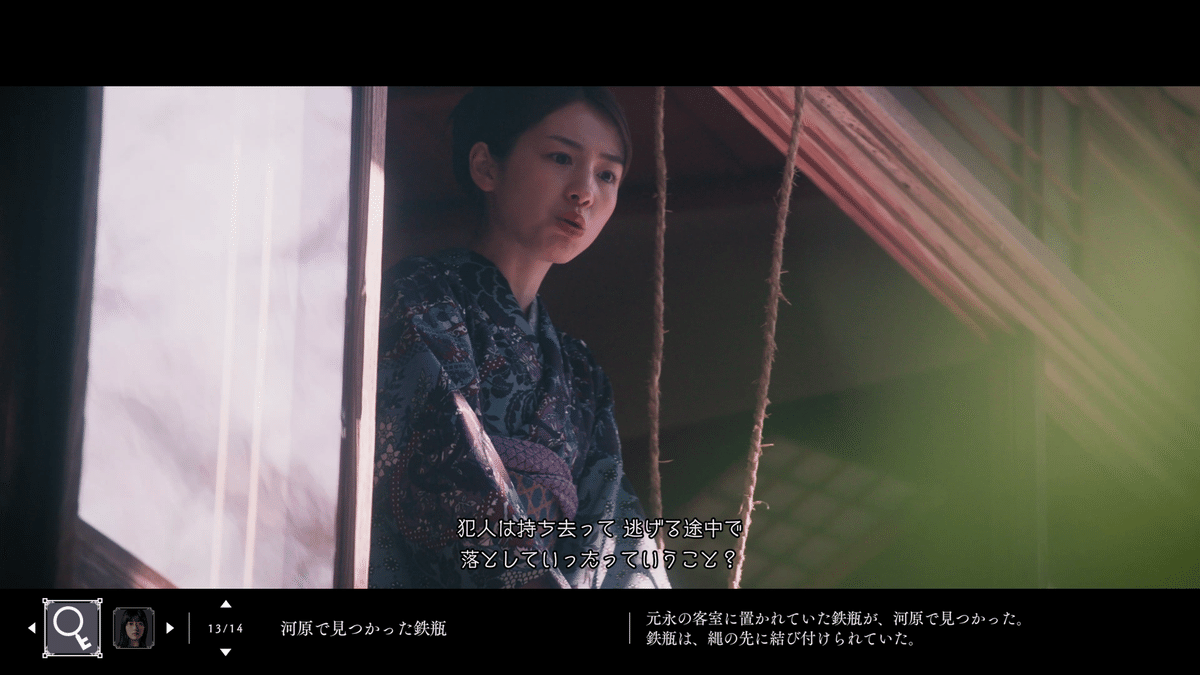
そして、そのプレイヤーの無意識な期待に、実写ゲーム、とりわけアドベンチャーは堅実に答えてきた。
「街」はザッピングを使って攻略することで、ゲーム性をストーリーラインに用意することに成功している。
「学校であった怖い話」「黒ノ十三」などのオールドなサウンドノベルも、ストーリーを淡々と見せるだけではなく、アドベンチャー要素や選択肢を用意することで、ただの読み物にならないように工夫がなされている。
どのゲームであっても、大なり小なり「ゲームになっている」工夫がある。
そして、特にこのゲーム性に挑戦的だったのが「IMMORTALITY」だ。
「IMMORTALITY」は、映画の切り取られたシーンを結びつけることで、プレイヤーにシーンを集める能動性を与えながら、そのシーンを並べ替えてストーリーを自分で組み立てる面白さを提供している。
この挑戦は実写ゲームとしては革命的であると同時に、映画をテーマとして扱ったことで、「受動的コンテンツである映画への挑戦」のようにも見え、非常に良い。
ゲーム性も与えながら映画の基本である起承転結を破壊しプレイヤーに補完させるという大胆なシステムは、映画の面白さを見せるだけ、役者の面白さを見せるだけではなく、映画では真似出来ない「探索の面白さ」を見せることに成功している。
映画との差別化を考えるうえで、映画をテーマにしながらゲーム的魅力を出しているという点で、現代の実写ゲームに一石を投じた傑作だ。
制作者のサム・バーロウ氏も、「IMMORTALITY」を「探索ゲーム」と認識しながら、探索の重要性を述べている。
バーロウ氏は「デジタルストーリーの可能性について考えた際に,ゲームこそがそれを推し進めるポテンシャルを持っている」との見解を述べた。
バーロウ氏はデジタルストーリーの可能性を追求するにあたり,「ストーリーをいかに探索可能にするか」に着目したとのこと。従来型のゲーム──たとえば「バイオショック」はゲーム内を自由に探索できる一方で,メインストーリーは1本道だった。このようにゲームプレイとストーリーがまるで水と油のような関係だったが,たとえば音声ログを探索できるようにならないか,「スーパーマリオブラザーズ」のプレイ体験をストーリーに落とし込んだらどうなるかといったことを考えたそうだ。
また「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」は,プレイヤーが気になるところを見つけて探索すると,そこには必ず何かが隠されており,好奇心が報われる構造になっている。バーロウ氏は「そうした構造をストーリーに落とし込むことで,まったく新しいゲームを作れるのではないかと考えた」と語る。
では、レトロチカはどうなのか。
正直、本作は実写ゲームとしての意義は薄い。
なぜなら、本作の見せたかったものはあくまで「ミスリード」であり、「ゲーム性と実写の融合する意義」では無いからだ。
少なくとも、本作は面白さをゲーム最終盤のミスリードに用意しており、全く面白くない、というわけではない。
しかし、その面白さはあくまで「読み物的」であり、ミスリードに対して「ゲームとしての能動性」は一切存在しない。
だから、このゲームをクリアした時点で思ったのは「別に映画とか小説でよくないか?」という点だった。
映画は役者がいるからミスリードを引き起こすこともできるだろうし、小説でもキャラクターを読み手の脳で補完するから、話し方ひとつでミスリードを誘導できる。
だから、このゲームは面白いところを「ゲームにする理由がない」。
その点でゲームとしての完成度は確実に落ちるし、ゲーム的体験の乏しさに疑問を抱かずにはいられない。

そもそも、本作は仮説や推理以外は映像を見させることに注力している。
証拠を集めるシーンは映像を見せられ続けるため、映画を見ている状態とさほど違いがない。
証拠が突然出てくるため油断できない分、途中で休憩できないところまで映画館で見る映画そっくりだ。
そして映像を見せていると言わんがばかリに、「一時停止ができるボタン」がついている。
そんな風にムービーを見ているわけだから、プレイヤーは「いや、映画でよくね?」と思ってしまう。
長編の映像を見せられる展開は明らかに「受動的」であり、コントローラーがテレビのリモコンと同じ役割しか果たしていないのなら、実写ゲームとしては明らかに「価値が少ない」。
言い方をより悪くするなら、テレビの地デジでやってたミニゲームと大して変わらないレベルである。
推理シーンも中途半端で前時代的だから、ゲームとして微妙になっている仮説収集シーンはなおさら目に余る。

これは言っておきたいのだが、演技が悪いとか、映像技術が低いとか、そういった技術面は悪くない。
むしろ完璧すぎて驚くぐらいだ。
しかし、それをゲームというジャンルでやられても、「いや、そういうのを求めてたわけではないし、それを見るなら映画でいい…」と微妙な反応になってしまう。
本作は、映画やストーリーの価値に重きを置きすぎて、肝心のゲーム性があまりにも雑になっている点で、実写ゲームとしては挑戦的ではない。
奥ゆかしくも古めかしいタイトルになっている。
よく言えば古典的で美しいのだが、悪くいってしまえば陳腐で前時代的だ。
正直、今の時代なら後者の方に意見が寄るだろう。
自分としても、レトロゲームが好きであるとはいえ、今の技術だけを使ってここまでゲーム性が薄いものを作られても、映像技術を誇示されただけに見えるし、役者の演技に頼り過ぎているような気がして、ゲーム好きとしてあまりいい気分ではない。

「IMMORTALITY」は、ゲームとしての能動性を「探索」として前面に出し、映画をテーマにすることで受動的な映画、実写ゲームの可能性を一気に広げた。
「街」も、25年前の作品でありながら、実写ゲームやノベルゲームの限界を超えようとしており、ザップを用いて展開を変えることで、ゲームとしての能動性を生みだそうとしていた。
改めて言うが、私は実写ゲームが「他の実写コンテンツと比較されること」に意味があると考えている。
「IMMORTALITY」や「街」はそうした面でかなり挑戦的かつ画期的で、プレイヤーとしてゲームを思いっきり楽しめた。

一方、レトロチカはどうか?
推理ゲームとしてもオールド、見せたい部分は映画…。
ミスリードは素晴らしく美しいが、本質がストーリーの驚きや入れ替わりである以上、ゲームとしての価値も低い…。
こうした視点を見ると、「レトロチカ」は明らかに前時代的で、意味づけが薄すぎる。
歴史的文脈の一端として、今の人たちにオールドなゲームを楽しんで欲しいという姿勢で「レトロ」を強調したかったのかもしれないが、それにしても目新しさがない。
「レトロチカ」は、ある意味「映像美を見せたがっている」ようにしか見えない。
それは一昔前のFF7のような、「俺たちはここまでできるんだぞ!」というスクウェアの姿勢のようにも見えるし、そうであったとしても、映像美が確約されている今のハードでは全く意味がない。

やはり、実写映像を用いてプレイヤーを引き込むのなら、ゲームとして出す意義を十分に出せるタイトルであって欲しい。
それは「IMMORTALITY」が実践しており、その実力は折り紙付きだ。
だから、「レトロチカ」のような映画を見ることが中心になってしまうゲームは、正当な進歩であるものの「前時代的」な評価に陥ってしまう。
その前時代的なものを打破できなかった点で、私は本作を「古めかしい作品」として判断した。
4.終わりに - レトロからデジタルへ
時代は変容する。
新しいものが次々に生み出される一方で、レトロな作品は逆説的で陳腐でありながらも、独特の魅力を見せている。
Vaporwaveとしてレトロなサウンドが今になって愛されるように、レトロなものには価値があると再認識されるフィールドも増えてきた。
しかし、それにはブラッシュアップが必要不可欠である。
埃を被っただけの逸品を見せただけでは価値がない。
それを光らせるだけの言葉を乗せるか、それそのものを改変してより良く見せるか、といった工夫が必要になる。
意味のある進歩が要求されている。
「レトロチカ」は、歴史的なものをそのまま見せたという上では、現代のサウンドノベル、アドベンチャーとして重要な作品である。
その価値は重要であるし、ムービーを高品質で取り込んでいるうえでは、ハードの進歩を見せることもできたと言える。
しかし、それは今の時代では陳腐になってしまうし、文字通り「レトロ」だ。
ストーリーだけではなく、ゲーム性が「レトロ」であっては、おそらくプレイヤーは「古めかしい」と言ってしまう。
特にデジタル性が強いゲームというジャンルでは、レトロという骨董品の価値は古いものにしかつかない。
古いものの真似をしても、それが「何をもとにしているか」が明らかにならなければ、「○○ライク」と呼ばれることもない。
ゲームの再解釈というものは、それだけ難しいことなのだろう。

ゲームの可能性は広い。
その間口を広げる行為に、進歩とデジタルな発展がある。
特に映画と比較される実写ジャンルは、その間口がより広くなる。
実写ゲームだからこそ見せられる、オリジナリティを持った作品が出ることを願うばかりである。
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

