
こよみだより *小暑* / *七夕*
2021.7.7
明日は、二十四節気の「小暑(しょうしょ)」入りです。
7月7日ですので、日本古来の年中行事「七夕(たなばた)」 (「七夕(しちせき)の節句」)と重なります。
小 暑
暑さが 本格的になる頃。
梅雨も終わりを迎える時季です。

二十四節気をさらに三つに分けた七十二候では、次のように続きます。
❍ 温風至(あつかぜいたる)
夏らしいあたたかな南風が吹いてくる季節。
❍ 蓮始開(はすはじめてひらく)
蓮の花が開き始める季節。
❍ 鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)
鷹の雛が、飛び方や獲物の取り方を覚え、一人前になる季節。
この七十二候を見ると、暑さが とびきり苦手な私でも、風情を感じます。
*

*
七 夕 (七夕の節句)
「七夕(たなばた)」 (「七夕(しちせき)の節句」)は、次の3つことが融合して生まれた行事だと言われています。
❍ ロマンティックな『星伝説』
牽牛星(けんぎゅう・わし座のアルタイル)と、織女星(しゅくじょ・こと座のベガ)が、年に一度だけ逢える日として知られていますね。
牛使いの牽牛と、天帝の娘・織女は、仲睦まじい夫婦でしたが、仲が良すぎて仕事をなまけたために、天帝の怒りをかって天の川に隔てられてしまい、年に一度、7月7日だけ逢うことを許された、という、古代中国の星伝説です。
旧暦の7月7日頃に、最も輝きを見せることから、2つの星がお互いを求めているように見えて、この 七夕ストーリーは生み出されたとも言われています。
❍ 中国古来の行事『乞巧奠(きこうでん)』
牽牛星は農業を司る星、織女星は裁縫を司る星です。古代中国では、この二つの星を祀り、織女星にあやかって、裁縫などの上達を願う「乞巧奠」という風習が生まれました。7月7日に針などを供えて、祈りをささげるそうです。
「乞巧」は 巧みを乞う(上達を願う)こと、「奠」は祀ることを意味しています。
❍ 日本古来の伝説『棚機つ女(たなばたつめ)』
日本には、水の神さまを祀り 穢れをはらう神事があったと言い伝えられます。「棚機つ女」と呼ばれる神衣を織る女性が、人里離れた川で神さまのための衣を織り、機屋(はたや)に籠って神さまの来臨を待つというものです。
「棚機(たなばた)」は、その衣を織る 織り機のこと。七夕を「たなばた」と読むのは、ここから来ているという説もあります。
*
奈良時代になり、星伝説や乞巧奠が日本に伝わると、日本の「棚機つ女」と「織女」が結びついて、宮中節会として取り入れられたそうです。これが現在、日本に伝承される七夕のもとです。

五色の短冊
「七夕飾り」の起源は、平安時代の末期と言われています。
宮中では、織女にちなんで芸事の上達を星に祈り、五色の糸や、梶の葉などを飾ったそうです。
五色は、中国の陰陽五行説に由来する 青(緑)・赤・黄・白・黒(紫)。また梶の葉には和歌をしたためていたと言われています。
これが五色の短冊となり、願い事を書いて吊るすようになったのは、江戸時代末期のこと。
江戸時代になって 七夕が五節句の一つになり(※)、庶民にも伝わると、寺子屋の普及に伴い、子どもたちが書道の上達を願って短冊に歌などを書き、笹竹に吊るすようになったそうです。
今では芸事だけでなく、様々な願い事が笹の葉に揺れていますね。
笹竹
短冊を吊るす竹は、冬の寒さにもめげず、まっすぐに すくすくと育つ生命力があることから、神聖な力が宿っていると信じられていました。
また竹は成長が早く、願い事も早く天まで届くという考えから、笹竹が使われるようになったとのこと。素敵な考えです。
… 明日も雨?
かつての農村部では、お盆の行事の一環として、この時期の雨を清めの雨と捉え、短冊が流れるほどの雨降りを望んだそうです。
きっと2つの星は、雨は望んでいないでしょうけれど。ね。
*
(※)五節句とは
・1月7日 人日(じんじつ)
・3月3日 上巳(じょうし)
・5月5日 端午(たんご)
・7月7日 七夕(しちせき)
・9月9日 重陽(ちょうよう)
の五つの節句ことです。
古くから続く節句の中でも、江戸幕府がとくに重要なものとして定め、公的な行事、祝日としたことから庶民にも広まりました。
今もそれぞれ、七草粥、雛祭り、こどもの日、七夕、菊の節句として親しまれています。
なお「節句」は、神様にお供えをしていたことから、元来は「節供」と書きます。
* * * * * * * * * *
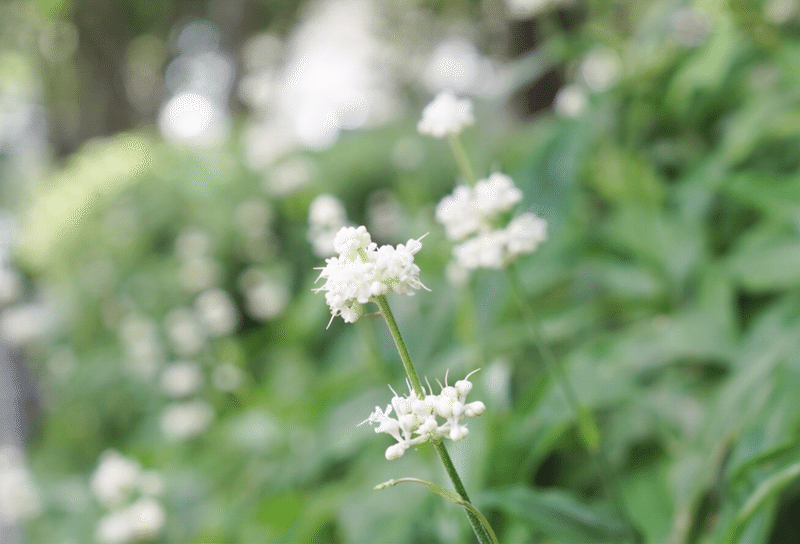
今、雨を望まないのは、2つの星だけではありません。
どうかこれ以上、雨の被害が広がりませんように。。
このたび被災された方々に 心よりお見舞い申し上げます。
*
最後までお読みくださいまして、
ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
