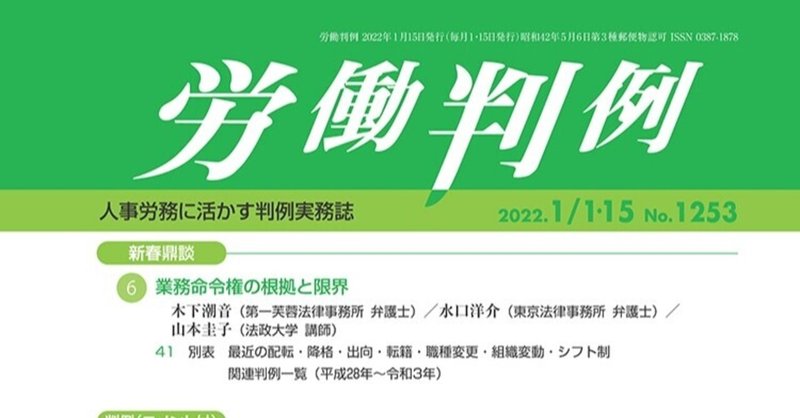
労働判例を読む#360
今日の労働判例
【A社ほか事件】(札幌地判R3.6.25労判1253.93)
※ 週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)
※ 司法試験考査委員(労働法)
※ YouTubeで3分解説!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK
この事案は、退職前の3か月間、会社Yで100時間を超える残業をしていたなどの環境にあった元従業員Kが、退職した4か月後に自殺した事案で、労災の認定に続き、裁判所が、遺族Xらに対する民事の損害賠償についてもYとその代表者個人の損害賠償責任を認めた事案です。
労働時間の認定、業務起因性(因果関係)の有無、過失の有無、代表者個人の責任、過失相殺の可否、損害額など、多くの論点がありますが、ここではうつ病の認定について検討します。
1.うつ病の判断枠組み
裁判所は、うつ病に関し、国際分類(ICD-10)による診断のガイドブックを判断基準として採用しています。世界的には、2019年にICD-11が承認されていますが、日本ではその和訳と日本での適用について検討が進んでいる段階であり、現時点ではICD-10が権威あるルールとなっています。
この中で、うつ病については、以下のような基準で判断されます。少し長いですが、この機会にそのイメージを確認しておきましょう。
① うつ病エピソード
・ 典型的な抑うつのエピソード
A. 憂鬱な気分が続いている
B. 何に対しても興味や喜びの気持ちがおきない。
C. 疲れがとれない。疲れやすい。
・ 他の一般的な症状
1) 集中力と注意力が落ちた
2) 「生きている価値がない。」「まわりに迷惑かけている。」などと無価値観や罪責感がある
3) 将来に対する希望のない悲観的な見方
4) 自分を傷つけたり自殺したくなる考えや実際に行為をおこなうこと
5) 睡眠がとれない
6) 食欲がない
・ 身体症状
a) ふつうは楽しむことができると感じる活動に喜びや興味を失うこと
b) ふつうの目覚めが普段より2時間以上早いこと
c) 午前中に抑うつが強いこと
d) 明らかな精神運動抑制あるいは焦燥が客観的にみられること
e) 明らかな食欲の減退
f) 体重減少(過去1年で5%以上)
g) 明らかな性欲の減退
② 軽症うつ病エピソード
AからCのうち少なくとも2つ さらに1)から6)にうち2つの症状がありいずれも著しい程度ではないもの最短の持続期間は約2週間。
身体症状をともなうものはさらにa)からg)のうち4つ以上はあること
③ 中等症うつ病エピソード
AからCのうち少なくとも2つ さらに1)から6)のうち3つ(4つがのぞましい)が存在すること。最短の持続期間は約2週間。通常社会的、職業的あるいは家庭的活動を続けていくのがかなり困難になる。
身体症状をともなうものはさらにa)からg)のうち4つ以上はあること
④ 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
かなりの苦痛と激越を示し自尊心の喪失や無価値観や罪責感をもちやすい。身体症状はほとんど常に存在する。
AからCの症状すべて、さらに1)から6)のうち4つ、そのうちいくつかが重症であること。社会的、職業的あるいは家庭的活動を続けることはほとんどできない。
⑤ 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
重症うつ病エピソードに加えて妄想、幻覚あるいはうつ病性混迷が存在する。
⑥ 他のうつ病性エピソード
他の診断基準にはあてはまらないが診断から抑うつ的と示唆されるもの。例えば身体的に異常がない頑固な痛みや、疲労を伴う身体性の抑うつ症状が混合しているものなど。非定型うつ病。
2.事実認定とあてはめ
この判断枠組みのうち、結論的に上記②に該当すると認定しています。AB1)5)6)のエピソードがある、という理由です。
すなわち、裁判所は❶疲れたとの趣旨の発言やイライラする様子があった、❷不眠傾向や、深夜にぼうっとすることがあった、❸毎日剃っていたひげを剃らず、作業着も洗濯せずに出勤するなど身なりに気を遣わなくなった、❹食事量が減り、痩せていった、❺休日に外出せずに昼寝をすることが多くなった、❻趣味の釣りやルアー作りもしなくなった、➐飲酒量が増えた、とするXの主張を、当事者の証言を主な証拠として認定しました。Yからは、職場でそのような様子は見れなかった、別の医師の意見書ではうつ病ではないと診断された、等と反論しましたが、「うつ病に罹患している場合であっても、苦痛に耐えながらも相手に気取られぬように努力し」ている場合があることや、Y側の医師の意見書はY側の説明に基づいて作成されており、❶~➐の前提など条件が異なること等から、これらの反論を否定しています。
3.実務上のポイント
一見すると、医師の意見書を裁判所が否定し、うつ病を認定していることから、その専門性について疑問が生じるところです。
けれども、特にICD-10は、具体的なエピソードの数に基づいて判断するもので、エピソードの有無さえしっかりと確認できれば、医学的な専門性による判定の違いは生じにくい基準です(もちろん、専門家による判断の方がより安心ですが)。しかも、Y側の医師の意見書の信頼性が、一方当事者の主張だけを基に作成されたことを主な理由として否定されていることの裏返しとなりますが、裁判所では両当事者の主張や証拠を吟味して各エピソードの有無を慎重に判断しますから、この点を見れば一方当事者の意見や記憶だけで行われる診断よりも、客観性はむしろ高いと評価できるでしょう。
もちろん、多くの場合、XY双方から医師の診断書を提出させるなどして、医師でない裁判官によるうつ病の有無の判断を避ける工夫がされますが、この事案のように、エピソードの有無や数で判定するというICD-10の特徴に基づいて裁判官が認定する場合もあるのです。
※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
