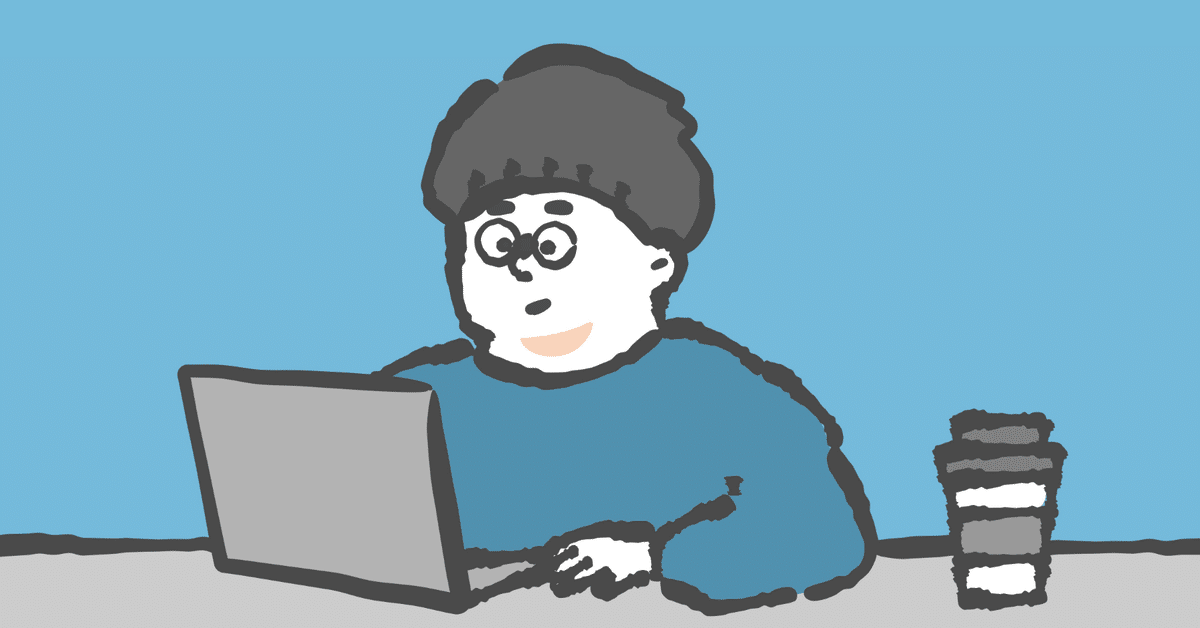
Photo by
ayanoillust
大学で学ぶマーケティングのだめなところ
大学で4年マーケティングをそれなりにまじめに学んで感じた、現状の仕組みの欠点、それは
「実務が無い」。
不満はいろいろあったが、これが結局根源だと感じた。
○○理論、○○分析などを学んでも実際に使う機会がほぼ存在しない。
半期の授業だと90分×十数コマ、20時間弱学んで得られるものは使い方がよくわからない知識の羅列だった。成績秀を取ったとて、数か月後に覚えていることはほとんどない。
私は授業を受けつつ、「座学にめちゃくちゃ力を入れて、試合はしない部活」みたいだなと思った。最新の戦術や理論をみっちり学び、基礎的な体力づくりをするが試合は数か月に一回、そんな部活では誰も強くなれない。
大学でも外部講師や企業を招いたり、ゼミだったり、実践的な機会もあるにはある。
しかし頻度が少なすぎる。実際に使うための業務なのに、理論:実践=9:1くらいの比率。明らかにおかしいんじゃないかと思う。
解決法ももちろんある。一つはインターンなどで大学生の内から知識を用いる機会を設けることだ。自分は結局やらなかったが、今になって後悔している。もう一つは働いてから大学で学びなおすことだ。これについては本当に実現できるのか、社会に浸透しているのかは知識がないのでエラそうに語るのは避けようと思う。
・・・おそらく、ゆくゆくは大学で学んでてよかった、そう思う時が来るのかもしれない。だから、少なくとも知識は得られる今の大学の仕組みも「最悪」ではないんだと思う。しかし、実務とのつながりが強い道具としてのマーケティングを学ぶのに、もっと最適な大学の在り方があるのもたしかなんじゃないだろうか。と思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
