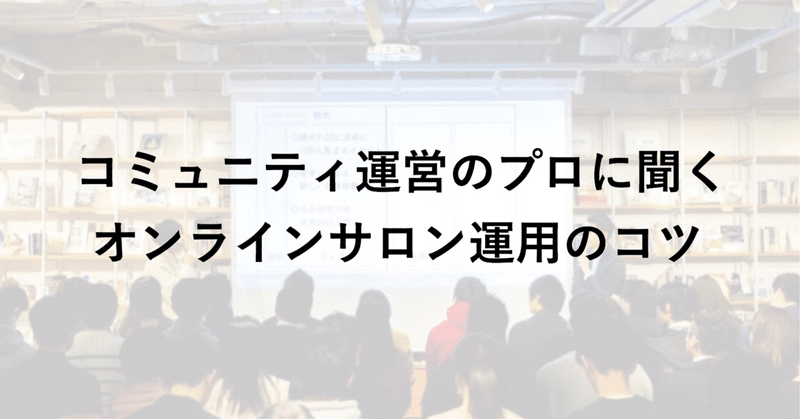
コミュニティ運営のプロに聞くオンラインサロン運用のコツ
信頼するゲストを丸裸にして価値ある情報をお届けするnote。
今回のテーマはコミュニティ運営のプロに聞くオンラインサロン運用のコツ!
コロナの影響もありオンライン上のコミュニティが増加傾向にある今、自身のコミュニティの立ち上げを検討されている方も多いかとおもいます。
そこで渋谷の早起きコミュニティ 朝渋・代表 井上さんにオンラインサロン運用のコツをお伺いしてみました。
※文章読むのが苦手という方は【最後に】にラジオのリンクを貼っておりますのでそちらからご確認をどうぞ。
私自身も5月から初の試みとして自分が代表を務めるオンラインコミュニティ【Shareit(シェアイット)】を立ち上げ一か月がたちました。そこでの学びはおいおい触れていこうと思いますが、いろいろとむつかしいな~と思うことも多く。。。
4年にわたりオンラインサロン・朝渋の村長として活躍している5時こーじこと井上さんだからこそ知るあれこれを教えていただいたのでぜひ参考に!
朝渋とは…
早起きを広めたいという想いで井上さんが立ち上げたコミュニティ。書籍のPRイベントを月4回実施。朝7時半という早朝から実施しているイベントにもかかわらず平均参加数はなんと100名弱。出社前に差がつく朝のインプット習慣を得たい方におすすめのコミュニティ。※現在はコロナウイルスの影響でオンラインにてイベント配信中
コミュニティ立ち上げ・運用に大事な3つのポイントって?
①勝負の7割は立ち上げ前から決まっている 周りの人の反応をチェックせよ
まずコミュニティ運営を始める前に大事なポイントから。いざコミュニティを立ち上げようと思ったとき、なんとなくやりたいテーマ、できそうな方向性が固まっていてもどのようにするか、具体案が定まらず迷ってしまうという方も多いと思います。
しかし、コミュニティが成功するかどうかは、始める前にすでに7割勝負が決まっていると5時こーじさんは語ります。
立ち上げ前に周りに『こんなことを始めようと思っている』というのを伝えた時の反応はしっかり見極めたほうがいいです。
『めちゃくちゃいいね~』とか『そういうの求めてた!』みたいに圧倒的に感謝されるかどうかをチェックしてください。
コミュニティリーダーになりたいとか、立ち上げたいという人は多いが、
それ誰が興味あるの? という内容だったり、趣味に偏りすぎているものは世の中事しません。知らない人でも何が得られるか、そこに入ったらどんな自分になれるのか、参加者がイメージを持てるようにすることが大切です。
立ち上げ前に自分が持っているスキルを活かし、やりたいことにトライしてみて、コミュニティを立ち上げる前に小規模でも検証することが大切。
それが蓄積されたところで立ち上げるのがベストだと語ります。
私自身もShareitという、SNSや働き方で悩んでいる方向けのコミュニティを立ち上げましたが、それは1年以上を通し、自分自身のSNSにてマーケ関連の情報やSNS分析などの内容を発信し、その知見やノウハウがある程度たまった上でのスタートの決断でした。
この事前準備というのは、反応をジャッジしてニーズをくみ取るという点ももちろんですが、自分がコミュニティオーナーとして立ち上げたいと考えている領域でのイメージ作りにも役立ち、集客の際の大事なポイントになるとも言えそうだなと思いました。
ちなみに、、Shareit立ち上げの告知・集客時気を付けた発信方法については以下にまとめています。
②リーダーの圧倒的な熱量、コミット力
これからのビジネスとしてますます注目を集めているオンラインサロンですが、正直コスパは良くないと5時こーじさんは語ります。
自分も運営をしてみて思いますが、細かな気配りやケア、満足度を落とさないこと…などなど日々考えることがとても多いです。
オンラインサロンにかかわらずどの仕事でもそうですが、手間や労力は当たり前にかかりますし、楽して稼げる…というのは一切ないなと思います(笑)。
コンテンツは常に生み続けないといけない、参加者が得られるものを常にアウトプットし続けないといけない、飽きのないコンテンツ設計などなど改善しながら日々運用をしていくうえで、お金以上に自分がやりがいをもてているかどうかとうのもコミュニティオーナーに必要な資質です。
当たり前ですが、立ち上げるだけで終わりではありません。集客は(サロンの形態によりますが)月ごとに実施する必要があるし、ずっと参加してくれているメンバーにとっても良い環境であり続ける必要がある。続ける、続けられることができる環境を作り、コミュニティを繁栄させるにはオーナーの熱量、思いが大事になってくるということですよね。
思いに共感してくれるメンバーと一緒に成長できる場づくりというのも大事なのかもしれないなと感じました。
③コンテンツ設計はアンパンマン理論で!
みんなおなじみアンパンマンといえば、毎回登場人物や問題は異なれど、全体的なストーリーには共通項がありますよね。
バイキンマンなどが登場して、アンパンマンの顔がぬれたり、戦ったり?して、ジャムおじさんが顔を交換してくれて…最後はハッピーエンド!…のような。見ているひとにとっても安心感がある設計だと思います。
5時こーじさんは、それと同じで、コミュニティのコンテンツ設計にも安心感が必要だと話します。
イベントの型、コンテンツの配信頻度(曜日)など毎回見ている側が困らない工夫を行うのも大事です。毎回毎回コンテンツの取り組み方が違うと、参加者が不安になってしまったり、疲れてしまったりします。
このコラムには自分も意見を書き込まないといけないのかな?
あれ、月曜朝更新だと思ってたのに、金曜の深夜になってる…… などなど、”いつもの型”がバラバラだと把握もしにくいので、参加者が安心してコンテンツを確認できる設計にしておくのが良いです。
確かに、自分自身を参加者側に置き換えて考えても、どういうフローなのか、どういう参加スタイルなのかがわからないとそれだけで心理的ハードルがぐっと上がりがちだな…ということを思い出しました。(そしてめんどうにおもってしまったりもする…)
自分が運営する上でもこの部分が盲点だったので、さっそく役立てさせてもらおうと思いました(5時こーじさんありがとう(笑)!)
今回お話いただいた3つのポイントは、コミュニティ運営だけに限らずSNSの運用や、サービスの立ち上げなどにも通じることでと思いました。ニーズによりそった設計ができているかは大前提。そのうえで、参加者が”入ってよかった”と思える工夫を常に忘れず、コミュニティオーナーとして参加者の得られるものや入ったバリューを最大限に出し続けていくことが大切だと言えそうです。
最後に
今回の内容をもっとフランクにかみ砕いてお話している様子をラジオトークでも配信中!
文章より音声派!という方は通勤通学やお風呂や料理中のおともにぜひ聞いてみてください。
こーじさん、貴重なお話ありがとうございました✨
参考になったらぜひ スキ よろしくお願い致します!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
