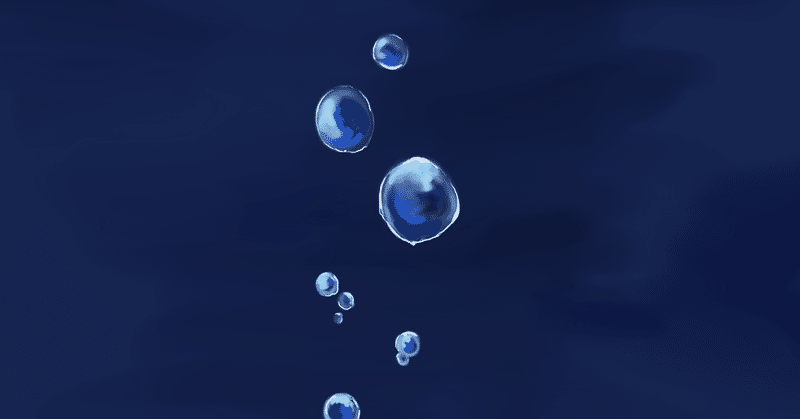
読書はポコンを探す作業
読書好きの方はたくさんいらっしゃると思うし、みなさんそれぞれお好きなジャンルがあり、読み方もそれぞれだと思います。
僕の場合は、あまり多読ではありません。たくさんの本を読むよりも、同じ小説を何度も読んだりすることが比較的多いと思います。
一番好きな小説は多分20回以上は読んでいると思います。それ以外の小説でも気に入ったものであれば2~3回は読んでいます。
小説以外のドキュメンタリや実学書のようなものもの、数回は読みます。その一方で、読んでも全く頭に入ってこないもの、一回読んだだけで本棚の飾りになってしまうものもあります。あ、読み切らないで本棚へ、、、という本もかなりあります(笑)
さてさて、表題の読書は「ポコン」のポコンってなんなん?ってお思いの方、たくさんいらっしゃると思います。あ、読んでいただけ方がたくさんいらっしゃればの話しですけど( ;∀;)
簡単な例を挙げてみます。
「みにくいアヒルの子」ってお話し、おそらくほとんどの方がご存じだと思います。
あれが一番わかりやすいポコンです。
ほかのアヒルの子と自分は違うアヒル。実は成長したら白鳥であり、自分の本来の群れにかえっていく。
異物である状態(非日常)から普通の状態(日常)に戻る。この戻ることを僕はポコンと呼んでます。
このお話しは解釈がいろいろあって、醜かったものが実は美しかった。それによってアヒルを見返したとか、、、
ただ、僕としてはここで醜いか美しいかはあまり意味がなく、本来あるべき場所に戻った。ということが大事なんですね。アヒル側もそうです。あいつ俺らと違うやん!と思って行動してたら、いつのまにか白鳥になって去っていった。自分たちは普通のアヒルとしての生活に戻っていった。ポコンです。
ポコンは必ずしもストーリーの結果として現れない場合もあります。
例えば、作品中に突き刺さるような言葉であったり、表現であったり。
あ!このポコンを浮かび上がらせるためにこの物語を小説家は書いたんだな!と思える瞬間が僕にとって大事なんですね。
物語が立ち上がってくる瞬間とでもいうのでしょうか?ぼくはこのポコンが発見できた本が面白い本だと思ってます。
小説であるということは物語である。ダイナミックな展開や予想もしないどんでん返し、複数張り巡らされた伏線、、、確かにそれも重要な魅力ではあると思います。しかし、そのようなプロット部分にだけに力点が置かれてしまうとどうしても僕の中では小説としての魅力が半減してしまうのです。
Twitterを始めたころに、文学ボットみたいのに登録しましたが、たびたび有名な小説から一文を抜き出して、名分のようにツイートするものがありましたが、抜き出された一文ってあまり意味がないなと思いました。
その一文が輝くのは、やはりその小説(物語)全体から支えられてるからだと思うんですね。
小説や文章はあくまでも構造物で、その構造物から一部の部品だけ抜いてきても、価値はないんです。
小説で使われる言葉は、僕たちが理解できる言葉で書かれています。日本の小説なら日本語で。当たり前ですよね。作者は読者に伝えるために僕たちが普段使っているのと同じ言語をつかう。そして、物語のうえで、普段使っている言葉が一瞬でも輝くように物語を構築しているんだと思うんです。
僕が、若いころに出会って、何度も読んだ本があります。
その小説の最後は『僕の新しい歌だ』の一文で終わります。
この小説を読むと、この一文はまさにポコン!と小説が立ち上がった瞬間なんですね。
しかし、この小説を読んだことが無い方は、ここだけ抜き出されても「は?」となるでしょう。
実は、この小説は村上龍原作の『コインロッカーベイビーズ』です。
上下2巻からなるこの小説を読むと、この最後の一文のためにこれだけの量の文章が必要だったんだ!というのがよくわかります。
僕はこの本を読んで、この最後の一文にたどり着くたびに、ザワザワと震えてしまほどなんです。
こういうポコンと浮かび上がってくるものを探す作業。特に小説と向かい合う時の僕の読書方法です。
そして僕も、ぼくの書いたポコンを誰かが発見してくれる小説を書きたいと思ってます。
うわぐっくスケキヨ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
