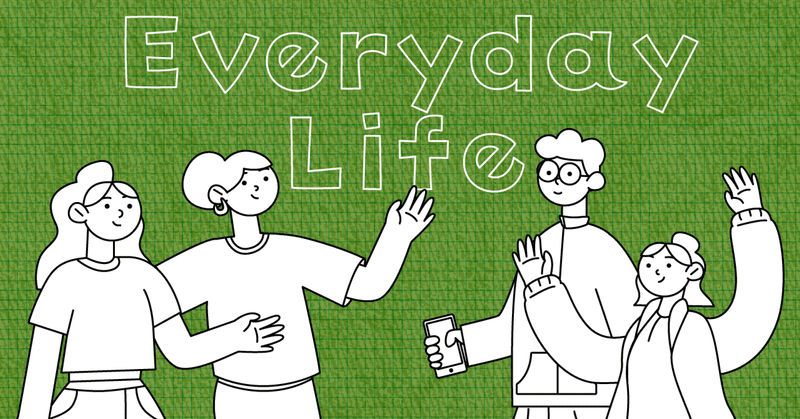
仲間とある分野を学習しています。[くま日誌]98号
■
昨日も引き続き、ある分野について学習をしていました。
自分の専門分野に磨きをかけようと思っています。
誰もが「無駄(生産性が低い)だと思われる事」をやることは、辛いことだと思います。
このような仕事をなくすには、より高いレイヤーの知識が不可欠だと考えるようになり学習を始めました。
■
例えば、目的や仮説なしに、データが出るというだけで作成されるレポート。
デジタルはデータが収集できる反面、膨大な無駄が発生しがちなんですよね。生産性を上げようという試みに反して、生産性を下げてしまっていることって実は結構あるんじゃないですかね。
このような場合に必要なのは、レポートを作るためのスキルではなく、目的や仮説を立案するための知識になりますよね。
イメージ的にはそのような一つ上のレイヤーの学習をしようと思っています。
■
学習をしようと思った後、偶然なのですが、
「一緒にこの分野を学習しよう」という仲間を見つけました。
自分も合わせて3人で、この分野を学習していく予定です。3人とも専門が違うので、課題感や目的意識は違うと思うのですが、逆にそれがよいですね。
チャットグループを作って、
情報を共有したりする、ゆるい繋がりを持ちながら、
定期的に、ディスカッションなどアウトプットの場を設けていこうと思っています。
異なるバックグラウンドを持っているからこそ、面白いですし、そのような多様性から新しい価値を生むのかもしれませんね。
■
今回のこのような小集団での学習というのは、自分が声を掛けたところから
全くの偶然始まりました。
集団学習というのは、誰も不幸にしないですよね。
モチベーション維持だったり、各々からの情報共有/インプット、また、アウトプットの機会を設けることができるというメリットがあります。
■
さらにチームとしての一体感も醸成されてきますしね。
将来、このチームで仕事するかもしれません。(笑)
この学習を通じたチームの構築というのは、個人戦から団体戦に移行していく一つの形態なのかもしれません。
■
学習をなんのためにするのか?
というのは、「他人様へより高い付加価値を提供するため」ですよね。
そう考えると、集団戦と言うのは、独りでは実現できないような
大きな価値を集団外へ提供することができますし、また集団内においても全員がメリットを享受できる仕組みですね。
■
このあたり、先日鮒谷さんから教えていただいた
「集団戦」「自作自演」「出来レース」という言葉を思い出しながら、
考えました。
これらのキーワードも改めて身体に編み込んでいこうと思っています。
■まとめ
なにかのテーマについて学習していくときは、集団戦を展開できないかを考えてみる。
よい学習集団を形成することができれば、アウトプット/インプット/モチベーション維持など各メンバーへ様々なメリットがある。
また価値提供という観点からも、集団戦はシナジーを生み、大きな成果を出すことができるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
