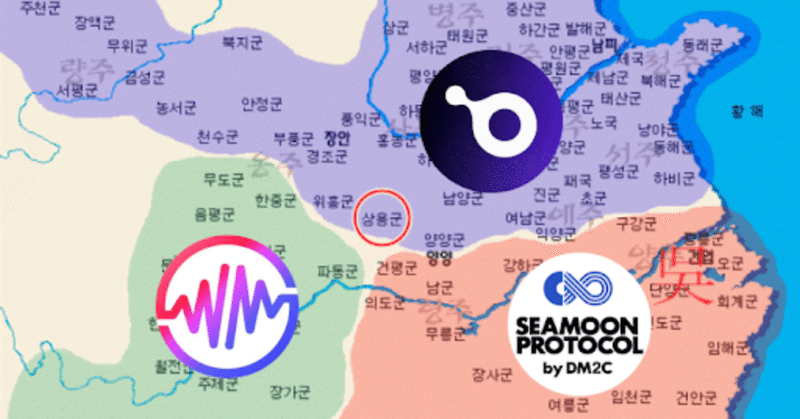
ブロックチェーンゲーム市場の教訓と新たな戦略について
初期ブロックチェーンゲームの教訓
ブロックチェーンゲームの代表作といえば、ローニンチェーンに展開するAxie Infinityだ。
2021年、新型コロナウイルスの影響で観光産業を中心に成長していた東南アジア経済が大きな打撃を受けたことで、ブロックチェーンゲームが生計手段として定着した。この時期に東南アジア市場で先導者であったAxie Infinityは大きな恩恵を受けた。
しかし、ゲームとトークンが組み合わされた”金融サービス”の性質上、ブロックチェーンゲームは必然的にブロックチェーン市場のサイクルとマクロ環境の変動要因にさらされる。このような変動性はゲーム経済やコンテンツに大きな影響を与えてきた。
初期のブロックチェーンゲームでの経験に基づき、現在のプロジェクトは市場の変動に対処するべく、さまざまなメカニズムを備えている。
その結果、ゲームインフラとゲームを一緒に開発してより持続可能な環境を作り出そうとする動きがある。例えば、トークンの変動性やインフレの問題によりゲームサイクルが短くなることに対処するために、レイヤー1、2、3などの複合的なインフラ開発が勧められている。
ゲームIP、インフラ、パブリッシング、先駆けとなる領域は?
ほとんどのブロックチェーンゲームスタジオは、上記の領域すべてを網羅することは難しいと感じている。そこで各スタジオは自社の強みを活かした戦略を取っている。
Web 2市場で確固たる地位を築いてきた資本力のある企業は、開発と出版についての専門知識と経験に基づいてWeb 3インフラの開発に注力している。
一方で、Web 3ゲームスタジオは、ある程度成功したWeb3特化のゲームIPやインフラの経験に基づき、ゲームIPの出版を支援しながら成長している。
これらの企業はどちらもまず市場の特定の領域を支配する戦略を採用しており、経路は異なるものの、最終的にはゲームIP、インフラ、パブリッシング、Web3対応デバイスなどを包括的に網羅することを目指している。
集中的なビジネスモデルから始め、いずれプラットフォーマーとして拡大することを目標としている。最近、この両方のアプローチを同時に活用する事例として、Xterioが注目されている。

Xterio(エクステリオ)は、FunPlus(ファンプラス)のWeb3ゲーム出版社であり、FunPlusは2019年にリーグ・オブ・レジェンドの世界大会でチームが優勝し、その際に名を挙げた企業である。
FunPlusは従来のゲーム市場で成功を収めたカジュアルゲームや戦略ゲームの開発・販売でよく知られており、「State of Survival」は世界中で1億以上のダウンロードを記録している。
従来の市場での成功体験を基に、FunPlusはXterioというWeb3ゲームの出版および独自IP開発のプロジェクトを立ち上げ、Binance Labsから1,500万ドルの出資を受けた。これまでに、総額で8000万ドルともなる投資を確保している。
Xterioは、Steamのように自社ゲームの開発に加え、外部プロジェクトに出資し、Xterioに独占的にローンチする計画をたたている。現在、5つのオリジナルゲームを開発中であり、他の開発者と提携して45個のゲームをプラットフォーム上にローンチする予定だ。
また、XterioはWeb3に特化したプラットフォームをすでに構築しており、もはやWeb2ゲーム会社の域を超えている。
同社はEigen Layerのリステイキングを通じて、イーサリアムネットワークのセキュリティで守られている「ゲーム専用チェーン」を開発した。イーサリアムベースのXterioレイヤー2チェーンは約120万枚のイーサリアムをリステイキングしており、これは約320億ドル(50億円)の価値に相当する。
また、現在はBNBチェーンのL2も開発中だ。複数のL2を構築する理由は、各ゲームに必要な仕様を満たすためである。
新しいゲームがXterioのエコシステムに組み込まれると、個々のゲーム内通貨とXterioのネイティブトークンとの間で相乗効果が期待される。さらに、ユーザーに定期的なエアドロップを提供することでユーザーの定着率を高め、ゲーム利用者が支払うガス料金がXterioの収益となり、これでエコシステムの持続力を確保できる。
ローカライゼーション(現地化)の重要性
Xterioの戦略は、主に英米および中国市場を初めから主要なターゲットとすることにより、グローバルな展開が期待される一方、日本や韓国などの重要な市場を見落とす可能性がある。
日本と韓国はゲーム開発者にとって魅力的な市場であり、ユーザーの高い購買力と比較的低い獲得コストが特徴だ。これら2つの国は、総合ゲーム市場の約18%を占め、アメリカと中国に次ぐ世界で3番目に大きな市場である。
韓国を代表するブロックチェーンゲームプロジェクトのWemixは、この市場を効果的に捉えており、親会社であるWeMadeのWeb2ゲーム開発のインフラや出版の経験に基づいて、韓国市場を戦略的にターゲットとしている。この戦略により「Mir 4」などのゲームは韓国で10万人の同時接続ユーザー数を記録し、グローバル市場でも2万人の同時接続ユーザー数を達成している。

Wemixは韓国市場の特徴を理解し、「韓国の代表的なブロックチェーンプロジェクト」という独自のブランドを確立した。
この戦略は、ゲーム運営方針に関する論争やトークンの過剰発行、検察の捜査などの逆境にもかかわらず、市場価値1.6億ドルを維持する上で重要な役割を果たした。
日本でも同様の国内市場を対象にしたWeb2ゲームプロジェクトはある。Web2で豊富な経験を積んだDMMグループを中心に、ブロックチェーンゲームインフラと仮想通貨特有の要素を組み合わせたプロジェクト「Seamoon Protocol」が開発されている。
日本発のブロックチェーンゲーム・プラットフォーム 『Seamoon』

DMMは1999年から日本でインターネットサービスを提供しており、年間約3,476億円の売上高を記録している大企業だ。
DMMは日本市場だけでなく、特にゲーム部門においてグローバル市場にも大きな影響力を持っている。2017年に設立されたゲーム部門はわずか7年で57億ドルの売上高を達成し、240のオンラインゲームを配信し、3400万人ものユーザーがプレイした。

DMMは主に世界的に人気のあるサブカルチャーゲームを出版しており、その中には韓国でも人気のある競馬ゲーム「ウマ娘」とアイドル育成ゲーム「アイドルマスター」などが含まれる。
最近のWeb2ゲーム市場では、キャラクターと対話できる「モデルキャラクターAI」技術が登場し、ゲーム市場では「原神」「明日方舟」「ニケ」などのタイトルが仮想通貨市場でもサブカルチャーゲームのトレンドをリードしている。
DMMが保有するサブカルチャーゲームのライセンスを活用すれば、Seamoonもこのニッチ市場を主導できる潜在能力を持っており、これはサブカルチャーゲームのグローバル化に大きく貢献する可能性がある。

Seamoonは、市場戦略と仮想通貨に対応したゲームプレイを合わせることで大きな成功を収めることができるはずである。
日本発のゲーム・チェーンであるOasysのレイヤー2としてゲームインフラを構築し、ゲームトークンの流動性を生み出す計画があり、さらにステーブルコインを担保としてDMMグループの$DM2Pトークンを供給し、ゲーム内で使用可能にするのだ。
ゲームとDeFiの要素を組み合わせた独自のゲーム内経済構造を作り出し、ユーザーに新しい価値と体験を提供することができる。従来のゲームモデルとは異なる戦略で、業界に革新的なモデルを提示し、市場における競争力を高めることが可能だ。
DM2Pトークンの価値は、Seamoonに統合されたゲームがDM2Pを基軸通貨としてどのように活用し、そして個々のゲーム内通貨の価値の向上がDM2Pにどのように反映されるかに左右される。また、$DM2Pは独自のDeFiインフラを通じて流動性を生み出し、DM2Pトークンの変動率を減少させることを目指している。
ゲームアセット間の取引によって発生する手数料や貸出金利は、このトークンの本質的な価値を構築するのに役立つ。ゲームユーザーの流入と資産取引が活発化するにつれて、DM2Pトークンの需要が増加する好循環が生まれることとなる。
懸念点の一つとして、DM2Pトークンがレバレッジを活用して作成された流動性プールに依存しているということが挙げられる。
ゲームユーザーの活動が減少した場合、流動性が失われ、トークンをデレバレッジする必要が出てくる。デレバレッジとはレバレッジを減らすことでトークンの価値が下落することで、すべてのゲーム内資産の流動性がDM2Pトークンに依存するため、これら資産の価値に悪影響を与える可能性がある。
そこで、ETHやステーブルコインに換金するための中間決済資産としてDM2Pトークンを活用できるようにすることにより、流動性を高め、エコシステム内で悪循環を防ぐことができる。つまり、より安定した資産への簡単な換金を促進することで、エコシステムはデレバレッジに対して強靭になり、流動性と資産価値の下降スパイラルを断ち切ることができるのだ。
もう一つの懸念点は、SeamoonがOasysのL2である以上、L1であるOasysのパフォーマンスに影響を受けるということだ。L1のネットワーク価値と流動性は絡み合っており、L1トークンの時価総額と流動性がL2トークンの時価総額を形成する上で重要な役割を果たす。つまり、OasysはSeamoonプロトコルの上昇ポテンシャルを制限する可能性がある。
しかし、Seamoonは仮想通貨エコシステムの「サブカルチャー専用チェーン」という独自のストーリー性を持っており、単にL1の機能を拡張するL2としてだけでは価値を正当に評価することはできない。将来、Seamoonがどのようなサブカルチャーゲームで新しい市場を形成していくかが楽しみだ。
結論
前回の強気相場では、ゲームとトークンが組み合わされて市場に投入された。しかし、トークン価格の変動がゲームに大きな影響を加え、さらにトークンの供給過剰とゲームコンテンツの魅力不足により、短いライフサイクルを迎えた。
現在の強気相場では、ゲームIP、ゲームインフラ、およびWeb3ネイティブ要素を組み合わせたゲームプロジェクトが登場している。前回の弱気相場の教訓を生かしながら、各企業はより持続可能なエコシステムの構築に取り組んでいる。
さらに、各市場に合わせたローカライズ戦略を持つプロジェクトが特に高く評価されるものと予測される。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
