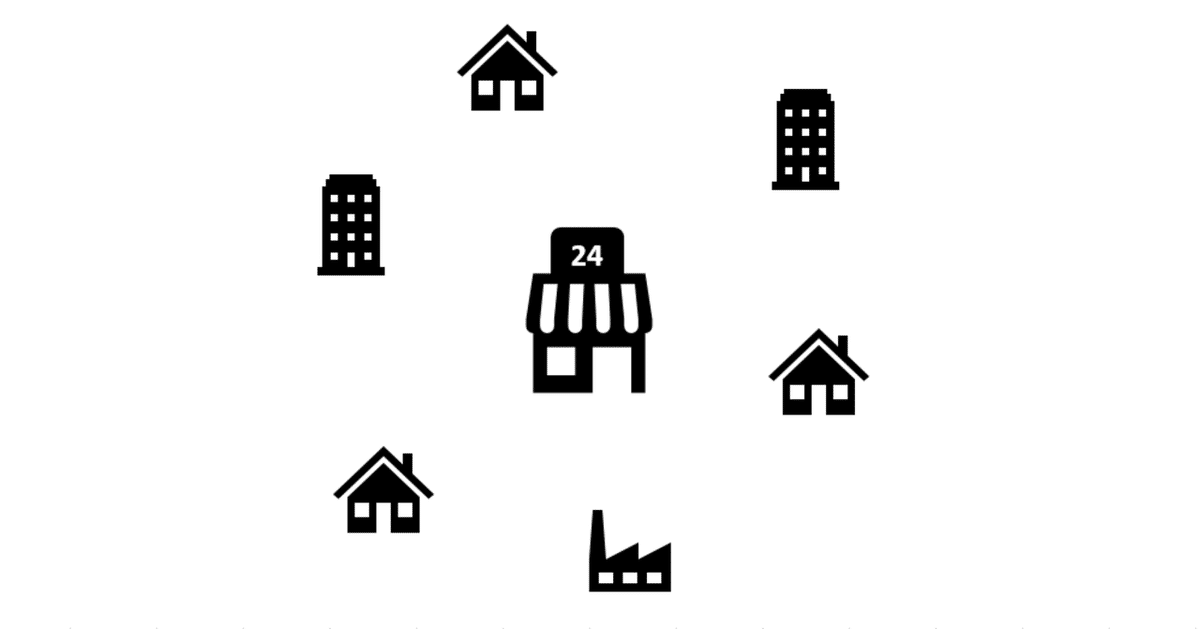
地域・自治体でのコンビニ・スーパー経営
搾取労働の典型がコンビニではなかろうかと。
昨年年末で閉店するコンビニを幾つか見かけました。
消費税が関係しているのかもしれませんが、ブラック企業扱いのコンビニチェーン店の店主への扱い用は、貧困ビジネスさながらに感じます。
スーパーも大型チェーン店の出現で、地域で買い物するのが難しくなってきてます。特にお年寄りは辛いかと。それを補うために送迎バスを走らせている店もありますが、全てのルートを補っているわけでもなければ、必ず座れるとも限りません。
やっぱり身近で買い物となると、コンビニは結構重宝します。
しかし、値段は高めですよね。
そこを競争として、大型チェーン店の格安バージョン店があったりもしてはいます。
ですが、地方も地方となるとどうでしょうか?。
完全に車社会。
便利と思いきや、地方は案外道が少なく、混雑もします。
やはり身近な昔ながらの商店は便利だと感じます。
少し考えたのですが、自治体や地域でスーパーを住人や公共事業体が経営するという事は考えないのでしょうか?。
ある種、失業者対策にもなりますし、備蓄場所としても確保できるのですが。。。
24時間に無理にすることもなく、自動化にしなくも良いかと。
それこそ、役場の中、郵便局の中、派出所の中に作ってもいいのです。
何も個人が経営する必要はありませんし、チェーン店に加盟する必要もありません。
周辺の農家の方や自作農園を持っている方が持ち寄って販売している場所もあるのですから、一緒に売買してもいいのです。
食料品、日用品の需給は公共機関が今後行って行く必要性が高まってくるでしょう。
大きな地震災害から10年近くなろうとしてますが、未だに備蓄管理できてない官公庁や国家施設は存在します。
自治体施設もこれでは信用できず、結局個人の行動にということになりますが、お年寄りや家が狭い方、収入が乏しい方は苦しいです。
自治体が備蓄を行い、安全面を考慮する必要もあるならば、自分達で販売・供給・備蓄が行えるよう経営してもいいのでは?と考えました。
誰がやるの?。
ええ、自治体職員と地域住民です。
ここが課題で、地域住民が率先して行動しなければならないのです。消防団と同じような考えですよ。
情報提供や考え方、そしてこれまでの苦々しい経験での対価として、ありがたく頂戴致します。
