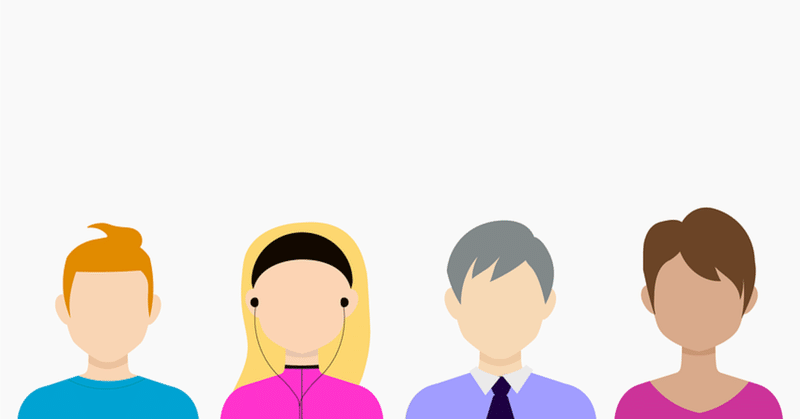
実は優秀!?Z世代との関わり方を考える
Z世代とは、1995~2009年生まれの人たち。
1. Z世代とは
1981〜1994年生まれた世代は『ミレニアル世代』と呼ばれ、さまざまな電子機器が普及した時代に育ったという意味合いで『デジタルネイティブの世代』なんて言われます(僕もこれにあたりますが、個人的には81〜94の間にもだいぶ差を感じる笑)。
それに対しZ世代は、10代からソーシャルメディアに触れて、スマートフォンを使いこなす『ソーシャルネイティブ』なんて表現をされます。
そして今、そのZ世代が成人を迎え、新社会人として働き始めています。
Z世代と、僕を含めそれ以前の世代とでは仕事に対する意識も異なります。僕の周りでも、Z世代を部下に持ち、そのギャップに頭を悩ましている人を見かけます。
然しながら、人口が右肩下がりの日本において若手の人材の活用は企業にとっても避けては通れない話です。
Z世代とのミスマッチを防ぐためにも、Z世代について深く知っておくことが大切だと思います。
2. Z世代の特徴
①保守的
②あらゆる場面で平等性を求める
③ 仕事を短期間でやめる
①保守的
お金を多く使わないのもZ世代の特徴の一つに感じます。またキャリアについても、学生が新卒で入社する企業選びのポイントで「安定している会社」と答える人の割合も多く、お金やキャリアに保守的な人が多くみられます。
これに対し、僕ら世代より前の世代になればなるほど、『金は天下の回り物だ!』『使った分だけ金は入ってくるだ!』と化石みたいな発言をします。
しかし、実際のところは毎年日本の年収中央値は下がり続け、2020年最新のデータによれば年収中央値は、男性425万円、女性315万円となっています。
あれ!?なんか低くないと感じた方は、平均年収を今まで見てらっしゃったかもしれません。上が馬鹿みたいに高かろうが(例えば年収5,000万円)それもひっくるめて人数割にするのが平均年収であるのに対し、中央値は一番上と一番下から順番に潰していって、ちょうど真ん中!の人の年収になります。
なので日本の現状を知る上では中央値の方がよりリアルな数字となります。
こういった社会人を見てきたZ世代が昔みたいにお金を使おう!となるでしょうか。僕はむしろ賢明な判断だと思います(欲を言えば、お金に働いてもらう事を考えなれると更に良い!)。
ブランドよりも個性や自分らしさ重視であるZ世代は、社会的に認められたブランドよりも、自分が気に入ったものを選びたいという志向を持っています。
『新しい』ではなく『ユニークさ』や『自分らしさ』でモノを選ぶ Z世代の基準は、見栄に引っ張られない豊かになる秘訣なのかもしれません。
② あらゆる場面で平等性を求める
Z世代の3分の1は、人間は皆平等であると強く信じていると回答していると言います。
人種、性別、ジェンダーなど、全て現代社会では平等に受け入れられるべきというのがZ世代の考え方です。それゆえに、社会人になると労働者の権利を主張する特徴を持ち始めます。
僕はこれについても『あり』だと思います。今の日本においてYesマンは搾取されるからです。ただ、やる事は全くやりませんが権利は主張しますというのはお勧めしません。上司や同僚の目もありますが、1番はスキルがつかないからです。
スキルをつけ、権利を使いお金を貯めていれば、何かあった時会社はすぐ辞められます。
③仕事を短期間でやめる
Z世代は忍耐力がなくすぐ辞めると言う人がいます。本当にそうでしょうか。忍耐力の問題で辞めていた人は僕らの時代でも多くいました。ではなぜこういった印象になるのか。それはきっと実際に辞めている人は多いからでしょう。
ただ、理由が違うのではないかと僕は思います。
僕はその理由を、他の仕事について『知る機会』『出会う機会』が格段に増えたからだと考えています。
化石世代の人達は、紙と足で転職先を探しましたし、その他の会社の中身なんて知る良しもありませんでした。
しかし今はどうでしょう。ソーシャルネイティブと呼ばれる世代はスマホを片手に1日で数十、やる気次第で数百という会社の仕事内容、社風、給与待遇、福利厚生等の情報を得られます。現状の仕事との比較は容易であり、自分にとってより良い環境にうつることに抵抗なんてありません。
会社にとってはリクルート、研修コストをかけているのでたまったものではありませんが、自分の会社の魅力度が足りなかったと反省する部分も必要かと思います。この状況下でも、就職希望者が溢れかえる企業はあるわけですから。
3. 最後に
会社では、Z世代に対し厳しい意見が飛び交います。僕の会社でも同様、Z世代との関わり方が分からないという人がいます。
そんな皆さんに言いたいのはただ一つ。まずはZ世代を知る事が近道となるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
