
GW読書感想文➀7つの習慣~自分を知り、他人を知る~
初めまして。ちゃんでらと申します。山形の山と海に囲まれた土地で18年間育ち、米どころの新潟で心理学を4年間学んだ後、東京で働いているものです。よろしくお願いします。
今回、このGWにかけて、自分が4月中に読んだ本をまとめて、より分かりやすく紹介したいと思い、読書感想文形式でまとめることにしました。今回は第一回として「7つの習慣」を紹介しようと思います。拙いところや解釈を間違えているところなどあると思いますが、その際はご指摘くださるとありがたいです。よろしくお願いします。
1.背景と概要
今回は「完訳 7つの習慣 人格主義の回復」について感想を書いていきます。スティーブン・R・コヴィー氏によって1989年に初版が出され、日本には1996年に出版されました。全世界で3000万部・日本でも200万部以上売れているビジネス書の大ベストセラーですね。近年は分かりやすく漫画などで書いてある書籍も増えたので、読んだことがある人も多いのではないでしょうか?
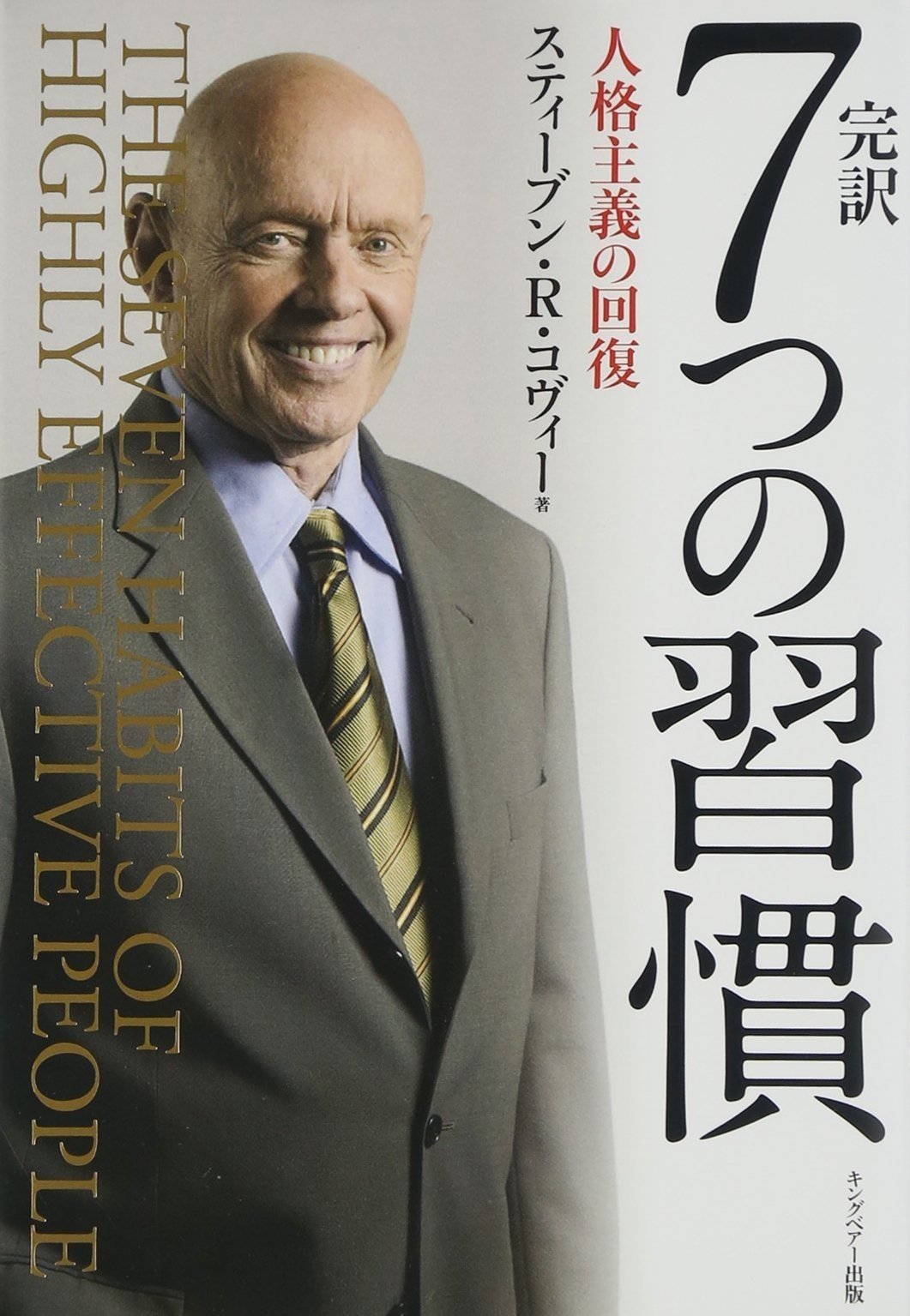
この本の特徴を一言で言うと、「成功するためには、どのような考えに基づいて行動すればいいのか?」について、具体的な7つの方法に基づいて記してある本です。コヴィー氏は直近200年の「成功」に関する本を調査し、成功は行動の根本になる「人格」が大切であると結論づけました。そしてその人格を習得し、自分自身の考え方(パラダイム)を改善するために「7つの習慣」が必要であるとして、この本を執筆したそうです。
ここでいう「習慣」とは、文中では知識(なぜそれをするのか?という問いに対する理論的裏付け)×スキル(どうやってするのかという方法論)×意欲(動機や情熱)の掛け算と定義されています。会話を例にすると「人の話は最後まで聞く」「頭ごなしに否定しない」といった基本知識がないと会話が成り立たず、話を聞くためのスキルも有していないと同様の結果になるでしょう。さらにこの2つが仮にあったとしても、自分自身に「話を聞こう」という意欲が無ければ意味がない、ということになります。感情・知識・スキルがバランスよく備わらないと「習慣」は生まれないという事ですね。
そんな7つの習慣は、個人に関する第1~3の習慣、他者との関係作りに関する第4~6の習慣、そしてそれらの効果を高める第7の習慣で構成されています。これらは著書の中でそれぞれ「自立による私的成功」「相互依存による公的成功」「自分自身の代謝を促進させる再新再生」と称されています。そしてこれらは、折を見て反復させること、人に伝えるつもりで学んでいくことが大切であるとされています。
というわけで、7つの習慣は具体的に何なのか?見ていきましょう。
2.7つの習慣とは?
この章では7つの習慣に関して、ごくごく簡単ではありますがその概要についてまとめていきます。実際の著書ではより具体的な実践方法が書いてあるので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
1.主体的である
・ここで言う主体的とは、積極的に活動することだけでなく、自分自身の選択や行動に責任を持つという「覚悟」の事である。もっと言えば「自分自身が人生の主役であり、状況や誰かのせいにしない」ということである。
・主体的であるためには、自分自身がコントロールできることとそうでないことをはっきり分け、前向きな気持ちでコントロールできることを増やしていくことが必要である。
・今すぐ人生の主導権を握るためには、約束を必ず守る事、目標を立てる実行することが必要である。
2.終わりを思い描くことから始める
・「自分が死んだとき、どう評価されていたいか?」を考える事で、その人の特性や思考がわかる。
・全ての事象は、脳内で思い描くことで一度、実際に行動することで2度作られる。いきなり「やる」のではなく、どこに向かうのか?どうありたいのかという「地図」を作ることが必要である。
・「地図」をつくるためには、自分の行動原則を知る事が必要になる。
3.最優先事項を優先させる
・この習慣は「自分自身を効果的にマネジメントする」とも言い換えられる。物事の優先順位を決め、それに従って行動するということである。
・優先順位を決めるにあたって、必要なのが「重要度」と「緊急度」という考え方。これらの掛け算でタスクを4分割し、「重要だが緊急ではない」ことに時間を使うことが必要である。
・優先順位を決めるためには、目標・ひいてはそれを構成する根本の価値観が必要。それを知るためには第1・2の習慣の習得が必要である。
4.win-winを考える
・win-winとはお互いの利益が最大限になるよう、尽力することを指す。
・win-winには、自分も大切にしながら相手の言い分も大切に使用とする「勇気と思いやり」をもつ事、自分自身が内面から満足し安定した上で、信頼関係を構築することが必要である。
5.まず理解に徹し、そして理解される
・他人の話を聞くとき、自分の物差しで考えるのではなく相手の立場になって考える事が必要。相手の言うことを理解し、その根底にある気持ちを知ろうとする姿勢が必要である。相手への理解があって初めて自分への理解が生じる。
・理解されるには、信頼感(エトス)・感情(パトス)・論理性(ロゴス)が必要。論理性ばかりに重きを置くのではなく、その源となる情熱や信頼性も兼ね備える必要がある。
6.シナジーを創り出す
・シナジーとはある要素が重なり合うことで、単体では生み出せないような成果を出すこと(1+1=100になるような関係性のこと)。
・シナジーを生み出すには、相手への深い信頼や協力の姿勢、勇気をもって自信を開示する姿勢が必要となる。
・シナジーを生み出すためには、相手との考え方や意見の違いを受容する器量が必要である。
7.刃を研ぐ
・ボロボロの刃では切れないように、自分自身の成果を生み出す資本を定期的にメンテナンスする必要がある。
・この資本は肉体・精神・知的・社会的側面の4つに分けられる。身体を動かして体力を養ったり、自分なりの精神安定を実施したり、ニュースや新聞を読んで知識を入れたり、今までの習慣を見直したりすることを、バランスよく行うことが必要である。
・第7の習慣を行うことで、今までの習慣も強化され、シナジーが生まれる事がある。
つまり、この習慣をまとめると、
・効果的に生きるためには、まず自分自身が道を切り開く覚悟と責任を自覚すること、自分自身の特性・ルールを知る事、そのルールに基づいてゴールを決め、優先順位を決めることが、個人レベルでは大事。
・そして他社とのやり取りの中では、自分と相手の違いを許容すること、その上で自分自身をさらけ出し、相手も自分も満足できるような関係を構築することが大事。
・最終的に、これらを維持できるよう、自分の体や精神をメンテナンスすることが大事。
ということになります。まず自分自身、「何があったら動くんだろう?」という源泉を知り、その上で「こうありたい」というゴールを決め、優先順位を決めて行動する。その上で相手の事を理解し、信頼しあった上で、強力な効果を生み出せるようにしていくという事だと思います。
3.個人的に印象に残ったこと
この本自体は一週間くらいで読み終わったのですが、思っていたよりも非常に読みやすかったです。著者の体験に基づく事例が多く、わかりやすい流れであったので、500pくらいあったのですがすぐ読むことが出来ました。また理論的な事だけでなく、実際に身につけるための実践的流れも多く書いてあったため、実生活に生かしやすいと思いました。
7つの習慣の内容自体は、どこかで聞いたことがあるような普遍的な内容から、今までのモヤモヤを晴らしてくれるような革新的な内容まで様々でした。その中で印象深く残っているのが、第一の習慣と第三の習慣の内容です。第一の習慣では、「自分が直接コントロールできること」「間接的にコントロールできること」「コントロールできないこと」に分け、自分がコントロールできることにフォーカスを当てて全力で取り組むことが印象深かったです。最近の情勢ではコロナによる弊害など、自分がどう頑張っても変えられないことに力を割くより、自分が今できることに全力を注ぐ必要性を強く痛感しました。
また第3の習慣で掲げられていた優先順位に関しても非常に刺さりました。自分はなかなか計画やスケジュール管理が苦手だったのですが、該当の章を読んで、「このような基準で分ければいいのか!」と知り、早速活かしています。それだけでなく、マクロ的な優先順位を決めるためには大きな指標となるものが必要だと感じました。
今回では大きく取り上げなかったのですが、7つの習慣を構成するインサイドアウト(内から外へ)と、信頼残高の考え方も非常に役に立ちました。読んでよかったと思います。
4.最後に
いかがでしたでしょうか。この本の魅力が少しでも伝われば幸いです。こういう試みは久しぶりだったのですが、自分自身の文章力のなさを痛感しております・・・・。単純に(創作活動やってる人、すげぇ!!)って思いました。言いたい事も言えないこんな世の中じゃ状態です(このネタわかる人いるんだろうか笑)。最後までお読みくださりまことにありがとうございました。次回もよろしくお願いします!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
