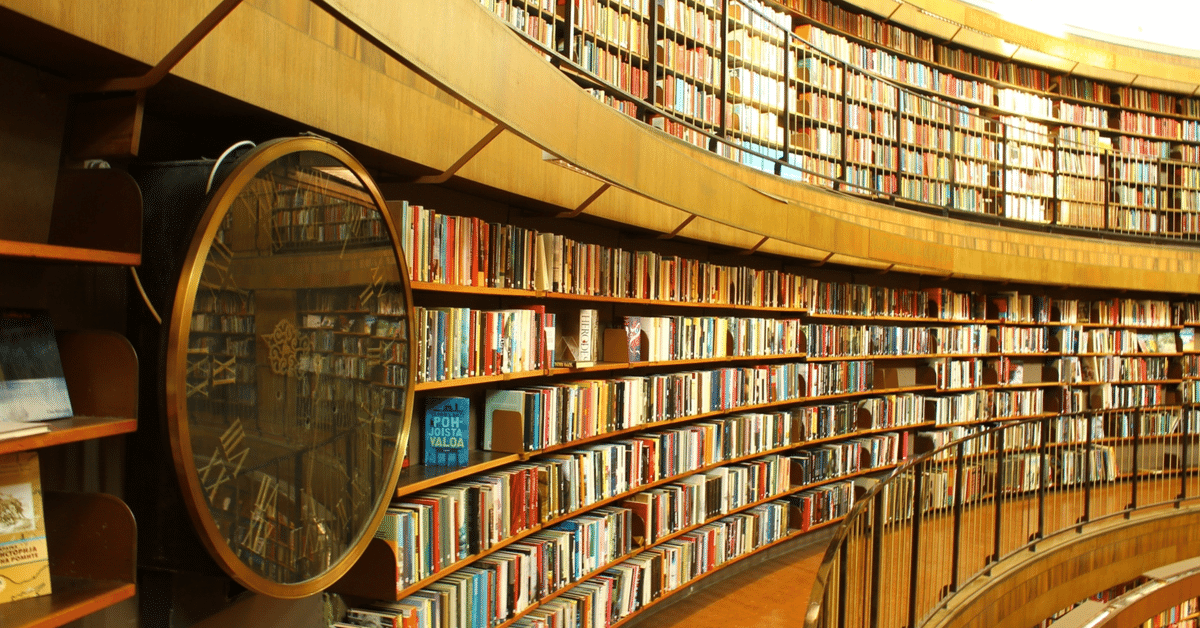
SAPIX組み分けや合不合で時間が足りない人発見!国語の時間で時間を確保する方法
中学入試国語を見てきて、最も多い質問のひとつに「模試の時間が足りない」というものがあります。
確かに入試全体が超長文化傾向にある中で模擬試験もそちらに寄ってきて、国語が苦手な子に関しては、この「速さ」というのが非常に高いハードルになっているように思います。
また、ゆっくりしっかり読み取る力があって、「本当は国語が苦手でない子」も超長文化の被害を被ってしまいます。
今回はこうした悩みを持つお子さんに向けた速く読むための方法についてまとめていきたいと思います。
そもそも何で間に合わないの?
模試や入試問題が超長文化していると書きましたが、実際にはどの程度の分量が読まねばならないハードルとなっているのでしょうか?
サンプルとして直近の模試の文章量を調べてみると、SAPIXの7月の組み分けが10000字程度、四谷大塚の第2回合不合が8000字程度となっています。
仮に全体の6割の時間を内容理解に費やすとしても、それぞれ1分あたり330字、270字を読んで理解し切らなければならない計算となります。
日経新聞の春秋や朝日新聞の天声人語といったコラムが500〜600字なので、大体あれらを2分で理解するくらいの速度だと思って頂ければ良いでしょう。
なかなかハードルが高いですよね。
さて、文章量に触れてきましたが、そもそも時間が取られてしまうのは文章の読解だけではありません。
どうしても、スピード≒読解の速度と考えてしまいがちなのですが、実はそれ以外の所にも案外時間がかかっている事があるのです。
文章読解以外に意識してほしいのは次の項目です。
①語句・知識分野の解答速度
②解答時のタイムロス
③諸々の所作の時間
①語句・知識分野の解答速度
実は国語で時間が余る子とそうで無い子の間で大きく違うのが①の速さです。
国語が苦手という子は、読解に取り掛かる以前に、知識問題で時間がかかり過ぎている(その割に正答率も低い)という事があります。
読解速度云々の前に既にそこで出遅れてしまっている。(理想は今回の合不合であればかけて3分、SAPIXの組み分けならかけて2分といったところでしょうか...)
ここでどれくらい時間が取られているかを確認して見てほしいところです。
②解答時のタイムロス
②次に時間が取られている可能性があるのが解答時の時間の部分です。
せっかく文章が理解できたとしても、a選択肢の吟味やb抜き出し箇所の把握、c記述答案の完成に手間取ってしまえば大きく時間をロスしてしまいます。
それぞれの対応方法が違うのですが、以下のポイントを意識して問題演習に臨むと、少しずつ改善されるかと思うので、実践してみてください。
a.選択肢の吟味
選択肢の吟味で時間がかかる人のよくあるつまずきは次の3通りです。
a1 選択肢ごとに本文を検証する
a2 選択肢と傍線の言い換えが比較できない
a3 選択肢の論理構造の把握が苦手
a1〜a3は、時間が取られる順に並べました。
まずa1に関しては、ひとつひとつの選択肢の度に本文を見にいって、本文に解答根拠を探しに行くというやり方で、もっとも時間が取られるパターンです。
このパターンでつまずく子は内容をきちんと把握できていない可能性があります。
理想は1.傍線を丁寧に読む→2.設問内容の把握→3.本文の必要な情報を把握→4.本文に戻る事なく選択肢を吟味です。
選択肢ごとに戻って探すというやり方は、中学入試(深い読解を求める学校は別ですが)、というか少なくとも模擬試験ではタイムロスをしてしまうので、そもそもやり方としてあまり実践的ではありません。
そのため、何度も振り返らない解き方を新たに身につけて行くべきでしょう。(因みに大学入試共通テストも同様の系統です)
a2に関しては、細かな語彙に対する意識がまだ十分に無いために間違えてしまうというパターンです。
この前の第3回の五ツ木模試の小説の選択問題(手榴弾が爆発するみたいなやつ?)がここに該当するでしょう。
2択に絞った後で本文的にはどちらもあっているはずなのにどうして片方の選択肢が正解になるのかが分からないという形で悩んでしまう子はここに該当します。
こういう場合、解答根拠は本文というより、語彙の差異にあります。
二つの選択肢を見比べて、表現に僅かな違いがあるところを見極め、傍線(或いは本文)には、どういう表現が用いられているかを検討するというのが解法なわけですが、その思考プロセスを意識することで、ここでのタイムロスは減らせます。
最後のa3については読解力というよりは論理的思考力の問題です。
「AだけでなくB」と「AでなくB」の違いみたいな、細かな論理構造の把握です。
ここが苦手な人は、主語述語関係や修飾語、それから接続語・接続助詞などの練習をして、一文を正確に読む練習が有効です。
その上で解説にある、他の選択肢が違う理由をしっかり実際に書き込んで確認するという勉強をしてみてください(←「書き込む」という部分が重要です)
b抜き出し問題について
抜き出し問題で時間がかかる人に関しては、まずはb0基本姿勢に加え、b1読解の最中に行うべき事とb2設問に向き合う際に意識する事がありますのでそれぞれまとめていきたいと思います。
まずb0基本姿勢に関してですが、抜き出し問題は思わぬ所で時間がかかり、足元をすくわれかねない問題であるという前提に立ってください。
本文にあり、かつ短い文字数だとすぐ見つかるように思いますが、その答えになる場所が近くにあるとは限りません。(ときに「なぜそれを取らせたら」と思うようなところにあることも)
ぱっと見つかると思って取り組んだはいいけれど見つからない場合、やがて「これだけ時間をかけたのだからあと少しで見つかるはず」という意識が芽生え、その問題にムキになってしまう。
経済学でいうところのサンクコストの呪縛に陥ってしまうわけです。
これが1番避けたいところです。
最悪なのは一つの問題にムキになり、他の取れるはずの問題を落とすこと。
したがってまずは解けない場合は深追いせずに後回しにという姿勢を保ってください。
次にb1の読解の最中に行うべきことです。
これは本文中に空欄がある場合(確かSAPIXの7月の小6組み分けテストの説明的文章の後半に出ていたかと思います)に行うことなのですが、「本文中に出てくる空欄に関しては、選択肢を見る前に、読みながら見当をつけて空欄に合いそうな言葉を書いておく」というやり方です。
空欄に出会い、選択肢を見ると、似たような選択肢が並んでいるため、見比べているうちにわからなくなってしまうことがあります。
また、そうでないとしても、数秒でも迷うのであれば時間がもったいないです。
こういう事態を防ぐために、あらかじめ読んだ時点で類推して書いておくというのがb一で言いたいこと。
もちろんこれはいきなり行うことは不可能です。
ですので、日頃の演習の時から、類推して空欄に入りそうな語句を書いてみるという習慣をつけていくことが大切です。
最後にb2について。
抜き出し系の問題で時間がかかる1番の原因はここにあるかもしれません。
おそらく書き抜きを苦手としている子の思考回路は以下の通り。
1.設問を読む
2.指定文字数を確認
3.文字数の中で該当する内容を探す
この考え方の子は3の部分に大幅にタイムロスをする原因を抱えています。
前にも書きましたが、抜き出しの本文該当箇所は必ずしも傍線の近くにあるとは限りません。
しかし、その該当箇所にたどり着く根拠は傍線の付近に存在することが多いのです。
したがって本来は傍線と設問を見て、その付近にある根拠となる内容を把握した上で、設問で要求される文字数に合う同一表現を探しに行くという事になるのですが、3の段階で「文字数制限」というフィルタリングをしてしまっている場合、該当箇所にたどり着くための根拠となる部分を見落としてしまいます。
したがって、このタイプの子は先の思考過程を次のように直すことを意識することが有効です。
1.設問を読む
2.指定文字数を確認
3.一度文字数は意識せずに、書き抜きの要件を満たしそうな表現を探す
4文字数が合わない場合言い換えを探す
また、4に関しても心がけたいのは、パッと見つからなければ保留するということです。
書き抜きの箇所が今まで読んできた部分にあるとは限りません。
したがって、パッと見つからない場合は、ほしい言い換えを頭の片隅におきつつ、読み進めるという読解を行う必要が出てきます。
そして、可能性がある言葉が出てきたら、その全てに線を引いておき、全部解き終わったらその問題に戻って検討するという取り組み方にしてみてください。
繰り返しますが長文化傾向のある時間で「何度も読み返すこと」は命取りになります。
それを防ぐための姿勢が今書いたものなわけです。
c記述答案の完成に時間がとられる
文字数が増えすぎてしまったので、これに関しては簡単に触れたいと思います(それほどタイムロスの項目としては大きくないので)
記述答案で時間がかかりすぎてしまう子によくあるのはc1設問要求の把握が曖昧なために記述の方針が掴めない、c2完璧な解答を求めるが故に書き始められないという2パターンです。
c1に関しては設問から出題者の意図を正確に把握する事が必要なのですが、こちらに関しては僕がこれまでに書いてきた過去記事にある、入試問題の記述解説を見ていただけたらと思います。
何が聞きたくてその設問でその文字数なのか?
この思考を習慣化して下さい。
次にc2の完璧主義についてです。
案外あるのが、大きく外れてはいないはずだけど完答ではなさそうだから書けないという子です。
いうまでもなく多くの記述問題は部分点がついてします。
したがって、避けたいのは0点解答あるいは空欄で提出することです。
これを防ぐためにも、部分点狙いの解答でも書き切る癖をつける事が大切です。
では、どうすればよいのか?
これは模試(塾に通っているのなら添削)を数多く受ける中で部分点のもらえる解答の相場感を掴んでいく事が最も効果的です。
もう、bまでの内容ができているのであれば、思考途中でも積極的に不完全な解答を仕上げる練習をしてみてください。
③諸々の所作の時間
②に文字数を割きすぎてしまったのですが、僕が案外重視しているのがこの部分だったりします。
とにかく行動のひとつひとつに時間のロスがありすぎるというパターンです。
国語の問題に時間をもって取り組める子は、いい意味でせっかち。
行動ひとつひとつがテキパキとしています。
問題に向き合う時点で視線がブレないように姿勢を固定している、ペンを置かない、ページを捲るときにパッとめくる、消しゴムで消すときにゆっくりダラダラ何度も往復しない、事を書く時に一字一字止まって書かないetc...
こういう細かな動作の一つ一つに絶妙な速さの違いがあり、それが全体として数分の差になって表れるわけです。
(このタイムロスはこう書くと「そんな大袈裟な」と思われるかもしれませんが、実際に指導する側に立つとかなりはっきりと違いが分かります)
時間制約が厳しい国語において、この数分は非常に大切です。
所作に関しては国語(というか勉強)にとどまらず、日常生活の中でも意識して改善する事ができる分野ですので、常に自分の動作に関して意識を持つようにしてみて下さい。
というわけで、今回は「時間内に解けない」という相談を受けた時に僕が検証するチェック項目について、ざっとまとめてみました。
この中にもしひとつでも取り入れられそうなものがあれば実損してみて下さい。
もしそれが勉強の助けになれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
