
2010年代小説ベスト(国内編)
先日の2010年代ベスト小説の海外編(リンクはこちら)に続き、国内編になります。
2010年代に国内で新たに出版された小説を対象としていて、旧作は対象から除外しています。
今回も著しく偏ったラインナップですが色々な自分の「好き」を詰め込んだ小説リストです。
1位 舞城王太郎 『淵の王』
(新潮社)

著者は2000年代の代表作『ディスコ探偵水曜日』で行き着く所に行ってしまった感があるけど、本作は『ディスコ〜』を含む過去作品に比べ遥かにリーダビリティーが高い。
にもかかわらず、以前とテーマ自体は一向にぶれておらず、そこから更に一歩進もうとする意思を感じる。
三つの短編という形態(中島さおり、堀江果歩、中村悟堂の三人の物語)を取りつつも、物語としては明らかに一つの長編であり、其々の語り手が相互に(ストレートでない形で)関連しつつ、「暗い穴に抗って何かを成し遂げることができるのか?」という問いへの答えに少しずつ近づいていく。
その結果辿り着く地点をどう感じるかは読み手次第だけど、ラストの感動はここ10年の国内文学の中でもピカ一だと自分は思う。
2位 佐藤 正午 『鳩の撃退法』
(小学館)

無店舗型性風俗店「女優倶楽部」の送迎ドライバー(元売れっ子の直木賞作家の主人公)が巻き込まれる偽札事件と一家三人失踪事件、暗躍する裏社会の「あのひと」と古本ピーターパンの行く末等、薄気味悪い事件とユーモアな語り口の妙に魅せられる。
登場する女性キャラクター達も魅力的で素晴らしい。
自分がエンタメ小説に求めるものが殆ど揃っていて、この作品こそ直木賞*に相応しいと思うんだけど候補にすらなっていない。
※次作の『月の満ち欠け』で獲りました。
3位 奥泉光 『雪の階』
(中央公論新社)

本作では摩訶不思議な奥泉ワールドも控えめで筋立ても飛び抜けてオーソドックスだけど、語り(騙りにあらず)は技巧的に最高レベルじゃないか。
アリバイ崩しみたいな普通のミステリーになるのかと思いきや、当然そんなことはなく物語のオチはつくけど収束はしない。
時折挿入されるユーモラスな描写もいいし、何といっても笹宮惟佐子やそれを取り巻く登場人物のキャラが格別に好みなので続編を希望してる。
4位 今村 夏子 『こちらあみ子』
(筑摩書房)

今村夏子の名を世間に轟かせた一品。
その後の沈黙期間を経てコンスタントに作品を発表してくれるようになったけど(どれも傑作)、結局のところ今村夏子という人はこの作品で完成していたとも言える。
著者の巧妙な仕掛け(「信頼できない語り手」等)は本作から健在だけど、寧ろ注目したいのは同時収録の「ピクニック」。
後年、芥川賞を獲る『むらさきのスカートの女』の「わたし」と「彼女」なんて、まさに「ピクニック」における「ルミたち」(この複数形もミソ)と七瀬さんの物語の反復だ。(悪い意味でなく。)
5位 山尾悠子 『飛ぶ孔雀』
(文藝春秋)

これこそ幻想小説の究極形態。
最初は「評判程難解じゃないかも」などと余裕で読み始めたが、いつの間にか完全に迷子になっていた。
「飛ぶ孔雀」も「不燃性について」も自分には解説抜きには読み解けない。
と言うか解説あっても読み解けない。
でもそれで良い。
「飛ぶ孔雀」の最終章は本当に圧巻。
6位 津原 泰水 『11』
(河出書房新社)
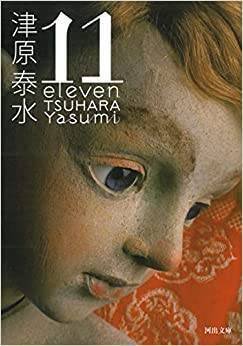
傑作と名高い「五色の船」から引きこまれ、その後もガツンとくる作品が続く。
時に幻想系、時にホラー系など様々なジャンルを越境し、「延長コード」、「微笑み面・改」、「琥珀みがき」、「手」、「キリノ」等どの作品も飽きさせない。(「キリノ」は「桐野夏生スペシャル」のために書かれたもの。)
この引き出しの多さとクオリティの高さは尋常じゃない。
7位 石川宗生 『半分世界』
(東京創元社)

吉田氏が電車を降りて自宅に向かう間で19329人となる「吉田同名」、縦に半分になった家で暮らし続ける一家と周囲の人を描く「半分世界」、全住民が白黒に分かれて300年間ゲームをし続ける「白黒ダービー全史」、荒野のバス停でバスを待ち続ける人々が寄り集まり、コミュニティを形成していく「バス停夜想曲、あるいはロッタリー999」と各作品を紹介するだけだと全く意味がわからないが、面白さは既に滲み出ている。
日本における異端系マジックリアリズム。
8位 小川一水 『天冥の標』シリーズ
(早川書房)

既に完結しているけど国内におけるエンタメ系SF小説の最高峰の一つと思っている。
第一巻『メニー・メニー・シープ』は残念(?)ながら2009年だけど、その後の『救世群』『アウレーリア一統』『機械じかけの子息たち』『羊と猿と百掬の銀河』『宿怨』『新世界ハーブC』『ジャイアント・アーク』『ヒトであるヒトとないヒトと』『青葉よ、豊かなれ』まで全てが10年代の作品だなんて信じられるだろうか?
9位 伴名練 『なめらかな世界と、その敵』
(早川書房)

どの作品もエモいし、痺れるし、クオリティー半端ない。
個人的好みは「ゼロ年代の臨界点」と「シンギュラリティ・ソヴィエト」だけど「美亜羽へ贈る拳銃」とか「ひかりより速く、ゆるやかに」の叙述の工夫はミステリ―好きにもささる。
これに「彼岸花」が収録されてたら百合SF傑作選としても完全体。
(既に充分に認知されてるとは言え)マスにももっと名が知れてしかるべきだが、変に映画化とかはしないでほしい。
10位 磯崎憲一郎 『赤の他人の瓜二つ』
(講談社)
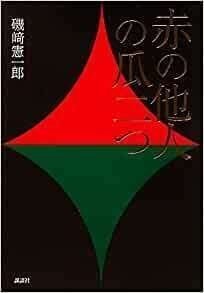
工場労働者の話がいつの間にかチョコレートの歴史だったり、コロンブスの話だったりにすり替わり、物語の主従関係や流れそっちのけで突っ走っていく。
あらすじの紹介さえ拒むようなフリーキーさ、ノーコードな展開により、読んでるうち、目の前の風景が知らない間に歪む感じ。
著者の「世紀の発見」もそうだけどスケールが大きいとか小さいとかじゃなくて、スケールが狂った作品。
11位 矢部嵩 『魔女の子供はやってこない』
(KADOKAWA)

なかなかグロイし、みんな吐くし、あっさり死ぬし「なんだこれは?」という感じだけど、歪ながらもどこか暖かさも感じる作風が癖になる。
痒い話や、友人の結婚式に出席する主婦に変装してあげる話など、個々のエピソードがどれもすごく良い。
因果応報的な終盤からの急展開で「地獄は来ない」なら「地獄に歩いていく」という発想の妙。
「魔法少女モノ」というジャンルを期待する向きにはオススメしないけど、安っぽいヒューマンドラマなんかじゃない分、自分が一番感動する類の小説。
12位 木下古栗 『いい女vs. いい女』
(講談社)

木下古栗が芥川賞獲ってないって正気か?
収録されてる三作とも良いけど、特に表題作のナンセンスさと計算された文章の緻密さのアンバランスぶりが凄い。
何が主題やら、誰が主人公やら、どうでも良いといった感じがたまらない。
Vネック耐久レースや全裸サークル等とふざけた挙句、最後はそうまとめるのか…という驚愕。(実際は一切まとまってないが。)
著者の『金を払うから素手で殴らせてくれないか?』も『グローバライズ』も当然傑作。
13位 小田雅久仁 『本にだって雄と雌があります』
(新潮社)

大阪の旧家で起こる本を巡る幸せな奇跡の物語。
舞台になってる土地柄のイメージ故か、(センチメンタルな部分もあるにはあるけど)基本的には底抜けに明るいマジックリアリズム小説になっている。
個々のエピソードや登場人物のセリフなどが一々くだらないけど面白く、存外、思慮に富んでいたりするから侮れない。
寡作な著者だけど本作の約10年後『残月記』でブレイクしたのも嬉しかった。
14位 小山田浩子 『工場』
(新潮社)

人工的で起伏の少ない物語(本当は起伏もあるし、カタルシスもある)は読む人によっては受け付けないかもしれないが、時代性に沿ったテーマを乾いた筆致で表現できる才能は素晴らしい。
読み方によって相当不穏ながら、登場人物達は必ずしも不幸であると感じているわけではない。(不幸とすら感じられない不穏な状況とも言えるわけだが。)
謎の工場=会社という閉じられた世界の特異なコードの中でブラックジョークにしか思えない虚無的な笑いが漂う表題作も、生と死、持つものと持たざるものの対比と共感の描き方が秀逸な「ディスカス忌」も、「むし」という生理的に嫌悪感を抱かせるキーワードを象徴的に使っている「いこぼれのむし」もレベルが高い。
15位 滝口悠生 『茄子の輝き』
(新潮社)

ある男性の二十代から三十代にかけてのおよそ十年程を綴った連作短編集。
各短編、何か特別なことが書いてあるわけでもないし、文脈も唐突に変わり、時も前後する。
「お茶の時間」 「わすれない顔」 「高田馬場の馬鹿」 「茄子の輝き」「街々、女たち」「今日の記念」といった何気ないエピソードのタイトルに因んだランダムな記憶。
どうやら一昨年公開の映画『花束みたいな恋をした』でキーアイテム(?)として登場するらしいのでどのような意味合いで使われたのか観たい。
16位 柴崎友香 『パノララ』
(講談社)

居候一家とのほんわかした日常生活、もしくは恋愛物と思わせつつ、唐突に出てくるループとかワープとかのSF(少し不思議)的な設定。
でもそうしたSF的設定がエンタメ方向に向かうことは決してない。
一見普通の人間関係(居候家族との疑似的家族関係、ワークショップ、母親との家族関係等)が上記のヘンテコな設定と共に立ち現れることで、随所に歪つで不穏な空気が漂う日常/非日常物の傑作。
17位 高田大介 『図書館の魔女』
(講談社)

自ら声を発することの出来ぬ「高い塔」の魔女マツリカと、彼のお付きとして遣わされた曰くありげな少年キリヒトを中心に描かれる国内最高峰のファンタジーシリーズ。(メフィスト賞受賞作品ぽくない。)
魔女が主役のファンタジーとは言え、派手な魔法合戦や魔物が出てくるわけではなく、声を持たぬマツリカを中心とした渉外事(外交)が物語全編の核となるのが面白い。
キリンとか双子座とかキャラも皆魅力的。
18位 円城塔 『道化師と蝶』
(講談社)

『Self-Reference ENGINE』のイメージから、ここまで別ベクトル(高度な幻想小説)書けるのかと当時は驚いた。
ナボコフへの傾倒もうかがわせる表題作(「無活用ラテン語」って冗談かと思ったら、本当にあるらしい)も「松ノ枝の記」(ザゼツキー症例って本当にあるのかと思ったら、こっちはない?)も良い。
19位 宮内悠介 『ヨハネスブルグの天使たち』
(早川書房)

近未来の世界5都市を舞台にした連作短編集。
夕立のように高層ビルから降り落ちる美少女ロボット(初音ミクにボディを与えたような存在)が作品の象徴であり、まさに2010年代のカルチャーを体現しているかのような佇まいを持つ作品。
著者の作品は他にも『盤上の夜』や『彼女がエスパーだったころ』もエモさ含めてとても好き。
20位 赤野工作 『ザ・ビデオ・ゲーム・ウィズ・ノーネーム』
(KADOKAWA)

2115年4月に開設されたレトロゲームレビューサイト「ザ・ビデオ・ゲーム・ウィズ・ノーネーム」において架空のゲーム(基本的には低評価を受けることになるゲーム)の数々の顛末が語られていく。
こういうアイディアは過去の文学にもあるんだけど作者はそれらを踏襲しているというより単純にゲーム愛から書いてるんだと思う。
既に2023年だから仮想現実「キミにキュン!人工ヒメゴコロ」は1年前にリリースされてることになる。
実はレビューの間に出てくる雑記が肝でもある(不)真面目なSF。
※著者は個人的に大好きな一人用人狼ゲーム『グノーシア』に協力スタッフとしてクレジットされている(が別に開発に携わってるわけではないらしい)。

番外 岸本佐知子編 『変愛小説集 日本作家編』
(講談社)

各著者の単行本に収録されている作品も含むけど、これだけは番外としてどうしても選びたかった。
なんと言っても、川上弘美、多和田葉子、本谷有希子、村田沙耶香、木下古栗、小池昌代、星野智幸、津島佑子、吉田知子、深堀骨、安藤桃子、吉田篤弘の作品が一辺に読めるのだよ。(流石、編者が岸本佐知子というだけある。)
日本が誇る作家陣の超贅沢な変愛小説集。
まとめ
次点はいっぱいあるけど以下あたりでしょうか。
月村了衛『機龍警察』シリーズ
上田岳弘 『太陽・惑星』
多和田葉子『雲をつかむ話』
横田創『落とし物』
野﨑まど『know』
高山羽根子『オブジェクタム 』
法月綸太郎『ノックス・マシン』
保坂和志『未明の闘争』
佐藤哲也『シンドローム』
-END-
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
