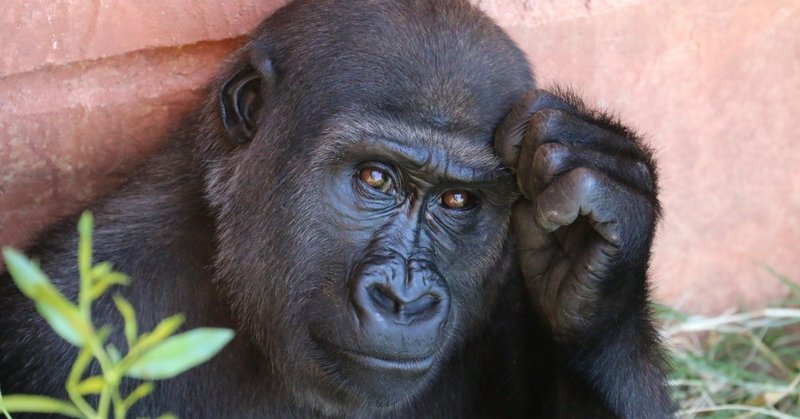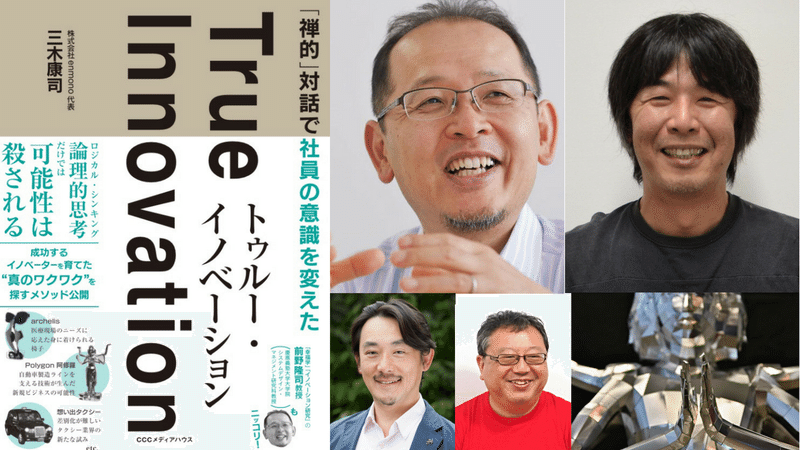
2018年6月に出版した「トゥルー・イノベーション」で記述しているトゥルー・イノベーションという概念について、本では語りきれない部分など投稿していこうと思います。
- 運営しているクリエイター
2019年8月の記事一覧

「IoTとイノベーションの罠 」 〜なぜ企業はIoT市場でレッドオーシャン祭りに突っ込むのか?〜(前編)(2016-09-17投稿)
※過去のブログ投稿を転載しております。情報はその当時のものになりますこと、ご了承ください。 『禅に学ぶイノベーションのあり方「脚下照顧」(きゃっかしょうこ) 〜イノベーションは外部ではなく、自分の足元にあり!〜』に対して反響が大きかったので、その続編記事を書こうと思います。 さて、最近はイノベーションとIoTという言葉が跋扈(ばっこ)しています。そのIoT市場を観察することで、企業が安易に求めるイノベーションの罠と、その結果陥るレッドオーシャンの危機について自分なりの考察

「IoTとイノベーションの罠 」 〜なぜ企業はIoT市場でレッドオーシャン祭りに突っ込むのか?〜(後編)(2016-09-21投稿)
※過去のブログ投稿を転載しております。情報はその当時のものになりますこと、ご了承ください。 前編より さて、「IoTのイノベーションの罠(前篇)」から続いて、論を進めたいとおもいます。さて、どうして企業は「Me-tooイノベーション」に陥ってしまうのでしょうか?その大きな原因は、企業の意思決定プロセスと予算にあります。 意思決定プロセスと予算確保のため 組織で運営している企業の中では、イノベーションを起こすためには予算確保がマストです。サラリーマンであれば、何をするのも