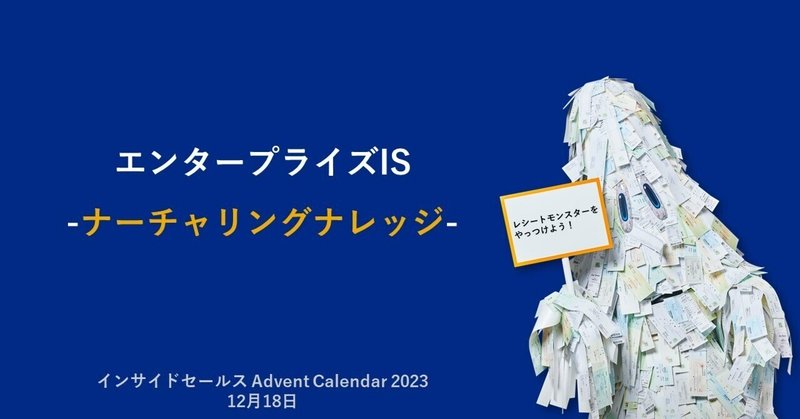
エンタープライズISのナーチャリングナレッジ
【インサイドセールス Advent Calendar 2023】の18日目の投稿記事です。
明日はISトレーナーのしぶさんの記事が公開予定です!
はじめに
自己紹介
こんにちは、コンカーでインサイドセールスマネージャーをしている山崎です。初めてのNoteの投稿で緊張しておりますが、少しでもお役に立てるよう書きました!今回初投稿の機会を作ってくださった茂野さん、ありがとうございます!
私は2019年4月にコンカーに入社し、初めてインサイドセールス(以降、IS)に携わりました。担当領域は以下となり、エンタープライズ領域の経験は4年半ですが、中堅企業、地方自治体、大学法人、既にコンカーを利用いただいているお客様に至るまで幅広い領域を担当し、20年1月にはリーダー、20年10月からマネージャーを務めています。
担当領域の変遷
・2019.4 - 12 東日本 大手製造業の企業様
※CRMの過去ログを読み漁り、商談同行し、早期にキャッチアップ
・2020.1 - 12 東日本 大手製造業の企業様、自治体様
※コロナ禍でアプローチ手法の大幅な見直しを実施、マネージャー就任
・2021.1 - 12 大手企業様、自治体様、大学法人様、既存のお客様
※デジタルセリングのモデルをグループで確立
・2022.1 - 12 大手企業様、自治体様、大学法人様、既存のお客様
※エンタープライズIS向けのトレーニング資料を作成・展開(30分 * 10回)
・2023.1 - 10 大手・中堅企業様、自治体様、大学法人様、既存のお客様
※中堅グループへ異動、上司が育休のため1-10月まで代行で全体を統括
・2023.10 - 12 中堅企業様、自治体様、大学法人様
※上司の復職に伴い大手企業様、既存のお客様の担当から外れる
本記事のテーマ
先述の通り私は入社以来、色々な領域を担当しましたが特に大手企業様を長く担当していましたので今回は、『エンタープライズISのナーチャリングナレッジ』としました。なぜナーチャリングなのか?、それは大手企業様にご利用いただく上では、アプローチ~ご提案~採用に至るまでには数年かかることも多くあり、かつ自身が試行錯誤しながらも数年間取り組んできた内容であるためにもっとも解像度高く書けるテーマだと考えたからです。
そのため、少しでも参考になる部分があれば幸いです。
テーマの前提
ISにおいては、取り扱う商材、自社商材のフェーズ、対象のお客様層(企業規模、提案先部門やお客様の役職)等に応じて自社に取り入れられる、または参考になる範囲が異なると考えるため、以下の環境の中で経験した内容が前提の記事となっています。
自社商材は、BtoB向けのホリゾンタルSaaS、具体的には経費精算・請求書管理・出張管理のクラウドサービス
自社商材のフェーズは、成長期~成熟期(私の見解)
提案先部門は複数部門にまたがり、また役職は担当者~役員までと広い
Must Haveではなく、Nice to Haveの商材(私の見解で大手企業様においては既に自社システム、いずれかのサービスを利用されているため)
エンタープライズISのナーチャリング
エンタープライズにおけるお客様へのナーチャリングの意味合い
私個人としては、以下の3つと思っています。お客様がいきなり検討を始めることはほぼないため、いつか訪れるタイミングのためにお客様の良き相談相手であり続けることが大事だと思います。相談相手というとおこがましいですがお客様から『いつも良い連絡をくれる人』と思ってもらえる存在になることが大切だと考えています。
1)関係性の維持、強化
2)信頼の醸成
3)提案に向けた機運を作る
最も大切だと思うこと
お客様に新しい”気づき”を与え続けられるか。
私は、この1点が最も大事だと思っています。現在、情報収集はいかようにもできます。メディア・書籍、各種イベント・ウェビナー、生成AI、各ベンダー、企業内の勉強会、SNS等など、様々な手段があります。その中で、〇〇だったらコンカーさんに聞きたい、と思ってもらえ続けるか。
最も簡単に今まで"気づき"を与えられていたかを確認する方法があります。それは、お客様に継続して打ち合わせの時間を取っていただけるか、です。エンタープライズISでは、一定の頻度で同じお客様にアプローチされると思います。その際にお時間がもらえるかどうか。もしもらえていないようでしたら一度新しい"気づき"を与えられているかどうかを見直してみてください。
あえて連絡しないというこだわり
エンタープライズISは外勤営業と連携して動くことが多いです。時にはお客様にとって有益ではないと判断出来る場合はあえてご連絡しない、という選択をします。1度でも微妙な連絡をしてしまうとお客様には、『わざわざ時間を割いてまで聞く価値はない』という印象が強く残ってしまいます。
外勤営業とは下記のようなコミュニケーションをしています。
※諸々省いてシンプルな例で記載
外勤営業:〇〇さまにご連絡しよう
IS:〇〇さまには3ヶ月前にお会いしていますよね、今このタイミングではアップデートできる情報も少ないため、〇〇さまにとって有益な時間にならないと思います。3ヶ月後であればいくつかニュースも重なるので良いと思いますがどうでしょうか。
アプローチのイメージ図
それではここから具体的なアプローチの流れを説明します。下記は私自身が経験してきた内容に基づくアプローチの流れです。エンタープライズのため、起点はアカウントプランです。(本記事ではテーマから外れるため触れませんがこれも重要ですので別の機会に記載できればと思います)この流れに基づいてポイントをお伝えしていきます。

Why you nowの構成
『なぜ今、あなたに連絡したのか』は、長年ナーチャリングでご連絡しているとつい忘れがちになってしまうことがありますので、連絡する際には改めて確認するようにしています。コンカーでは年度ごとに担当領域が変わることもあるため、新しく担当になった際には必ず自分で考えます。前任者の考えを聞くことも大事ですが、より自分自身に腹落ちさせる上では自分の頭で考えることが一番です。その壁打ち用に前任者の意見を聞くのが良いと思います。
全て埋めなければいけないということではなく、状況によってはないものもあると思います。必要なのは何があって、何がないのかを理解していることにあると思っています。
Why nowが個人的にはいつも考えるのに苦労します。短時間であるなしを判断する上では、顧客・自社・市場の視点が切り口としては考えやすいです。顧客のIR情報を確認する、自社のニュースや最新事例などを確認します。一方で、市場は範囲が広いため、短時間で調べるという点では、SPEEDA、FORCAS Sales等の情報ツールを活用して、PESTの変化、今後の業界トレンドやテーマ、ニュースが自社の提供する商材に直接的・間接的に関連するかどうかを考えています。

NHKの事実確認・仮説立て
NHKの事実確認とは、お客様のN:認識 H:反応 K:関心 を押さえるということです。NHKの考え方は、グロービスのクリティカルシンキングの講座で知ってから取り入れています。
過去にお会いした、やり取りしたことがあるお客様にご連絡する場合、過去の状況を踏まえることは必須条件です。踏まえるべきは以下2点です。
・過去の商談状況、やり取り
・NHKの事実確認
長年アプローチをしている場合、お客様からは、『この会社は担当者がコロコロ変わる』と思われがちです。現在の担当者が過去の情報をしっかり把握し、NHKを押さえてコミュニケーション出来れば、お客様にとって好感の持てる(少なくともストレスのない)連絡になります。
NHKの情報があれば、仮設立てもよりスムーズに行え、お客様に的確にアプローチを行うことが出来ます。一方で難しいのはNHKの情報を記録し続けること、引き継ぐことです。そのため、CRMのオペレーションをしっかり定め、浸透させることが大切です。
仮説立ては、Why you nowの構成をもとにNHKの内容を通じて、焦点を当てる項目の絞り込み、そして伝えるべき内容(伝える必要のない内容は排除)、重要なポイント、伝え方を練り上げます。

理解のしやすさの向上/納得感の醸成
CRECという伝え方の型で連絡する内容を整理するようにしています。
『Why you nowの構成』、『NHKの事実確認・仮説立て』を経て構成した内容をCRECに当てはめることで、お客様が理解しやすい伝え方となります。
お客様が理解しにくいとはどのような時か、を考えると、話を聞きながら『本当にそうなのか?』『それってどのようなロジックなのか?』『何か腑に落ちない(納得感がない)』等、話を聞きながら自然と疑問が湧いてくる状態だと思っています。そのような状況をなるべく回避するために、CRECで整理することをオススメします。抜け漏れがないかのチェックにも役立ちます。
また、納得感の醸成においては、Reason(理由)、Example(具体例)が『たしかに言われてみれば』『そうゆうことなら』『それは参考になりそう・聞いてみたい』等、お客様が多忙な中で時間を取る程の価値があるのかを判断する材料となりますのでここを徹底的に考え抜くことが大事です。

アプローチ
分業制だからといって常にISから連絡するということが良いとは限りません。特にナーチャリングにおいては、相手が役員の方であれば面識のある自社の役職者から連絡したほうが良いケースもあります。状況に合わせてお客様に最も響くアプローチを考えることが大事だと思っています。
お客様にベストなアプローチをするため、お客様、タイミング、自社の要素で外勤営業と認識を合わせます。その際に意識しているのが以下2点です。
・お客様にとって失礼のない連絡方法か
・お客様にとってもっとも受け入れやすい連絡方法は何か
中長期的に関係性を築くためにISではありますが商談同席・同行をよく行っています。やはり実際に一度対面で会うというアクションをすることでその後の連絡がスムーズに出来るようになることがしばしばあります。また、お客様の状況を正しく、深く理解することにも繋がります。

最後は、伝える内容と表現・言葉を磨くことです。以下の図はカッツモデルの図を参考に職位に応じてどのような関心事項がどの程度ありそうかをイメージしやすいように作成したものです(あくまで想定です)。
お客様の役職に応じて関心事項が異なるため、役職や立場に応じて適切なコミュニケーションのあり方を考えています。例えば役員の方に細かい業務課題のことをお話してピンとこない(中には業務に精通されている方もおり、一概には言えないですが)といった状況を避けることができます。

よく聞かれる質問にスクリプトは作成したほうが良いのか?があります。
正解はありませんが、私は何を目的にしているのか、を意識することが大事だと思います。例えば今回のエンタープライズISにおけるナーチャリングであれば以下の3点を確実に行えるように私はスクリプトを作成しています。
・伝えたいことを確実に伝えきる
・状況に応じて短く要約して伝える(会話出来る時間が短い場合)
・失敗する可能性を最小限にさせる
エンタープライズISは、良いコンバージョンレートを追うことも大事だとは思いますが個人的には常に勝負球を投げて、10戦10勝を目指す存在でありたいと思っています。
おわりに
~お客様への思い、ISは自社の成長エンジン~
最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも参考になった部分があれば嬉しいです。
最後になりますが、ISの業務は熱意も大事だと思っています。
エンタープライズに長年携わっているとロジックよりも最後はこちらの思いや熱意がお客様に伝わり、打ち合わせの機会をいただけることも実際には多くあります。10戦10勝という表現を用いましたが機械的なロジックだけでは達成出来ません。お客様にとって常に良い連絡をするための努力と自社サービスが社会に果たす役割や利益、良さを確実に伝える熱意を常に持ち続けることが重要だと思います。
ISを取り巻く環境は日々変化しています。テクノロジーの進化も早く、情報収集から実際にお客様へ連絡し、やり取りする部分までの一つの業務プロセスを切り取ってみても多くのツールを活用する余地がありますし、実際に取り入れてその効果を実感したり、改善するプロセスを回したり、はたまた業務そのものを変えたりと、多くの試行錯誤を通じて所属する企業の成長を牽引する面白い職種だと思います。コンカーのIS部門は長年企業の成長を牽引し続けていることもあり、他部門からは成長エンジンと呼ばれています。
最近はありがたいことに、他社のISの方々と勉強会をさせて頂く機会が増えています。エンタープライズ向けの勉強会はもちろんのこと、公共領域、既存のお客様向けのISはまだ少ないようで興味を持っていただいています。毎回思いますが意見交換やディスカッションの中で参考になること、気づきを得ることはもちろん多く、そして何より多くの刺激を受けて、『まだまだやれることはある!』とモチベーションが上がります。
今後も各社のISの方々と繋がりたいのでぜひ勉強会やカジュアルな座談会など、お声掛けいただけたら嬉しいです!(私からもお声掛けさせていただきます!)
もしコンカーのIS組織や製品に興味を持っていただいた方がいましたらぜひお気軽にご連絡ください。DMまたはHPよりご連絡いただけたら幸いです。
※50名程収容できるセミナールームがありますので勉強会で使えます!
https://www.concur.co.jp/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
