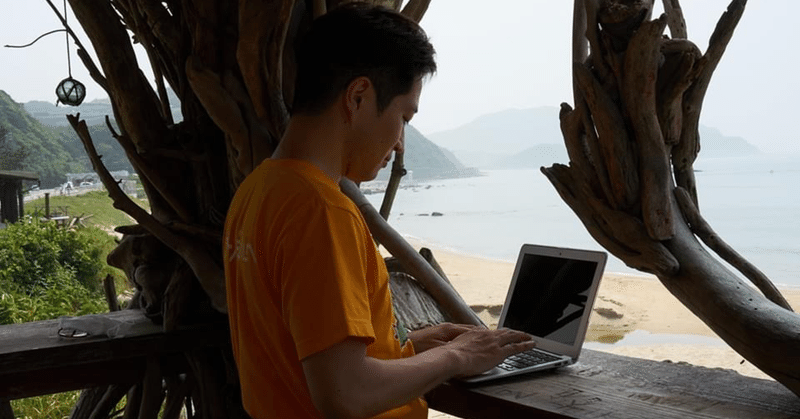
バズり続ける都市「福岡」に音楽スクールの社長が思うこと
こんにちは。オトノタビビトえびさわです。
たった一人で始めた音楽スクール「Music Schoolオトノミチシルベ」も、気づけば10周年を迎えました。お陰様でこの10周年で事業規模はみるみる大きくなり、4年ほど前から地方進出にも注力しています。日本はそれぞれ個性の異なる『地方』の集まりであり、音楽スクールのあり方や楽器、音楽の楽しみ方も地域によって様々で、その『個性』を磨き上げていく事で日本はもっと輝けるはずとひしひしと感じています。
そんな信念のもと各地を訪れる中で、自分を強烈に惹きつけたのが九州最大の都市である福岡県福岡市。今では「東京で一番福岡を愛する音楽スクール」というキャッチコピーをひっさげ毎月福岡を訪問。現地の先生や生徒さんと交流を深めながら福岡エリアの勢力拡大を狙っています。
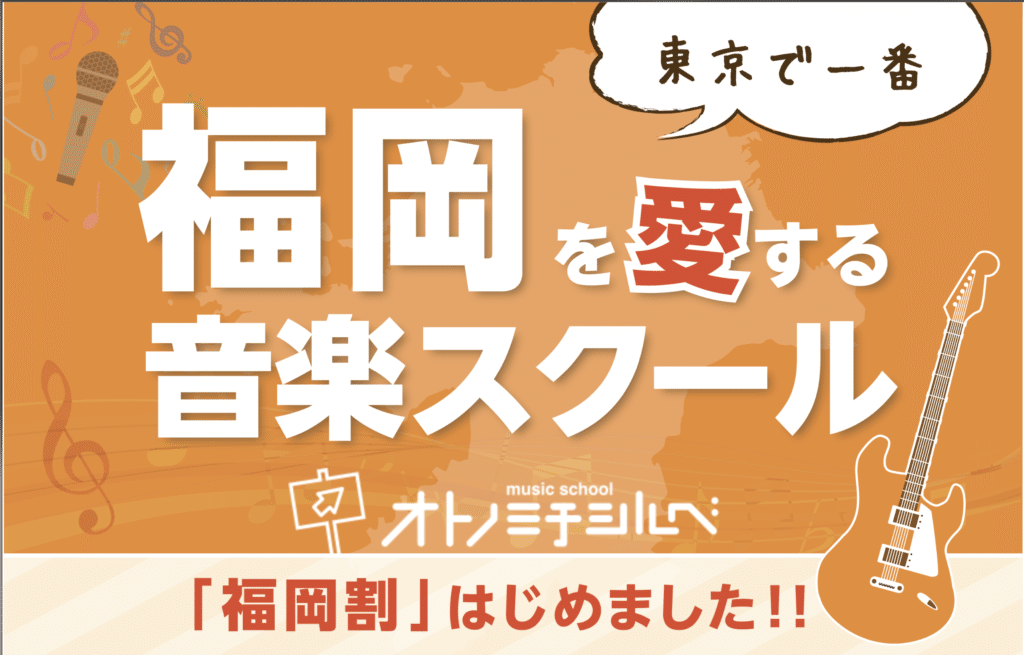
↑オトノミチシルベでは福岡市民にお得な「福岡割」キャンペーンを開催中!
人口158万人、都市の規模としては東京、大阪、愛知に続く4番手でありながらここまで人を惹きつける理由はどこにあるのか?自分の足と目で稼いだ体験と、参考文献から得た情報を元に音楽スクールの社長目線で紐解いていきたいと思います。福岡にお住まいの方、福岡に興味をお持ちの方、偶然このnoteを訪れた方にも楽しんで頂ければ幸いです!
データで見る福岡市
まずはデータで福岡市がどれだけイケているのかを見てみましょう。
それぞれデータをとった時期もバラバラだし「若者」が具体的に何歳以下のことを指しているのかなど詳細は記載しませんが、一つの基準としては2010年に高嶋宗一郎市長(2020年時点で現職)が36歳の若さで就任以降にもたらされた結果という事でご理解頂ければと。
『人口増加率』→政令市で1位
『若者の数』→政令市で1位
『出生率』→全国2位
『地価上昇率』→東京、大阪の倍
『国際会議の開催件数』→ 政令指定都市で2位
『税収』→政令指定都市で唯一6年連続過去最高を更新中
『成長可能性都市ランキング』→1位(野村総研調べ)
『世界で最も住みやすい都市ランキング』→7位(イギリスのグローバル誌)
『開業率』→21都市で1位
『都心から国際空港までのアクセス時間』→アジア13都市で一位 世界で7位
『世界の都市総合力ランキング』→「通勤通学の利便性」部門で世界44都市中1位
ご覧の通り、現在日本は福岡無双と言える状態です。あと定性的な魅力で言うとご飯美味しい、家賃安い、博多美(略)と、枚挙に遑がありません。

↑春吉にある人気店「元祖博多めんたい重」近影です
福岡市の魅力を爆発させる3つの距離
福岡で、もしくは福岡の人と仕事をしていて大きくギャップを感じるのは、人と人、人と企業、企業同士の距離の近さと交流の多さです。一人と友達になることで五人と知り合いになれるようなスピード感があります。その理由はどこにあるのか、僕なりに考えてみた結果が以下の「三つの距離」です。
①イノベーションとコミュニケーションの距離
②仕事と遊びの距離
③需要と供給の距離
①イノベーションとコミュニケーションの距離
福岡市内には、スタートアップ企業を中心に人脈や交流を広げるために用意された場がいくつもあります。代表的なものは2019年にリニューアルオープンした「Fukuoka Grouth Next」(通称FGN)と呼ばれるスタートアップ支援施設です。「最古の建物で最先端のビジネスを支える」というコンセプトのもと、廃校となった140年の歴史を持つ旧大名小学校を活用し2017年に設立。民間と行政が一体となり育成プログラムの提供やグローバルアクセラレーターとの連携、資金調達機会の創出をサポートしています。また日本は学校単位で街づくりをしているので、廃校になるとコミュ二ティがなくなり人口減少に繋がる。廃校となった校舎を有効活用することは、コミュニティの維持や発展をさせるという面でも大きな意味を持つのです。
そしてここで触れておきたいのが、『FGN』施設内にある「awabar fukuoka」の存在。
世にも珍しい泡専門スタンディングバーで、起業家、一般企業の会社員、スタートアップ関係者などがビジネスに対する熱い思いを日々語らいます。このようなコミュニケーションの場を創業支援機能と位置づけて設置し、スタートアップを集積することで様々なビジネスプランが可視化され、それによりまた新たな交流が生まれるという循環を生みます。イノベーションとコミュニケーションの距離を近づけるけることで、思いが形になりやすくなる。それが今後「福岡に行けば新しいビジネスが起こせる」という期待を集める事に繋がるのではないでしょうか?
②仕事と遊びの距離
福岡をはじめとした世界のイノベーション都市の共通点には「コンパクトであること」が挙げられます。中央集権から地方分権への流れの中で、街づくりもより合理的に「規模の論理」より「距離の論理」をベースに行っていくようになるでしょう。
上のデータにも記載しましたが、「コンパクトシティ 」の名のとおり、福岡市は都市機能が車で30分圏内に集約されています。なんと福岡空港から博多駅までは電車で2駅!それでいて1時間もあれば糸島の玄界灘を眼前にカフェ(おススメはSUNSET)やライブ(SUNSETライブ)を楽しんだり、柳川で鰻の蒸籠蒸しに舌鼓を売ったり川下りに興じたりとローカルな魅力も堪能できます。
『パッと仕事してパッと遊びに行ける』環境は最強。福岡市民は大人でも終電気にせず遊びます。皆家が近いから(笑)
ワークライフバランス、職住近接などという言葉が注目を浴びるようになった昨今、通勤のストレスなんてどこ吹く風というライフスタイルを送っているのが福岡市民です。
ちなみに上述の「SUNSET」は、糸島の海をこよなる愛するサーファーの林憲治さんによって作られたオーシャンビューのカフェ。元々は林さんの「いつでもサーフィンができたらいいのに」というシンプルな想いから生まれたお店で、「自然しかない田舎」を「自然があるオシャレな場所」という価値変換のブランディングが見事に奏効し、今では連日観光客で溢れかえっています。

↑糸島でリモートワークやってみた。これで家賃が払えなくなっても安心!
③需要と供給の距離
情報もサービスも均一化した今、これからの街づくりで求められるのは住民の要望にオーダーメイドで応えられるかどうかということ。年齢や性別分布などのデータはあまり意味を持たなくなるので、「人」を起点にサービスを考え都市機能に加えていかなければならない。
福岡はもともと官民が一体となり街づくりに取り組んできたという背景があるので、民間と行政それぞれが過度に負担を強いられる事なく、お互いの長所を生かし短所をフォローした、住民にとっても観光客にとっても魅力的な街づくりが可能なのです。これは定住人口、関係人口、交流人口の全てを増加させていくために大きな武器となっていると感じています。
また東京、大阪などの都市部は今や消費地になってしまい、世界中から色んなモノが集まってくるという利点がある反面、それを「消費するだけ」になってしまっています。つまりそれは都市圏が持つ「ここにしかないモノ」という魅力を十分に発揮できていない状態を表しています。
その点で福岡は需要と供給の距離が近いことから、地産地消を実現し、都市圏内での経済を回し足りないものを近隣からカバーする=経済的に自立した都市となることに成功しています。(2020年 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下、福岡市の高島宗一郎市長は県の対応に先駆けて市独自の休業補償を表明しその内容が話題となりました。これも福岡市が経済的に自立した都市である事の紛れもない証拠です。)
最後に
いかがでしたでしょうか?
音楽スクールの社長目線で書くと言っておきながら、音楽の話をほぼする事なく終わってしまいましたが(汗)福岡の魅力の一部をお伝えできたなら幸いです。福岡に遊びに来られる際は(?)えびさわまで一声かけて頂ければ美味しいお店、観光スポット、アテンドさせて頂きます!クレームは受付けませんが(笑)
次回こそ、音楽スクール目線で福岡戦略について解説が出来ればなと思います。
参考文献
頂いたサポートはオトノタビビトの活動資金に充てさせて頂きます!
