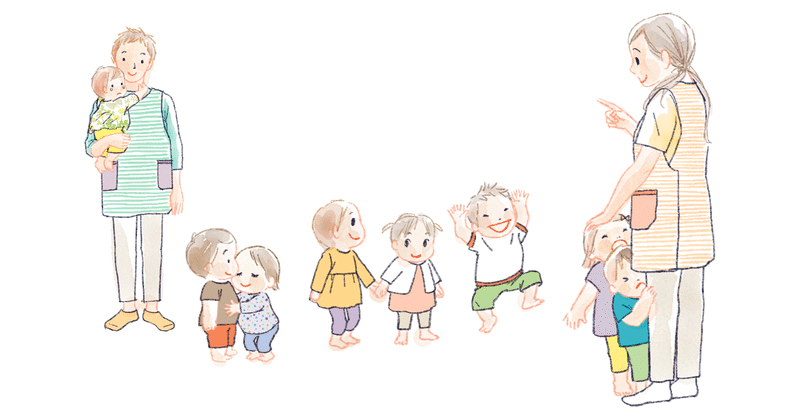
パパママ必読「保育施設の選び方」
こんにちは。ゆーママです。
ママが働く上で1番最初に直面する問題。そうです。
最大の関心事は預け先確保 問題!
パパママが保育園を選ぶ際に知っていて欲しい事を実体験をもとに保育士とSW(相談員)の目線を加えてお伝えします。
最初にお伝えしたいことは、
「保育園に落ちたり、希望の園に入れなくても大丈夫!!」
とはいっても、幼児持ちの子育て世代はよくご存知だと思いますが、この保育園選びって地味に時間がかかるし、待機児童もいて、みんながみんな希望の園に入れるわけではありません。子どもを預けるための条件がイロイロあって複雑だからというのもありますよね?!それに、かかるお金っていくらかかるの?保育料って年齢によって違うの?世帯収入によって違うの?無償化??えっ??でも幼稚園は??制服代は??一体いくらかかるの? ごにょごにょ。。。
保育園など預け先の種類
実際に認可保育園、認可外保育園、小規模保育園、幼稚園、認定こども園の違いって何??調べれば調べるほど、どのように選択すればいいのか混乱してくると思います。
正直に言います。このことは実は、保育士でも幼稚園教諭でもしっかりと理解している人は少ないです(笑) 結論、多くの園の中から実はこんな選び方がベストですみたいな方法もありません。ないんかい!!と突っ込みたくなりますが。。。
とは言え
違いと特徴は ↓↓↓↓↓↓↓↓こちら
↑↑↑↑↑↑↑↑↑こちらのサイトがゆるママ的に一番読みやすくまとまっていました。
保育園探しの具体策
保育コンシェルジュにとりあえず相談します。
保育園などに預けたい保護者の方のために自治体に設置してある相談専門窓口で対応してくださる方のことを「保育コンシェルジュ」と言います。全く持って情報知識が無く、子育て自体どうしたら良いのかという不安事態が明確になっていない方でも相談に乗ってくれます。
例えば、お住いの自治体名 ”○○市 保育コンシェルジュ 相談” と検索すると窓口電話番号がすぐに見つかります。主に保育施設や保育サービスの利用について相談できます。
ただし、すべての自治体が保育コンシェルジュによる相談サービスを提供しているわけではないです。*自治体に保育に関する相談をしたい旨を伝えれば保育コンシェルジュほど丁寧ではありませんが対応はしてくれます。
さてさて、相談できても実際に申請して選ぶのは保護者です。
ここで本題、いったいどうやって選んでいけばいいの??
子どもを預けるということとは?
2021年ももう時期終わります。待機児童、待機児童と叫ばれてる昨今ですが
実は、認可保育園であっても定員割れしている保育園は少なく有りません。このことは地方に限らず同じことが言えます。
ただ、待機児童が解消されたわけではありません。希望の園に入ることができていないか、実はもっとゆっくり子どもと過ごしたいのがママの本音で入園のタイミングを伺っているママもいます。そして、保育園に入れない訳ではなく、入りたい園を保護者が選ぶ時代になってきています。そして、保育コンシェルジュのようなサービスが必要とされているように、待機児童解消よりも、利用者と園のマッチングがうまく出来てない方が問題のように感じます。基本的には認可保育園の場合は保育を必要とする度合、つまり認定基準点が高い家庭の子から優先されるシステムなので希望通り(マッチング)いかないのはこのことが理由の一つです。
では、預け先を選ぶにはどうしたらよいの??
答え
「一度入園出来ても保活を終わりにしない」
ということです。
なぜかというと
子どもは成長発達の著しさや特性や思考が大きく変化します。
加えて、乳幼児の子育て世代は環境、ライフステージの変化も目まぐるしいからです。
例えば1歳児の時に入園した園が3歳になっても最適な園なのかどうかは子どもによって家庭によって違うという事です。
子どもと生活環境=保護者の変化に合わせてフレキシブルに転園することは大事な選択肢の一つです。一つの園に入園できないとしても、落胆することではなく、他の選択肢を試すことで最適な園が見つかっていくという考え方ができます。
引っ越しをすることもあるでしょうでし、駅近で通いやすい園で良かったなんて思っていると、幼児クラスになって体を動かしたいのに、園庭がなくずっと座学が中心の保育活動の園であったりすることは多くあります。転園するのはイロイロ面倒なので、体操教室に通うことにしたという保護者の声もよく聞きます。それも一つの選択肢の一つだと思いますし、子どもに合わせて、家庭の変化に合わせてフレキシブルに転園することも選択肢の一つというわけなのです。
なので、入園できて良かったけど、、、、入園してみて、保育方針が合わないとか、園生活が不透明だ、逆に保護者負担が大き過ぎるなんてことはよくあります。そして、私自身、どうしたらよいのか悩んだママの一人でもあります。そして、実際に4つの園にお世話になりました。
利用した保育施設の実際 体験談
以下に紹介するのが私自身が利用した保育施設です。
①病院内の託児施設→②公立認可保育園→③私立認可保育園(兄妹2人同じ園)→④私立認可保育園
と、現在は4歳年少1人を預けている先は4つめの私立認可保育園となります。
①のいわゆる院内保育所の
メリット
保活しないで入ることができました。私は看護師や医療職ではありませんが病院系列の施設での事務職で入職です。従業員であれば調理員でも介護職でも誰でも利用できます。院内保育や大企業はこのような託児がある場合もあります。厳密にいうと企業内保育施設とは違います。この辺も制度上分かりにくいポイントですね。
デメリット
保育方針や保育内容はあまり充実していませんが、2歳まで(1歳児クラス)までは保育内容は認可も認可外も保育内容はあまり変わらない気がします。感想としては集団保育ではなかったので上の子にとっては刺激が足りなかったかもしれません。発達が気になるお子さんにとっては、見落とされる危険性もあるかも。。。一概には言えませんが、個人的な感想です。
②から③についての転園に関してはさまざまな家庭内状況が変化したので転園は免れませんでした。③の私立認可保育園は立地的に条件は悪かったのですが定員割れの第4希望の園でしたが、第一子、第二子そろって同じ園に登園できたので結果的には良かったのかも知れません。なので兄弟一緒に同じ園にしたいのであれば、未就学時期が重なる時期だけでも、入所基準点でビハインドがあればあえて定員割れの保育所を希望して入所するのも一つの方法です。3つ目の園は園庭がとても狭かったのがデメリットでした。第一子は年少の夏から卒園まで過ごしました。公園にお散歩にいくなど園独自の努力はされていましたが、第二子は特に体を動かすことが大好きだったので、第二子に合うような他の園の募集状況を見ながら転園のタイミングを伺っていました。
④結果的に上の子が卒園のタイミングと第二子の入りたい園の募集時期が重なり無事に下の子は入りたい園に入れました。さらに自宅近くになり立地的にも好条件になりました。つらつらと個人的な転園の実体験をお話しました。
結論
入園してみない事にはわからない事と、最初から保活がうまくいくなんてことはないんですね。一度どこか入園してみて、モヤモヤ感があったら悩まずに、まず相談ですね。そのうえで、タイミング見つけて環境を変えてみると違った景色が見えてくるもんだなあと思いました。私のとってのデメリットは誰かにとってのメリットでもある可能性があります。1番言いたい事は一度の保活失敗で落胆することはありませんとお伝えしたいです。これが、ゆるママ的保育施設の選び方です。
皆さんの保活が上手く行く事を願っております!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
