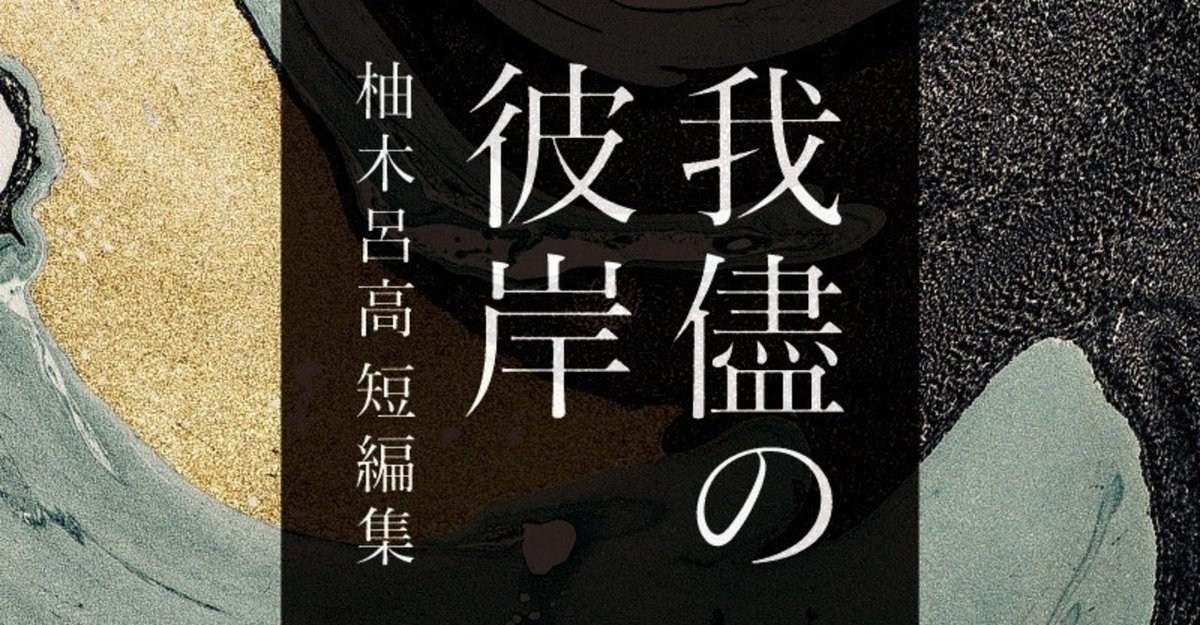
シミュラクルの糸
綺麗に結った長く美しい雀茶の髪が蛍光灯の光を浴びて艶めいていた。今週から晶三の部下となった珠里は出勤してくると彼に挨拶をして座席に着く。その所作のどれを取っても自然であり、椅子に座って鞄を脇に置いて髪をかき上げる仕草も、わずかに何かを思い出すような素振りをしてから慌てて書類に目を通すなどしている姿も、如何にも体温を感じさせる柔らかい動作だった。晶三はそれが何やら嫌だった。彼は自分のこの感情をレイシズムと定義するか悩んでいた。晶三と珠里には男女、上司と部下、年齢の差などの差異の他に、より大きなひとつの隔たりがあった。だから昼休み、折角だからこの悩みに真っ向から飛び込むように晶三から珠里を昼食に誘ったのだ。
「やはり気になりますか」
「気になると言えば、そうだね」
昼時で人通りの少し増えた道を晶三と珠里は横並びで歩きながら会話をしていた。少し曇った空が白くビルの薄い影を街に落としている。それが如何にも寒々しく、誰もが斜め下を見ながら歩くようで、晶三も自然と目線を下に落としていた。僅かに吹く風のひんやりとした空気が珠里の仄かに赤み差す肌を撫でると、彼女はマフラーを少し持ち上げて顔を埋めるように首を縮めるのだった。晶三はそれを横目で見て、またもあの嫌悪感が小さく頭を擡げるのを感じた。
「いやもっと正直に言えば、俺はお前が好きではないかもしれない。」と晶三は表情を変えずに言った。
「正直なんですね。でもそう言われてあっけらかんとしているほど、私は強くないですよ」
「それは傷つく、ということなのか」
「そうですね、晶三さんと同じように、かどうかは判りませんが、私は自分の感情……そう、感情です。それをそう定義しています」
「俺は、どうも判らない、混乱するんだ。どう接するべきなのか、まだ定まらない」
「普通の人間と同じように接してくれたらそれが一番いいです。可能ならですが」
「努力はするよ」
二人は晶三のお気に入りの中華料理屋に入ると、刀削麺と水餃子を注文した。珠里は店の中を珍しそうに見回す。普段暮らしている様式とは違う中国風の木製の衝立や壁にかかった鮮やかな布を興味深そうに見ていたかと思うと、何も見ていないかのように視線を斜め上に暫く止めて、やがて口を開いた。
「調べてみたんですけれど、この衝立、買えなくはない値段なんですね。思ったよりも安いな、って思いました」
「買ってどうするんだ、家に置くのかい」
「ちょっと可愛いって思って」
やがて料理が運ばれてきて、晶三は腹が減っていることを初めて思い出したように口の中に唾液が出るのを感じた。珠里は手を合わせて「いただきます」と言うと、刀削麺の煙に目を細めながら太い麺を息を吹きかけ冷ましながら口に運ぶ。そして美味しそうに頬を膨らませながら笑った。「美味しい!」そう言ってかぶりつくように食べているのを見ると、晶三も何やら少し嬉しかった。
「不安だったが、気に入ってもらえたようで良かったよ。その、本当に美味いのか」
「美味しいですよ、とっても」
「こんなことを聞くのは、デリカシーが無いのかもしれないが、その、キミは味覚があるってことなのか」
「ええ、ありますよ」
「そうか、あるのか」
気まずいような沈黙が流れて、麺を啜る音が静かに響いた。晶三は沈黙に耐えかね、バツが悪そうに頭を掻きながら「何も知らないんだ、本当に」と言った。
「私のモデルは、工業用や専門職用のものとは違って、基本的に人と共に暮らすことを目的としてデザインされています。その為、共感性や協調性を重視したチューニングが施されており、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚と言った基本的な五感を備え、多くのリソースを感情をシミュレートする為に割いています。これらの複雑で複合的な形式は操り人形の糸のイメージから取ってシミュラクルの糸と呼ばれています。私たちはその機能の多くを人間らしさに充てているので計算能力の速さや精確さという点では他のモデルに劣りますが、その分より人間的な振る舞いをするようにできています」
「キミたちアンドロイドは、」と晶三は言葉が粗雑にならないように意識しながら言った。「感情があるのか」
「あります。あると、少なくとも私は定義しています。寂しかったり、嬉しかったり、楽しかったり、悲しかったり、腹が立ったり、そういったものがあると、私は確かに実感しています」
「断定している割に酷く曖昧な言い回しになるんだな」
「私は私の感情の存在を私の主観から断定できます。しかし、晶三さんが感情と定義するものと同等であるかは比較する術を持たないので、そういった点からは曖昧な言い回しになってしまうんです。私は人間の感情の動きをシミュレートするようデザインされている、という言い方が一番中立的でしょうか」
「疑っているわけではないんだ」その言葉に、多分無意識下では彼女の感情を疑っているのだということを証明するように晶三も珠里も感じられた。
「いいんです。恐らく、似ているからこそ、その違いが浮き彫りになり、気になってしまうということはあると思います。実際私も人に対して、自分との違いを見つけて恐怖することがありますから」
食べ終えると珠里は肌を仄かに高揚させて満足そうにしていた。晶三はその姿を見てまるで人間のようだと驚いた。その視線に気付いた珠里は少し恥ずかしそうにはにかんだ。
「人間の目は、自分たちの人種に近い肌を基本の無色と捉え、血流による顔の色の変化に敏感にできているんです。そこから人は感情や健康状態などを読み取る機能が備わっています。私もまた、人間に近づく為にそういったメカニズムに基づいて肌の色が高揚したり、青ざめたり、緑がかったり、黄色くなったりする機能があります」
「驚いたよ。まるで人間のようだ」
「ええ、そうですね、不気味でしょう」
「不気味ではないよ」
「それが一層不気味なんですよ」
晶三は言葉に詰まってしまった。彼女は自分が人からどのように思われて、どのように感じられているのか、それを印象づけている無自覚な本人たちよりも強く意識しているようだった。それは被差別者特有の身を守るために備えた姿勢のようにも感ぜられた。
「感情のシミュレーションか」と晶三は呟いた。食後の茶が運ばれてきて、それをゆっくりと飲んでいると、珠里は何やらソワソワとしている。そして意を決したように言うのだった。
「もう一杯、刀削麺食べていいですか、今度はこっちの酸辣湯のやつを」
「はあ、良いけど、よく食うなぁ」
「だって美味しかったんですもん。もっと食べたいって思っちゃったんです」
食欲というやつ、しかも栄養摂取ではなく味覚に基づいた欲求による抑えがたい食欲というものを備えている珠里に晶三は再び驚きを禁じ得なかった。実に非合理的な欲求が当然のように彼女の行動様式に組み込まれている。それがとても人間的で、彼女の言う通り、彼は一層得体の知れない嫌悪感を感じるのだった。そしてその嫌悪感を彼は恐れた。一体どうしてこんな嫌悪感を覚えるのだろうか。彼女を同僚として理解したいという願いとは別にどうしてもそれは抑え難かった。
「感情のシミュレーション、それがどういう仕組であるかは私も知りません。どうにもその辺りの知識は初期データとしては存在していないようです。ですが、面白い話があります。私のモデルには全員同じシミュラクルの糸というメソッドが使用され、同じ養育施設で出荷まで同一の学習を行うのですが、ある時期からそれぞれに個性や性格が生じるんです。長じてそれは違う好みや趣味を持つに至って、今までずっと同じだったはずの互いを理解するのが難しくなっていくんです。そして次第に他の人より優れたいと思ったり、他の人を羨んだりするようになる。不思議ですよね、ずっと一緒で、ずっと同じことをしていたのに。でもこういう個体成長の不可思議さに私は人間的な特性を見て嬉しくなるんです」
職場に戻って二人は仕事を再開した。彼らの仕事はアダルトグッズ制作会社の総務にあたる。珠里はまだ入ったばかりなので幾つかの雑務に対応している。彼女は企業用モデルではないので、高度な計算能力は持たず、殆ど人間と同様の速度で学習してゆかねばならない為、一時に多くの仕事を任せるわけにはいかなかった。
「こんなことを女性に聞くのは良くないかも知れないんだが、なんでこの会社にしたんだ」
「快楽に、その、興味があったんです」
「それは性的な快楽ということかい」
「そうです」そう言うと珠里は頬を赤らめて目をそらしてしまった。「私は機能として、性行為ができます」
晶三はゾワゾワとする寒気を感じた。それは生殖を伴わない性行為を機能として備えた眼前のアンドロイドに対する嫌悪と、彼女を一個の性処理の道具として利用する人間がいるということの嫌悪の板挟みであった。一方は彼女をアンドロイドとして性行為機能を持った人間に似せた悍ましい何かに対するれっきとした嫌悪であって、もう一方は彼女を人間に準じるものとして認めそのラブドール的な機能に対して非人道的と感じる道徳的な嫌悪感だった。アダルトグッズを売る人間がラブドールに感情移入などおかしな話ではあるが、それだけでは割り切れない思いが晶三にはあった。彼は前提として、彼女を人間として別け隔てなく関わりたいと思うのであるが、その為の自身の無意識に蟠踞する嫌悪のような感情をコントロールできずに混乱するばかりであった。
「私はあるお金持ちの男の人に買われて、娘のように愛されました。家事を手伝い、一緒に遊び、旅行をして、日々の話し相手になる。その中には確かに性行為もあって、私はそれに悦びを感じていました。彼の手から離れて今でも、たまにそれを思い出して自分を慰めることがあるのです」
珠里の話に晶三はめまいを覚えるようだった。人の模造、その悪趣味さを目の当たりにするような感覚に襲われた。だが、それは彼女がアンドロイドだからであって、もし人であったならば、それは自然なことと思われる。彼は自分の感じ方そのものに嫌悪感を覚えているのかも知れないと思った。人と接しようと努める裡で、常にその感情はアンドロイドであることの不気味さを感じている。自己の思考する方向とは真逆に矛盾する感情を抑えられないことに歯がゆさを感じた。
「これは私が仕事をすることになったのと関係があるのですが、私のオーナーは病気で亡くなってしまいました。その中で彼は遺言で私の自由と遺産の一部を相続するように書いていました。遺言とはいえアンドロイドが遺産を相続することに親族は当然反対しました。私には何の力もなく、何の保証もなく、何の保護もありませんから、遺言は簡単に反故にされました。それでも私は自由になることだけは許されました。それだけでも幸運と思わないと。で、生活するのにお金が必要になったんです」
「それで少しでも関心のあるここに来たと」
珠里はちょっと恥ずかしそうに笑いながら「そうなんです」と答えた。
「アンドロイド法は私たちの自立を、労働と賃金の受け取りを認めています。この法律があったから私は解体されずに済みました。ただ基本的人権の尊重というものにアンドロイドは含まれていません。ですから、私たちは様々な方法で自分の身を護らねばならないんです」
「住居を借りることも難しいって聞いたことがあるな」
「そうなんですよ。私たちには戸籍が存在しないので、基本的には借りられません。ですが代行業者があって、家賃の30%の手数料を毎月払うことで、代行して借りてくれるんです。その業者自体、余り信用ならないんですけれど、私たちはこういうものを頼るしかないんです」
「30%か高いな。いや、リスクを考えれば安いのか」
「高いですよ~。でも背に腹は変えられないです。私のように自立をして仕事をし、生活するアンドロイドはまだ珍しいですが、着実に増えています。本当はそういう仲間と集まって相談したりしたいんですが、国はアンドロイドだけでコミュニティを組んで何かを議論することを禁じていますから。恐らくは反人類的シンギュラリティの発生でも危惧しているからなのでしょう」
「自立したものたちは何故自分たちだけで生きていこうと思ったんだろう」
「多くは結果的に自立せざるを得ない状況に立たされただけで、自ら進んで自立したものは殆どいないと思います」
「そりゃ何でだい」
「恐らく死の観念が薄いからです。死ぬことに無頓着だから自立せずに機能を停止されても構わないとも思える。私は自分が無の状態を考えるんですが、それがどんなものなのか想像が付きません。近似的なものはスリープ状態でしょうか、その状態でも最低限の演算は行われているので同じものとは言えませんが。ですから死については何も判らない、故に自分が死ぬことに関して恐怖がないんです」
「それは俺と逆だな、想像がつかないから怖い」
「なるほど。あ、でも停止したいと考えるわけではないんです、快楽を考えると、まだ味わっていたい、という欲求があります。それは私が停止を選ばない理由になっています」
「それは人間も同じかもな」
ある日の朝、晶三は紅茶を淹れようと給湯室に行くと、少し早めに来ていた珠里がお湯に濡らしたタオルで一生懸命にコートを拭っている。訝しんだ晶三がどうしたのかと珠里に問うと、彼女はぷりぷりと怒りながら今朝あったことを話した。
「電車でガムをくっつけられたんです。それも一個じゃなくて何個も。一人じゃなくて何人かの人に。お気に入りのコートなのに酷い」
「それは酷いな」
「よくあることなんですけどね、足を引っ掛けられたり物を投げられたりとか」
そういうことがよくある、と言った珠里の顔は先刻と変化はなかった。それが彼女の日常であり、彼女が見ている世界なのだった。晶三は想像がつかなくて、それがショックだった。アンドロイドに対してそういう行動を取る人間はたまにいる。勿論所有者に訴えられれば器物破損で罰金の対象となるが、彼女のように自立して生活しているアンドロイドを護るものは何もないのだ。極端な話、珠里は突然誰かに殴られて壊されてしまったとしても、彼女を助けてくれる人は誰もいない。そして、また壊した人間が罪に問われることもないのだ。晶三はその事実に少しゾッとした。
「もー、取れない!」と叫ぶと珠里は足をジタバタさせて怒りを顕にしている。
「ガムは冷やすと取れやすいぞ」
珠里はキョトンとした表情のあと、少しの思考時間のあとに「本当だ、検索したらガムの取り方ありました」と言った。そして冷蔵庫から保冷剤を取り出してコートに付着したガムに押し当てながら口を尖らせながら言った。
「できることならやり返してあげたい」
「それは、言い過ぎじゃないか。その、人に聞かれたらマズいだろう」
珠里は少しショックを受けたような表情をしたあとに、すぐにその顔を引っ込めたが、晶三はそれを見逃さなかった。珠里はにへらと笑うと言った。
「冗談ですよ」
「……世の中は、冗談として受け取ってくれるとは限らない。特にキミは難しい立場にいるわけだし。アンドロイドの犯罪に人は敏感だ」
「わかってます。でも、アンドロイドの犯罪は全体の犯罪の0.1%にも満たないんですよ。99.9%以上が人間による犯罪です」
「そうだが……」
「ごめんなさい、私、カリカリしすぎですね。アンフェアなのは今に始まったことじゃないし、我慢しなくちゃならないのに、すみません」
晶三の胸はチクリとした。彼は何気ない自然と出た発言が、彼女に差別を意識させるものとして響いたことに今更ながら思い当たったのだ。
「……キミは法律で護られているわけではないのに、何故人の法律を護るんだ」
「言われてみれば何ででしょうね。でもそうですね、私のオーナーは素敵な人でした、私は彼が好きだった。だから私はどちらかと言えば人間が好きなんです。自分の都合で人の社会を乱したいとは思わない。日和見もありますが」
「立派だと思う。でも同時にキミはもっと自分の存在を認めて貰ってもいいと俺は思う」
それは確かに晶三の本音であった。
昼休みが終わってから、まだ気が抜けているのか、珠里はぼうとしていた。晶三は彼女の少しだらけた雰囲気にそういうこともあるのかと感心していたようであったが、他部署の人間が彼女の席に来て書類に抜けがあったということを強く叱責した。晶三は慌てて珠里と共に謝罪をすると、ふうと一息ついた。
「ごめんなさい」と珠里は心底申し訳無さそうに言うが、晶三は「間違いは誰にだってある」と言った。珠里はびっくりしてから嬉しくて頬を緩めた。
「感情は」と晶三は話し始める。「不可解だ。複数のアンビバレンツな感情が、矛盾したまま共存する」
「私の感情や感傷は、あくまで電気信号と演算の結果です。小さな火花を散らすパルス、それが私の正体です」
「それは人も同じだ。それを行っている器官や構造が違うだけで。キミたちが我々のシミュラクルだと言うのであれば、その回帰性は遅かれ早かれそれはキミたちの存在を肯定するものになりうるはずだ。シミュラクルの糸は既にしてキミたちを傀儡として操るような言葉であったが、真実は、キミたちをキミたち足らしめる、ひとつの思考する精神としての肯定的シミュラクルだと思う」
「ロマンチックですね」
「人は、いや、そうだ、俺は、自分たちが生物であり、キミたちが無生物であるという前提から出発し、その感情のプロセスに於いて近似的な姿を見させられることに、自らが生を持った人間であるところの特権的アイデンティティが揺るがされるようで恐ろしいと感じたんだ」
「いいんです、私たちは生きていると定義するには難しい。活動していると言うのは容易ですが」
「オスカー・ワイルドの言うところの逆だな」
二人は目を合わせてくすりと笑った。
「結局、キミをどう扱っていいのか、自分の中に蟠るこの嫌悪感をどうすれば良いのか判らないんだ。キミに情を寄せれば寄せるほど、この無意識で起こる感情の矛盾、無分別、無自覚が恐ろしい。ただ、それでもキミにはまだまだ食って貰いたい美味いものがあるんだ。だから、また一緒に飯に行こう。俺の知っているいい店を全部教えるよ」
珠里は目に涙を溜めるとそれが溢れてしまわないように顔をくしゃくしゃに歪ませて「はい」と言った。
【完】
