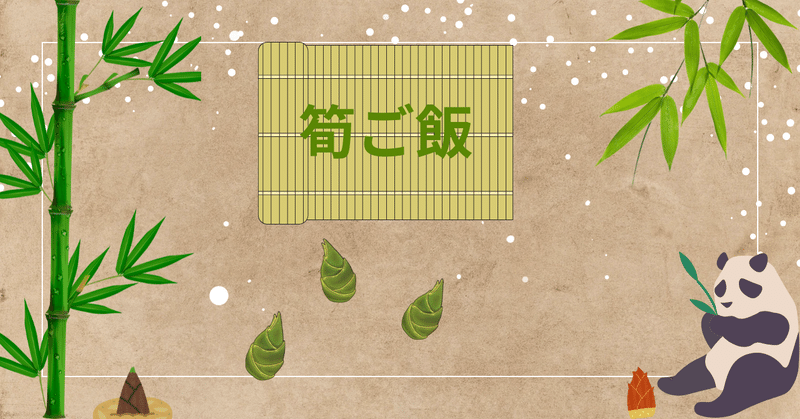
vol.3 筍ご飯
修業が始まり、数週間もすると随分と仕事に慣れてきます。その日、私は営業開始までに朝の準備を終えたので、残り時間に筍ご飯の筍を刻む仕込みを始めました。
一斗缶に入った水煮の筍を半分に割り、白い粒々を竹串で擦り洗いします。この白い粒々はアミノ酸の一種でチロシンが結晶化したものです。生の筍を湯がく場合ですと滅多に見ませんが、水煮で市販されているものには大抵入っています。
仕込みの単位が一斗缶ずつでしたので、この白い粒々を除くだけでも結構な時間を使います。私はこの仕事を営業までに終わらせると心に決めました。
仕事を黙々と進めていると、後ろからいい匂いが漂ってきました。若竹煮の香りです。懐石弁当の炊合せの献立が若竹煮だったのです。私の持ち場で扱っている筍とは違い、こちらは朝掘りの筍で、これを煮方の職人が朝一番に炊き、営業開始直前に八寸場(懐石の八寸を担当する持ち場の名称)に回します。そして時を同じくして焼き場や油場からも出来上がった料理が続々と八寸場と配膳場に集められます。私も時計の針を見て、既にセットしてあった筍ご飯の釜に火を入れました。

こういった周囲の動きに、仕事に慣れてきた私は漸く気付けるようになっていました。ボールの中で筍の白い粒を取り除いていると、段々と後ろの方が騒がしくなってきます。配膳場の方でも人の出入りが激しくなってきて簀の子を踏み鳴らす音が徐々に大きくなってきます。板場の裏口横にある私の持ち場だけは他に比べて位置と向きが異なっているため、私は時々後ろを振り返りながら見ていました。
「~さん! 鰆の小串上がりました! 後ろに置いておきます! 」
威勢の良い声で焼き場の先輩が八寸場の先輩に声を掛けます。
「おお。サンキュー」
八寸場の先輩は横に広い八寸場を右に左に移動し、後ろも振り返らずに返事をすると、台一杯に並べた三つ切りの器に料理を一心に盛り込んでいます。すると今度は、油場の先輩が声を掛けます。
「~さん。田楽は何人前ですか? 」
「う~ん、一発目は20で頼むわ」
八寸場の先輩は忙しく手を動かしています。手と足の動きは段々と早くなっているように見えます。冷蔵庫からタッパーを取り出すためにしゃがんだかと思えば、開いたドアから一瞬でタッパーを取り出し、しゃがんだ際の勢いでバウンドするように立ち上がっています。或いは、盛り付けていた料理が足りなくなり横の扉を開けたかと思えば、体操の側転さながら、上半身を左右に倒しながら片足を少し上げて、さっと目当てのタッパーを取り出し一瞬で元の体勢に戻ります。そうやって料理を一種類ずつ全ての器に盛り込むために左から右へと蟹歩きを繰り返し、一つの料理を盛り終わると上半身を左に捻りながら左手で空のタッパーを後ろの台に置くと同時に、右手で冷蔵庫の扉を開け次に盛り込む料理の入ったタッパーを掴み出すのです。それらの風のような華麗な動きを目にすると、胸にさっと重い向かい風が吹き込んで、私の指の動きも自然と早まります。
今度は全体を見ようと、私は立ち位置をずらしました。持ち場であるはこ場からは上半身を大きく傾けない限り煮方は見えませんが、焼き場と向板は見えます。
焼き場では大きな俎板の上に串に打たれた鰆の切り身が何本も並んで積まれています。その横のスペースで焼き場の先輩はサラマンダー(焼き用ガス器具)に背を炙られながら、鰆の切り身を掴むと手を前へ前へと突き動かし、次々に波串にしています。3メートル程離れた私の位置からも波串が綺麗なアーチを描いているのが分かります。こちら側を向いた先輩の目は獲物を狙いすましたスナイパーのように瞬きをしません。一つ打つ度に奥を睨み、串を持った腕を上下に波打たせています。その真剣な眼差しに私の目は惹き込まれていきました。
焼き場と向かい合った向板(お造りを作る持ち場の名称)では、三つ切りの弁当に収められる小さな器がぎっしりと俎板の上に並んでおり、背を向けた向板の先輩がお造りを盛り付けています。俎板の中央に立ち、上半身だけを小さく動かしながら、右から左へ水の流れるような小さな動きを見せてます。
すると今度は、配膳場から、
「ただいま、お待ち10名です」
と、開店を待っているお客がいると伝えてきました。配膳場の床に敷かれた簀の子も忙しない音を盛んに立てています。
私は再び、立ち位置をずらして、今度は配膳場を眺めます。八寸台と向かい合った配膳台は八寸台と同じ幅があり、懐石盆が一度に6つ用意できるように並んでいました。
こういったそれぞれの持ち場の動きに感心していると、私が目をやっていた反対の方から大声が聞こえました。突然のことで何を叫んだのかは聞き取れません。ただ、何かが通ると叫んだようには聞こえました。私が驚いて目を向けると、板場の奥から配膳台の方向へ太い人影が猛然と移動しているように見えました。そしてその動きに合わせて焼き場と油場の先輩にも動きがあったように感じました。人影は更に何か短い言葉を叫んでいます。良く見ると、その人影は煮方の職人でした。職人は焼き場と油場を通過し八寸場に行き当たると直角に曲がり私の方へ猛然とやって来ます。10ℓほどの寸胴鍋をヤットコでがっしりと掴み、眉間に皺寄せ、真一文字に結ばれた口が開いたかと思うと、
「赤出汁通るぞ! 」
と大声を張り上げました。そして八寸場の端まで来て直角に曲がると、今度は、
「熱いの通るぞ! 」
と叫びます。職人の通る先々で皆が勢いに押されて動きを止めます。職人は配膳場のガスコンロの上に鍋を置くと、厳しい表情のまま、もと来た道を戻りました。勢いに飲まれながらその背を見ていると、勢いで膨張した職人の通った道がその背に向かって吸い込まれ仕舞われていくようで、ふっと惹き込まれるのです。しかし、長々と見とれているわけにはいきません。自分もいつかは彼らに並ぼうと思うからです。いつの間にか浅くなっていた呼吸に息苦しさを憶えると、私はひとつ大きく深呼吸をして再び大急ぎで手を動かし始めました。
暫くすると、タイマーが鳴ります。はっとして、筍ご飯を炊いていたことを思い出しました。窯の火を止めて、配膳場に保温用のお櫃を取りに行きます。
立体炊飯器(給食室向けの大きな機器)の扉を開けると、筍ご飯の香りが漏れ出てきました。窯の蓋を取ると、出汁と醤油が釜の底で薄っすらと焦げた香りと湯気に包み込まれます。それは、熟した出汁が開花したような鮮烈で芳しい香りです。
湯気の中から顔を出した米粒は煌めいており、小麦色にも金色にも見えます。これは、学校帰りの夕暮れ時に目にした、陽の当った稲藁干しの輝きでしょうか。或いは収穫間際の金色の田園風景でしょうか。その暖かでゆとりある懐にスライスされた筍が思い思いの場所に身を沈め、抱かれています。その中に、ひと際白く優しい薄卵色をした穂先の部分がほのぼのと横たわった様はまるでうたかたのようでもあります。


私は時計を見ると、急いでお櫃に移しました。そして配膳場の保温器に入れ、再び筍の白い粒を取り除きます。この長いトンネルを抜けるような仕事も残り僅かとなっていました。終わりが見えてくると、俄然手が早くなります。何故ならこの次はスライスをする工程だからです。新人の私には包丁仕事が楽しみでなりません。早く終わらせて、流れるように切りたくて仕方がないのです。なにせ、その一時を自分が熟練した職人のように輝いて過ごせるからです。
そう想像しながら最後の一本を手にした時、後ろから鋭い叫びが聞こえました。油場の先輩の名を呼び、
「~さんが通るぞ! 」
と、煮方の職人が煮方ー焼き場ー油場ー八寸場に繋がった道を通ることを焼き場の先輩が知らせます。皆の反射的な動きが私の耳と肌に波のように伝わってきました。私は驚いて後ろを振り返り首を伸ばします。
「若竹煮上がった! 」
職人が太鼓を叩いたような野太い声で空気を割り、やっとこで深いバッカンを音を立てて掴みながら、今まさに動き出そうとする瞬間が目に入りました。頬と口元を引き締めた職人の顎には幾筋もの筋肉が浮き上がり、目はくわりと開いています。
「熱いぞ! 」
バッカンを持ち上げ、動き始めた職人は再び叫ぶと、途中にあった焼き場と油場用の2台の補助台を腰を伸ばし、或いは捻りながら避けて通ります。それはまるで凹凸の激しい道を進みながら、左右に砲弾を飛ばす戦車のようです。腰を伸ばし、ぐいぐいと捻るものの上半身は微塵も揺れていません。そして八寸場の先輩の名を呼び、
「若竹煮上がった! 置いとくぞ! 」
と叫ぶと、八寸台にあったホットプレートの上にバッカンを置きました。バッカンには出汁がたっぷりと入っているはずです。しかし職人は一滴も溢さずに運び、元来た道を戻っていきます。私にはこの職人の図太い体のどこにこれだけの繊細さがあるのか分かりません。呆気に取られていると、職人の通り道にいた焼き場と油場の先輩が私の目に映ります。その姿を見て、私は、ハッとし、見てはいけないものを見てしまったかのような罪悪感を憶えました。何故なら彼らは両手を挙げて、焼き場の先輩はサラマンダーに、油場の先輩はフライヤーに落ちそうな程にへばり付いて、通り道に残された曳かれたカエルのような恰好をしていたからです。
(あぁ、憐れな兵隊さんだ・・・)
そう感じ、ドクンと鳴った私の胸が冷やりとします。私ははっとして慌てて目を逸らし、最後の一本を掃除します。しかし目を逸らす間際の二人の取った行動が目に焼きつき、避けられぬ未来が背中から押し迫ってくるように感じました。焼き場の先輩の顔色を変えずにサッと仕事へ戻った歯切れの良さと、口元を窄め怪訝な流し目を見せた油場の先輩の重く粘りのある深みが螺旋の渦を巻いて私の目に飛び込んできたからです。
平然とした焼き場の先輩はあの勢いをどのように割り切ったのだろうか。そして仰々しく目で追った油場の先輩はあの細い目で何を見ようとしていたのだろうかと思うのです。そこに憶えた感覚が冷たい向かい風のように、私に鮮やかに問い掛けてくるのです。
私は背を丸め、最後の一本を片付けました。確認の為、ボールに入った筍を何本か取り出して見ると所々に微かな粒が残っています。水の溜まった節の所にも溶けた粒がもやもやとしています。反射的に苛立った私は水道の蛇口を思い切り捻り、一気に洗い流しました。
筍を笊に上げて時計を見ます。もう、営業間近です。しかし、心に決めた目標を何とか達成できて、私は肩で息をつき周囲を見渡します。準備を整えた周囲の先輩たちは盛んに目を動かして漏れがないか確認しています。私はシンクにボールを入れ、俎板をシンクの左側に寄せて縦に渡しました。そうして右側にできた隙間に、包丁を滑らせてスライスした筍を落とせる態勢を整えました。
手早く切る順序としては、俎板に半割りにした筍を縦向けに数個並列させ、まとめて横に1・5㎝程に切ると、今度はまとめて縦にスライスするというものになります。そして切ったそばから包丁を右に滑らせてボールの中に落としていきます。これを全て遣り終えるまで何度も繰り返すのです。
気持ちを整えようと深呼吸を重ね、牛刀を握ります。既に体勢は春の新芽のように駈け出そうとしてます。心は羽のように軽く、新芽の先に残った赤みのように先へ先へと萌えています。左手で筍を抑え、ゆっくりと包丁を向うへ滑らせると、すっと入っていきます。もう一度やると、またしてもすっと入ります。そうして力加減とリズムを掴んだ私は徐々にペースを上げていきます。感覚を研ぎ澄ませ、左手の5本の指で5つの小片を抑え、少しずつ手をずらせながら、右手を前後に大胆に動かし切り進めます。呼吸は断続的に長く一定に抑え、一本分を切ると、隣に移り、次々と切り進めていきます。俎板に並べたものをボールに落とし、次を並べる際も、再び切り進める際も呼吸は常に体の振動に合わせて小刻みに長く吸い込み、小刻みに長く吐き続けます。

ほんの暫く後に接客係が開店を告げ、注文を伝えてきました。その声に私はやや動きを抑え、首を持ち上げると、「よぉー」と大声で応えます。背中から聞こえる先輩たちの声と私の声が重なり板場に反響します。その熱に、厚みに私の血は滾ろうとします。自分がいっぱしの職人になったかのように思え、血が喜びに湧き立とうとするのです。筍の肌に幾つもの筋と紋様が鮮やかに浮かび上がってきます。目が筍に吸い付き、包丁が手になったかのように感じ、慎重さが消えていきました。音が止み、匂いが消えていきます。そしてやがて背景は流線の如く流れていきました。
夜、7時半になると、私は包丁を磨き始めました。先輩たちの包丁を集め、8時のラストオーダーとともに先輩たちが包丁を研ぎ始められるように、磨き終えなければならないのです。お盆に白い布を敷き、それを目の高さに持ち上げ、下賜せられた格好で受け取った20本ほどの包丁を磨き粉と錆び落としを使って一本ずつ丁寧に磨いていきます。背中からはまだ料理をする音が聞こえてきます。しかし既に、自分の仕事である漬物などの充分な盛り置きを終えた新人の私にはそれを気に掛ける必要がありません。
シンクの下の棚に仕舞ってあった磨き粉と錆び落としを、三方から取り出すような張りのある気持ちで手にすると、シンクに渡した板の上に置きます。包丁を板の上に載せ、磨き粉を振りかけ、丹念に磨き、錆びを落とします。それから水で濯ぎ洗い、乾いた白い布巾で丁寧に水気を拭き取ります。布巾から顔を覗かせた包丁は深く沈んだ底冷えのする重い光を放っています。私はそれを吸い付くように眺め、再び白い布を敷いたお盆に並べていきます。一本磨く度に生まれ変わった包丁が並んでいきます。代わりに背中から聞こえる先輩たちの声と料理をする音は徐々に小さくなっていきます。まるで板場の熱が包丁に仕舞われていくように感じます。力を込めた私の手が錆びを落とす度に板場の熱は包丁に仕舞われていきます。私は丹念に熱を拾い、一本一本の包丁に仕舞っていきました。
8時になり、皆がそれぞれの持ち場で思い思いに包丁を研ぎ始めます。
「シャッ、シャッ」
砥石と包丁の擦れる音響の僅かな差が板場に重なり合い、自分の包丁を磨く私の耳にも入ってきます。その音を聞いていると、頭から血の気が引いていき、深淵の闇が板場を覆っていくように感じられました。それは誓いを持って鳥居の前に立つ微細な存在が、畏れを抱き、社殿を望むような感覚です。
私の目に夕闇に沈む神社の境内が浮かび上がってきます。私は森に囲われた神社の鮮やかな朱色をした鳥居の前に立ち、一本の長く続く石畳とその先にある白川砂利を敷き詰めた境内を眺めています。
境内はまさに闇に紛れようとしています。呉須で染められた空に群青の森が黒々と浮かび上がり、その底で微かな光を反射した白川砂利が薄っすらと浮き立って見えます。私の胸の中でぼぉ~と生まれた小さく柔らかな波が全身へと波動していきます。すると、中心に向かって密接していたものが微かに離れていく動きを感じるのです。その時、白川砂利の上に存在を明瞭に誇示していた現世(うつしよ)の社殿が、闇を重ねる群青に霊気を鎮めていくように見えました。私はその動きをもう一度確認しようと試みます。しかし、なかなか上手くいきません。そうして何度か繰り返していく内に、やがてその光景に自分の体が引き込まれていくように感じました。
私はふっと空恐ろしくなり、包丁を磨く手を緩めます。やがて、ひとり、ふたりと先輩たちは順に帰っていきます。その背を見送り、板場から徐々に人気が失われていくと、熱の仕舞われていく板場は幽世(かくよ)の如く思われてきます。最後に油場の先輩が板場を後にすると、遂に夜の帳が下りてきたように感じました。昼間の熱の一縷の余韻も失った板場に寂しさを憶え、ふと後ろを振り返りました。煌々と明かりの灯った板場は闇夜の如く深々と静まり返っています。体は自然と動き出し、私は八寸場の前から板場の奥を見ます。そして明かりの筋を追い、天井を見上げました。すると天井には呉須に染まった空が広がり、職人達の奏でた萌ゆる思いが矜持となって光り輝いて見えたのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

