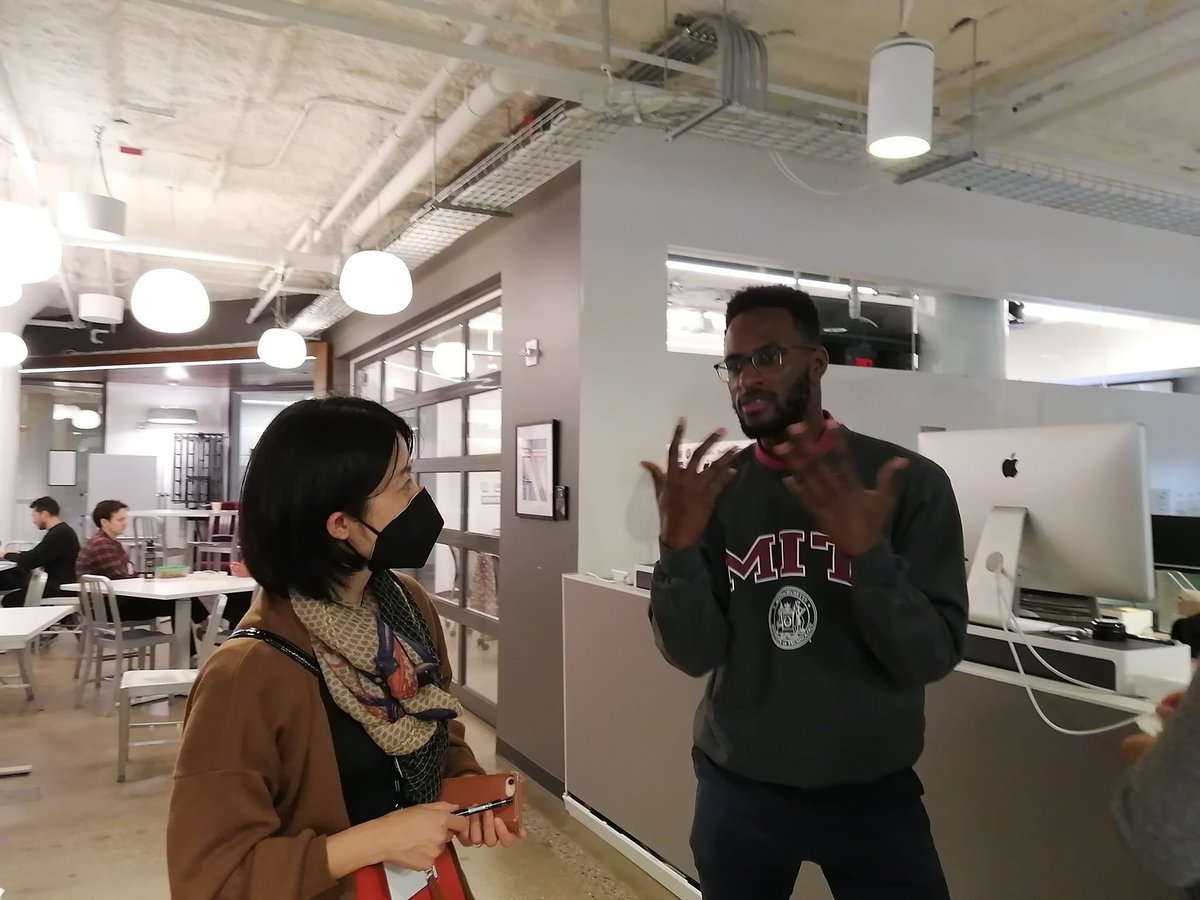【ボストン研修レポート9日目】振り返りと中間発表
9日目となるボストン研修レポート。外出禁止のアパート待機3日目に入りました。ZOOM見過ぎて目がバキバキになってくるので時々伸びをしながら、立ちながら過ごしています。9日目の研修の朝9時までに、英文アクションプランと5枚スライド(5分以内プレゼン)をオンラインで提出。
その後、9日目は振り返りとバブソン大学山川教授とフィッシュファミリー財団創設者のフィッシュ厚子さんのフィードバックをいただける中間発表。学んできたことを出し切るつもりが、、、うーん。悔しいなぁ、学ぶことと、それを形にすることがこんなにもつながらない。

午前の振り返りは、全員この1週間何を学んだのか、という点のみならず、Crisis Management(危機管理)について話ました。まさに、今回のようにコロナによって即ZOOMに切替研修継続をする等、何が大事なポイントなのか、一人一人のリーダーがどのようにその判断をするのか、等について意見交換しました。
◆危機管理において大事なポイント
(私がこの皆さんの振り返りや意見を聞いておもったことになります。大事なポイントは人や団体によって異なります)
・迅速さ(みんなで話し合うということが大事なテーマやタイミングもありますが、危機のタイミングは時を争う。迅速な判断、そのための情報収集が重要)
・透明性(「今こういう状況です」「こういう判断をするためにこの情報を必要としています」「皆さんに求めることはこれです」と短く的確な指示がとにかくたくさん飛んできました。やっていいこと、やってはいけないことの「範囲」が的確。これは危機の時には範囲の設定は大事)
・振り返り(危機管理の最中から振り返る➤今の状況においての不足はなにか、どうであったら更によい危機管理が今後できるか等。渦中だからこそ振り返りで出せる意見がある)
◆発表において大事なポイント
午後は来週に向けてのオリエンテーション(来週からは1週間のバブソン大学での授業が毎日入ります)と中間発表(バブソン大学山川教授とフィッシュファミリー財団フィッシュ厚子さんに向けて&フィードバックを得る)でした。
発表において大事なポイントは、
・What,Why,How 原則はこの3つをおさえること
・フックが大事 関心をもってもらう最初の出だし
・Howにおいては、実際にその実現ができる道筋を一緒に聞いている人が理解し、自分の関わりしろが見えてくること
・補強する数字とエビデンス
・ビフォーアフターの価値の明確化(KPI等)
とてもアメリカらしいポイントです。ここでは本当にエビデンスが全てなんだなと改めて実感する2週間。逆にエビデンスがないことは説得力がないこと、だからデータをいかにとるかとれないデータはいかに表現できるもので代替して表現できるようにするかにとても時間とお金をかけるのだなと理解できました。
人に関わることは数値化しにくいことが多いです。KPIや指標は、それが独り歩きして目的化し、人が置き去りになってしまうこともあります。そうならない、関わりしろをうむための数字の使い方について考える時間になっています。
発表の結果
結果惨敗・・・というか、うーん。自分のできることできないことがとってもわかりました。
私に今最も欠けているのは、
・課題の設定が不明瞭
・子育ての状況を知らない人に、その困り感や嬉しいことがより手触り感が伝わるようにしっかり表現をすること
・こういう社会をつくりたいというのはあってもそこに向けてのステップが不明瞭
・何が起きたら自分たちにとって「成功」なのか「失敗」なのかの設定が不明瞭。
逆に、少し意外だったフィードバックが
・「こまち」ということの名前がいい(意外な反応)
・しっかりとブランディングをするといい
ということもありました。
「どんな子育てにもコミュニティがある」状態をどのように本当につくれるのか。孤立が低下している状態、たくさんの人が関わっている状態、どういうことをしたら本当にその二つに効くのかな。
私たちも2016年から数字に落としていける実績管理表をつくり(目標値は存在せず、させるつもりもないです)毎月進捗管理をマネージャー会議でしていますが、この指標でよいのかな。と改めて考える時間をもらっています。
最後にあまりにも写真が少ないので、おまけの写真。全てJWLIからお借りしています。