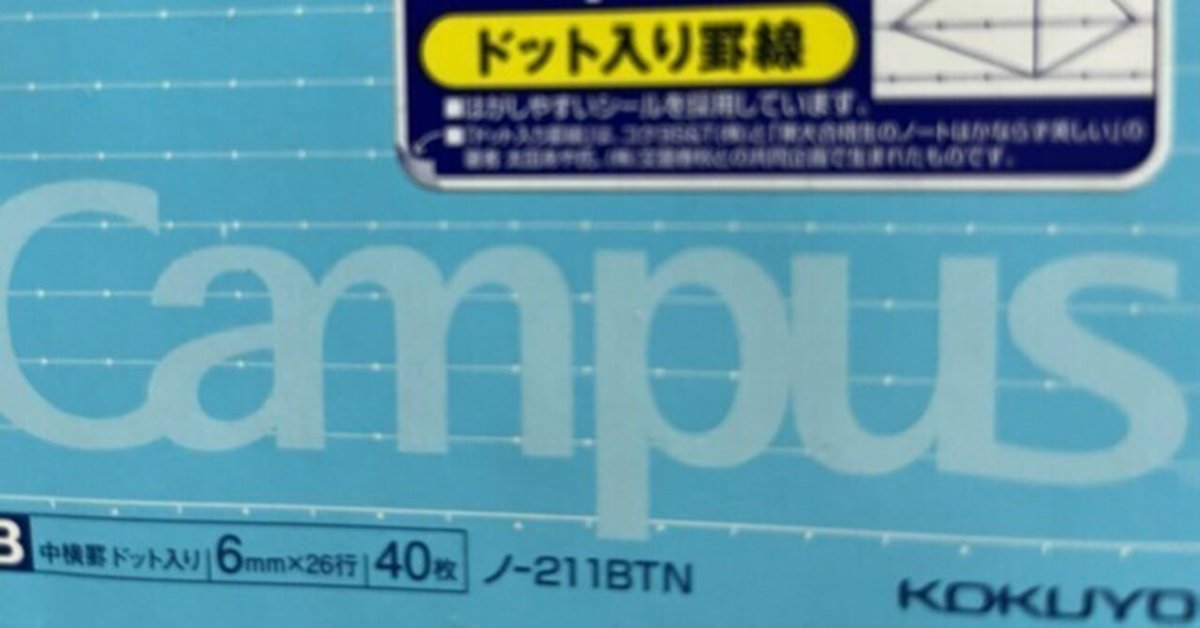
研修のミニノート 「看取りについて」
2014年5月、10年前のB6のミニノート
ケアマネ5年目だったか、転職先が比較的大手で、本社での合同研修会。
講師は悠翔会在宅クリニック 佐々木淳医師(コロナ番組では何度かテレビに登場された)
私のノート

在宅で看取るということ、在宅医療を実践されている医師の話を聞き洩らさないようにメモしている。今では広まっていることだが、10年前に聞けたことは幸運だった。その後、何人か自宅での看取りのケアマネをした。医師の直の言葉を聞いていることは強みだ。
認知症
10年前後の経緯で死亡する
アルツハイマーそのものは治療できない
年間10万人胃ろう
口から摂れる範囲の食事と水分だけ
1か月 もしかしたら1週間
たんに長生きさせる意味はない
尊厳の保持 「その人らしさ」を重視 本人の意向重視
日本では 家族の意向重視
積極的な意思表示がなければ
病院で延命治療を受けながら死ぬ
「意思決定支援」が重要
看取りとは 残っている人生を見守る
死亡率100%
死を先延ばしするのが良いのか
終末期を受け入れた時から看取り始まる
元気になれるポイントを超えたらADLでなくQOL
本人の尊厳を守るためのケア
ご家族に対するケア
医療機関と密に連携
臨終は日々のケアの延長上に自然にある
点滴をしないことが緩和ケアである
点滴をしないことで 脳内エンドルフィンやケトン体が増加
鎮静鎮痛作用
英国・米国・オーストラリア
点滴は 医師倫理に反する
日本では・・・
「経管栄養は終末期患者に不利益をもたらす」
認知症
胃ろうは肺炎治療の意味 人生最後のQOLは低下する
これ以上の治療は本人を幸せにしない
治療によって運命は変えられない
治療を卒業する
死に目に会えない可能性ある
看取りを経験したご家族 良かった ほとんど
グリーフケア
大切な最期の時間
どう死ぬ=どう生きるか
以上、ノートの抜粋である。
※「死目に会えない可能性がある」
ことについては、夫の母親の看取りの時に訪問看護ステーションから渡された説明書にも書いてあった。一字一句は覚えていないが、ニュファンスでは
「息を引取る時に気づけないこともあります。そのことに罪悪感を感じないでください。本人は苦しまないで亡くなったのです。」「まず訪問看護ステーションへ連絡ください。医師が追って死亡診断書を書きます。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
