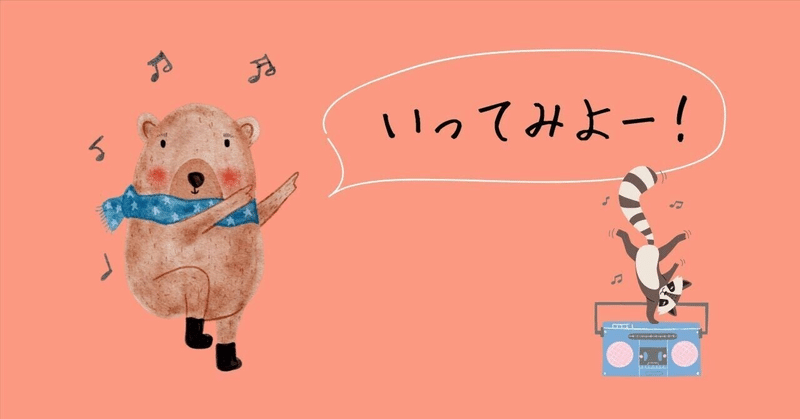
【捨てられない人の、失敗のない快適空間】
以前このnote で紹介した代表的な三人のプロの手法を学び、実践に即した工夫を重ねたものです。その結果、オリジナルとしておすすめできる自信のあるものになりました。
第1部
『次の説明を2〜3度読んでみて、イメージングしてみてください。そして、これならできそうと思われたら…もう成功はほとんど間違いありません』
エリアごとにスケジューリング
思い立ったらというより、前もっていつどこをと、スケジューリングしておく方が実行しやすい。
(やりやすそうな順にどうぞ)
•玄関周り(靴箱)
•本箱
•クローゼット
•台所、食器棚
•デスク周り、事務スペース
なお、欲張らずに一ヶ所づつからでも。
また、とりかかったからにはそこだけは完遂しましょう。
その都度、完成後の達成感を味わうことが大切です。
いよいよ片づけの手順です❗️
❶ひとアイテムごとにすべてを床に出す
❷次の三つに分ける
A.必ず使うもの
B.捨てられるもの
C.捨てられないから、とってお
きたいもの
❸ Cをまた4分割し、床をゾーン分け
(養生テープで)する
過去軸•未来軸•他人軸•保留
に分ける
過去軸のものとは
思い出の品
他人軸のものとは
→友人の結婚式でもらったから捨てるのは申し訳ない
→義理の母から譲り受けた不要な大皿
→お土産の木彫りの熊
…など、つい他人の気持ちを忖度してしまい、溜め込んでしまった
モノのことです。
未来軸のものとは
将来役にたちそう、使いそうだ
からとっておくもの
(小物・バッグ類・収納系・文
具 ・食器など)
◎過去軸のモノは無理に捨てない
◎他人軸のモノは基本捨てる
◎未来軸のモノはさらに分類
• 必ず使うもの…とっておく
• 大好きなもの
(ときめくもの)
…とっておく
→それら以外は捨てる
◎どうしても迷うものは、
→保留ケースへ
以上(❶〜❸)で完了です。
片づけ終了後の三原則
(リバウンド防止のため必須です)
●同じアイテム同士で常に一箇所にまとめる(分散しない)
●床に直接ものを置かない
●以後おく場所を決めて、必ずそこに戻す
終わりに
どうでしたか、今回は手順の骨子を紹介しました。
これだけだと理解しづらいかもしれませんかもしれません、第2部では各項目の解説をしたいと思います。
また、もしその解説を待たずとも一歩を踏み出せそうなら、
まずは理想の部屋にするために
必要な行動を、具体的にリストアップしてみましょう。
一気に片づけようと思うと途方もないことのように感じられますが、行動を細分化してハードルを下げておけば、最初の一歩を踏み出しやすいもの。
一度行動できてしまえば意識が片づけに向くので、次のステップに進むことができます。
今はここまでのイメージトレーニングにとどめておくことでいいかもしれません。
その際大切なのは、憧れの完成形
をイメージすることです。
第2部
『物と記憶は同一』という理論があります
これは、ある科学寄りの哲学が出典です
ですから、捨くてられない人が捨てたくないのはモノ自体でなく“思い出”のほうのはずです。
そしてそれは捨てなくてもいいという朗報を紹介します。
❶過去軸のもの(思い出の品)は基本捨てなくていい❗️
なぜなら、誰しも老後は過去の良い思い出と共に生きることが最大の喜びになります。そして良い思い出がたくさんあるほど豊かな人生なのです。むしろそれがない場合は、虚しい老後になってしまいます。
もちろん若くても、折に触れよい思い出に心がホッコリすることは、心の癒し効果になりますよね。
(ただしネガティヴな記憶にまつわるものなら捨てるべきでしょう)
❷未来軸のものは、基本捨てる
それは、将来のためにこれがないと心配であるモノ、すなわち「不安」と同義です。
そしてこの心理は、動物と違い先を見通す能力を持った人間であるが故の習性です。
そこで、つい先のことを考えてしまう傾向が強い場合、
「今•ここ」に意識を常に保つ訓練が必要になってきます。
未来軸のものとは?
①将来役にたちそう、使いそうだからとっておくもの(小物•バッグ類•収納系•文具類・食器など)
⇒うんと気に入っているもののみを残す。ただし量を最小限に減らす
②しまいっぱなしの速読や英会話教材などの教材系
⇒本気で再挑戦する気があるのか?自分自身に深く問いかける
→これを明確にすることは、潜在意識レベルに降りて、進むべき使命・運命なのかを判定すること。
これを今行うべく与えられた最終チャンスと捉える
③サイズが合わないけど、体型が戻ったら着られるはずの服
⇒ものすごく気に入っているも
のなら保留
→期限を決め(例.一年)捨てる
④好きじゃないデザインや色柄だけど使える食器や服など
⇒必ず捨てること
❸他人軸のものは、よっぽど気に入っているもの以外は、まず一番に捨てましょう。
→友人の結婚式でもらったから捨てるのは申し訳ない
→義理の母から譲り受けた不要な大皿
→お土産の木彫りの熊
…など、つい他人の気持ちを忖度してしまい、溜め込んでしまった
モノのことです。
まとめ
なお、ここで「未来軸のものを捨てる」ことと、「すべての心配を手放す」ことは確かに相関関係にあることがわかります。
ここでは、機械的(物理的)に捨てるという、モノに働きかける行為を習慣づけることにより、溜め込む原因となっていた『不安心理』を半ば強制的に解消させていくわけです。
「思い切って捨ててみたら、なんと清々しいことか」
「捨てることの後悔が意外なほど感じられなかった」
「心がどんどんクリアーになってくる」
など、捨てる効果を感じるごとに不安癖が少しづつ解消されてくる。そんな実感をぜひ味わってみてください。
そして、❶で申し上げたように思い出のモノは捨てなくてよいのです。
❷と❸のものならどうでしょう。これならなんとか決心が、つきませんか?
それでも決心がつきかねるなら、❷と❸のものを一旦保留しておく場所を作りましょう。
そして、こころの準備が出来るまで、待ってみましょう。
認知行動療法
なかなか心のお掃除が、うまくいかない場合は、
「部屋の片づけ」をうまく活用するというやり方があります。
これは心理学の分野で認知行動療法と呼ばれる手法。
心のあり方やクセを自ら変えるのは難しいが、「行動」によって心に働きかけ、それを変えていくことが有効とされる。
《参考》
『物理学では物質もエネルギーであるとされる。
モノから波動(電磁波etc.)が放出されている。モノの環境が乱れた状態であると、発せられる波動も当然乱れ、それが脳波と干渉しあって、脳側が乱れるという仮説もありうる。そこで、逆にモノ側の波動を整えれば、脳に干渉して、脳波を整えることが可能となる』
要するに、「片づけ」を思考の混乱を整えるための手段にしてしまうわけです。なおこの理屈は、逆も真なりです。
心が整うに従って、気づいたら部屋が片付かないという問題が改善の方向に向かっているというわけです。
#片づけ #断捨離#捨てられない#捨てなくていい片づけ#認知行動療法
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
