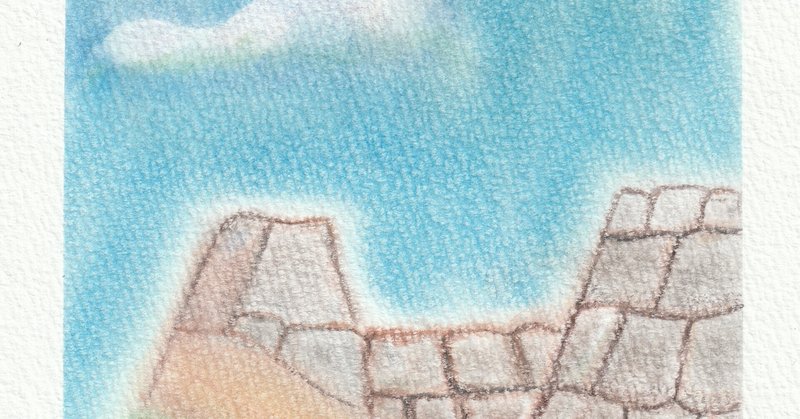
米子城
オフィスのある鳥取県米子市は城下町だ、と書くと、米子周辺を知っている人は首をかしげる。彼らは、米子は商人町だと思っているからだ。しかし、私はれっきとした城下町だと信ずる。
米子城は町中の平城ではなく、中海に望む標高約90mの湊山に築かれ、戦いからの守りを意識した山城。その名は湊山城(みなとやまじょう)。現在は米子城。城の周辺から町が形成されたのは地図をみればよくわかる。今はもう城跡として石垣しか残っていない。
この米子城は応仁の乱が始まる頃に築城されたというから、松江城より古い。山頂の本丸には吉川広家が築いた四重天守(四重櫓)と中村一忠が築いた五重天守がある珍しい城だったらしい。本丸の西北には内膳丸、東の飯山には出丸、さらに山麓にかけて二の丸・三の丸を配し、周囲には中海の海水を引き入れた堀をめぐらしていたと文献は語る。
にもかかわらず米子の人々が商人の町だと主張するには、根拠がある。今でも細かく区切られた町名には、紺屋町、寺町、博労町、大工町、茶町などあり、職人さんと商人達がにぎやかに生活していたと想像できるし、遊郭もあった花園町など地名も残っている。
しかし私が城下町だとこだわるのは米子が地形的に要衝だったことと、城跡の大きさだ。現在の米子市は鳥取県の西部で島根県と隣接し、伯備線・山陰線・境港線の発着駅。高速道路は東西につながり、中国山地をぬけて岡山へと伸びている。戦国時代に城を築く意味もあったというものだ。
それでも敢えて米子市民が「ここは商人町だ」と言って、城を意識したいと思わないのには訳がある。戦国時代が終わり、江戸時代に入ると米子は鳥取藩(因幡の国)の支配下になった。東から藩の代官として赴任してきた鳥取藩主席家老荒尾氏は米子に圧政をしいた。徳川300年の時代が終焉し、明治4年の廃藩置県で米子城は士族に払い下げられた。その士族は年間の維持に明治初期の貨幣価値で370円かかるため、米子城を持ちこたえることができなかった。そこで現・米子市に土地建物合わせて3500円で売却したいと持ち掛けた。だが、米子の人々は、『米子は非生産的な物を買い取るほど豊かではない』と買い取りを拒否した。顛末はわずか37円で道具屋が建物を買い取って解体したという。
解体後、圧政をしのいだ米子市民は、建物の木材を風呂の焚き木にしてしまったというから凄い。いかに虐げられたか、想像に難くない。以後、城の再建計画が何度かあったが実行に至っていない。
山陰も鹿児島に遅れること10日ほどで桜が開花した。米子城跡と中海縁に整備された湊山公園は桜の名所で市民の憩いの場だ。気温も上がり、海から吹く風も心地いい。晴れた日は遠く大山ものぞめる。言うにおよばず桜の木の下では花を見ながら宴会というグループも数多い。けれどもアルコールの勢いをかりてこの場所で、鳥取について褒めたら、大変なことになる。Gvsタイガース戦の東京ドームの一塁側に縦ジマのユニフォームを着て座るようなものだ。どうして、これほど?と何度も思ったが、米子市民のDNAに書き込まれている情報は脈々と伝わっているらしい。
昨年東京からいらしたお客様が、廃藩置県も終わりもう長い時間をたったのだから、いいじゃないか、といわれたが、我、傍らの人さえ、それはならんと首をふっていた。
ゆうこの山陰便り NO.24
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
