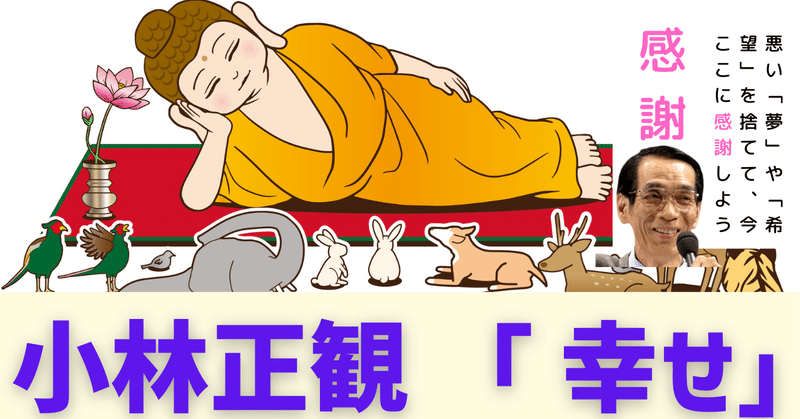
小林正観の「幸せ」①実は「夢」や「希望」にも2種類あった!
それでは、前回の続きになります(^-^)。
前回はないものねだりのように自分にかけているもの、例えばお金とか容姿とか学歴とかを、いつまでも執拗に求めるのは煩悩であり、人生をかき乱してしまう悪い欲求だと整理しました。
そして、究極の心の平安である悟りを目指そうと意欲を発揮してそれを育てたり、仲間を見つけて一緒に仏道に励んだり、そして、まだ悟れていない不幸な境遇な人を(衆生)を救いたいと願うことなどは、積極的な欲求だと、こちらも整理してスッキリしました。
前回はインドで生まれたお釈迦様の考えからそれを整理したわけですが、今回は、わたしたち一般的な日本人がいかに、悪い欲求にとらわれていて良い欲求に目が向いていないか、というのを小林正観さんの本から探ってみたいと思います。
この本はとても示唆的で、わかりやすいイメージでわたしたち日本人が知らず知らずのうちに当たり前と思っていることに疑問を投げかけて、それを良い方向に導くヒントをたくさん与えてくれます。
まず、まえがきにこんな事が書いてあります。
なぜか足りないものだらけの日常生活……なぜこうなった?
私たちは、子どものころから、「あるひとつの教育」を受けて育ってきました。
それは、「今、足りないものをリストアップして、それを手に入れたら幸せだが、手に入れられなければ不幸だ」という価値観です。
たとえば学校で、「数学が不得意」といえば、数学を頑張って勉強しろと言われる。「漢字の書き取りが不得意」といえば、漢字の勉強をしてもっと漢字ができるようになれと言われる。
「根性が足りない」ということになれば、「根性を持て」、「もっと努力しなければいけない」、「もっと頑張らなければいけない」と言われることになります。
「ここが足りない、あれが足りない。足りないものを手に入れるために努力をしろ。頑張れ。努力しないヤツはダメだ」という価値観を叩き込まれました。
「洗脳された」といってもかまいません。私自身、子どものころ、父親からそういう「洗脳教育」を徹底的に叩き込まれました。
「努力しないヤツはダメだ」
「頑張らないヤツはダメだ」
「そういうヤツは、社会的な価値がないんだ。生きていても意味がないんだ」と、何十万回、父親に言われたかわかりません。
99%の人がそうであるように、家庭でも学校でもそういう教育を受けました。
ですから、私も昔は、世の中には「そういう価値観しかないんだ」と思い込まされて育ってきました。
この価値観は、大学生の時遊び呆けているときは忘れているかもしれませんが、社会人になって仕事を始めると、いきなり全開!フルスロットルになりますよね。
つまり、上司と一緒に今年の目標設定をして、朝礼や就業中、帰社するまでずっと「足りないもの」(営業成績など)を針のむしろに座らされてチェックします。

家に帰ったら帰ったで、奥さんからはお金が足りない、と言われ子供からはどこにも連れて行ってくれないとかで愛情が足りないという目で見られ、少しは自分の人生設計をしようかと思っても、これから新しいことをしようと思っても時間がない。
見渡せば周りは「足りないもの」だらけです。
小林正観さんはこれについて、こんな鋭いことをおっしゃてます。
「夢」や「希望」は、人間の向上心からくるものなのか?
「夢」や「希望」という言葉を検証してみます。
「夢」や「希望」というのは、もしかすると…、
足りないものをあれこれ挙げつらねて、
もっとほしい、まだまだほしい、
手に入れたいと言っていること
にほかならないのかもしれません。
「夢」や「希望」という「聞き心地のよい言葉」で、実は、私たちは、「欲望」をかきたてられ、「要求」を宇宙に向かって突きつけるのがいいことだ、とずっと洗脳させられてきたのかもしれません。
この指摘はみこちゃんにはかなり衝撃的でした。
世の中の価値観というものには囚われていないつもりでしたが、「夢」とか「希望」というものを疑ったことは一度もなかったからです。
でも、前回考察したように、欲求に正しい欲求と悪い欲求があるのならば、「夢」と「希望」もまた、良い欲求から出ている「夢」とか「希望」がある。そして、同時に悪い欲求、煩悩から出てくる「夢」と「希望」もある、ということになります!
これは、すごく納得でしたね。

私たちは「夢」とか「希望」という言葉は全部まるごと無条件に肯定してしまっていますが、欲求に「良い欲求」と「悪い欲求」があるのならば、もしわたしたちが「夢」とか「希望」現状苦しんでいるとしたら、それは悪い「夢」や「希望」だということになります。
将来の夢を語らないのは現状の家庭に幸せだからだ!
では、小林正観さんはどのように考えたら良いと言っているのでしょうか。
人間は、「今、いただいているものに気がつき、感謝をはじめる」と、あれがほしい、これがほしいという気持ちが、いちじるしく減っていくようなのです。
「でも、人間には向上心が必要ではないのか」と言う人がいます。一般的にいわれる「向上心」というものは、本当に必要なのでしょうか?
「あれをよこせ、これもよこせ、あれもほしい、これもほしいと言っている人間の向上心」というものと、「あれに気がついて感謝」、「これに気がついて感謝」、「まわりの人に感謝」、「天上界の方々に感謝」をしている人の向上心と、どちらが本当の向上心なのでしょうか。
世の中の出来事というのは、1人でできることなどは、たぶん、ひとつもないのではないかと思います。
「すべてのことは全部、自分以外の方々のおかげで成り立っている」そこに気がついて「感謝すること」のほうがむしろ、人間として向上することなのかもしれません。
私たちは子供の頃から大人に「将来の夢は」と聞かれっぱなしでしたよね。その時に「別に夢はない」とか言ったもんなら、大人はたいてい非難がましくこう言いましたよね。
「夢がないなんて、何てなさけない。子供らしく将来こうなりたい!っていう大きな志を持たなくてどうするんだ、子供の頃から現状で満足しているなんて将来怠け者になるに違いない」

みこちゃんは、実はこういうことを言う子供でした(笑)。ですので、大人からはよく「向上心がない」と非難されました。考えてみればこれはかなり理不尽ですよね。
親からは幸い言われたことはなかったのですが、親から言われて人もいると思います。
でも、よく考えてみるとそれはおかしいです。
子供は今育っているこの家庭が本当に幸せなので、現状生きていることに満足している。満足しているので、早くこの家を脱出して〇〇になりたい、という欲望が出てこないので、それはお父さんとお母さんが作ったその家庭が満点だ!と子供がほめていることになるわけです。
反対に、こんな狭い家は一刻もはやく出て一人暮らししたいとか、こんな貧乏な家は嫌だから将来金持ちになってやる!とか、お父さんがあまりに男として情けないから、素敵な男性見つけてお父さんのことは早く忘れたいとか(笑)、そういうのはみんな現状にものすごい不満があるわけです。
反対に、現状満ち足りている子供は、そういう不純な動機から将来の「夢」や「希望」を語りません。

そのように考えてみると、やはり、手放しで「夢」や「希望」を持つというのは、おかしいですよね。現状を否定したいというのがそもそも不幸なわけですから、現状を正しく肯定すれば、悪い欲求で豪邸で一人暮らししたいとか、金持ちになりたいとか、いい男捕まえるとか、いう発想がない。
こういう悪い欲求からなにか頑張ろうとしても、運良く欠乏動機が満たされたとしても、長続きしないでまた次の欲望にさいなまれますし、たいていそういう不純な動機からなにかやっても、物事うまくいかない。
では、そういう悪い欲求から出てくるよこしまな「夢」や「希望」を断ち切って、正しく現状に満足するにはどうしたらよいのでしょう。
それについても小林正観さんは明確にある言葉を丁寧に説明してくれます。
それは「感謝」ということなのですが、長くなりましたので今回は第1回「小林正観の「幸せ」①実は「夢」や「希望」にも2種類あった!」として第2回で、感謝がなぜ悪い欲求=煩悩を断ち切ることになるのかを考えてみたいと思います。
(^-^)②に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
