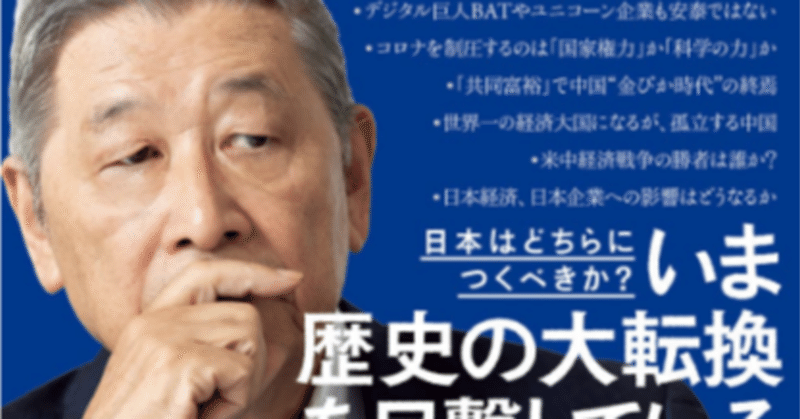
『入門 米中経済戦争 』:全文公開 第6章の7
『入門 米中経済戦争 』(ダイヤモンド社)が11月17日に刊行されました。
これは、第6章の7の全文公開です。
7 「中国は金融デカップリングを恐れていない」という見方も可能
中国への資金流入は増加している
本章の4では、ディディなど米市場でIPOする企業に対して中国当局が規制を強めているのは、米中間の金融的なつながりを切断する経済的に非合理な行動であり、中国の今後の発展に重大な悪影響を及ぼすだろうと述べた。
しかし、この問題については、別の見方をすることも可能だ。それは、中国がコロナ克服に成功したことから、さまざまなチャネルを通じて中国への資金流入が増加しており、そのため、外国市場上場という形での資金調達が減っても、もはや中国は困らない、という見方だ。
だから、情報流出の危険を冒してまで、あるいは中国のプライドを犠牲にしてまで、外国市場に上場する必要はないということになる。
このような見方の背景には、中国の国際収支の金融収支で、つぎのような変化が最近起きていることがある。
①中国対外直接投資の減少
②対中直接投資の増加
③対中証券投資の増加
(注1)金融収支は「直接投資」「証券投資」「金融派生商品」「その他 投資」および「外貨準備」からなる。現在のIMFのルールでは、対外資産が増える場合にプラスと表示することになっている。
国際収支に関しては、つぎの関係が恒常的に成り立つ。
経常収支+資本移転等収支─金融収支+誤差脱漏=0
ただし、中国の公式統計では、IMFのルールとは逆に、対外資産が 増える場合にマイナスと表示しているので、注意が必要だ。
中国の対外直接投資が急減
第1は、中国の対外直接投資の動向が変化したことだ。
企業の海外進出を奨励する「走出去」の後押しによって、中国の対外直接投資はこれまで拡大してきた。2000年代半ばには、経常収支黒字の拡大と海外からの直接投資増大によって資金流入が増加し、国内に過剰流動性をもたらす恐れが生じたため、対外投資がさらに奨励されるようになった。
その結果、対外直接投資は1990年の9億ドルから2007年の248億ドルまで拡大した。その後も、16年まで拡大傾向で推移し、中国の対外直接投資額は世界第2位となった。世界の対外直接投資に占める割合は12・7%にまで拡大した。日本でも、中国資本による不動産の買い占めなどが話題となった。
しかし、17年以降、中国企業の対外直接投資は欧米向けを中心に急減した。19年の中国の対外直接投資は、前年比18・1%減の1171億ドルとなった。
その背景には、つぎのことがある。第1に、不動産業、娯楽・観光業への直接投資に対して、中国当局の管理が強化されたこと。第2に、欧米諸国で外国企業に対する投資規制が強化されたこと。アメリカでは18年8月に「外国投資リスク審査現代化法」が成立した。
ただし、アジアへの投資は「一帯一路」戦略に関連したインフラ建設投資などを中心として増加している。
中国が直接投資の最大投資先国になった
第2は、中国への直接投資が増加したことだ。国連貿易開発会議(UNCTAD)の年次報告によると、2020年の世界の海外直接投資(FDI)において、中国がアメリカを抜いて最大の投資先国になった。対中投資が1630億ドルで、対米投資が1340億ドルだった。19年には、対米2510億ドル、対中が1400億ドルだったのだが、対米新規投資はほぼ半減したのだ。一方、対中投資は前年比4%増だった。
このように、中国の対外直接投資が減って受け入れが増えているので、ネットの対外直接投資は減少している。
ネット投資額は、16年にはプラス(中国対外純資産の増加)だったが、17年にはマイナス(中国対外純債務の増加)となり、20年に至るまでその額が増大している。
対中証券投資も増加
第3は、対中証券投資も増加していることだ。とくに、中国国債への投資が増えている。
香港経由で中国の債券を売買できる「ボンドコネクト(債券通)」などを利用した外国人の元建て債券の保有残高は、過去1年間で約6割増え、2021年3月末には3兆5581億元になった。
外国人の中国国債の保有額は、16年初めには2500億元程度だったが、18年夏には1兆元を超えた。そして、21年5月には前年同月比46%増の約2・1兆元になった。
新型コロナウイルスに対応して、米欧などの主要国は金融緩和を進めた。このため、国債利回りが顕著に低下した。他方で、中国は早期にコロナを克服して経済の正常化を進めたため、10年債の利回りは3%程度を維持している。これに着目した機関投資家や中央銀行が、中国国債を購入していると思われる。
また、人民元高が続いている(詳細は次項で述べる)。これによる為替差益の期待も、国債購入を増やしていると思われる。
証券投資は、15、16年はプラス(対外資産の増加:中国からの外国への証券投資)だったが、17年からはマイナスになり、20年にはその額が拡大している。
人民元高容認が意味すること
中国の経常黒字は、2018年には縮小した。しかし、20年には、コロナ制圧に中国が成功して中国経済が回復したため、増加した。
通常の国であれば、経常収支が黒字であれば、直接投資あるいは証券投資によって、対外資産を増加させる。そして、金融収支はプラスになる。その結果、経常収支と金融収支がバランスを保つ。
ところが中国は、これによって人民元高の圧力が生じることを防ぐため、これまでは商業銀行が企業から、そして中央銀行が商業銀行から外貨を買い取り、外貨準備を増やしてきた。この点で中国は特殊な国だった。
しかし、18年以降は、このようなことはなくなった。アメリカから19年8月に為替操作国と認定されたからかもしれない(なお、認定は20年1月に解除)。
人民元レートは、20年5月から一貫して増価している。20年5月には1ドル=7・1元だったが、21年6月1日には1ドル=6・38元台に達した。7月22日では1ドル=6・47元だ。
前項で述べたように、元高の期待が対中証券投資を増加させ、中国への資金流入をさらに増加させている。
中国がIT企業に対する規制を強めていることは間違いない。これが「第3次天安門事件」と呼べるほどの大きな方向転換であることも間違いない。
問題は、それが中国経済に与える影響の評価だ。本章の4では「深刻な影響があるだろう」と書いたのだが、以上で述べた資金流入状況を考慮すれば、「ニューヨーク市場でのIPOが減っても問題は大きくない」と考えることも可能だ。
1989年の第2次天安門事件の際には、外国からの投資は90年代の初めまでは停滞した。しかし、92年の鄧小平の南巡講話をきっかけに回復した。今回は、すでに資金流入が増加しているのだから、影響はさらに少ないかもしれない。もしそうであれば、中国共産党は自信を深め、今後、さらに規制を強めるかもしれない。
ただし、中国の統計には不透明な部分も多く、最終的な判断はまだ下しにくい状況だ。今後の事態の推移を見守る必要がある。
(注2)中国の統計には、不透明な部分が多い。
第1に、「誤差脱漏」が巨額だ。多くの年において金融収支より額が 大きい。
第2に、「その他投資」とされているものが巨額だ。多くの年におい て直接投資や証券投資の収支より額が大きい。これらが具体的にどのような内容のものであるかはまったく分からない。
この背後には、中国の国際金融取引が香港を通じて行なわれていることがある(第9章の1参照)。また、台湾からの投資がケイマン諸島などのタックスヘイブンを経由していることも影響している(第9章の2参照)。
統計の重要な部分が内容不明になっているのは誠に遺憾なことだが、やむをえない。ただし、さまざまなチャネルを通じての中国への資金流入が、とくに2020年に増加しているという傾向には変わりはない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
