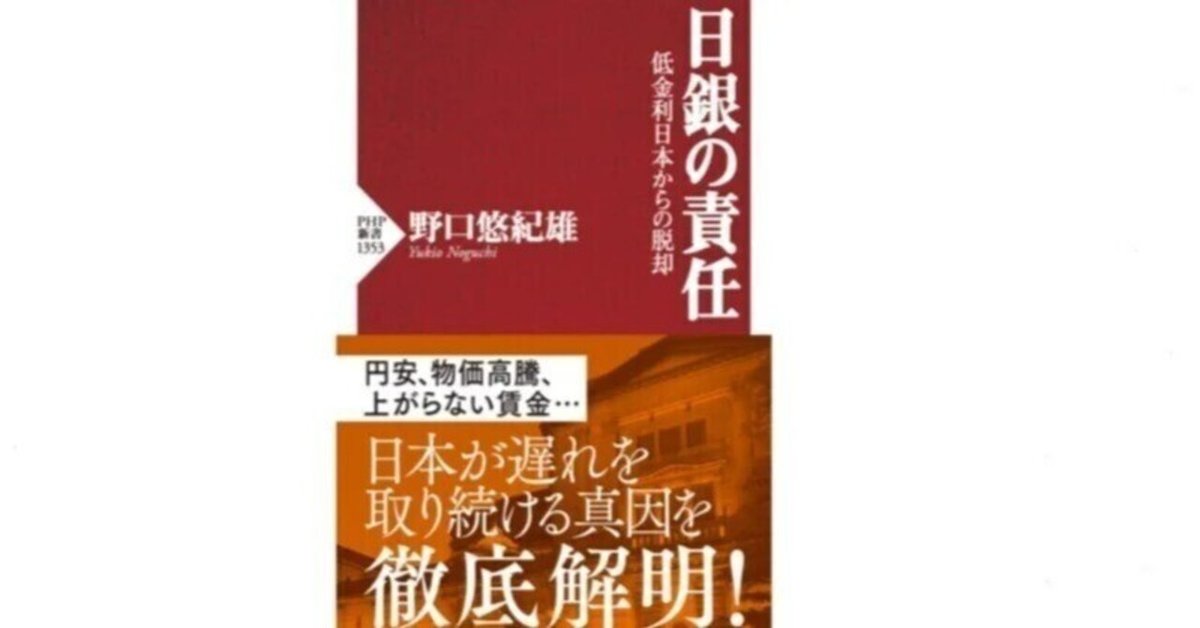
『日銀の責任』低金利日本からの脱却 全文公開:第4章の2
『日銀の責任 』低金利日本からの脱却 (PHP新書)が4月27日に刊行されました。
これは、第4章の2の全文公開です。
2 ー金融緩和で物価が上昇するはずはない
「紙幣を刷った」と誤解している人が多い
前節の最初の項で指摘した第二の問題、つまり、金融緩和が物価を上昇させるメカニズムについてはどうか? 異次元緩和の政策手段は、国債の大量購入だが、これにより、いかなるメカニズムを通じて物価上昇が実現するのか?
多くの人が想像したのは、「国債購入によってマネーストック(貨幣供給量)が増大し、それが貨幣数量説的なメカニズムを通じて物価を引き上げる」ということだった。
多くの人が、「金融緩和政策とは、日銀(あるいは、中央銀行)が、政府から国債を買い、その対価を紙幣で支払うことだ」と考えている。異次元緩和政策もこうした政策であり、「日銀が輪転機を回して日銀券を刷って市中に流通させ、経済をマネーでジャブジャブにした」という説明がしばしばなされる。
こうした理解と、「マネーが増えれば物価が上がる」という貨幣数量説の単純な解釈を結び付ければ、「国債の大量購入によって物価が上がる」ということになる。しかし、この理解は全く間違いだ。
日銀は、政府から直接に国債を買っているのではなく、民間の銀行が保有している国債を買っている。その代金は、銀行が日銀に保有する当座預金に振り込まれる。この結果、日銀当座預金が激増した。
ただし、日銀当座預金は、「マネーのモト」であって、民間の経済主体が支払いや決済に使える「マネー」ではない(日銀当座預金に日銀券を加えたものを「マネタリーベース」という)。当座預金が引き出されて民間銀行の預金になればマネーが増えるが、そうした動きは顕著には生じなかったのである。この意味では、異次元緩和は空振りに終わったのだ。
マネーは増えなかった
マネーが増えなかったことは、統計によって確かめることができる。図表4─1は、2000年から現在に至るマネタリーベースの推移を示す。

日銀当座預金は、2013年から急激に増加した。2013年4月末に61・9兆円であった当座預金残高は、2年後の15年4月末には206・2兆円に増加した。23年2月末の残高は519・6兆円だ。その半面で、日銀券は、ほぼ100兆円のレベルで、あまり顕著な増加を示さなかった。
図表4─2には、マネーストックの推移を示す。「マネーストック」とは、日銀券と銀行預金等の合計である。現代の経済では、銀行預金が重要な支払い手段だ。銀行預金としてどの範囲をとるかによって、M1、M2、M3の3つのデータがある。

M2の平残(平均残高)で見ると、それまでは3%程度だった対前年伸び率が、2013年以降4%程度になった程度の変化しか生じなかった。つまり、異次元緩和で顕著に増えることはなかったのだ。
経済理論では、金融政策が経済活動に影響を与えるのは、マネーストックの変化を通じてであると考えられている。そのマネーストックが増えなかったのだから、物価が上がらなかったのは当然だ。
日銀は、人々の期待が変化し、それによって物価が上昇するという説明もしている。しかし、「期待」などという捉えどころのないものに本気で依存しようとしていたとは考えられない。
実は、仮にマネーストックが増えたとしても、日本の場合には物価が上がらない可能性が高い。実際、コロナ禍で緊急融資が行なわれた結果、マネーストックが急激に増加したにもかかわらず、物価は上がらなかった。これは、すでに述べた「フィリップス・カーブの死」と言われる現象と関連している。
2022年に物価上昇率が高まったのは、アメリカをはじめとする諸国でインフレが生じ、それが輸入物価を高騰させたからだ。つまり、国内要因で物価が高騰したのではなく、外生的な要因で高騰したのだ。
この問題については、第5章の3で「総需要、総供給のモデル」を用いて再び述べる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
