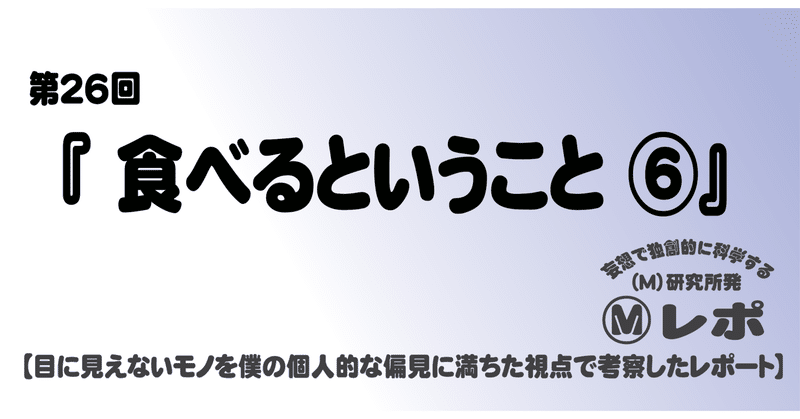
『 食べるということ(6) 』
今回は「食べるということ」の最終回として、靈的な学びも情報エネルギーとして、エネルギー収支の面から「何を食べるべきか」を考察していこうと思います。
今回も十人十色、百人百色の一つとしてお付き合いください。
(※リンク先や画像は検索情報からお借りしてます。フリー素材にも感謝)
・・・・
【「魂」の情報収集 】
「魂(靈)」は学びに貪欲で、常に情報を求めています。
「靈」の世界は時間の制約が無いため「求めること」に対しては一瞬で多くの情報を集めますが、興味がないものには収集能力も働きません。
例えば誰かとすれ違うだけでもお互いに影響し合い、逆に「あたりまえなこと」は気にも留めない能力も高く、情報を整理しながら必要なものを効率よく吸収していきます。
特に自他の違いからの学びは大きく、己の中に無いモノを得る貴重な機会として魂と魂は触れ合います。

違いが大きすぎて「拒否反応」が出ることもありますが、それでも少しずつ吸収し変化して、どんなに刺激的な情報であっても次第に「普通」になっていきます。
実はその普通こそが大事で、他者の中に「同じ」を見つけると安心感が得られ心が安定するため、次なる刺激を求めて情報を収集し始めるのです。
そうやって魂は少しずつ成長を繰り返していきます。

そういった情報収集の機会の中でも、命を伴って食べられる動植物は「食」こそ一期一会として、より多くの情報を得ようとします。
【「食」とエネルギー収支 】
僕たちは「魂」も「肉体」も宇宙という大きな神の一部、神の子(因子)であり、宇宙という情報エネルギーの質と密度を上げ、無限変化進化するよう良いエネルギーを生み続けるために存在しています。
ちなみに「悪魔」とは悪い事の面から他者に学びと変化を与える役職名であり、広く長く見れば大きな喜びを生む存在で、やはり神の子として働きの一つです。

そして僕たちは「食べる」という行為から良くも悪くも情報を生みます。
物質的に見れば「肉体の融合」であり、靈的には「魂の触れ合い」です。
食べられる側は肉体からの情報は無くなり、靈的な面からのみ吸収するため思考感情からの影響はより強く表れます。
神の子としては「何を食べれば良いエネルギーを増やせるか」が大事なのですが、全体をエネルギー収支として見れば分かりやすいかもしれません。
まずは「プラス」となる良いエネルギーの例から。
「肉体」を通じて得る良いエネルギー
・五感から得る「喜び」(食べる側)
・空腹や栄養が満たされる「喜び」(食べる側)

「相手から」得る良いエネルギー
・相手の「喜び」「感謝」(お互いに影響する)
・己に無い情報(相手の経験や知識など)
「己に無い情報」とは、魂の学び(経験)の違いから得るものです。
例えば人と「小さな動物」では、それまでに学んできた情報量がまるで違うため、学びを得て進化するよい機会となります。

それは誰かとの日常会話の中に気付きを得るようなもので、そこから吸収できるものは僅かに思えても、その僅かな成長がその後にずっと影響を与え続けるため、結果的には「大きな喜び」を生みます。

次に「マイナス」となる悪いエネルギーの例です。
前回、前々回にも書きましたが、物理的、靈的共にあります。
「肉体」を通じて得る悪いエネルギー
・苦痛(食べられる側)
・食べ物に付いた毒(血や肉に溜まるもの)
・食べ物に憑いた毒(転写された悪い波動)
・食べ物に加えた毒(薬物や添加物など毒物)
「相手から」得る悪いエネルギー
・死に対する恐怖・苦しみ悲しみの念(想念毒)
・恨み辛みの怨念(想念毒/怨靈に取り憑かれるとずっと受け続ける)
これらプラスとマイナスを元に、個別にエネルギー収支を考えていきます。
【 微生物・植物と人との融和 】

草や微生物には神経が無いので痛みがなく、個ではなく集合意識で生きているため「死」を恐れません。
人との違いは大きく、様々な情報を得て成長します。
(※植物でも樹木は長く生きて集合意識の学びを深めていますから、実や葉を食べる方が良いです)
微生物や植物は人間に食べられることを喜び、人間側も喜びを頂くため良い循環が生まれ、どちらも収支はプラスです。
【 小さな動物と人との融和 】

ここでの小さな動物とは、例えば小魚のように集団行動で生きているような「個の意識」が少ないものをいいます。
感情も知能も控えめなので「死」にも大きな恐怖を感じず、生まれる負の念も少なめです。
動物側は賢くなるほど負の念が増えるため答えは微妙ですが、エネルギー収支はぎりぎりプラスとしておきます。
(※加工食品化されると、マイナスになります)
人間側は五感による喜びもあるので、ぎりぎりプラスです。
【 大きな動物と人との融和 】

ここでの大きな動物とは、人間に近い「知性の高い」動物のことです。
「大きな動物」は思考能力も高く、喜怒哀楽もはっきりしています。
「死」を恐れ強い負の念を生むため、情報収集より恨むことを優先する場合もあります。
動物側は負の念が強く、エネルギー収支は大きくマイナスです。
人間側も強い負の念を受け、大きくマイナスです。
人も動物も負のエネルギーが溜まり、悪循環に陥ります。
【 特殊な例 】
かなり特殊な例として、食べられる側に高度な知能があっても「食べられること」に喜びを生む場合を挙げておきます。
仏教の説話集『ジャータカ』(お釈迦様が「釈迦」として生まれる前の「前世の物語」)に、腹を空かせた僧に我が身を提供しようとウサギが自ら火に飛び込む話があります。
そのように、もし動物が「あなたのような方に私を食べて頂きたい」と心から願うならば、その動物は肉体苦以外は喜びとなるので、意識の高い動物を食べたとしてもエネルギー収支はプラスになります。
まぁそんな人が本当に食べるかは知りませんけど。

もう一つの例は、漫画「ブッダ(手塚治虫)」の登場人物である、予知能力を持った「アッサジ」です。
自らの死期と、己と動物との因縁を理解していたアッサジは、飢えた獣にその身を投げ与えて死んでゆきます。
その存在と死のあり方は、ブッダにとって生涯にわたり大きな影響を与えることとなります。

寿命は決まっている。ならば食べられて他を喜ばせ、因縁解消すればいい、、、
己の寿命を正しく知った上で、過去の因縁を解消しつつ、食物連鎖の中で喜びを生み、自ら穏やかなる「死」を迎える。
その場合は毒となる脳内物質も発生せず、想念毒も憑かないでしょう。
、、、これはかなり難易度の高い選択ですけどね。
【 家畜の思いは? 】
さて、動物たちは「家畜」をどう考えるのでしょうか?
近年、グラスフェッド(牧草飼育)が再注目されています。
「生きた植物から良いエネルギー + アーシングでストレス減」といった効果が期待されています。
もしかすると、檻の中は嫌だけど放牧ならばOKと思うモノもいるかもしれません。
大自然の中で厳しい食物連鎖に生きるよりも、柵で守られた屋根つきの家で人と共に過ごし、多くの喜怒哀楽を学び、寿命が来れば誰かに食べられても良い、、、そんなあり方も否定できません。
まぁ、そこまでいかなくても、動物の自然な死をAIが感知して傷まないうちに処理できれば、毒の少ない畜肉を得られるでしょう。
ずっと先の地球では家畜を食べることは無いようですが、その中間期の人々の欲求を満たすための手段としてどう思うのか、未来の動物たちに聞いてみたいものです。

【 何を食べるべきか 】
結論から言えば「毒物」と「大きな動物は食べない」方が良いと思います。
身魂から毒を減らしていけば次第にエネルギーに敏感になり、自然と細かい答えも分かるようになるのではないでしょうか。
「大きな動物」は食べ続けるほど負のエネルギーが溜まり、食事自体にも感謝できず、負の循環の中でお互いに苦しみ続けます。

さらに昔と違って今のように複雑に加工され流通されれば、「いつ誰に食べられるのだろう? あれれ?廃棄されちゃうの?」と魂の触れ合いもありませんから動物は「苦しいだけ」です。
昔から「三里四方の食によれば病知らず」と言いますが、地産地消といった顔の見える身近なものを食べる生活は、多くの面で良い結果を生むのです。
今は人も動物も「苦し∞苦し」といった「Lose-Lose」の食関係です。
この先は「Win-Win」という「うれし∞うれし」と喜びが循環する食関係を目指したいですね。

そうはいっても、生きるためには選べない場合もあります。
また、肉体がある時だけの「物理的に食べる経験」は貴重ですから「多少の毒を分かった上で食べる」ことも否定しません。
ならば、アイヌ民族の「イオマンテ」のように食べる動物の靈を癒したり、身体のデトックスといったことも、セットで考えるべきだろうと思います。
僕はこれからもビーガンを続けるつもりだし、みんなの選択も自由です。
全ては自己責任だけど、ある程度は因縁をみんなで支え、解消し合うことも地球人類としての課題であり、有意な学びかもしれません。
みんなが総合的に知識を得て、よく考え、必要な量を、そしてなるべく毒の少ないものを食べるならば、きっと自己責任の範囲で何を食べても良いのでしょうね。
・・・・
さて6回に渡って書いてきましたが「食べるということ」はとりあえず今回で終わりです。
「食べる」はどこまでも深いので、また別の形で書いてみたいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
