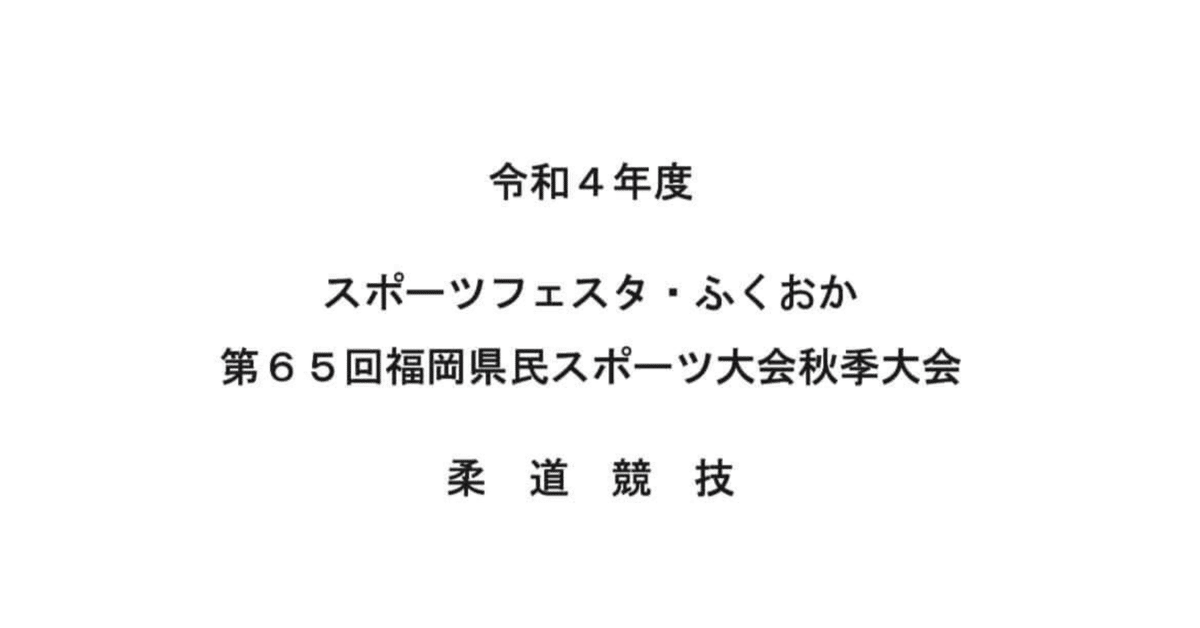
KUNDE柔道してきました【県民スポーツ大会】
KUNDE柔道プロジェクト最初のイベントは、私の地元・福岡県の県民スポーツ大会でした。
9月25日に久留米市の久留米アリーナで開催された福岡県民スポーツ大会秋季大会 柔道競技は、例年通りの一般の部と青年の部での市町村対抗団体戦に加えて、『視覚障害者の部』が公開競技として実施されました。
本来は昨年の大会から実施される予定でしたが、感染拡大によって大会が中止となったため、今年からの実施となりました。
昨年は、実際に視覚障害者柔道家を集めて試合を実施する計画でしたが、競技人口が少ないことから試合を行うのに十分な選手数が確保できず、視覚障害者柔道のデモンストレーションを行うということで準備が進んでいました。
今年はそれに加えて『KUNDE柔道』という新たな競技方法が考案されたことを受け、視覚障害者柔道の紹介・デモンストレーションに加えて、視覚障害者柔道選手と晴眼の高校生とでKUNDE柔道の試合を行うことになりました。
KUNDE柔道の詳細についてはこちら
こうして自分の地元で最新の取り組みを実施できることはとても嬉しく思います。大会を運営してくださった皆様、ありがとうございます。
福岡は非常に柔道が盛んな地域です。今後KUNDE柔道を広く普及するにあたっては、ここ福岡を起点として展開していけたらと思っています。
・・・・・
今大会では一般の部、青年の部のそれぞれ準決勝までが終了後、決勝の前に視覚障害者の部が実施されました。

視覚障害者の部の様子はYouTubeで公開しています。(これのためにチャンネルを開設しました。)
動画はやや長いですが、視覚障害者柔道、KUNDE柔道を知っていただくためにぜひじっくりと見ていただきたいです。
特に、小志田先生によるルールの説明などは、とても詳細に解説してくださっているので、ぜひ!
概要欄にタイムスタンプも貼っているので、参考にしてください。
私も高校生とKUNDE柔道で試合をしました。
実際に試合をして気づいたことは、対戦してくれた高校生・堤くんがこのルールでの戦術を事前にしっかりと考えていたという点です。
KUNDE柔道は常に接近戦なので、腕力でいかに相手の体や腕の動きを制することができるかがポイントです。そのことに彼は気づいたようで、序盤から私が引手を絞れないように体を左前方に倒すようにして釣手を浮かせていました。
おかげで私は非常に攻撃が難しくなりましたが、彼がそのように考え、作戦を立てていたことに驚くとともにとても嬉しく思いました。
私のこれまでの経験や感じ方からすると、視覚障害者柔道の技術というのは、当事者以外にはほとんど見向きもされません。仮に柔道経験者であっても、視覚障害者柔道の技術を探究したり試合においてこれを批評したりする人はほとんどいません。健常者の大会では、誰の試合のあの技は良かったとか、こういう入り方があるのかと勉強になったとか、あの選手のこの動きは合理的でないとか、あそこはこの技をかけるべきだとか、そういった批評がメディア上や仲間内の会話で展開されます。しかし、視覚障害者柔道については、技術を知らないのか、遠慮しているのか、そもそも興味がないのか、こういった批評をしてくれる人はほとんどいません。
これはつまり、視覚障害者柔道の技術を探究・批評・議論する場面はほとんどいないということであり、それはつまり技術体系の発展が遅いことを意味するのではないかと思っています。
私は以前からずっとこの点を改善したいと考えていました。
なぜ、誰も技術の批評をしないのか。答えは簡単でした。当事者でないからです。組み合ってから始める柔道は経験がないし、今後やる予定もないので、その技術について探究する必要がなければ興味もない。一般の柔道の技術を探究し、批評・議論するのは、自分や教え子の稽古や試合に活かせるから、もしくは以前にそうした経験があるからです。
つまり、視覚障害者柔道の技術を発展させるためには晴眼者を当事者にしてしまうことが必要なのです。
そこで『KUNDE柔道』です。
晴眼者も組み合って始めるスタイルを積極的に実践するようになれば、技術の探究・批評・議論は活発に行われるようになるでしょうし、それによって視覚障害者柔道の技術も大きく進歩することが期待できます。
これも私がKUNDE柔道を普及させたいと思う理由のひとつであり、こうした理由から、今回対戦してくれた堤くんの姿勢はとても嬉しく思いました。
参加してくれた高校生の皆さん、ありがとうございました。

・・・・・
今後私は、組み合って始める柔道の技術について研究をしたいと思っています。
私自身は全く技術派の柔道家ではないので、この研究に適しているとは思いませんが、KUNDE柔道を通してその技術を明らかにし、晴眼者が組んで始める柔道を実践するメリットを提示したいと考えています。
そして、これが、組み合って始める柔道の技術に関する議論のキッカケにもなれば良いなと思っています。
まずは普段の稽古の中で少し試してみる程度でも良いので、どうか、たくさんの方々に協力をいただきたく思います。
『KUNDE柔道』をどうぞよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
