
FLE x ICT Expo 2019から広がるカジュアルでフラットな学びの場(1)
ゲストスピーカーとしてお招きいただきました。今回はADE仲間が4人も登壇ということでそちらも楽しみでした。

幼児教育から大学まで、ICT x 大学でわっしょい!
主催の神谷先生。実は、本当にわっしょい!っておっしゃっています(笑)研究会の始まりはいつもこれだそうで、しょっぱなから面白い。
研修会とか学会って堅苦しいものが多いのですが、FLE x ICTは肩の力を抜いて学べる場という印象。特に、幼児教育から大学という幅の広さは通常ではありません。年齢で「この学年にはこの学び」というのではなく、むしろ子どもの教育から学ぼうという姿勢にわたし背筋がのびました。

ADE2015タンタンこと反田先生
ADEとはApple Distinguished Educatorの略で、2年に一度全世界から600人程度選ばれる教育者の輪です。今回はたまたま4人が居合わせました。それぞれの実践をご紹介します。
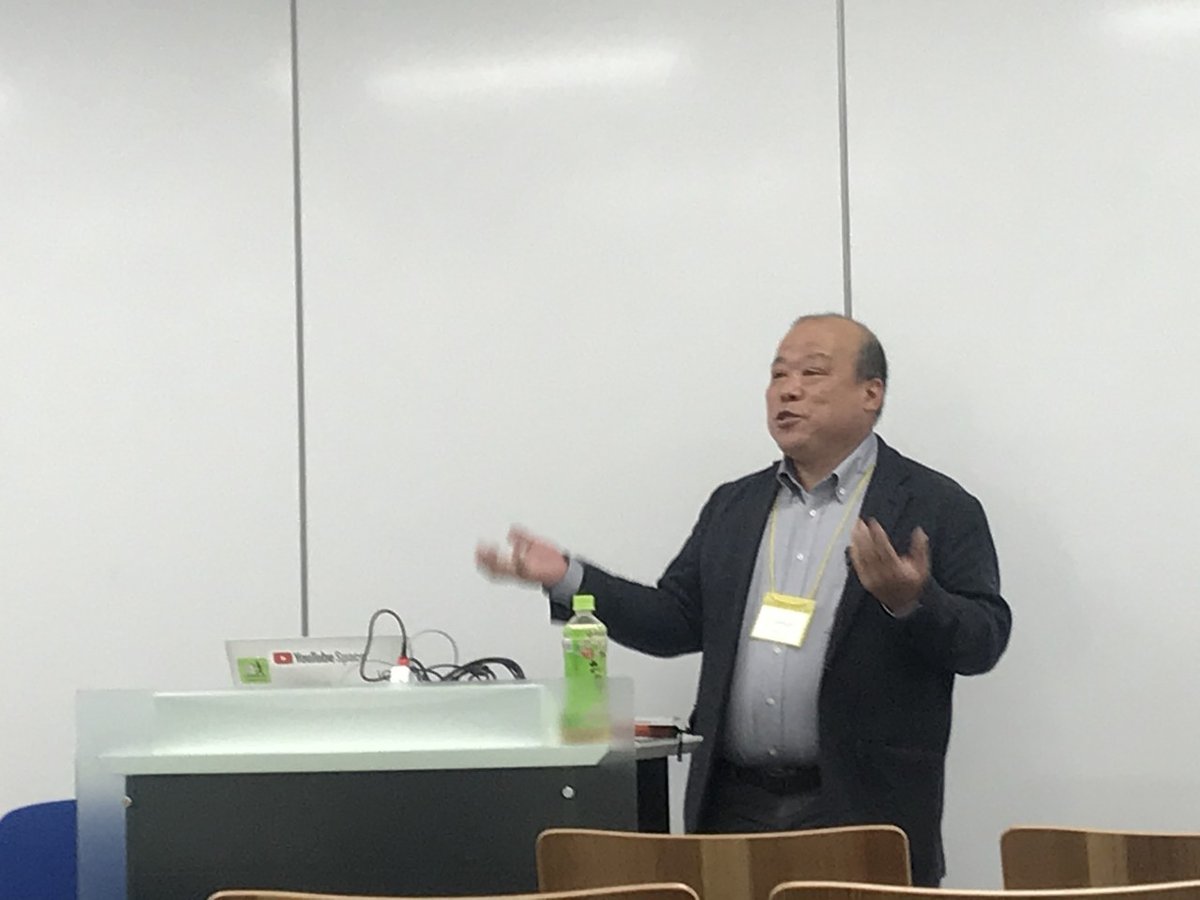
STEM教育をより身近にという反田先生。大学の栄養学の先生にもご協力いただいているというお弁当プロジェクトは幸せを運ぶ素敵な取り組み。STEMというと難しそうという印象ですが、身近なお弁当を題材に生徒は英語だけでなく感謝の気持ちや、大学生とのやりとりを通じてコミュニケーション力も身につけたようです。

ADE2015のDavid Wingler先生
オススメの自作アプリを提げての登場です。
動画の中の生徒たちが楽しそう!次男に一度させてみようと思います。英語教育のアプリは個人で勉強するものが多いのですが、これはチームでゲーム感覚で学ぶことができます。

教えてらっしゃる学校での一コマ。休み時間なのに単語で盛り上がって、止まりません。

クラスルームティップスも紹介。

さいごに
どの先生のも面白かったのですが、やはりADEの実践を聞くのは楽しい。STEMはわたしも以前書いたと思いますが、料理との親和性がとても高いんです。お弁当プロジェクトでは生徒の意外な一面も知れたようです。
ADEはいろんな背景からの先生がいらっしゃるので、代が違っても「この辺でコラボをお願いしたい」というところから話が広がります。学校の枠を超え、年齢の枠をこえた学びの連鎖はわたしも学びたいところです。
次回のブログではそれ以外のADEの紹介と、実践についてです!
いただいたサポートで参加者がハッピーになる仕掛けを増やします^^
