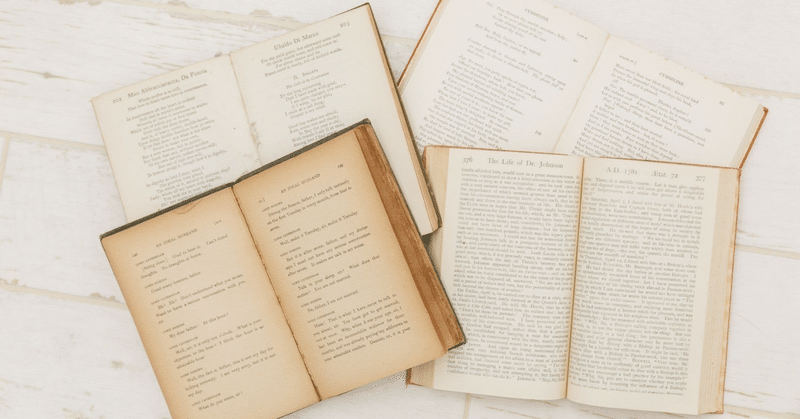
読書記録3
2023年9月
幅広いジャンルを読めた気がします
・エゴイスト
著者 高山真 小学館文庫
ボーイズラブの話かと思い読んだのですが、読むと家族愛の哀しい話だった。良い意味で期待を裏切られた。最近読んだ本の中では短めで、サクサク進んでいく文章ですが、胸を重く打つ感動と読了後の放心感はすごかった。
「愛」というものを相手に伝えるのはとても難しいことで、自分の思う「愛」の表現の形が、いつのまにか相手を傷つけてしまっていることもあれば、暗闇から引き上げるきっかけになることもある。
愛なんてものは結局は自分のエゴの究極系なのでは、と私はひそかに思っている。
十四歳で癌で母親を亡くした主人公浩輔は、自暴自棄までとはいかないがどこか自信を投げているような、そんな生き方をしていた。ゲイの男と付き合い、貪るようにセックスをして、別れる。それを繰り返していくうちに「恋」に距離をおくようになった。ある時、体の緩みを友人に相談したところ、龍太というパーソナルトレーナーを紹介される。彼と会って、トレーニングをし、抱いて抱かれるという関係を重ねていくうちに浩輔は龍太に惹かれていく。その後、なんやかんやあって二人は恋人同士になるのだが、やはり真っすぐに幸せになることはできない。
同性愛が当たり前のこと、なんの批判も反発もないこと、世間に全面から受け入れられていたとしたら、ふたりは悩まず自分たちの愛を信じることができただろうか?龍太にとって体を売ってお金を得ると言うのは、どうしても悲しくて虚しいことであるし、そんな自分を大事に思えるかと言われれば難しいことだったのだろう。
愛とエゴの違いは何か。自分が今龍太に向けているものは愛ではなく、エゴで、独りよがりのこれは龍太を苦しめているかもしれない。そんな葛藤が浩輔を襲い、こちらも読んでいてなかなかしんどくなる。
自分のエゴなんだから、という言葉で正当化している行動はいつの間にか相手に重い負担を強いているのかもしれない。でもそれは間違いなく「愛」であり同時に「エゴ」なのだろう。
ここまで読むとボーイズラブものだと思われるかもしれないが、正直そんなことはどうでもいい。一番に描かれているのは「母が息子を思う心」そして、「息子が母を思う心」。そして、「愛」。歪んでいるように見えてもそれはやはり「純愛」で相手のことを最大に想った結果なんだと思う。
浩輔のやったことはエゴなんかではないと、私は感じている。本当にやさしさに溢れている物語。
ところで、この本は作者である高山真さんの自叙伝的小説らしい。彼はもう亡くられているとのこと。ご本人は天国などを信じていないらしいが愛した人たちと天国で再会していることを願ってやみません。
「性愛も血縁も超えた愛のカタチ」
なるほど、その通り。
・みんなちがってみんなステキ―LGBTの子どもたちに届けたい未来—
著者 高橋うらら 新日本出版社
LGBT(Q)について考える機会が多くある。
それは学校の授業であったり、ニュースであったり、Twitterであったり。いろんなところ、いろんな場面でその言葉を聞くようになった。それはこの数年でより顕著にみられると感じられる。
ただ、私たちは「耳にしている」だけであり、本当に当事者の苦悩をわかっているかと言われると一概には言えないだろう。私たちが知っている、想像していることなど、当事者からしてみれば全く違うのかもしれない。
LGBTの人たちは、AB型や左利きの人と同じ割合でいるというから少し驚いたが、落ち着いて考えるとそうも驚くようなことではない。人の好み、趣味、考え、性格が多種多様無限にあるのだから、性的少数者だって身を潜めてはいるがたくさんいるはず。
ひとりじゃないと思えることで大きな力をもらえる。
この本には「ReBit」という、LGBTへの理解を深める活動をしているNPO法人団体の活動と当事者のエピソードが描かれている。LGBTと聞くとどうしてもゲイやレズビアンなどの同性愛者を想像してしまうのだが、トランスジェンダーの人もなかなかつらい思いを抱いてこの世を生き抜いていると気づかされた。
LGBTのことを完全に理解するのは難しいが、それでも当事者に寄り添うことはできる。
彼ら、彼女らが「同性が好きなんだ」「心と体の性別が逆なんだ」と他人に伝えても「そうなんだ!」と言って、笑いあって当たり前のこととして受け入れられる社会になったら良いと思った。
・みんな自分らしくいるための はじめてのLGBT
著者 遠藤まめた ちくまプリマ―新書
今月二冊目のLGBT関連の本。
人は知らないうちに「当たり前」を固定化してしまっていることがあり、それが知らず知らずの間に人を傷つけてしまっているかもしれない。女に「彼氏できた?」男に「彼女できた?」だったりとか三十を超えた人に「結婚しないの?」だとか。
「女性は男性を好きになり、男性は女性を好きになる。人間は異性と恋に落ちやがて結婚する」みたいなことが前提として居座っているから、そういう発言が出るのは仕方ないことなのかもしれないが、それが刃になっている可能性がある。そもそも、この世のすべての人間が恋愛をするわけではない。したいと思ってない人、恋人がいなくてもいい人、恋愛感情が理解できない人、いろんな人がいる。
結婚指輪をしていない先生を見つけたら、あの人結婚してるのかな気になるな結婚しないのかなできないのかな、なんてコソコソ噂しあうような場面も「人は結婚するのが当たり前」というのが薄く漂っているからのように思えた。学校と言えば、最近は保健の教科書でもLGBTのことや、結婚することだけが「幸せ」ではない、といった記述が追加されている。昔の教科書は「思春期になると”異性”のことが気になってきます」と書いてあったというから、相当な進歩ではないか?
同性愛、両性愛、トランスジェンダーなどの性的少数者の場合、しばしば自己を偽らなくてはいけない場面に追い込まれる。好きでもない異性のタイプを答え、着たくもない服を着用し、必死に異性愛者やシスジェンダーのふりをして生きなければいけない。それは精神に酷い負担を与えるのだ。
・夏の庭 The Friends
著者 湯本香樹実 新潮文庫
三人の少年たちのひと夏の物語。
木山、河辺、山下の小学生三人組は、町はずれでたった一人で暮らす老人を夏休みに観察することにした。きっかけはいたって単純で、山下のおばあちゃんが亡くなり彼が葬式に行ったことで、河辺が人が死ぬ瞬間を見たいと言い出したから。最初は渋っていた木山と河辺だったが、結局おじいさんを「観察」することにする。ただの観察だったそれは、次第に暖かい交流へと変化していく。
生きていれば誰もが一度は「死」について考えるだろう。死んだ人はどこに行く?死体はどうなる?「死」は私たちに根源的な恐怖を抱かせるものであると同時に、好奇心を掻き立てる存在でもあり、時には淡い期待を寄せる対象となるものでもある。
大人と子どもの関係というのは不思議なものだと思っている。大人が子どもにいろんなことを教える存在であると同時に、子どももまた大人に知らず知らずのうちにいろんなものを与えているのだろう。
交流していくうちに、三人を泥棒扱いしていたおじいさんが彼らに心を開き、少年たちもまたおじいさんと会うことを楽しみにするようになる。その過程が暖かく、微笑ましい。三人の少年にとって、この夏休みはかけがえのない思い出となるだろう。
大人になって、三人でまた集まって、この夏のことをしみじみと語っていたら良いなと思った。
・怪物
脚本 坂元裕二 監督 是枝裕和 著者 佐野晶 宝島社文庫
安藤サクラら実力派俳優が主演をつとめた映画のノベライズ。この映画を見に行きたかったのだが、結局映画館に足を運ぶことは叶わなかったため、小説で味わうことにした。見に行った人に感想を聞くと、「おもしろかった」「深かった」「最高だった、狂いそう」のような肯定的なものから、「意味が分からない」「後味悪い」「何が言いたいのか理解に苦しむ」などの否定的まではいかないがネガティブなものまで多岐にわたっていた。人によって好き嫌いがわかれるということだろうか?どんなジャンルにしても好き嫌いが分かれると言うのは当たり前のことであるのだが、この作品はそれがより顕著な気がした。
全体は三つの章からなる構成になっており、Ⅰはシングルマザーの早織、Ⅱは担任教師の保科、Ⅲは早織の息子の湊によってそれぞれ語られる。
ある時から、息子の湊が不審な行動をするようになる。以前よりも反応が淡白、髪を風呂場でバッサリ切る、スニーカーを一足なくしてくる、水筒の中に石や泥が入っている……。それが続き、早織は学校でのいじめを疑うようになる。担任教師もこれに加担しているのかもしれない。そう目星を付け、学校に直接言いに行くが何とも言えない対応をされてしまう。
目線が変わり語られていくにつれ、不可解だった点が結ばれ一本の線になっていく。人間くさいすれ違い、人間であるがゆえの葛藤や防衛本能が怪物を生み出していくのかもしれない。
自分が今見ている景色が全てだと思わないこと。いつか必ず、道が開ける。それが明るいものなのか納得のいくものなのかはわからないし、そうなる保険もどこにもありはしないが。
・乱反射
著者 貫井徳郎 朝日文庫
読んだ後、少しドキッとさせられる。
「これくらい大丈夫」「ちょっとくらい手を抜いたっていいだろう」みたいに思って行動すること。こんなことは誰にでも経験があるはず。例えば、家庭ごみをサービスエリアのゴミ箱に入れる、散歩時の犬の糞を放置しておく、たいした病状でもないのに夜間診療をやっている病院にいって混雑を避ける。他にも挙げていけば枚挙にいとまがない。そんなこと自分はやらない!と思う人もいるだろうが、他にはどうだろう?人間、何かしらひとつはそうした「小さな罪」を犯している。
ひとりひとりがやったことは、たわいもない小さな罪なのだとしても、それが偶然によって重なっていけば酷く痛ましい事件となってしまう…かもしれない。だが、その場合、被害者の怒りはどこに向ければいいのか?誰に罰が与えられる?残念ながら、誰も罰せられることはない。ひとりがやったことは法律で犯罪として指されるはずもないことだからだ。
この話はそれをこれでもかというほど描いている。ほんの小さな、何気ない悪事、非常識、怠惰、暇つぶし、責任転嫁、虚勢。最初は群像劇的な感じで物語が進行していく。しかし、各人物の行動がそれぞれリンクしていき彼らの「小さな罪」が見事に重なり合った結果、事件は起こった。こんなにうまく重なることなんてあるのだろうかと思う自分がいる一方で、強く否定できるというわけでもない。
「加害者」という形で呼ばれる小さな犯罪者たちは、自分の何気ない行動が人死にに繋がったと知っても、謝罪の意思も責任を持つ姿をもまるで見せもしなかった。むしろ、「自分は悪くない」と責任を放棄し、被害者を追悼しようともせず、自己防衛に走る。それには読んでいて憤慨を感じたが、もしも自分がこの状況に置かれたとき、同じ思考と行動に至らないと言えるだろうか。
ともあれ、この著者は人間の描き方が途方もなくうまく、たしかにこんな人いそうだよね、みたいな妙な現実味がある。近所に住んでいるかもよと言われても、全く違和感を感じない。登場人物はたくさんいるが、それぞれに濃いリアリティがある。彼らのほとんどが自分を正当化する自己中心的な人間だと感じて、読んでいてとてもイライラしたが周りにはこういう人間がゴロゴロいるし、自分もそのうちの一人なのだと思った。だからこそ、この物語は他人事だと、所詮創作話だと笑い飛ばすことができない。
・他人事
著者 平山夢明 集英社文庫
なんでこの本を読んだのか?と聞かれたら私も困る。本を買うとき、書店に並ぶ背表紙をザーッと流し見していって、気になったタイトル、目に入ったタイトルのものを引っ張り出す。そして、あらすじを読み、中身を数行読んで購入するかを決める。この本もそうやって出会った。
数行読んで理解した。これはマトモじゃない!裏表紙を見て、胸糞が悪い話の寄せ集めだと察したが本を棚に戻すことができなかった。そのまま何かに操られるかのようにレジに持って行き、購入した。
どうしてこうなってしまったのか、なにが原因だったのか。何もわからないめちゃくちゃで、残酷で、無様な運命が各話の登場人物を襲う。人間の闇とか、そういう陳腐な言葉では言い表せない「理不尽」を煮詰めに煮詰め、最悪な形で提供しているかのような。
最後に報われる話なんて、何もない。皆、絶望の中廃人になって、あるいは血や内臓を撒き散らして、あるいは肉塊となって、終わる。一文字一文字を目に入れて読み、繋げていくたびに胸をえぐらえて、気分が悪くなってそのまま倒れてしまいたいくらいの気持ちになるのに、なぜだか読むのをやめられない。
まさに、「尻の穴が開き、脇の下がトプトプしてしまう」感じだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
