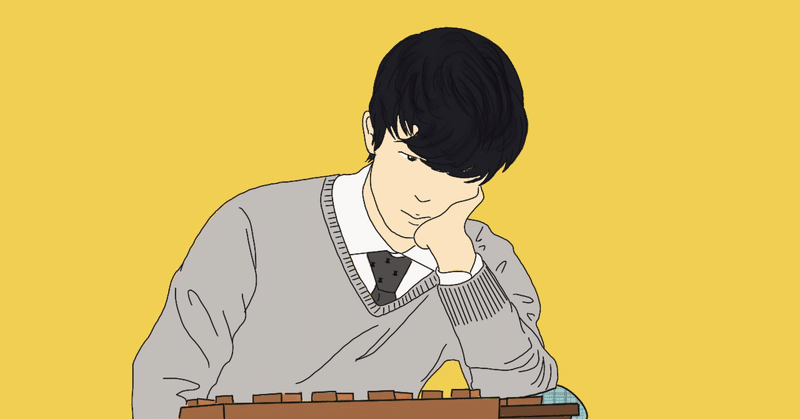
おとなになって「将棋」をはじめ、「初段」になるまでにやったこと
2014年7月に将棋をはじめて、2019年4月に念願の初段となれました!

将棋は小学5年生で1ヶ月ほどクラスでブームとなり、戦法・囲いもわからないまま、飛車をぶん回して遊んだくらい。時は経ち大人になって、ふとしたきっかけで「将棋ウォーズ」というアプリに出会い、将棋のおもしろさに目覚め、今では大切な趣味の1つとなっている。
このnoteでは、大人になって将棋をはじめた初心者が、どうやって初段にたどり着いたのか、実施したことやどれだけ時間がかかったか、をざっくり書いてみようと思います(がんばった努力の供養として)
☖ ☗ ☖ ☗ ☖
【前提】
以下、自分ひとりで進んでいったように見えるかもしれないですが、ありがたいことに下記のような環境で楽しみながら将棋を「続けられた」ことが、初段になれた一番の秘訣と感じています。
会社の将棋サークルに所属し、メンバーと楽しみながら切磋琢磨できた(一人だと挫折していた…)
将棋サークルにプロ棋士の先生が定期的に指導に来てくださり、弱点や悩みを気軽に相談できた
年に2回、全国の会社対抗での将棋大会(職団戦)に参加でき、がんばる目標があった
会社の将棋メンバーと、街の道場や将棋イベント、将棋合宿(杉の宿 @湯河原)に行ったりと、将棋のモチベーションが上がる機会があった
TL;DR
4年8ヶ月(2014 / 7〜2019 / 4)で初段になれた
30→4級:2ヶ月
「四間飛車」で、攻めと守りの型を覚えて勝てるように(特に守り)
4→3級:2ヶ月
「量」をこなし将棋に慣れることで勝てるように
3→2級:16ヶ月
四間飛車の攻めが難しく勝てなくなった。。
居飛車に転向し「矢倉」を覚え、少し攻めやすくなった
「手筋」を覚えて勝てるように
2→1級:14ヶ月
矢倉の攻めがこれまた難しく、勝てなくなった。。
「右四間飛車」を覚えて、グングン勝てるように
「相手の戦型に応じた序盤の駒組み」を覚え、苦手な攻められ方を克服した
1級→初段:22ヶ月
右四間飛車を組めないときの勝率が悪くボトルネックに。。
「角換わり」を第2戦法に加え、ボトルネックを克服した
3手詰を10秒以内に解けるまで繰り返すなど、「終盤力」をとにかく鍛えた
※段位はすべて将棋ウォーズのもの
☖ ☗ ☖ ☗ ☖
将棋をはじめた最初のころ(4ヶ月間)
30→4級
・かかった期間:2ヶ月
・対局数:53局
・得意戦法:四間飛車
4→3級
・かかった期間:2ヶ月
・対局数:57局
・得意戦法:四間飛車
将棋ウォーズと出会い、エフェクトが出てくる楽しさや古臭くない雰囲気に魅了され、将棋を強くなりたいと決意。ただ、何をしたらよいかわからなかったので、いろいろと調べた結果、まずは安定の羽生先生の本に落ち着いた。
この本で、将棋には囲いや戦法があることを知り、すごく衝撃を受けた。特に戦法は自分の奥底にあった厨二心をくすぐり、格闘ゲームでキャラクターを選ぶ感覚で、自分にフィットした戦法を使いこなしたいと強く思った。
そこからは、どの戦法にするかをいろいろ悩んで、いろんな本に手を出した結果、振り飛車の大家である藤井猛先生のこの本に出会った。
この本はとにかくわかりやすかった。1手1ページの設問形式で解説が進んでいき、なぜその手を指すのかが、初心者にもわかりやすくロジカルに書かれていた。よくある将棋の本だと、棋譜の羅列が並んだ解説がどんどん進み置いてけぼりになることに辟易していたので、まさに渡りに船。この本で、明確に「四間飛車」を指そうと決意した。

この本を読んでから、将棋を適当に指すことは無くなり、ちゃんと囲いをつくり、攻めの形を整え、相手にぶつかっていくことを覚え、変な負け方が極端に減った。
この本は後半から難しい変化も多くなり、そのとおりに相手が指してこないこともあり、自分にとっての価値は薄れてきたが、最初3分の1ほどを丁寧に読むことに価値があった。なので、何度も読んだ。
序盤の構え方や気をつけるべき変化、攻めのタイミングや囲いの発展のさせ方など、基礎をしっかり覚えられただけでもだいぶ違い、量をこなすことで勝率もついてきて、結果3級まで苦労なく昇級できた。
☖ ☗ ☖ ☗ ☖
最初のおおきな壁だった2級(16ヶ月間)
3→2級
・かかった期間:16ヶ月 ※うち半年ほどは将棋を離れてしまった
・対局数:169局
・得意戦法:四間飛車、矢倉
四間飛車で将棋の基本を覚え勝てるようになったが、3級になるとだんだんと思うように勝てなくなっていった。
相手の攻めが的確になってきたり、速攻で攻められて受ける間もなく潰されたり。ただ、1番問題だったのが、「うまく攻め込むことができなかった」ことだった。
四間飛車は一般的に「カウンター型」の戦法のようで、相手の攻めをいなしながら反動で攻めていくスタイル。本のとおりに相手が攻めてくれば攻めが決まるのだが、本のとおりに攻めてくることは稀で、違った攻めをされたときに上手くカウンターできず、結果押し込まれて負けるというモヤモヤした将棋をしばらく指していた。
ちょうどそのころ、プロ棋士の先生にご指導いただいたとき、「あなたは居飛車のほうが向いてますね」とアドバイスいただいた。
どうやら、自分はコツコツと覚えて積み上げていくスタイルが得意で、そういう人は居飛車が向いているらしい。反対に振り飛車が向いている人は、指しまくっていくなかで強さを身につけていける人が向いているとのこと(正確に覚えてないが、ざっくりとそういう意図だったと思う)
それからは、前述した羽生先生の本にも書かれていた、居飛車の代表格である「矢倉」を指し始めた。
この動画の説明がわかりやすく、矢倉いいなと思った
矢倉は自分から攻めていくスタイルにもできるので、四間飛車のころよりも指していて楽しく、少しずつ勝てるようになっていった。ただ、矢倉の攻めは分岐が多く複雑で、指しこなすには時間がかかった(結果、指しこなせず、後に話す右四間飛車に転向した)
そんなこんなでそこまで棋力は上がらず、3級の達成率40%ほどをウロウロし、将棋から少し距離を置く時期があったりとムズムズ停滞していたころ、この本に出会い、開眼して棋力がググッと上がった。
級位者がぜったい知っておくべき手筋が一問一答形式で、200問ほど載っている名著。
各駒の使い方の手筋、囲い崩しの手筋、受けの手筋、あと有り難いことに「端攻め」の手筋まで載っていて、1ページめくるごとにこんな技のかけ方があるんだ!とワクワクしながら読んだのを覚えている。1回読んだだけでは絶対覚えられないので、最低3周することを強くオススメする(それくらい良本)

この本をコツコツ解いていくうちに、攻めに厚みが出てきて、序盤・中盤・終盤すべての棋力が上がっていくのを感じた。結果2級になれたのもこの本の恩恵が大きかったと思う(とはいえ、すぐに棋力が上がることはないので、時間はかかった)
この本は、そのあと初段になるまでに4〜5周は問いた。
☖ ☗ ☖ ☗ ☖
どんどん道が険しくなる1級(14ヶ月間)
2→1級
・かかった期間:14ヶ月
・対局数:556局
・得意戦法:矢倉、右四間飛車
ようやく2級に上がれたものの、さらに道は険しくなっていった。
格上の1級や初段に勝てないと達成率は上がらず、またこのレベルになると、さまざまな戦法をある程度指しこなせる相手が増えてくるため、対策をしていないと序盤で戦力差がつき、そのまま押し込まれて負けるケースが増えてきた。
矢倉の攻め方をつかめていないままであったこともあり、手筋を覚えても、なかなか勝率が上がらず苦しかった。

そんなもがいていくなかで、一筋の光が見えてきた。
「右四間飛車」という戦法だった。

高い攻撃力を誇り速攻も狙えるので、相手の出方に左右されず、「自分の土俵」に持っていける。右四間飛車に対する相手の出方も、分岐がそこまで複雑でなく、コツコツ覚えていく派の自分との相性もバツグンだった。
そこからは、以下の本やYouTubeをもとに、数パターンの攻め方を身に着け、格上相手も撃破できるまでに指しこなせるようになっていった。
右四間飛車については、プロ棋士の遠山六段も推奨しており、級位者で戦法がうまくフィットせず伸び悩んでいる方には、一度指してほしいオススメ戦法。
また、もう1つ厄介ごと。
2級になると、自分が右四間飛車を指しこなしてくるように、相手もいろいろな戦法を指しこなしてくることだ。
特に右四間飛車に持って行きにくい戦法を相手が指してきたとき、ある程度互角に指せるように準備していないと、気づいたら相手の術中にはまる、ということがよくあった。
なので、ゴキゲン中飛車や升田式石田流、筋違い角など、使用する相手が多い特定戦法については、YouTubeをみて、個別対策をぼんやりと頭のなかで覚えて、指せるぐらいにはした。
クロノさんのYouTubeには、本当にお世話になりましたm(_ _)m
※クロノさん主催の将棋大会にも参加でき よい思い出に
このようにして、「右四間飛車を指して優位に立つ」「相手の土俵戦法に入っても互角に指せるようにする」 でジワジワと勝利を上げていき、念願の初段まであと1歩である、1級までたどり着くことができた(手筋本は引き続きコツコツとやっていた)
☖ ☗ ☖ ☗ ☖
あきらめなくて良かったと感じた初段(22ヶ月間)
1級→初段
・かかった期間:22ヶ月
・対局数:974局
・得意戦法:右四間飛車、角換わり
「右四間飛車」+「基本手筋」で格上も倒せるようになり、初段へもこの調子で行けると思いながら、1級へ昇級したのもつかの間。そこから約2年ほど修行の日々がはじまった。
このあたりまで来ると、相手も極端なミスはしなくなり、仕掛けの技術や間合いのとり方、玉を捕まえるスピードなど総合力が問われてくるようになる。
要は、ハッタリが効かなくなった。
「右四間飛車」も、的確に受けてくる相手が増えてくる。
「基本手筋」も、そもそもやらせてくれる状況に持っていけなくなる。
将棋はよく「序盤」「中盤」「終盤」に分けて語られるが、その3つをバランスよく高めることが、初段となるには求められるように感じた。

こうして、あらためて自分の将棋を見つめ直し、どこをどう鍛えていけばよいか、自分の将棋を再構築していく日々が始まった。
見つめ直すにあたり参考になった本、分かりやすいです
序盤について
3つのなかでは得意な部類。特に、右四間飛車に持っていけば、ある程度の変化までは少し有利ぐらいまでに持ち込める自信があった。
ただ、問題は右四間飛車に指させてもらえないケースがあったときだ。具体的には、相手が角道を止めないケース。角道が止めてくれないと右四間飛車の攻めができない、これがネックだった。
そんなとき、これまでは以前指していた矢倉や速攻棒銀で紛らわしていたが、初段を目指すにはちゃんと対策しないと上がれない。そう考え、いろいろ調べた結果、「角換わり」にたどり着いた。

とにかく相手の土俵で戦わないことが大事。角道を止めてこない相手には、こちらから角交換して、角換わりを志向していくスタイルにした(一手損になるがやむ無し)
角換わりは、互いに角を手持ちにしているため、1手間違うと角を打ち込まれたり、全体のバランスが崩れて形勢を大きく損ねる可能性が高い戦法。

(出典:『賭博黙示録カイジ』7巻113~114ページより)
その場での対応力も必要だが、どれだけ手を研究しているかが重要な戦法であるため、自分のスタイル(コツコツ覚えていく)とも肌が合った。
結果、以下の本で数ヶ月角換わりを勉強し、なんとか指しこなせるくらいにまで持っていくことができ、自分のなかで序盤の戦い方を確立できていった。
中盤について
どう鍛えればよいか、未だにわかっていない分野。
部分的な手筋やこの流れだとこうやる、というある程度の常識は知っているが、未知の局面が出てくることがほとんどなので、以下3要素を加味して、これが最善手かな?といつも頭を悩ませながら指している。
玉の固さ
駒の働き具合
たがいの持ち駒
プロ棋士の棋譜を盤でならべるのが勉強になる、という話も聞くが、まだ試せていない(二段を目指す際に、ぶち当たる壁になりそう・・・)
終盤について
得意ではなかったが一番伸びしろがあると思い、力を入れていた分野。
以前、プロの女流棋士の方に「初段になるまで何をやっていましたか?」と伺ったところ、「詰将棋だけやっていたら、初段になりました」と言われ、びっくりしたのを覚えている。
プロの方の意見なので、そのまま当てはめるのは危ないかもしれないが、将棋は結局王様を捕まえるゲームなので、捕まえる力が強ければ、序中盤が多少悪くてもひっくり返せるため、たしかにそうかなと思う。
なので、詰将棋本をひたすらコツコツとやっていった。
具体的には、以下のような方法をとった。
<短手数(3手詰)>
10秒以内に解けることが目標(見た瞬間に分かるレベル)
1日20問を問いて、かかった時間を記録
1冊を何周も問いて、瞬時に解けるところまで持っていく
実戦でも、このかたちにすれば詰むと直感的にピンと来るようになる
<長手数(7〜9手詰)>
スピードよりちゃんと解き切れることに重点を置く
1日2〜3問
5手目ぐらいでモヤ〜っと曖昧になるので、そうならないよう鍛える感覚
実戦でも、諦めずに詰みを読むようになる
詰将棋は、詰みの手が見えることも大事だが、手を読むことを諦めない力が付くことが、何より財産になると思った。「将棋ウォーズ」などの短い時間の将棋だと、どうしても読む時間を取れずに指すことが多いが、ちゃんと読むことで、劣勢に見えていた局面も実は優勢であることがよくある(本当に!)
なので、実は終盤だけでなく、中盤力も鍛えられたなと実感している。
上記のように、地道な努力を積み重ねながらも、達成率は上がったり下がったりと乱高下していた。ただ、こうやればいいんだと方針は決め切って、あとはやることを固定してひたすら積み重ねて行った結果、なんとか初段になることができた。
☖ ☗ ☖ ☗ ☖
さいごに
以上、これまでやったことを直線的に書いてみたが、実際はものすごく紆余曲折していて、あれもこれも試してはを繰り返し、諦めたりやる気になったりとアップダウンしながら、ようやくたどり着いたのが実態です。
初段になる直前の数局(達成率95%ほど)も、本当に正座をして、手を震わせながら、息が少し出来なくなるくらい緊張しながら指していた記憶があります。
そこまでして何か良いことがあったのか、と言われると「将棋?少しできます。棋力ですか?いちお、初段です(ドヤァ…)」と少しだけ自信を持てるようになったくらいで、特に変化はなく、初段になってから将棋から少し離れてしまったこともあり、棋力も当時より落ちてしまった。
ただ、ここには書ききれなかったが、初段になっていく過程で本当にいろんな人と真剣勝負をしたりバカみたいに笑ったり、と人生の密度が濃い瞬間をいくつも経験できたことが、何より将棋やっていてよかったなと思っている。
将棋に限らず、なにか打ち込めるものができて、それで誰かと強くつながれたなら、それは人生の楽しい1ページだし、「将棋」はそれができるだけのパワーを持ったコンテンツだと胸を張って言える。
今回はざっくりとしか書けなかったけど、また折をみて将棋の話も書いてみたい(将棋界の話、個別戦法の話とか)
あとは、新年だしこのタイミングで新たに二段を目指すべきか、悩ましい。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
