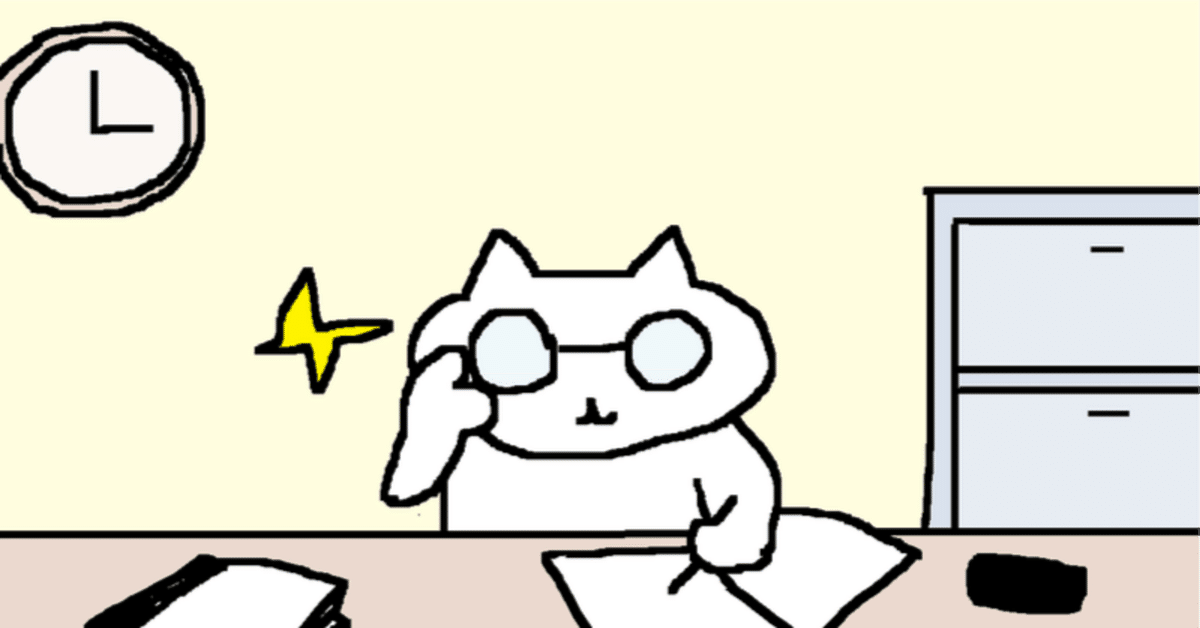
論文過去問・令和4(2022)年度を分析してみた(司法試験)
やっと全部読めた😭
LECの令和4年度論文過去問の通読完了です。問題と答案例に合わせて掲載されていた、出題趣旨・採点実感も隅々まで読みましたよ。マジで疲れた・・。
2022年12月に勉強を始めて以来、論文過去問の答案例を読んで、その後の学習方針を確立することが、密かに大きな目標でした。
まずは、論文過去問の答案例を読んで気付いたことをまとめたいと思います。
長いので目次付けておきます。
条文や有名裁判例の規範の、「要件」部の深い理解が大事
・論文は自由作文ではなく、各科目である程度、「何を書くか」が決まっている。
・たとえば憲法なら、
当事者の一方の行為や状態は、憲法X条で保障される権利に該当するかどうか。
仮に憲法上保障される権利であるとして、その制約が許されるか否か
など。
・こういった問いに対する「答え」として、適切な条文または、関連する判例を意識してその場で定立した規範を駆使して、結論を導く必要がある。
・条文も規範も、基本的な形式は、「要件1、要件2..→効果」であり、法的三段論法を用いて条文や規範の結論部分である「効果」に、問いの事例から特定できる要件を結びつけることで、事例に関する結論は導かれる。
・つまり、事例から、b1, b2, b3が認められる場合、
大前提(規範 or 条文):a1, a2, a3ならばxである
小前提(あてはめ):b1, b2, b3は、a1, a2, a3である。
結論:よって、b1, b2, b3が認められる本件は、xである
・判例上の規範に、仮に5つの要件が挙げられているとして、その全てを答案に書く場合はほとんどない。
・問いの事例から特定でき、検討できる要件のみ、記述することになる。
・だから、判例の学習をする際には、ある判例で挙げられた個々の要件の重要性や、要件相互の関係(andかorか)、なぜ、そういった要件があげられているのかについてのかなり深い理解が必要になる。(でないと、援用する規範の要件の取捨選択はおろか、そもそもどの規範を援用するかの判断さえも不可能である)
・そして、条文や、有名判例で定立された規範の「要件」一つ一つは、実際、そういった深い理解を得るためのあらゆる考察に耐える意義や根拠に基づいている。
・ただ、だからといって裁判例に、そういった規範が導かれる理由や根拠が、試験で利用できるほど詳細・明確に提示されていることはあまりない。
・結局、ある判例において定立された規範の意味を理解するには、その規範が援用された別の法的議論の前後を見て理解するしかないような気がする。
・そして、「論理的整合性」が評価される司法試験において過去作成された模範答案例が一番、そういった規範の意味についての記述が厚く提示されている気がする。
・あるいは、読んだことはないが、予備校講師や実務家、研究者が司法試験を意識して書いた事例問題集の答案なども、規範の意味を理解するための情報源として良いかもしれない。
・ともあれ、1科目1冊の基本書だけだと、やや頼りない。
基本書の意義
・では、予備校のテキストや基本書は不要かというと、全くそうとは言えない。
・なぜなら、実務家や研究者にとって議論の余地のないような条文の「効果」を導く要件でさえも、全て条文に明示されてるとは限らないからである。
・分かりやすいものだと、窃盗罪(刑法235条)の条文に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあるが、窃盗罪の要件として条文から読み取れるものは、「他人の財物」「窃取」の2つしかない。しかし、テキストでは、窃盗罪が成立するための要件は、(1)他人の財物を(2)故意に、(3)不法領得の意思を以て、(4)窃取することの4つが挙げられている。
・(2)故意や(3)不法領得の意思といった書かれざる要件は、刑法という法の性質や、他に規定された類似した罪との識別のために必要となるもので、こういった書かれざる要件を条文を通して一から読み取ろうというのは、不可能ではないかも知れないが、無駄な努力でしかない。
・信頼できる教科書を通して、いつでも事例問題に使えるよう、知識として整理しておく必要があるように思う。
・また、ある法が予定している「効果」が全て条文に書かれている訳ではないので、事例を法的に判断するためのツールとして、教科書等を通して、「要件→効果」をたくさん理解し、用意しておく必要があるように思う。
・そのような訳で、基本書にせよ、予備校のテキストにせよ、依るべき教科書は絶対必要になると思う。
条文は不要なのか。
・それでは、条文は不要なのか。
・条文に多くの不備があるのは、法律を変更することに伴うコストが大きすぎるためであるが、そういった不備にも関わらず、解釈の出発点は条文である。
・ある法領域のある事例を判断するために、既に確立している規範があったとしても、そういった規範が前提にしている条文が変更されたり、追加されたり削除されたりすることで、その規範の要件や効果は違ったものになり得る。
・また、そもそもある条文のある箇所の解釈の違いのために、同じ事例に適用しうる複数の規範が存在し得る。
・そういった規範の選択や批判は常に前提となっている条文の特定の語句の解釈から始まるわけだから、司法試験の答案を書くための学習課程において、条文が不要ということはあり得ない。
・ただ、他の法律系資格試験だと、事情は変わるかもしれない。
・条文は置いておいて、争いのない規範の要件と効果を整理して理解するだけでも、見えてくるものは案外大きいかもしれない。
条文の語句の意味を特定するために、規範が定立されることもある
・例えば、民法第177条の第三者といえるためには、など。
・ある事例を判断するために必要な様々な段階で、「規範」は登場する。
・そういった「規範」の意味、とりわけ、「要件→結論(含、効果)」として捉えた場合の個々の要件の意味や機能、根拠について、明示されていることは少ないにも関わらず深い理解が必要とされることが、司法試験が難しい所以な気がする。
・令和4年度の論文過去問を通しで読んでみて、特にそういった困難を感じさせられたのは民法だった。
・条文数が多いせいもあるだろうが、ある規範の個々の要件について厚みのある解説を見いだせることが本当に少ない。どうすれば良いか、正直分からない。
科目別で必要とされる判断のリスト
全く恣意的であるが、気付いたことを片っ端から列挙してみる。
○全て
・~はxx法第xx条のある語句(例:民法第177条の第三者)に該当するか否か。
・~は定立された規範のある語句(例:背信的悪意者)に該当するか否か。
・~はある規範のある要件(例:因果関係の存在、損害の発生)を満たすか否か
○憲法
・~という権利は憲法第xx条によって保障されているか否か
・憲法上保障されると見做せるある権利の制約はどのような要件を満たす場合、可能か
・~は合憲か違憲か
○行政法
・Xには原告適格が認められるか否か
・処分の根拠法令はどれか
・ある規則は法令と目的を共通する関係法令(行訴9II)にあたるか否か
・その根拠法令はある被侵害利益を想定していると言えるか否か
・その利益を個々人の個別的利益として保護していると言えるか否か
・取り消す対象は依然、存在していると言えるか否か
・ある行政行為は処分と言えるか否か
・その行政処分は違法と言えるか否か
・その行政処分に裁量はどの程度認められるか
・その裁量を逸脱した処分が為されたと言えるか否か
・ある行政行為にある義務違反(例:個別事情考慮義務)が存在するか否か
○民法
・Xには~権が認められるか否か
(例)
所有権、
所有権に基づく請求権(引渡し、妨害排除、妨害予防)
所有権移転登記請求権
損害賠償請求権
・権利侵害があったか否か
・Xには~という義務があったか否か
・義務違反があったか否か
・~という事案には、~条を適用できるか否か
・~という事案には、~条を類推適用できるか否か
・契約が存在したと言えるか否か
・契約にある項目が存在したと言えるか否か
・契約が有効か否か
・契約を取り消せるか否か
・~権は移転したと言えるか否か
○商法
・民法に同じ
○民事訴訟法
・ある民事訴訟の原告は誰か
・ある民事訴訟の被告は誰か
・ある当事者の陳述は自白と言えるか否か(自白の場合、その撤回に制限が生じる)
・その自白の撤回は許されるか否か
・原告または被告の追加は許されるか否か
・ある証拠(例:USBメモリ)に、書証の規定を準用(民訴231条)することができるか否か
○刑法
・ある行為は何条何項のどの罪にあたるか
・違法性阻却事由は存在するか
・責任阻却事由は存在するか
・故意はあったと言えるか
・過失はあったと言えるか
・ある罪は既遂か未遂か
・正当防衛(刑36I)は成立するか否か
・過剰防衛(刑36IIは成立するか否か
・緊急避難(刑37I)は成立するか否か
・2つ以上の行為と罪の関係は何か(併合罪以下、複数の罪と評価される場合の方が、結果的に刑は重くなる)
単純一罪
包括一罪
科刑上一罪(刑54)
併合罪(刑45)
単純数罪
○刑事訴訟法
・憲法に同じ
・加えて、ある態様で行われた捜査(例:おとり捜査)は適法か違法か
・ある捜査は任意の処分か強制の処分(刑訴197I但書)か
・ある事案において、訴因の事実と罪となるべき事実の間に変化があった場合、訴因の変更をせずに事実を認定し、判決を下すことは許されるか否か
・ある証拠を採用することは許されるか否か
○法律実務基礎・民事(予備試験のみ)
・訴訟物は何か
・請求の趣旨は何か
・請求を理由付ける事実は何か
・抗弁を機能させるために必要な事実は何か
・ある訴訟手続を利用して行える訴訟行為は何
・挙げられた証拠や供述から認定できる事実は何か
・差押さえ命令に対し、弁護士として取れる手段は何か
・ある権利を主張するために立証すべき事実は何か
○法律実務基礎・刑事(予備試験のみ)
・供述の信用性はどう判断するか
・ある手続を裁判官が求めた根拠は何か
・接見等禁止請求は認められるか否か
・訴訟手続のある段階においてある行為は許されるか否か
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
