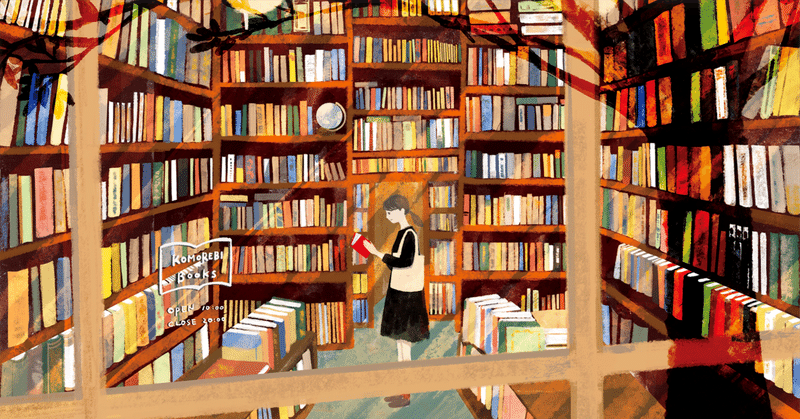
”思いつき”定義集Ⅱ⑪「く」ー②
【功徳】おもに老人が過去への言い訳として使う常套句。過去の後ろめたい行為への反省・贖罪の意識も多少はあるかも(ない人もいるけど)。伝聞でいうと、高齢者を乗せた高齢のタクシー・ドライバーいわく「最近は少しでも人の役に立ちたいと思うし女房にも少しは残しておきたくて老体に鞭打って頑張ってますんや。お互い功徳を積まなあきまへんな」「そうですね~。一日一善と言いますからね~」。確かに最期はいい人でありたい。その陰のない心持ちは尊重されて然るべき。
しかし「悪人世にはばかる」。功徳を積むべきと思われている人に限って善行から遠ざかるのは人類共通か。
◆推し映画:老人を主題にしたものとして『わたしは、ダニエル・ブレイク』(2015年製作;イギリス=フランス=ベルギー)。
【軍隊】殺人とそれに耐えることを学ぶ学校。本番の「有事」に備え規律は必須科目。もちろん国家安全保障の意義を叩き込まれる。主権国家システムを基軸とする現代においても軍隊は是非ではなく当為として存在し続ける。「中立国」として有名なスイスでさえ軍隊はある(正確を期して言えば「中立」などあり得ないのだが)。国際社会の未熟さの反映だが成熟する見込みは(残念ながら)皆無。なので死語になることもない。
軍事的殺人には「距離」が求められる。殺す相手を間近に認識する時、人は人を簡単に殺すことはできない。逆に言えば、巡航ミサイルや空爆による殺人はより容易となる。原爆投下を想起されたい。無人機による殺人はすでにゲームとして化している。実例――フロリダのコンピュータ・ルームから中東や中央アジアの「悪党」を爆撃するなど。もちろん民間人を巻き添えにして。AI兵器は日進月歩。命の序列化がいっそう進むかもしれない。
◆注:戦場経験者が退役後に発症するPTSD(心的外傷後ストレス症候群)の実態は依然不明だが、自殺者が極めて多いことは確認されている。どの政府も不都合は隠すもの。例外はない。
◆推し文献:デーヴ・グロスマン『戦争における「人殺し」の心理学』(ちくま学芸文庫、2004年)。ノーム・チョムスキー『覇権か、生存か』(集英社新書、2004年)。古いと思われるかもしれないが、とくに前者は元軍人による極めて優れた洞察と分析。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
