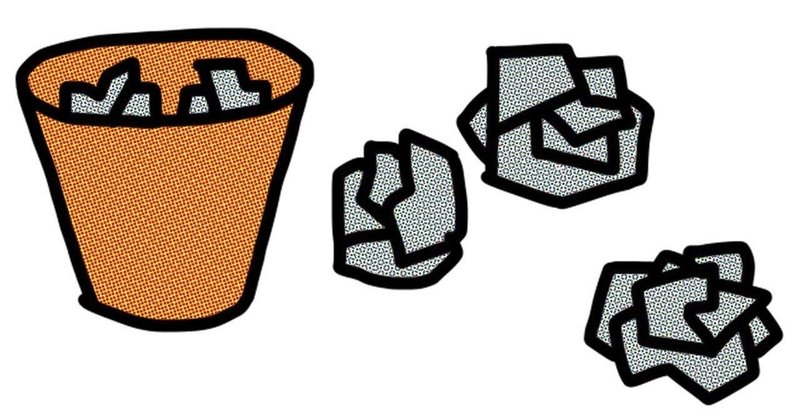
宇宙のゴミ問題を考えておこう
みなさんがお住いの地球、その周りを回っているものって何かご存じですか?
月、人工衛星、国際宇宙ステーション、その通りです。しかし、今回は地球の周りに浮かぶゴミ、スペースデブリのお話。
ゴミと言うからには掃除が必要ですが、宇宙空間のゴミは一筋縄ではいきません。部屋の掃除も、早め早めに片付けておくことが肝要、地球をゴミ屋敷にしてしまう前に一緒に考えてみましょう。
<知っておこう>スペースデブリとは
そもそもスペースデブリが何か、と言うと、故障した人工衛星やその破片など、つまり近年生まれた人工のゴミです。(最初の衛星は1957年に打ち上げられました)
現在、その総数は約18,000個(10cm以上の大きさの物体の推定個数)と言われています。これまでのデブリの個数の推移を見ると、大きな事故などによって著しく数が増えたことがわかります。

スペースデブリの何が問題かと言うと、デブリは地球の周りを高速で飛び回っているため、稼働している人工衛星にぶつかると大きな被害をもたらします。
【補足】人工衛星は地球の重力に負けない遠心力を得るため、高速で軌道を周回しています。地球からの距離によりますが、高度約400kmにある国際宇宙ステーションの場合、およそ7.7km/s、東京大阪間を1分程の速さとなります。スペースデブリも同程度の速度で地球の周りを飛んでいます。
さらに、大きなデブリとなると、地球上に落下することもあります。衛星軌道を周回するデブリとは異なりますが、2020年5月には、中国が打ち上げたロケットの一部がニューヨークの上空を通過し、わずか15分後に大西洋に落下しました。
スペースデブリが厄介なのは、スペースデブリ同士が衝突すると、バラバラになってさらに数が増えていくことです。増えれば増えるほど、衝突の危険性は高まるため、このままでは、人類は自らのゴミによって月探査はおろか、地球から出ていくこともままならなくなるかもしれない、と懸念されています。
<ワーク>じゃあ、どうやって減らす?
この新しい環境問題、スペースデブリを減らしていくためにはどうすればいいのでしょう。世界的な対策が検討されています。ここでは、家庭ごみの減らし方3Rを参考に宇宙のゴミを減らす方法を考えてみましょう。(実際の取り組みは後半で紹介しますが、まだこれが絶対正解と言える答えはありません。頭の体操と思って考えてみましょう。)

いかがでしょうか。宇宙空間ならではの難しさが見えてくるでしょうか。ReuseやRecycleは少し難しいかもしれません。
続いては、では誰が回収するのか?発生したスペースデブリの責任は誰がとるのか?を考えてみましょう。

ワーク1では技術を、ワーク2では制度を考えてみました。
先にお伝えした通り、現段階で正解はありませんが、考えたアイデアを評価してみましょう。

このグラフは、スペースデブリの個数の今後の推移をシミュレートした結果です。デブリ同士が衝突しても、数が増えていってしまうため、年間5個以上除去していかないと、減少していきません。さて、考えた技術やそれを支える制度は年間5個以上持続的に除去していくことができるでしょうか。
<まとめ>新しい環境問題、スペースデブリ
デブリ低減の視点には、新しいデブリを発生させないことと、現在あるデブリを除去することの2つがあります。
現在、検討されているデブリ除去技術は、ロボットアームや網で捕獲する技術、テザーと呼ばれる電流の流れるヒモをデブリに取り付け、電流と地磁気で生まれる電磁力をブレーキに大気圏に落下させる方法、レーザー照射によって軌道を変化させるなどの方法が検討されています。
また、スペースデブリに対する、低減ガイドラインが国連で制定されています。このあたりについては詳しく書かれている方がおられたので、紹介しておきます。
いずれにせよ、技術的にもコスト負担も、誰がどうやって、ということは定まっていないことが問題です。このまま見て見ぬふりをしていると、新たな環境問題は私たちのこれからの宇宙開発のみならず、GPSなどの生活インフラにダメージを与える問題となる時が来るかもしれません。
この新しい環境問題は、あなたの立場で考えるとどのような問題につながりますか?将来の世代や違った立場の人にとってはどのような問題になるでしょうか?最後に少し考えてみませんか。

今回は、宇宙のゴミ、スペースデブリによる新しい環境問題をテーマにお話をしました。何か考えるきっかけになれば幸いです。
#科学技術 #大人の宿題 #科学ワークショップ #いま私にできること
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
