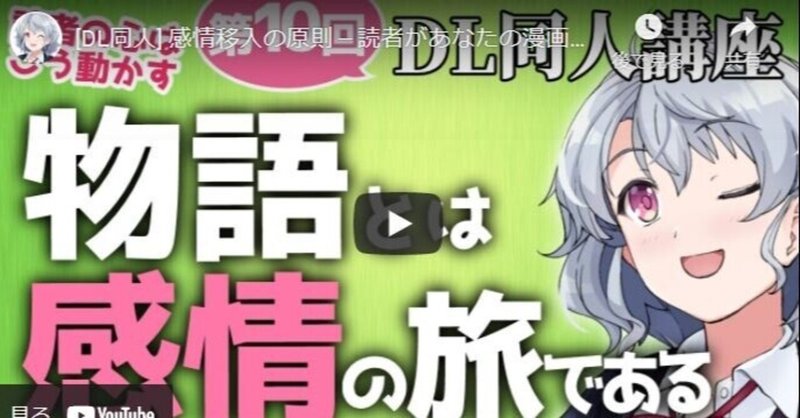
「ハルヒスキーのDL同人教室」10回目感想:読者の感情を自分の目指すゴール(射〇)に連れていくために作者にできることは?
今回の内容は9回目とセットの内容になってます。
ストーリー作りが下手な人から上手な人になるために、物語の「動かし方」を知ろう
前回で物語の「エンジン」は出来上がりました。しかし前回の話だけで作品を作ろうとすると、物語が上手く動き出しません。
なぜなら「読者の感情を置き去り」にしてるからだといいます。
今回は「ストーリー作りが下手な人」の話からスタートして、どうすれば読者を引き込むお話作りができるのかについて説明してくれます。
今回はかなり濃い話になってます。最初は抽象的な話から始まりますが、しっかりエロ同人に特化したキャラメイクの話につながります。
単なる出来事の羅列と物語を分けるものは何か?


同じ情報を伝えるにしても、物語形式にすることによって「ストーリーを通じて読者の感情に変化をもたらすことができる」というところが重要です。
逆にいうと、それができていないと物語とは呼べません。
初心者の作ったストーリー :ストーリーの中で起きている話に感情移入が阻害されたりそもそも感情移入できない
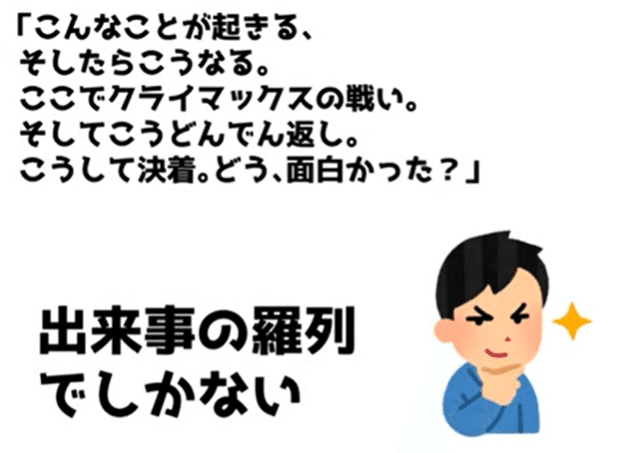
エロ作品は感情移入がものすごく大事。
失敗している作品はストーリーがダメなところが目立つ。「ノイズ」「邪魔」になって感情移入が妨げられ読むのをやめてしまう。(ストーリーは「よいのが普通」なので特に語られない。悪い時は少しでも悪いとぼろくそに語られ、褒められるのはめちゃくちゃいい時だけ。語られない=十分いい作品)
脱初心者を目指すためには、それぞれのシーンで読者にどういう感情を持ってもらいたいかを考えなければいけない


まずゴールを決めて、そのゴールに向けてどういう道筋で読者の感情を導くかを考える。
読者の感情をどこに導きたいかが決まったら、そのゴールにあったキャラクターを考える

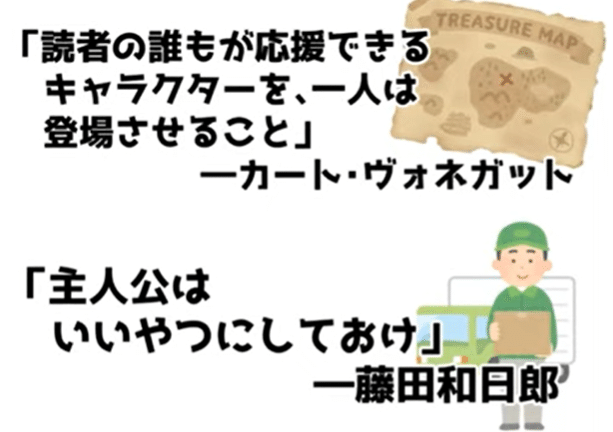
ここでいう「いいひと」は、善良である必要はなくて読者がシンクロしやすいという意味。主人公を、作者の理解できないキャラクターにしない。
探偵ものでいえば「シャーロックホームズ」ではなくワトソン、脳噛ネウロでいえば弥子、ムヒョロジでいえばロージーを主人公にする。変人が主人公だと読者は結構とまどうので、そういう人物と読者をつなぐ役割が必要なんですね。
この観点でめちゃくちゃお薦めしたいのは、野球嫌いな私でも面白いなと思って楽しめている「忘却バッテリー」という野球マンガです。凡人だけど努力家の主人公が超高校級の選手たちと読者の間をうまくつないでくれます。
同じ展開の物語でも、誰に感情移入させるかで物語の印象がガラッと変わる


読者は作品に対してどういう感情を抱こうか決めかねている→読者は作中のキャラクターの反応を模倣するという原理を利用しよう


このあたりは「泉信行」さんが「マンガをめくる冒険」という作品でめちゃくちゃ熱く語ってたのを思い出しました。
絵「だけ」で読者を興奮させるのは限界がある。絶対にただのCG集になるな!
つまり、作中でキャラクターを興奮させて読者を引っ張る必要がある

健全CGやTwitterでは二次絵が圧倒的に強く、エロ目的の同人はちゃんとストーリーとかシチュエーションがあるオリジナル作品が強い理由も、ここにあるのかもしれませんね。すでにキャラ同士のイメージが固まってる原作があれば一枚絵は説明なしで楽しみやすいが、エロになるとそれが逆風になりやすい。
エロ担当のFGOキャラとかエロイ設定が導入しやすい艦これとかアズレンならいいんですが、そうでない作品の二次絵はどこか無理が生じやすいのに対して、オリジナル同人は効果的にエロに特化したキャラクターと関係性を作れる。この技術がすでにあるキャラクターを使う二次創作を上回ってきているのではないかと。
エロ同人よりもergの方が顕著かもしれません。erg好きな私としては、「ストーリー抜きでエロCGだけ見てもちっとも抜けないんじゃー」的な話でめっちゃ語りたい(笑)
4つのルールに沿って、読者の感情の流れを設計する

読者の感情は、作者のコントロールから逃れやすい!ということを強く意識する必要がある。そのため、がっしり捕まえて逃がさないためにいろんなテクニックが必要になる。
・設計だけじゃなくて「提示」部分が大事。感情を高めるための仕掛けをどれだけ作れるかは作者の持ち味の見せ所。(ハルヒスキーさんは荒木飛呂彦先生の例を挙げて「掛け金を上げる」という表現を使われてました。)
・読者と登場人物の感情がズレたら一気に読者の感情値が0になる。読者の期待とずれさせない。ずれるならツッコミ役などの補正役がいる。
・「溜めコマ」を使うことによって、読者の感情を追いつかせる工夫などが必要。
感情を溜めるための応用編 マンガ版のモンタージュ技法



最近はやりのこの4コマも「3コマ目」が機能してるなあと思いますね。

などなど、今回はかなり実践的な内容になっていました。
ざっくり紹介してるので、細かいところが気になった人は動画で確認してみてください。
動画中で紹介されていた書籍や作品など
はるきちさん、めちゃくちゃ読書家ですよね……。ポンポン本が出てくる
①今回のお話の全体のタネ本
②ルームランナーを走る「だけ」の話をこれほど面白く緊迫感をたかめるえがきかたができる作家が他にいるか?と絶賛
動画では1時20分以降に人気ジャンプ作品語りをされてるんですが、これについても目の付け所が面白くて作品語り単品でも十分一つのコンテンツになりそうな感じでした。
私もこんな感じで独自の視点を持って作品を語れるようになりたいな……。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

