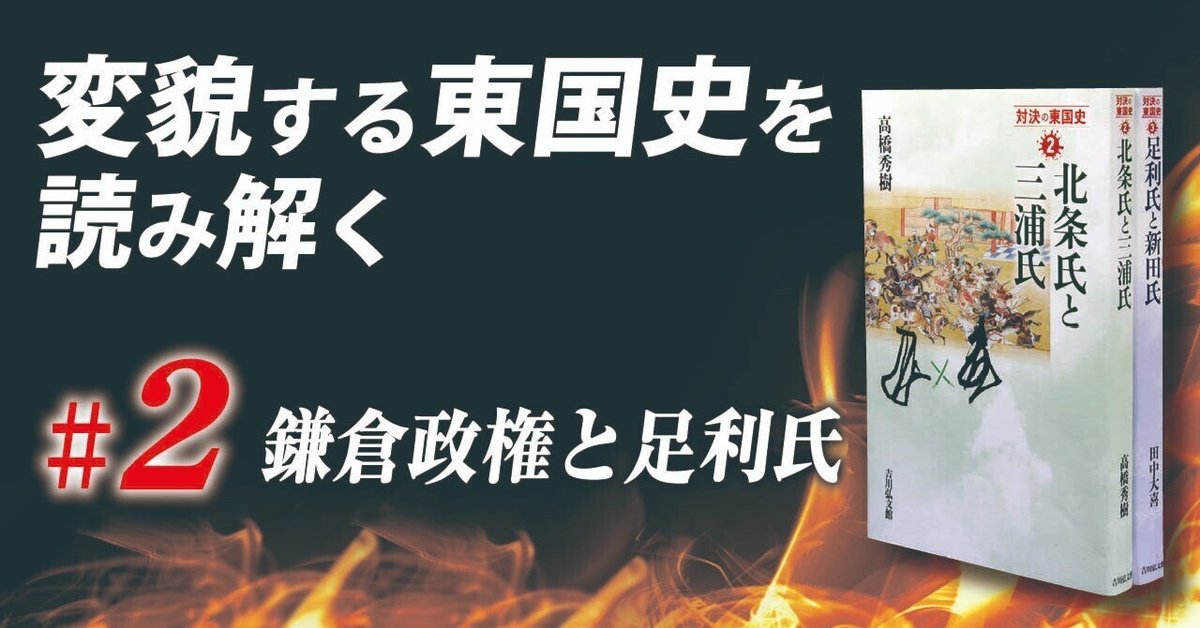
『対決の東国史』刊行記念鼎談 変貌する東国史を読み解く #2
2021年12月から刊行が始まり、おかげさまで売れ行きも好調な シリーズ『対決の東国史(全7巻)』。刊行前に収録された刊行記念鼎談を6回に分けて特別公開いたします。
著者である高橋秀樹・田中大喜・木下 聡の3名をお迎えし、企画のなれそめから、最新歴史研究トークまで、様々な話題が飛び交う盛沢山な内容になりました。
今回は、第2回「鎌倉政権と足利氏」お楽しみ下さい。
鎌倉政権と足利氏
―― 東国の四百年を見通しますと、鎌倉という土地がキーワードに挙げられます。鎌倉幕府は、のちの政治体制に影響力があったわけですけれども、次の足利氏に引き継がれていく要素として、どのような影響力があったとお考えですか。
高橋 鎌倉幕府の存在というのは大きいのですが、東国と鎌倉幕府との関係を見ても一色ではないのです。関東の御家人(ごけにん)がみんな鎌倉に住んでいるわけでもないし、将軍に日常的に奉仕しているわけでもない。やはり鎌倉に住んで、将軍の行列に供奉(ぐぶ)して、当番で御所に泊まり込んでいるタイプの御家人と、そうではない御家人とは、温度差があるはずなのです。
氏族の規模によっても、それから世代によっても違います。頼朝挙兵を知っている世代と、その二つ後の世代、三つ後の世代とは結構温度差がある。だから、鎌倉幕府と東国というのは、たぶん一色ではないのです。本当はそこを細かく見ていくのが必要だけれども、残念ながら十分な史料が残っていない。そこが難しいところかもしれません。
田中 そうですね。
高橋 鎌倉幕府は、東国に位置付けられるのと同時に、中世の国家の中にも位置付けられていて、そこを無視してしまうといけない。天皇・上皇を中心とする社会の体系の中に武士たちもしっかりと位置付けられているわけで、鎌倉幕府しか見ていないと、朝廷との関係を見失ってしまうのです。たとえば、鎌倉幕府は独自の新しい身分秩序をつくれないので、あくまで朝廷の位階・官職という身分秩序を借りて存続していく。それが社会の基盤にあるので、あまり東国の独自性だけを捉えようとすると見失うものもある。東国の特質だけではないというところですね。
鎌倉幕府と中央との関係が基本にあって、室町幕府だってそれをお手本にしているわけです。もちろん鎌倉殿と室町殿ではポジションが違うし、京都にいるか、いないかでも全く違う。室町殿は左大臣として節会(せちえ)の内弁(ないべん)を務めたりもしている。ただ、それにしても基本は鎌倉幕府と朝廷の間で取り決められた枠組みから、大きく飛び出してはいないので、鎌倉幕府と中央との関係の在り方が、その後の室町幕府と中央との関係の在り方を、根幹の部分では規定しているのでしょう。
―― 室町幕府は、鎌倉時代の構造をどういうふうに受け継いでいったのでしょう。
田中 よく言われることですけど、観応(かんのう)の擾乱(じようらん)まではやはり、東国政権としての在り方、末期鎌倉幕府の統治方法を意識したつくりになっています。足利尊氏と直義は、末期鎌倉幕府をモデルとして行動していたと私も思います。
高橋さんが御家人の世代によって幕府への対応の仕方が違うとおっしゃられましたが、最近刊行された『京都の中世史4』のなかで山田徹さんもそのようなことを書かれています。末期鎌倉幕府を知らない世代になって、室町幕府は独自性をようやく発揮し始めるというような議論をされていて、非常に説得力があるように思いました。
政権をつくり上げていくときには、自分の知っているものがまずベースにある。足利尊氏と直義は結局京都に拠点を置きますが、彼らのお手本はやはり末期の鎌倉幕府だったと思います。足利氏は鎌倉幕府の中枢に居続けたので、尊氏や直義は末期鎌倉幕府の統治の仕組みとか、得宗(とくそう)の行動を彼らなりに会得していたでしょう。また、幕府の奉行人(ぶぎようにん)の一族を被官(ひかん)として抱えていたので、足利氏は統治技術を蓄積できたことも政権を握るうえで大きかったと思います。
高橋 室町幕府の政治方針を示した「建武式目(けんむしきもく)」でも、北条義時・泰時の政治を目標として掲げている。遠くにある手本としては延喜・天暦の治もお題目のように唱えるけれども、目の前の目標はやはり義時・泰時時代。現実として見てきた貞時とか高時の時代ではない。そこには反面教師的な部分もあるかもしれない。
木下 それと建武政権に足利氏の家臣と一族が起用されているのが結構大きいのではないですか。そこでさまざまなノウハウを頂いているというのがあるでしょうし。
田中 そう思います。建武政権内で奉行人同士の交流もあったはずですよね。
木下 そのとき急に出てきた足利一門がいますので。
田中 彼らも建武政権に加わることで、奉行人たちと交流したでしょうね。
木下 それまでは本当に零細御家人だったのが、急に足利氏の被官として起用されています。あの辺で、国の大将としてそのまま派遣されたり守護となったりして大きくなっていきます。細川氏も一色氏もそうですね。
高橋 そのクラスにしても、やはりベースには、しっかりした漢文、中国古典の素養がある。そうした基礎的な学問はほとんどの武士が持っていますよね。
木下 ええ。どこで学んだかは分からないですけど。
田中 そこが分かると面白いですよね。
高橋 鎌倉の寺院なのか、地方の寺院なのか、家で学んだのか。それなりの学問的な素養があるから、京都に行ったときに奉行人的な差配ができるわけです。そこは東国武士に限らず、世間が思っているよりも武士たちの教養は高かった。
木下 歌を詠むにも、いろいろ教養は要りますからね。
高橋 鎌倉御家人がかなり勅撰(ちよくせん)歌人になっているわけです。基礎的な教養としては、もちろん和歌だけではなく、漢籍に対する教養も高いと思うのですが、今まで歴史研究者はあまり注目してこなかった部分です。
木下 その辺、禅僧などとの関係もあるんでしょうか。
高橋 うん。あると思う。
木下 足利義満も若いころ、京都で義堂周信(ぎどうしゆうしん)とかその辺りにいろいろ教えてもらったりします。鎌倉公方の足利基氏、氏満も禅僧からですね。
田中 武士の一族から僧侶を輩出するのは一般的だったので、寺院との関係を考えることは大事ですよね。
高橋 子供のころお稚児(ちご)さんで寺院に入って、僧侶にならずにそのまま俗人として成人する者もいるわけだし。
木下 今回のシリーズの「対決」というくくりだと、寺院勢力はあまり話題に出てこないので、本文には盛り込めないでしょうけれども。もちろん僧は本来、戦乱には関わってはいけないものでもありますが(笑)。
高橋 でも軍隊にくっついている坊さんはいるけれどね。
木下 陣僧(じんそう)がたくさん出てきます。私の執筆した第5巻でも岩松氏に仕えていた松陰(しよういん)なんかはいろいろ活動していますし。キリスト教宣教師は、日本の僧侶は戦争に出ていくと批判しています。
高橋 どこに行っても坊さんと陰陽師(おんみようじ)はいますよね。それはもちろん貴族社会もそうで、共通している基盤があるはずなのです。その上に貴族社会も、武士たちの世界も成り立っている。その共通基盤をちゃんと理解しないと見失ってしまうものがあるのではないかと、やはり思ってしまうんです。
(3回目へつづく)
【関連書籍】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
