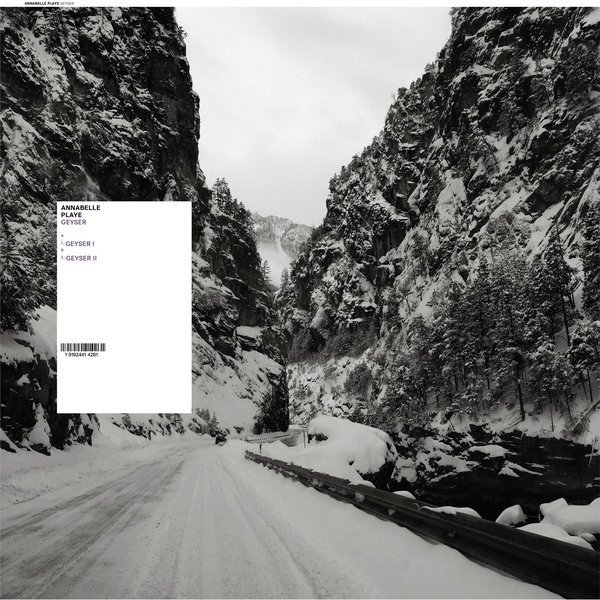2019年のベストアルバム - ドローン・ミュージック
2019年の音楽を振り返った時に特に印象的で、また個人的に嬉しくもあったのがドローン・ミュージックの傑作が多かったということでした。
私は普段からそういった音楽をよく聴くので、毎年そういった傾向のもので「これは!」という作品がいくつかはあるものですが、2019年については一定の水準を超えてくるような作品の量がとても多いように感じました。
なのでそれを確認し記録に残しておこうという思いで2019年のドローン・ミュージックの作品で特に印象に残ったものを纏めた記事を作成しました。記事の方向性が“数の多さ”を示すということであるため最初は30作品掲載するつもりでしたが、文字数や記事の長さ、読みやすさなどを考慮し最終的に15作品に絞りました。掲載順には順位などの意味はありませんが、最初と最後と記事の真ん中に当たる8作目については考えがあったうえでその位置にしています。画像には試聴や購入ができるページ(ほとんどはbandcamp)をリンク付けしていますので気になるものはクリックしてみてください。
*ドローンは厳密には単音で変化の無い長い音を指す音楽用語ですが、本稿では単一でなく複数の音程、音色を用いていてもそれらがシームレスに接続されていたり、長い音の扱いがその作品の中で重要であったり耳を引くものであった場合、そして単一の音を聴き続け音色を凝視するようなミクロな視点で制作された音響作品なども含めて定義を広く捉えたうえで、ドローン・ミュージックという語を用いています。ドローン(が聴き取れる)ミュージックくらいな認識で読んでいただけると幸いです。
・Ben Vida『Reducing The Tempo To Zero』
Town And CountryのメンバーでありJoan Of Arcの元メンバーでもあるという、何気にシカゴ音響~ポストロックの重要人物的な位置づけも見出せそうなBen Vidaの作品。彼は近年はソロリリースに力を入れていて、作風は割とリリースごとにバラつきがあるフリーキーな作家というイメージでしたが、本作はトータル4時間に及ぶハードコアなドローン作品。フィジカルはUSBカードでのリリース。およそ一時間前後の4つのトラックが収録されており、その個々のトラックもまたいくつかのドローン状のパートが移り変わっていくような成り立ちなので、ちょっと入れ子構造的な感じがあります。録音期間が2016~2019年と長い期間に渡っていて、作品のキャプションにはデジタルとアナログの音合成の産物といった記述があるので、最初から完成図を描いて制作されたとうよりは日常的に行っている音実験によって得られた様々なサウンドを纏めた作品という傾向が強いのではと思います。全体通しての構成や表れる個々のサウンドについても特に目新しさなどは感じなかったのですが、時にチェロやコントラバスの弓弾きのようであったり、オルガンのようであったり、またはただただ扁平な電子音であったりと表情を変えながら、そしてゆったりとした時間配分で現われるドローンサウンドがどれも本当に素晴らしく、こういった音楽を聴いていて強く求める部分である音が徐々に身体の奥深くに浸透していくような感覚を存分に味わえる4時間なので、聴いている間は本当に幸せな気分になります。例えば自分がどういう音楽が好きか他人に伝える場合にはこれ差し出すのが一番適切なのではとか思えるほど、とてもシンプルに好きな作品です。
・Yann Novak『Slowly Dismantling』
2010年代を通して何枚もの傑作ドローン作品を生み出し続けたロサンゼルスを拠点とするアーティストYann Novakの最新作。素材としてEMS ElektronmusikstudionやMelbourne Electronic Sound Studioで録音されたサウンドを使用。2019年には彼は『Scalar Fields』、『Stillness』、そして本作と3枚のアルバムを発表しましたが個人的な好みでいえば本作がダントツでした。前2作が20分の作品2つを収めた構成や、その中で音のレイヤーの塗り替えが起こらない持続性が非常に強い作風などあらゆる点で共通しているのに対し、本作は音が途切れない実質40分の作品ではあるもののその中で音の出入りやレイヤーの移り変わりは小気味いいペースで起こります。また使用される音色の特性やその扱いにも異なる点があり、前2作が複数のサウンドが既に同時に鳴っている、レイヤーが形作られている状態でフェードインしそのままフェードアウトしていくのに対し、本作は飛行機の稼働音のようなボワボワとした低音、オルガンを思わせる優美なドローン、ザラついた質感を残しながらも耳に痛くないようトリートメントされたノイズ的なサウンドなどが個別のタイミングで現れ重なり消えていくという構成ですし、前2作がシマーリバーブ的なギラギラとした倍音をメインとしたサウンドだったのに対し本作はそちらであまり聴かれなかった低音やオルガン的な音色が多用されています。自分がこれまでの彼の作品で特に惹かれる部分は長時間の切れ目ない音の繋がりの中でノイズ/雑音のような響きが入り混じる中から優美なドローンが徐々に前面に出てくる音の遷移の部分にあったので、それが味わえない『Scalar Fields』と『Stillness』はこれはこれでいいと思えはするもののあまり求めてはいない方向性だと感じたのですが、本作はある意味自分が求めているものがコンパクトに凝縮されたような一作で(まさかこういう風にくると思ってなかったので)すごく驚きました。本当に大好きな一作。
・Ellen Arkbro『CHORDS』
スウェーデンの作曲家/ボーカリストEllen Arkbroのアルバム。「CHORDS For Organ」と「CHORDS For Guitar」という2つの作品が収められています。なんとも素っ気ないタイトルがついていますが、内容もかなり振り切ったものになっていて、それぞれの楽器で簡素な和音を執拗に鳴らすことで音響的、または構造的特徴に耳を向けさせるような意図が非常に強く感じられます。オルガンのほうは最も簡素な和音である五度の和音をルートを変えながら鳴らしていく作風なのですが、いろんな倍音がブーストされたような響きでそれが行われるため厚みやうねりを感じるサウンドになっています。オクターブ違いの音も含めて鳴らされる場面などは聴いているうちに楽器というよりは掃除機の稼働音と何かのブザー音がユニゾンしてるみたいに聴こえてくるサウンドで(オルガンが空気の圧縮と移動によって発音される管楽器であることを考えればこの例えは的外れではないと思います)、オルガンという楽器の倍音の強さを印象付けられます。この曲の和音や展開の分析はギターで音取りながらやったのですが、その時に鳴ってるオルガンの和音と同じ和音をギターで弾いてもそれらが(少なくとも譜面の上では)同じ音であるとはとても思えず耳がすごく混乱したのが面白い体験でした。ギターのほうも面白い響きで、撥弦楽器には聴こえるもののギターというよりは弦モデリングのシンセで作った架空の楽器の音のように聴こえてきます。こちらも和音はシンプルで五度と二度を1オクターブ半くらいの音域に渡って下降するのをギターが得意なキー(E→A→D→Gといった具合)でやっています。最後のほうは少し違う和音が出てきますが。ピックを高音弦のほうから滑らせるような発音の仕方であることや、おそらくギター2、3本の音を左右に振り分けて立体感を出していること、そしてくっきりと捉えられることでどこか非現実的な響きを作り出している録音の具合など様々な要因が重なってか、この曲には天上から音が降ってくるような神聖なイメージを抱きます。長めに捉えられたサスティンの微かに揺らぐような響きも、雲間から射す光の揺れのようにとても美しい。
・Clarice Jensen『Drone Studies』
ACME(アメリカ現代音楽アンサンブル)の芸術監督であり、チェロ奏者や作曲家としても活動しているClarice Jensenの作品。昨年発表されたデビューアルバム『For This From That Will Be Filled』にはJóhann Jóhannssonが関わっていて、そちらでもドローン的な音の扱いは聴くことができましたが、まさかこんな真っ向勝負みたいなタイトルの作品出してくるとは。といっても作品の内容はハードコアな単一ドローンというわけではなく、持続音のレイヤーや切り替えを用いて作られた美しい音楽作品です。特にオルガンと声をメインとした①は持続音で構成された複数のパートが移り変わっていく組曲のような形式なのですが、現れるパートどれもが例えば不穏さ、柔らかさ、力強さ、暖かさなど複数のイメージを同時に感じさせるような絶妙にありきたりじゃないサウンドになっていて素晴らしい。
・Shuta Hiraki『Across The Empty Lot』
橋の上で工事をしていたミキサー車2台が放つ持続音を離れた地点から場所や時間、レコーダーを変えて録音し、音色を加工することなくミックスしてまとめた作品。音源が複数あることによる干渉効果や、周囲の高低差によるフィルタリング効果(録音場所は多くが発音されている場所より下がった土地)のためか、機械音というより増幅されたオルガンやエオリアンハープなどを思わせるようなサウンドが捉えられています。
・Abul Mogard『Kimberlin (Original Soundtrack)』
工場労働者として半生を過ごし、定年退職後に音楽制作を始めたというセルビアのエレクトロニック・ミュージシャンAbul Mogardによる作品。Duncan Whitleyの映画『Kimberlin』のためのサウンドトラックとして制作されています。ファルフィッサ・オルガン、モジュラー・シンセ、マニピュレートされたフィールドレコーディングやエフェクトを使用。この人は数年前から気になる存在で、立て続けにリリースされていたEcstaticからの作品群も作を追うごとによくなってる印象がありましたが、今作でいよいよ文句のつけようがないくらいアルバム作品としてまとまりのあるものを出してきたなと感じました。以前から持ち味だった霧に包まれるような感覚を想起させる深みのあるシンセのサウンドが、今作では非常に効果的なパンの動きによってより空間を想起させるものとして機能している印象があり、スピーカーの前でじっとして聴いていてもある空間の中をゆっくりうろついているような程よい運動性が感じられるのが興味深いです。眠たくなるようなサウンドですが、人気のない場所を散策する時とかに聴くのも合いそう。そして何より本作の白眉はラストの17分に及ぶ「Playing On The Stones」でしょう。この曲ではそれまでの3曲とはやや異なり、中央で鳴り続けるオルガンの存在感が強くスタティックな印象はありますが、オルガンとシンセの音のゆったりとした揺らぎやミックスのバランスが本当に素晴らしく、また後半にかけて音の色合いが変化していく様もとても自然で、本当にずっと聴いていたくなるような音が鳴ってます。
・William Basinski『On Time Out of Time』
主にアンビエントの系譜で語られることの多いNYのアーティストの新作。“13億年前の二つの離れた巨大ブラックホールの合体音を捉えたLIGO(レーザー干渉計重力波観測装置)の干渉計からの音源記録を利用したもの” と何やらヤバそうなキャプションがついています。バシンスキーの作品では音楽家としてのバシンスキー個人の姿というのは、まるで滲みや汚れや擦れの堆積した古い写真の中で見るように、時間や何かしらの障壁を経て変形/抽象化されたかたちでしか認識できない感覚があったんですが、本作に関しては本人がシンセを弾いている姿がかなり素直に浮かんでくる仕上がりで、故に異質で評価の分かれる作品なのではないかと思ったりします。自分としてはとにかく冒頭から10分くらいの低音や打音、チリチリとしたノイズっぽい高音、そしてそこに入ってくる中音域のシンセといった辺りのサウンドが好きすぎて、それだけで重要な価値を持つ作品になってしまったという感じでした。ドローン・ミュージックというよりダイナミックなアンビエントといったほうが適切な音楽だとは思いますが、特に前半部では固定的に鳴り続けるサウンドも多く聴き取れますし、その扱いにとても惹かれるものがあったので入れました。
・Kali Malone『The Sacrificial Code』
スウェーデンのストックホルムを拠点とする音楽家Kali Maloneによる、シンプルなオルガンの演奏をCD3枚組に渡って収めたアルバム。今年いい作品が多かったオルガンを用いたドローン的な作品の中でも最も多方面から高く評価されたのが本作でしょう。音楽の成り立ちを見るとドローンに分類するのには疑問符がつくようにも思いますが、そこから得られる感覚から多くのドローン・ミュージックを、それを聴く時の感覚を相対化して捉えさせる作品ということができるのではないかと思うので、ここで挙げている他の作品と是非とも並べて聴いてみていただきたいです。(詳しいレビューはこちらにあります)
・ASUNA & Jan Jelinek『Signals Bulletin』
日本とドイツの音楽家による共作。シンセ、オルガン、フィールドレコーディングなどを用い、持続音やゆったりとした周期を持つ電子音をレイヤーしていくというとても真っ当なドローン系電子音楽。柔らかさやナチュラルな厚みを感じさせる中音域に煌びやかな高音域がアクセント的に降り注ぐみたいな展開が特に印象的で、大きな音で聴いていると星空を写し取ったような雄大さとそれを見上げる際のロマンチックな心情までも音だけで喚起されるような感触があります。電子音を多く用いたドローン寄りの電子音楽ならではのクールはしっかりあるうえに、長尺の曲の後半などのサウンドから感じられる豊かなエネルギーに満ちた表情も印象的で、アルバムとしてのまとまりもよくなんというか凄く美味しい音が詰まった作品に思いました。普段あまりここで紹介しているような音楽をあまり聴かない方にも聴いてみてほしい一作です。
・Andreas Trobollowitsch『Ventorgano』
ウィーンのサウンドアーティストAndreas Trobollowitschによる、ギターの弦と木製の共鳴体、チェロ演奏用の弓の毛を素材としたプロペラ上の機工でできた自作楽器“Ventorgano”を用いたアコースティックな音響作品。基本的には複数の弦を連続的に振動させて倍音の波を聴くようなタイプの作品で、サウンドや発想はエオリアンハープに近いといえそうです。エオリアンハープのサウンドには魔法じみた魅力がありますが、その魔法を手元に置き思うがままに操作したいみたいな執念を感じます。発音の仕組みとしてはおそらくプロペラ上の機工に用いられてる弓の毛が風で弦を振動させるわけではなく直接弦に当たるように作られているようで、周期的なアタック音を際立たせてリズミックなサウンドが発せられる面もありますし、機械的な作動音も明らかに意図的に作品の一部としてミックスされているので、例えば今年Thomas Brinkmannが発表した織機の録音作品『Raupenbahn』のような純粋な機械録音に通じる視点を感じ取ることもできます。
・Hideki Umezawa + Yoichi Kamimura『re/ports』
共に音楽制作だけでなくインスタレーション、サウンドアートなどの分野を横断するような活動を行っているアーティスト梅沢英樹と上村洋一による作品。様々な場所で捉えられた環境音と、生成された電子音を重ね合わせた一遍の音響作品で、それ自体は別段風変りなものではないと思うのですが、本作の特筆すべき点はそこで現れるひとつひとつの音の解像度の高さ、音像の明瞭さです。本作は多種多様な環境音と電子音をマテリアルとして重ね合わせるという点では例えばジム・オルークが今年発表した作品『To Magnetize Money and Return a Roving Eye』に通じるということもできると思うのですが、ジム・オルークの作品が音響合成の技術を用いてそれらを判別が機能しない地平を変質的に指向しているのに対し、本作は意図的に溶け合わすようなエディットはなるだけ行わずに、まずは環境音と電子音を徹底して明瞭に、それこそミクロ的ともいえるような視点で捉えることで、結果的に一つの空間で同時に鳴らしたときにそれらが近似値を示すような時間が表れはしないだろうか?という模索的というか、フィールドワーク精神みたいなものを強く感じさせます。様々なマテリアルを一つの作品に纏め上げる段階で(アンビエントやミュージック・コンクレートの技法を活かしたような)音楽的成形が行われていることを強く感じさせる場面もあるので、そこは実験音楽を求めて聴くと評価が分かれる部分かもしれません。しかし持続的な音と反復性が一切ない環境音/ノイズ的な音のレイヤーがマテリアルを変えて幾度か現れては消え、その度に環境音と電子音が響きをより噛み合わせ、同一の空間と時間で一発録りされた響きに聴こえてくるような感触の変遷は、長い一遍の作品を聴くことでしか得られないものでしょうし、それが本作をリポート以上のものにしているようにも思えます。
(画像のリンクはレーベルのページにしていますがbandcampでも販売されています。)
・Phil Durrant『Sowari Modular』
即興の分野をメインに活動する英国のヴァイオリン/エレクトロニクス奏者Phil Durrantの作品。本作はモジュラー・シンセとセミ・モジュラー・シンセをメインに電気モーターやワイングラスの音も取り入れた電子音楽的傾向の強い音響作品となっています。タイトルに用いられている“Sowari”という語は彼の最初のソロアルバムのタイトルでもあり、参加するユニットTrio Sowariにも使用されている単語ですが、何かのコンセプトを表しているのかなどはわかりません。本作には8曲が収録されており、そのうちドローン的といえるのは①、④、⑧の3曲で、他は持続性のない音が明滅する電子音の即興といった方向性です。ドローン的な音の扱いを見せる3曲はどれもいいですが、特に⑧は扁平な持続音に徐々にノイズや新たな周波数を加えていく手つきから精神的静けさのようなものが感じられて、再生すると自然に音を集中して聴く状態に誘われる感じが本当に素晴らしい。こういう自然に意識を引き寄せる音作ってみたい。あとおそらく電気モーターやワイングラスのサウンドも使用していると思われる①はTrio Sowariの演奏に通じるものがあって興味深いです。
・Annabelle Playe『Geyser』
作曲家、歌手、ライターなどとして活動するフランスの女性アーティストの作品。瞬間的な音の切断もあり、音のレイヤーの切り替えも何度も起こるので、いわゆる一つの響きの持続と揺れだけで成り立つようなドローンからはかなり距離のある音楽ですが、そこで用いられる様々な響きの中でも時に弦楽のクラスターを思わせるような複雑な倍音を持った持続的な音響の扱いに耳を引くものがあったので本稿でも紹介することにしました。おそらくその複雑な音響は複数のオシレーターを積んだタイプのガジェットシンセなどで発しているのだと思いますが、他にも出しっぱなしの一つの発音信号に他の信号を介入させ切り替えたりすることで変化を生み出し、演奏を成立させているように感じられる箇所もあり、実際音には表れなくともその背後に出しっぱなしの信号にどうアクセスしていくかという電子ドローンの礎となるような意識が感じられる時間は結構あるように思います。とはいっても点描的な音の作りに巧さだったり、強力なノイズでクライマックス感を作り出したりと他にも聴きどころは沢山あるので、ドローンもあくまで一つの素材として扱ったスリリングな電子音楽というのがやはり適切かな。この記事で紹介している他の作品とは聴くことで呼び起こされる感覚が異なるのでやや異質な感があるかもしれませんが、ノイズだったりミュージック・コンクレートを聴く時の感覚なども思い出しながら接すると割と掴みやすくなる音楽かなと思います。ということはそれらのどれとも断言はできないってことでもあるので、なかなかありそうでない感じの作品ですね。
・Helene Breschand / Eliane Radigue / Kasper T. Toeplitz『Octopus』
過去にElliott SharpやMichel Donedaなどと共演作をリリースしているフランスの女性ハープ奏者Helene BreschandがEliane RadigueとKasper T. Toeplitzの作曲作品を演奏したアルバム。Eliane Radigueの作品からは彼女が近年発表し続けている「Occam Ocean」シリーズの1つと思われる「Occam Ocean XVI」という曲を取り上げています。
*収録されている曲目は1曲目にラディーグ作の「Occam Ocean XVI」、2曲目にKasper作の「Convergence, Saturation & Dissolution」となっているのですが、DiscogsやArt into Lifeの商品ページに表記されている情報(ラディーグの作品はアコースティック・ハープ、Kasperの作品はエレクトリック・ハープとライブエレクトロニクスのために作曲)と両者の近年の作風を踏まえて音を聴くと1曲目がKasper作、2曲目がラディーグ作であるように思うので、以下はその前提で書いています。私はbandcampでデジタル版を購入して聴いているのでCDでは事情が違うかもしれません。
長尺の2作品どちらも素晴らしいですが、個人的には最初に収録されている曲(おそらくKasper作)により惹かれました。こちらではハープと聞いてまず思い浮かべるような複数の弦が軽やかに流れるように鳴らされるサウンドは表れず、おそらくは弓やE-bow、エフェクターなどを駆使することで引き出される持続音や歪んだサウンドによって構成されているので電子音楽に近い感触で聴くことができるように思います。場面によっては結構ノイジーになりますが、あくまで一人の奏者によって演奏されている音楽であることから簡素さや音のまとまりの良さを感じることができるところが特に気に入りました。2曲目(おそらくラディーグ作)もおそらく弓弾きによるものと思われる音の掠れや揺れなど雑味の多いドローンが引き出されていて面白いです。様々な音響を示しながらもどこか構成美のようなものが感じられるという意味で近年のジョン・ブッチャーのソロ演奏に通じるものを感じたりもしました。
・Jim O'Rourke『To Magnetize Money and Return a Roving Eye』
ジム・オルークによるCD4枚、トータル4時間に及ぶ作品。継続的にリリースを続けているSteamroomの作品群、中でも30番台後半辺りから顕著になってきた音楽性の延長線上にありつつ、環境音をより積極的に取り込みじっくりプロセッシングを施した作品という感じでしょうか。Steamroonの43や44で顕著に聴き取れたハーモニーの反復もうまく用いられていますし、その辺り含めトータルの印象では42の正統進化系みたいに思えました。本当に音響的な情報量が途轍もなく多い音楽で、ここの音が好きとか凄いとか挙げ始めるとキリがないんですが、総合的にはディスク3が一番好きかなあ。最初聴いた時はすごくいいけど自分はSteanroom作品くらいの規模であったほうが好きかなと思ったりしたのですが、聴けば聴くほどこちらのほうに深くハマれるものを見出し始め流石……となりました。記事の最初に挙げたBen Vidaとジム・オルーク、キャリアの中で共通項が見い出せるこの二者が近いタイミングで同じく4時間の作品を出したことには不思議な縁を感じてしまいますし、それもあってこの2作は傑作が多かった2019年のドローン・ミュージックの中でも特に強く印象に残るものとなりました。
(Steamroom作品についてはこちらにまとめています。『To Magnetize~』を聴くうえで役に立つ情報もあると思うのでよかったら目を通してみてください。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?