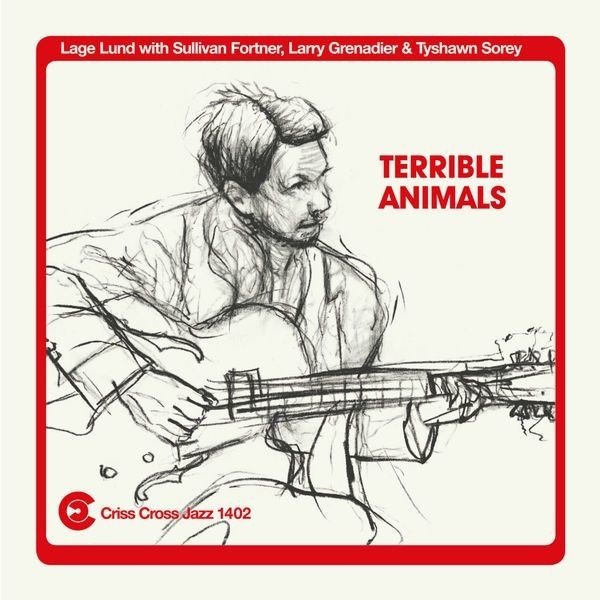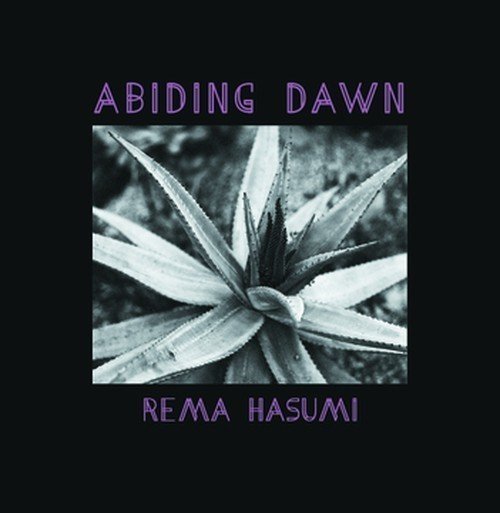2019年のベストアルバム - ジャズ
2019年の自分の音楽の聴取においてジャズは決して優先度の高いものではなかったように思います。これは単純に聴いた作品の数が昨年や一昨年に比べ少なかったということもありますが、話題作や高く評価されている作品を手に取った時にクオリティが高いことはわかるのにあまり素直に入り込めないことが多かったりと、自分のリスナーとしてのモードがあまりそちらに向いていないことを実感する場面が多かったためにそういう印象になっている側面が強いです。私は元々ジャズをプロパー的に聴いてきた人間ではないのでそのこと自体は不思議なことではないはずなのですが、2017年、2018年とここ数年はジャズミュージシャンが見せる様々な音楽的方向性に割とそのどれもを楽しめるような状態になってきていたので、それがやや落ち着いたような2019年の自分のモードには多少ギャップみたいなものを感じて驚いたりもしました。しかしそんな中でもしっかり意識を引き付けられる作品はそれなりに存在していたので、整理し並べてみたところ今自分がジャズに求めているものがなんとなく浮かび上がってくるようなセレクトとなったため一つの記事として残すことにしました。具体的にはリズムの組み方やアンサンブルの形成の仕方に創意工夫を感じるものに強く惹かれることが多く、無意識的に求めていたのかなと思います(これに当てはまらない作品も結構入っていますが、ここから更に作品数を絞るならそういった作品が残ります)。
全15作品。並びに順位など意味付けはありません。画像には試聴や購入ができるページのリンクを貼っていますので気になったらクリックしてみてください。
・Anton Eger『Æ』
Phronesisの現メンバーでありその激テクニカルなドラミングが度々注目を集めるAnton Egerの初リーダー作。シンセ類やwurlitzer、エレキギター、エレクトリックベースなど、電子的なサウンドがかなり支配的なんですがそれを凄いテクニックでめちゃくちゃフレキシブルに操るんでやたら生々しく肉感的。収録曲はどれも楽器編成やメンバーが異なる二つのパーツというかセッション(?)を繋げた構成になっていて(といってもだいたい最初のがメインで後のはアウトロ的位置づけといった感じですが)、そのパーツの中でも結構大胆な展開があったりするので、それらの切り替わりの瞬間とかスリリングな聴きどころになってます。ジャズっていう音楽のグルーヴ・ミュージックとしての側面を現代のセンスでビルドアップしたらこうなるのかなって仕上がりですが、いろんな楽器/サウンドが入り乱れ、一つのグルーヴを長時間煮詰めることなくバンバン上書きしていくような態度や速度感は最早コラージュ的にすら感じます。最初は自分の好みからするとちょっと忙しなさすぎるかなとも思ったんですが何回か聴いて慣れたらたまらんほどかっこいい…。わけも分からず情報量に引っ張りまわされるだけでもかなり楽しい音楽だと思いますが、サウンドの切り替わりとかしっかり意識して聴きたい方はbandcampのページなどに記された曲ごとのメンバー見ながら聴くのおすすめです。参加メンバーには近年個人的に注目してるPetter Eldh、Otis Sandsjö、Christian Lillingerなんかの名前も。特にPetter Eldhの大活躍っぷりヤバいです。
・Kris Davis『Diatom Ribbons』
カナダ出身でニューヨークを拠点に活動しているピアニストKris Davisの作品。彼女はMary HalvorsonやIngrid Laubrockなど共演の多い音楽家の中でも近年評価の高まりが著しい印象があり、本作も様々なメディアの年間ベスト的な記事でよく見かけました。多くの音楽家の参加が表記されていますが、その全員が一つの曲に同時に参加することはなく、基本的にはKris Davis、Trevor Dunn(ベース)、Terri Lyne Carrington(ドラム)のトリオに曲によって1~3人がゲスト的に加わるといった成り立ち。ゲスト的な奏者たちの人選も面白く、曲によっては互いになかなか共演することがなさそうな組み合わせが実現したりしています(Esperanza SpaldingとTony Malabyなんてそう実現しなさそう)。内容もそのような人選の妙を反映してか、これぞコンテンポラリー・ジャズって感じの創意工夫が凝らされた形式を持つ①、エスペランサの歌をフィーチャーした比較的柔らかい雰囲気の②、DJのエフェクティブなサウンドや声を用いた実験的な印象の④や⑦、真っ向からフリーな演奏をかます⑨など音楽性に結構幅があります。それでいてアルバムとして聴いた時に流れに違和感を感じるといったことはなく、そこから音楽的な多様性やバランスを考慮しながら一つの作品を形作るといった面でのKris Davisのディレクション能力の高さが伺えます(これには全ての曲でスマートで地に足のついた演奏を披露しているTerri Lyne Carringtonの貢献も大)。思えば彼女の2016年作『Duopoly』も活動領域や音楽的方向性の異なる様々な奏者とデュオ演奏をしつつトータルでの聴き心地も素晴らしいという仕上がりでしたし、本作にもどこか繋がる部分があるように感じます。このような創作でしっかりクオリティがコントロールされた作品を出せる音楽家は多くないですし、それができる彼女は今後もきっと素晴らしいものを出してくれるだろうと確信させられるような一作でした。
・Christian Lillinger『open form for society』
ドイツのドラマー/作曲家Christian Lillinger率いる9人編成のユニット作品。彼は2018年にリリースした『C O R』も素晴らしかったですが、本作もそれに連なる、音響やフレーズをモザイク状に配置していくような手腕が感じ取れる作品になっています。各楽器の音が点的にというか、分離して個別に耳に入ってくるような感覚がある一方で不思議な一体感があり、デコボコとしていながらも美しさを感じさせる抽象画を連想させるような、不思議な快楽性を持ったアンサンブルを構築しています。ドラム、ベース2本、アップライトピアノ、ピアノ、シンセサイザー、ヴィブラフォン、チェロ、マリンバというなんとも想像のし難い楽器編成なんですが、これらのサウンドがわかりやすく重奏という形容が当てはまらないようなかたちで噛み合わされることでこんなクールなサウンドが立ち表れるのか!っていう驚きがあります。サウンドを空間に配置していくことで徐々に音楽を組み上げていってるような感触もあってその辺の手つきは少しミュージック・コンクレート的なものも感じさせるような。また、これはツイッター上で繋がっている亡霊さんという方のツイートで気付かされた部分なのですが、Christian Lillingerのドラムの音色はサンプリングの質感をセッティングの創意工夫で再現したような、わかりやすく言うならChris Daveを思わせるようなものであり、グルーヴが前景化する場面がそれほど多くない中でこのサウンドを用いているところに目新しさが感じられます。ビート・ミュージックのエッセンスもラージ・アンサンブルの要素も見出せるけどそのどちらとも違う聴き心地を持った異形な一作。
・Contrast Trio『Music For Luminale IM』
ドイツのピアノトリオContrast Trioの作品。メンバーのYuriy SychとTim Rothがインスタレーションのために共に音楽制作を行ったことがきっかけとなり作られたアルバムということで、音楽性もそれが頷けるような心地よい隙間やほどよい緊張感がありつつアンビエントとしても機能するようなものとなっています。ゲスト奏者として参加したLeonhard HuhnのサックスやメンバーのTimが用いるモジュラーシンセの音色も音楽にさり気なく色合いを足すように機能していてとても好印象。とにかく聴き心地がいい一作です。
・Steve Lehman Trio + Craig Taborn『The People I Love』
2012年にアルバム『Dialect Fluorescent』をリリースしていたMatt Brewer、Damion Reidとのトリオに、Craig Tabornをゲストとして加えた編成での一作。『Dialect Fluorescent』でも約半分がメンバー以外の作曲を取り上げたカバーでしたが、本作でもAutechre、Kurt Rosenwinkel、Jeff "Tain" Watts、Kenny Kirklandの曲が演奏されています。また自作曲に関してもうち2曲はSteve Lehman Octetで既に演奏されていた曲なので、新曲と言えるようなものは2、3曲目の2つと少なめ(1、5、10曲目は短い即興みたいな感じ)。しかしその2曲がこの人たちの演奏におけるリズム解像度の高さをビンビンに感じさせるやつで本当に最高。もちろん新曲もっと聴きたかった~という欲を抜きにすれば他の演奏もそれぞれにめちゃくちゃスリリング。演奏の中でそれぞれがどういうグリッドや枠組みで音を発しているのか掴めない時間が多いんですが、にも関わらず(むしろだからこそ?)それらの絡みにすぐに自分の手をすり抜けていってしまうような危うい魅力を感じます。Steve Lehmanのリーダー作という意味では前作と前々作にあたる『Sélébéyone』と『Mise en Abîme』があらゆる意味で傑作という凄すぎる作品だったので今作は割とライトな佳作という風に感じてしまうんですが、これをそんな風に感じさせてしまうこの人のディスコグラフィーのヤバさ……。
・『Swiss Jazz Orchestra & Guillermo Klein』
Swiss Jazz OrchestraがGuillermo Kleinをゲストに迎えた作品。Guillermoはコンポーズとアレンジを担当しているため彼の音楽性が主に反映された作品と捉えていいでしょう。奇数の拍や音数でループするアルペジオやリフをアクセントに、パルス的に鳴る単音やメロディアスなフレーズなどが連なって万華鏡のような色彩感と動きを感じさせるアンサンブルを作り出すという彼の音楽の旨みがポップに摂取できる作品のように感じます。彼のメインユニットであるLos Guachosなどと比べ本作が特段にクオリティが高いとも思わないのですが、そこで試みられているクロスリズムなアレンジ、奇数と偶数を頻繁に行き来するようなフレーズなどに対し自分の耳が以前よりしっかり聴き取れるようになってきていることが影響して今までの作品よりしっかりとした実感を持ちながら楽しみ聴くことができました。
・Matana Roberts『Coin Coin Chapter Four: Memphis』
ミックスメディアサウンドアーティスト、サックス奏者、作曲家として活動するマタナ・ロバーツによる、「パノラマ・サウンド・キルティング」と表現されるシリーズの第四弾。本人のサックスはもちろんエレキギターやフィドルが非常に大きな存在感を放つフリーな演奏パートと、声の折り重なりや特徴的なjaw harpの音の上で力強く読まれるリーディングのパートが入れ替わり立ち代わり現れる構成で、それらが切れ目なく流れていく様は正にキルト的。シリーズの前作『Coin Coin Chapter Three: river run thee』はジャズ及び様々なジャンルの認識を飛び越え時も場所も違う様々な人間の瞑想や祈りが封じ込められた録音物って感じで、個人的にあまりに衝撃的かつ豊かで深く引き込まれる作品だったんですが、今作はメンフィスという地がテーマということもありブルースやカントリー、ゴスペルなどのルーツ・ミュージックの影響がかなり具体的に表れていて、一つ一つの楽器の音の力強さやドライブ感がまずは印象に残ります。そしてそういった力強い演奏の数々が、その間に挟まれるリーディン、歌唱、そして時には呻きのようである声との接続によって様々な感情(悲しみ、怒り)やシチュエーション(母が子をあやす場面であったり祝福、祭事)を想起させるものとして響いてくるのが彼女のこのシリーズならでは。聴いていると “メンフィスの地に息づく多様な音楽を巡る旅” みたいなイメージが思い浮かびますが、おそらく実際に同じ時と場所で耳にすることは難しかったであろう個々の音楽の断片をつなぎ合わせ、それらがまるで空間や感情を共有して鳴らされているような、ある種フィクショナルなパノラマともいえるような作品に纏め上げているところに偏執的な才を感じます。例えば人が頭の中で思い浮かべる海の波の音と実際のそれが異なるように、Coin Coinシリーズにおける音楽のつづれ織りも過去のどこにも存在しなかったものであるはずなのですが、なぜか彼女のこれらの作品は過去を参照に作られた現在の音楽というより聴き手をどこかの過去に連れ込み体験させるみたいな感触を強力に有しています。自分は音楽を聴く時にその音楽が自分にとってリアルなものであるかどうかっていう観点は(自分なりの考え方で)大事にしていて、強く惹き付けられる作品というのは何らかの意味でそれを感じさせてくれる作品であることが多いのですが、彼女のこのシリーズを聴いている時はそれが全然わからなくなります。
・Tomeka Reid Quartet『Old New』
チェロ奏者Tomeka Reid率いるカルテットの新作。サイドマンにはMary Halvorson(ギター)、Jason Roebke(ベース)、Tomas Fujiwara(ドラム)が参加。シンプルでノリのいい作曲と、そのうえで繰り広げられるチェロとギターの奔放なアドリブが聴きどころって感じの爽快感あるジャズアルバム。チェロ、ギター、ベース(コントラバス)という大きさの異なる弦楽器3つが入った編成とジャケットのイメージからかアーシーな印象を抱くサウンド。楽器自体の大きさや構造はもちろん、弓、ピック、指とそれぞれ異なる方法で演奏されるそれらの音のキャラクターの違いも聴いていて面白いです。個人的にはやはりMary Halvorsonの演奏に特に耳が引かれるわけですが、ここでの彼女の演奏は近年いろんな作品で聴いてきたものの中でもドライブ感を強く感じさせるものになっているように聴こえました。単純にテンポが速めの曲があったり、チェロと並走するような場面があることでそういった印象になるのかもしれませんが、いずれにしても彼女のインプロ/アドリブ能力をわかりやすいかたちで堪能できるアルバムって勧め方はできるかなと。また、ベースが曲の根幹となる存在感あるフレーズを太い音色で演奏してる場面が多いのも耳を引きます。ジャズ聴いてベースが強く印象にのこることはあんまりない人間なんですがこれはかっこいい。
・Petter Eldh『Koma Saxo』
スウェーデン出身で現在はベルリンを拠点に活動しているベーシスト/プロデューサーPette Eldh率いる5人組のバンドプロジェクトKoma Saxoの初作品。メンバーには近年刺激的な活動で注目を集めている音楽家が参加していて、中でも本記事で既に作品を取り上げたChristian Lillinger、昨年発表したリーダー作『Y-OTIS』が素晴らしかったOtis Sandsjöは個人的に注目しているプレイヤーだったのでクレジット見た段階ですごくテンション上がりました。リーダーのPetter Eldhについても前述の2者の作品への参加をはじめいろいろなところで名前を目にしていたので待望のリーダー作という感じでした。サックス奏者3名という編成を活かした無骨なブラスリフが印象に残る曲が多く、そこにChristian Lillingerのビートミュージックを昇華したトラッシーかつグルーヴィーなドラム演奏が加わることで前のめりな推進力を感じる音楽になっています。リフの推進力が全体を引っ張る音楽って意味ではSons Of Kemetなんかとも通じるように思いますが、こちらはレゲエ/ダブ的なグルーヴは用いずレイドバックしたノリでの演奏も少ないので、その辺りが大きな差異といえるかなと。故に突進力というか、聴き終えた時の爽快感みたいな部分では本作に分があるように思いますし、各曲が短めにまとめられていることも相まってビートテープ聴くような感覚でラフに接することができるアルバムのようにも感じます(そういえば音質もどことなくそんな感じ)。かなりキャッチーな音楽性だと思うのでいろんな方に聴いてみてほしいです。
・Larry Ochs, Nels Cline, Gerald Cleaver『What Is To Be Done』
サックス、ギター、ドラムによるパワー系フリーセッションといった感じでそれ自体には特別目新しさとかはないんですが、何よりNels Clineのギターの凄まじさに完全にヤラれました。この人は今までいくつかリーダー作聴いてみたことはあるもののイマイチよくわからない…って感じだったんですがこんなヤバいギタリストだったとは。こういう小編成でのフリーキーなギター演奏だと、楽器編成や方向性は異なりますがScorch TrioでのRaoul Björkenheimとか好きですが、衝撃度ではそれに勝るかも。マジでかっこいい。
・Pedro Martins『Vox』
Kurt Rosenwinkel『Caipi』への関わり以降注目度がより高まったブラジルの音楽家Pedro Martinsのリーダー作。ギター、ヴォーカル、鍵盤、ドラムをはじめ様々な楽器を操るマルチプレイヤーで本作でも多くの演奏楽器がクレジットされています。また参加メンバーにはお馴染みのKurt Rosenwinkel、Antônio Loureiro、Frederico Heliodoroらに加えBrad MehldauとChris Potterの名も(豪華すぎ…)。リリースされてすぐのタイミングで聴いた時はあまりピンとこなかったんですが最近聴き直したらハマりました。特に最後の5曲くらいの流れ名曲揃いで凄すぎる。彼が参加していた昨年リリースの作品Daniel Santiago『Union』ほどコントラストは強くないものの、細かに刻まれるドラムやリズムシークエンスの上をゆったり泳ぐような声やギターがここでもとても魅力的に響きます。特にドラムが強弱のニュアンスの幅を抑えた(ドラムマシン的な)マシニックさを際立たせるような演奏をしている場面や、シンセの電子的な彩りがある曲ではそれが一層映える感じで最高。あと自身のリーダー作だけあって随所でギターのテクニカルな演奏がしっかり前面に出てくるのもかっこいい。
・Sam Ospovat『Ride Angles』
ニューヨークを拠点に活動するドラマーSam Ospovatの作品。Matt Mitchell、Kim Cassとのピアノトリオを基本に曲によってはBrandon Seabrook(ギター)、Nick Lyons(アルトサックス)、Lorin Benedict(スキャット・ボイス)がゲストとして加わるといった編成で録音されています。Ospovat自身が全曲を担当している作曲がとても面白く、ギミックの多いリズム/フレーズを多く用いながら決して長くはない演奏時間の中でそれらの循環と切り替えが小気味よく起こる様にとても惹かれます。3連符のような時間の奇数分割(もしくはパルスの奇数個の積み上げ)を援用した感じのフレーズがあちこちから聴こえてくる感覚が聴けば聴くほど身体に馴染んできてクセになりますし、それをそれぞれに迷いなく乗りこなすドラム、ベース、ピアノのアメーバ的な掴み切れなさが本当にかっこいい。各々が自由に変形しているようですごく一体感を感じます。同じく2019年に発表されたMatt Mitchellのリーダー作『Phalanx Ambassadors』でも素晴らしい演奏をしていたKim Cassがこちらでも非常に耳を引く存在感があって特に2曲目とか凄いです。また本作のピアノトリオを基本に曲によってゲストが加わるという成り立ちは本記事で既に挙げているKris Davis『Diatom Ribbons』とも通じる部分ですので、そちらが好きな方には是非とも本作も聴いてみていただきたいです。
・Anna Webber『Clockwise』
アメリカのサックス奏者/フルート奏者/作曲家Anna Webberの作品。自身のフェイヴァリットである20世紀の作曲家(Iannis Xenakis、Morton Feldman、Edgard Varése、Karlheinz Stockhausen、Milton Babbitt、John Cage)へのオマージュとして、彼らの打楽器作品を研究し制作された一作。レビューはこちらにあります。
・Lage Lund『Terrible Animals』
彼の作品にはこれまでしっかり耳を通したことがなかったのですが、本作聴いた印象だとフォーキーな暖かみのある旋律がスウィング的な揺れが発生しやすいよう設計されたようなリズムに乗るって感じの作曲にすごく味わい深いものを感じました。そしてその曲をLarry GrenadierとTyshawn Soreyというゴツいリズム隊が演奏することで柔らかい印象だけに留まらないめっちゃ骨太でかっこいい音楽にもなっています。本作で初めて耳にしたピアノのSullivan Fortnerも随所で耳を引く演奏をしていてこの人も只者じゃないと感じさせます。このセレクトは割とアブストラクトな音楽性のものが多めですが、本作は所謂ストレート・アヘッドなコンテンポラリー・ジャズと呼ばれるものに比較的近い作品かと思うのでそういうの求める方には是非とも聴いてみていただきたいです。
・Rema Hasumi『Abiding Dawn』
ニューヨーク在住の日本人ピアニスト/ヴォーカリスト蓮見令麻の3rdアルバム。これまでの作品は他者を迎えたバンドもしくはアンサンブル的な内容でしたが、本作は全て自身が演奏したピアノ、声、アナログシンセのみによって成り立つソロ作。シームレスに繋がった8つのトラックが収録されていて、その中にはある程度予め用意されたフレーム(いわゆる作曲の概形みたいなもの)が感じ取れるものから即興でピアノを弾き探り探り声を発する様子が結果的にメロディーになったように感じられるものまで流動的に存在してる印象。シンセが柔らかい音色でコードを流す場面があったりはするものの、ピアノに関しては音をポツポツと置いていくような(アンビエント的と表現されるような)演奏はそれほど多くはなく、歯切れのいい打鍵と饒舌にも感じられるような音の動きがある紛れもなくジャズな演奏なのですが、ペダルによる残響の用い方なのか自然な奥行きが感じられる録音によるものなのか、意識の外で鳴らしておくような聴き方にもとても馴染む仕上がり。作品の成り立ち上こじんまりとした空間で鳴らされるパーソナルな音楽といった雰囲気を帯びるのは当然に思うのですが、その空間にじっと腰を落ち着けて聴くだけでなく、その前を素通りしながら接してみたいとも思わせられるような、作品が受け入れられる聴き手との距離感のレンジがとても広く感じられるのがすごく不思議かつ魅力的。そういった意味では同じく2019年の作品であるSolange『When I Get Home』と通じる感触があるように思います(影響の現れ方は違いますが、Alice ColtraneやSun Raなどスピリチュアルと称されるような音楽の薫りが微かに感じ取れる点も通じるかも)。ジャズの作品からはあまり喚起されることのない印象が自分の中に多く表れる一作で、それ故に様々な人に一度触れてみてほしいと強く思います。
最後に今回のセレクトに入れようか迷った作品をいくつか。しかし決してジャズにいつも以上に大きく関心が向いていた一年ではなかったにも関わらず、しっかり振り返ってみるとこれだけいろいろ書きたくなる作品があるっていうのが逆説的に近年のジャズリリースの充実ぶりを実感させますね。
・Brad Mehldau『Mon chien Stupide』
・Christian Scott aTunde Adjuah『Ancestral Recall』
・Chrisoph Irniger Pilgrim『Crosswinds』
・Tyshawn Sorey and Marilyn Crispell『The Adornment of Time』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?