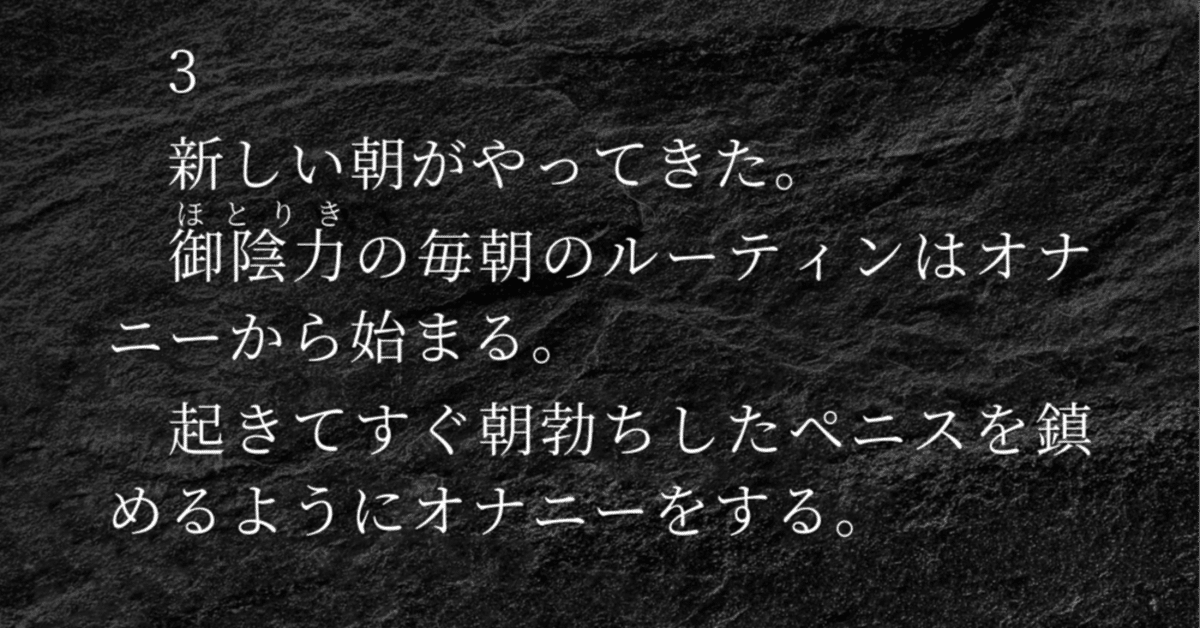
小説「ベーションマスター」3
3
新しい朝がやってきた。
御陰力(ほとりき)の毎朝のルーティンはオナニーから始まる。
起きてすぐ朝勃ちしたペニスを鎮めるようにオナニーをする。
それから朝食を食べて身支度を整え学校へと向かう。
いつもなら目に入ってきても気にしなかったベーションルームに自然と視線が吸い寄せられてしまう。
通学路を歩くだけでこんなにも多くのベーションルームが設置されていたのかと新鮮な驚きを得た。
ベーマスという競技のことはまだよくわからなかったが、これだけオナニーすることが当たり前になってる世界で自分だけがオナニーを恥ずかしいものだと捉えていること自体おかしなことだなと自覚はしている。
それでもやはりまだ公共のベーションルームを使うには抵抗があった。
同じように通勤や通学で歩いている他の学生やサラリーマンは何の躊躇もなくベーションルームへと吸い込まれていく。
それこそ朝のコンビニでちょっと飲み物でも買っていくかのような自然さだ。
周りの人たちもそれをみて何も思うことはないのだろう。
自分だけが、あの中でみんなオナニーしているのだと意識してしまって胸の奥が熱くなってしまう。
はやくオナニーがしたい。自分ももっと自由にいろんな場所でオナニーしてみたい。
純粋な好奇心と相反する羞恥心に阻まれながら力は学校へとたどり着いた。
朝のオナニーを終えたばかりだというのに力のペニスはすでにはち切れんばかりに怒張していた。
これではまともに授業を受けることさえ難しい。
今からベーマス部の部室へ行ってベーションルームを使わせてもらうか。
いやしかしこんな朝から部室が空いてるわけがない。
放課後まで我慢できるか。
さすがに無理だ。今すぐにでも射精して気持ちよくなりたい。
力はありったけの勇気を振り絞って、一年生の校舎にあるベーションルームの前までやってきた。
さすがに登校してきてすぐにベーションルームを使う生徒はいないのかいくつかあるベーションルームはすべて空き室だった。
周りに誰もいないことを何度も確認すると、力は意を決してベーションルームの中へと入った。
はじめてのベーションルーム体験。昨日の競技用のベーションルームとは違いとても簡素な部屋だった。
オカズを登録するような端末もなければ、オカズを投影するモニタ類も存在しない。
シンプルにオナホールを設置する穴だけが無造作に置かれている。
衣類を収納する棚もそれほど大きくはなかった。
本当にオナニーするだけの部屋という感じだ。
学校のベーションルームだからなのか、それとも公共に存在するベーションルームはみなこういうものなのか、力には判断つかなかったが、とにかく自分のオナホールを穴にセットする。
計測音などは鳴らなかったが自動でオナホールが動き始めた。
動き方も結構雑で競技用のベーションルームとは似ても似つかなかったが、自分で動かすよりもそれは気持ちよくて、朝のホームルームが始まるまでに三回も抜いてしまった。
こんなに朝から抜いたのは小学生以来かもしれない。
新しいオナニー方法を次から次へと試していたあの頃に力は思いを馳せるのだった。
放課後になった。
一度ベーションルームを使ってしまえばなんてことはない。
もうトイレで隠れてひっそりオナニーする必要がなくなった力は授業の合間や昼休みに時間を見つけては何度もベーションルームへ足を運んだ。
さすがに何度もベーションルームを利用していると、思ったより自分以外の利用者が少ないことに気づく。
生理現象とはいえ、トイレと違いオナニーはそれなりに体力をもっていかれるので普通は一日に一、ニ回が平均回数らしいことはなんとなく知っている。
ベーマス部に所属している優や心でさえ部活以外でのオナニーは基本的にしないと言っていた。
もしかしたら自分は人よりオナニー回数が多いのかもしれない。
誰かと比べたこともないのでとくに意識はしていなかったが、これだけ何度もベーションルームに足を運んでいると自分しか利用していないのではないかと錯覚しそうになる。
「力が……ベーションルームから出てくるとこ……はじめてみた」
「うわ!」
突然背後からボソっと話しかけられてとびのく力。
振り返るとそこには見知った顔が書類を抱えて棒立ちしていた。
「な、なんだ。いずか」
「………」
彼女は珠戸いず。力の幼馴染である。
近所に住んでいるということから小学校はもちろんのこと中学校も同じだった。
そして高校生になった今も同じ学校である。
さすがにクラスは違うので頻繁に顔を合わせるということはなかったが、まさかこんなに間の悪いタイミングで顔合わせするとは思っていなくて力は気まずくなり押し黙ってしまう。
「……ベーマスでもはじめるの?」
いずは特に気にした風もなく自然と疑問を口にする。
「あ、いやこれは別にそういうのじゃ……」
ベーマスのことは、はっきりいってまだ何もわかってない。始めるも何も自分はまだベーションルームにハマりはじめたばかりなのだから。
どう答えれば良いのか迷っていたら、いずが手にしている書類を見て誤魔化すように自然と「僕も運ぶの手伝うよ」と口にしていた。
いずはありがとうとだけ口にするとそれ以上何も追求してこなかった。
長年の付き合いだけあってお互いに何をしてほしいのかしてほしくないのか自然とわかっているようでもあった。
無事職員室に書類を届けると、力は
「じゃ、僕はこれで」
「……うん」
足早に職員室から離れていく力の背中をいずは、力が見えなくなるまでずっと無言で見送った。
力はベーマス部の部室前に来ていた。
また来ると宣言した以上今日もベーションルームを使わせてもらいにやってきた。
先ほどいずに聞かれたことが頭から離れない。
『ベーマスでもはじめるの?』
即答できなかったのには理由がある。
自分はただオナニーがしたいだけだからベーマスという競技には興味がない。
昨日までは本気でそう思っていた。
でも優に出会ってはじめて人前でオナニーしたら世界が違って見えたのも確かだった。
あれはただ目新しい体験に興奮していただけじゃないのか。
ならもう一度試して――
「どうした入らないのか?」
「え? あ、部長!」
またしても背後から突然声をかけられて振り向く力。
優は扉に手をかけるとするりと開け放つ。そして力の背中をそっと押した。
「遠慮しなくていいんだぞ。今日もベーションルーム使いに来たんだろ。ほら入った入った」
「は、はい」
部室に入るとすでにベーションルームが稼働していた。
どうやら心が中にいるらしい。
「ほう。心が積極的にベーションルームを使ってるのは久しぶりにみるな」
優は何やら嬉しそうに語りながらベーションルームに駆け寄り、外からポンポンと箱を叩いている。
力はこの部屋にはひとつしかないベーションルームを眺めながら所在なさげに棒立ちしていた。
心が出てくるまでは完全に手持ち無沙汰だった。
「やっと来たのか。次はお前の番だ」
汗だくの姿でベーションルームから出てきた心は、力を見て開口一番そう答えた。
「え、あはい」
心の勢いに押されて力は理由もわからずベーションルームへとなだれ込む。
すると、ルーム内に心の声が鳴り響いた。
『そこにあるオナホをセットしろ。そしたら音声に従って昨日みたいにオナニーしてみろ』
「え、自分のオナホじゃだめなんですか?」
『いいからさっさとしろ』
「は、はい」
はじめますかと機械音が鳴る。
力にはなんのことかさっぱりわからなかったが、心に言われるがままセットしたオナホにペニスを差し込む。
すると自動でオナホが動き始めた。
いつもと違う感覚に腰が引けてしまう力。
オカズを見る余裕すらなくオナホに挿入してからたった五分で射精してしまった。
「はぁはぁ。どうしてこんな……」
「やっぱりな。お前。ハヤマス選手になれ」
いつの間に開け放たれたのか、ベーションルームの扉の向こうから心が力に向かって堂々と宣言していた。
「僕が? 選手?」
言葉の意味は理解できても、何を言っているのかは理解できない。
力が返答に困っていると優が間に割って入ってきた。
「こらこらこら。力はただオナニーしに来ただけなんだから、そんな無理を言うものじゃない」
「ちっ」
勢いだけでなんとかなるとでも思っていたのか、心は不貞腐れると再びベーションルームの中へと入っていった。
今回は部室を飛び出していくような状況ではなかったらしい。
「すまない。心は熱くなると一直線なやつだから」
「あ、いえ。それよりハヤマス選手って……」
力はなぜそこまで心がハヤマスにこだわっているのか不思議だった。
そもそもハヤマスとは何かわかっていないので、自然と疑問が口を出た。
「お? ハヤマスに興味ある感じ?」
力がしまったと思ったときには時すでに遅し。
優はハヤマスとは何か早口でしゃべりはじめた。
「ハヤマスってのは俗称で正式にはスピードマスターベーションって呼ばれる競技のことだが、射精するまでの時間を競う競技のことだ。ハヤマスでは基本的に統一された規格のオナホを使用する。さっき力が使ったやつだな。自分の手でオナホを使うのも禁止だ。統一されたオナホ。統一された動きによる射精を合計三回計測する。その三回のうち射精までの時間がもっとも早かったタイムが結果として残る競技のことだ。心はこのハヤマスで全国三位の成績を残してるからな。力の射精速度に興味を持ったんだろう。なんせハヤマス初心者がいきなり五分なんてタイムを叩き出したんだから。俺でも驚いたぐらいだ」
「そんなにすごいんですか?」
自分のことなのにまるで自分のこととは思えない力が口を挟む。
「すごいなんてものじゃない。高校のハヤマス大会では五分は優勝候補に名を連ねてもおかしくないぐらいのベストタイムだ。平均でも十五分近くかかるのが普通なんだから、力は飛び抜けて早いと言っても過言ではない。心が熱くなるわけだ」
「そう……なんですか」
どれだけ力説されても力にはピンとこなかった。
これまで射精までの時間なんて計測したことなかったし、何より早く射精することを意識したことなんて一度もなかったからだ。
さきほどもただ心に言われるがままオナホをセットして、慣れない刺激に驚いて射精してしまっただけなので、どちらかというと事故に近い形だ。
毎回あの速度で安定して射精できるとは到底思えない。
「もう一回やってみろ」
いつの間にベーションルームを出てきたのか心が力の背後に立っていた。
優はやれやれと首をふるだけで、どうするかは力に委ねるという顔をする。
「わ、わかりました」
力は再びベーションルームに入ると、先程と同じように指定されたオナホをセットし、はじめますかの合図でオナニーを開始した。
しかし、先ほどとは打って変わってなかなか射精に至らない。
頭の中でいろいろな考えが渦巻いてまったく射精に集中できなかった。
すべてが終わった時には、二十分という時間が表示されているだけだった。
「考えすぎだ。射精は一番気持ちいい時の自分をイメージし、常にそこに自分を合わせていくのが大事だ。今のお前に足りないのは圧倒的練習不足。これから毎日ハヤマスモードで練習しろ」
心は聞いてもいないのに謎の忠告を残すと再びベーションルームへ吸い込まれていった。
もう力には興味ないみたいな感じだった。
「あ、あの僕、また心先輩を怒らせちゃいましたか?」
「気にするな。ああいうやつなんだ。それよりちょっと疲れただろ。今日はこのぐらいにしてまた明日来たらどうだ?」
「そ、そうですね。オナニーでこんなに疲れたの初めてです。ベーマスってこんなに疲れる競技なんですね」
「ははは。オナニーとは本来ただの排泄行為みたいなものだからな。そこに競技性が足されるだけで肉体や精神に負荷がかかる。これまでの力はただただオナニーしたいからしていただけだからそんなことまで考えていなかったと思うが、ベーマスはむしろ頭や体を酷使する競技だからな。同じオナニーとはまた違う世界が広がっている。でも力はそこまで気にすることはない。これからもベーマスに関係なく好きな時にベーションルームを使ったらいい。好きでもないことを無理やりするなんてそれこそオナニーじゃなくなるからな」
優の優しさが身にしみる力だった。
入学式の時に初めて見たときは破天荒な人だなと思ったが、こうしてみるときちんと部活の部長をやっており、部員のことをしっかりを考えてるいい部長だった。
いつもとは違う心地よい疲労感に包まれながら力は帰宅の途についた。
投げ銭大歓迎!
