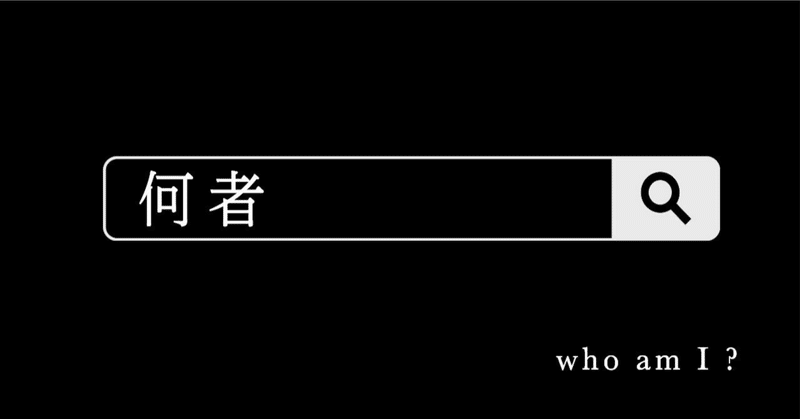
『アーキテクトの教科書』 著者経歴
2024年7月22日に、翔泳社さんから書籍『アーキテクトの教科書 価値を生むソフトウェアのアーキテクチャ構築』を出版します。
ECサイトの書籍情報には文字数の制限もあるため、いったいこれは何の本で、どんなことが書かれているのかといったことをnoteにまとめたいと思います。
そもそもお前誰よ?ってことで、筆者のこれまでの経歴をまとめました。ちょっと長くなってしまったので、本の内容については次の記事にて。
筆者は何者?
一社目(ユーザー系SIer、2000年〜)
筆者が新卒で社会人になったのは2000年のことです。ユーザー系SIerに就職し、研修を終えた後はJSP+Servlet+EJBで作られた業務システムの保守を担当することになりました。これがまぁ絵に描いたようなレガシーシステムで、数千行のJavaクラスやストアドプロシージャと格闘する日々でした。開発者というのものは、こんな大量のコードを脳内メモリで処理しないといけないのか!と当初は思っていました。ですが、結城浩さんのデザパタ本と出会って、オブジェクト指向でちゃんと設計ができればもっと保守性の高いコードを書けるはずだ、と気づき、オブジェクト指向の虜となりました。
その後別のシステムの担当となり、そこで見習いアーキテクトとして仕事をする機会をもらいました。といっても既にできあがったシステムの二次開発だったので、アーキテクチャ設計というよりも、共通ライブラリの開発や標準化の推進、コードレビューなどが主なタスクでした。そのシステムもそれなりのアーキテクチャの「形」はあったのですが、思想が隅々まで行き届いていないというか、結局はレガシーと化してしまったコードが多々存在していました。
二社目(豆蔵、2004年〜)
もっと良いアーキテクチャがあるはずだと思った私は、マーチン・ファウラー氏のPoEAA(書籍『エンタープライズアプリケーションアーキテクチャ』。この良書が翻訳されるまで少し時間がかかったので、当時は頑張って原著で読んでいた)やら、アーキテクチャ関連の書籍を読みあさり、アーキテクトという職種への思いが強くなりました。
オブジェクト指向とアーキテクチャの両方の経験を積むことができる場所として、株式会社豆蔵に転職したのが2004年のことです。豆蔵では、顧客の社内フレームワークの開発支援やプロダクト開発支援など、いくつかのプロジェクトで経験を積みました。当時、IT業界ではITアーキテクトという職種が脚光を浴び始めた頃で、そのままズバリ「ITアーキテクト」という雑誌が創刊されたのが2005年だったと記憶しています。こういった雑誌やWeb媒体で連載を持っているような著名なアーキテクトが、私が働いているプロジェクトでリーダーを務めていたので、いつかこんな風になれたらと憧れを抱きながら、彼らのもとで研鑽を積んでいました。
ただ、そういったエース級のアーキテクトは複数の案件を掛け持ちしていて多忙なので、体系的に何かを教わったというよりも、「見て盗む」という感じだったように思います。
三社目(電通総研、2008年〜)
大規模システムの開発プロジェクトでアーキテクトとしての自分の腕試しをしたいと思った私は、二度目の転職活動を行い、株式会社電通国際情報サービス(当時。2024年1月より株式会社電通総研に社名変更)に入社しました。
希望どおり、ERPの導入プロジェクトにおいて周辺系のスクラッチシステム開発のアーキテクトの役目を任命しました。ただ、当時SIerという組織においてアーキテクトという職種は希少種だったので、一人アーキテクトチームという体制でした(途中からパートナーさんを入れてもらって二人体制)。
それまでリーダーという役割で仕事をしたことがなかった私は、技術力には多少の自信はあるものの、いざアーキテクチャ構築となるとどこからどう手をつけていいかさっぱりわかってませんでした。
わからないことは都度調べて、学んで、なんとか頑張ってやり切る、という仕事のスタイルでした。今にして思えば本当に未熟者だったので、きっと周りにたくさん迷惑をかけていたのだと思います。
その後複数の大型SI案件にアーキテクトとして関わってきましたが、毎回そんな感じです。ことアーキテクティングに関しては誰かに教わるという機会が一切なかったので、書籍等で必死に勉強して、都度必要なスキルを身につけ磨いてきました。なので、「本当にこのやり方で正しいんだろうか?」みたいな不安感は常にありましたね。
プロダクト開発(2016年〜)
自社開発のパッケージソフトの基盤となるプラットフォームを構築するというプロジェクトが2016年に立ち上がり、2016年の末頃にジョインしました。当時のSIerとしてはかなりモダンな開発にチャレンジしていたプロジェクトだったので、周りにアーキテクチャや技術の話が通じる仲間がたくさんいたのは嬉しかったです。
プラットフォーム構築だけでなく、その上で動く業務アプリケーションの開発支援も行い、2018年からは同一シリーズの新プロダクトの製品開発リーダーを拝命しました。自分としては「リードアーキテクト」と名乗ってますが、プロダクトのコンセプト設計から要件定義、アーキテクチャ構築、アプリケーション基盤開発、メイン機能の実装、テストとほぼ全ての工程を担当していたので、「何でも屋さん」といった方が正しいのかもしれません。2021年初頭に製品をリリースしてからは、営業に同行してのプリセールスや、獲得した案件の導入支援などもやっていたので、もはや自分の職種が何なのかわからなくなったりもしました(笑)。
そんなこんなで
振り返ればいろんな仕事を経験させてもらいました。一つ一つの経験が今の私を形作っていることは間違いないのですが、一方でアーキテクトとしての仕事の仕方や必要な知識を学ぶのにとても苦労したなという思いもあります。もっと体系的に効率よく学習ができていたら、もっとスキルを上げてもっと大きな貢献ができたんじゃなかろうか、と。
今回僭越ながらアーキテクトの入門書の執筆をお受けした背景には、このような思いや、何らかの形でIT業界に還元していきたいといった気持ちが少なからずあります。
次の記事では本の中身について書きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
