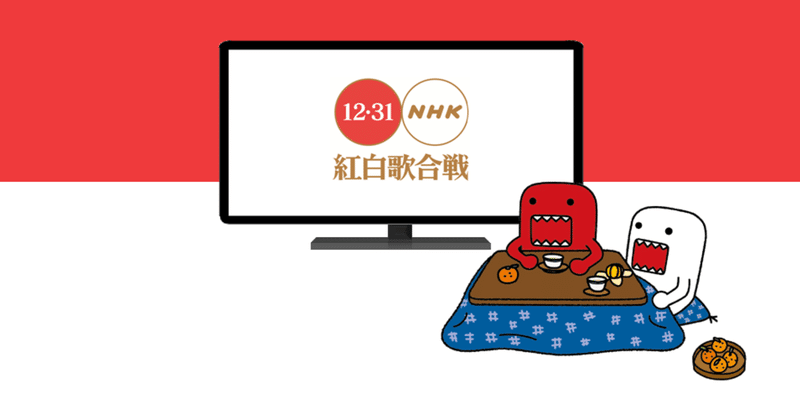
いつまで紅白に分かれて合戦するのか?
紅白歌合戦が好きである。毎年、最初から最後まで他にチャンネルをまわさずに観ている。
嵐が中継、かつオオトリでなかったことに代表されるように、(無観客なためにステージを広く使えるため、演出に広がりがあったけれど)なんだかこじんまりとした印象。収録やCG、中継を駆使しているという意味で制約から解き放たれているはずだったのだが、だからこそ緊張感のようなものがそがれたようにも思う。個人的にはライブにおける観客の重要性を今一度噛み締める紅白歌合戦となった。
いくつか「おっ」と思うパフォーマンスはあったが、自分の中では以下の2曲に時代の分岐を感じた点が印象深く残っている。
自粛期間に、たくさんの人を楽しませた星野源さんの『うちで踊ろう』。
うちで踊ろう ひとり踊ろう
変わらぬ鼓動 弾ませろよ
生きて踊ろう 僕らそれぞれの場所で
重なり合うよ
星野源が『第71回NHK紅白歌合戦』にて披露した「うちで踊ろう(大晦日)」の歌詞をアップします!
— 星野源 Gen Hoshino (@gen_senden) December 31, 2020
元々の歌詞に2番を加え、新たなバージョンでお送りしました。感想もぜひお送りくださいね!#うちで踊ろう #DancingOnTheInside#NHK紅白 #星野源 pic.twitter.com/8FbxbRrzzf
そして、福山雅治さんの『家族になろう』。
⚪️福山雅治さんで
— NHK紅白歌合戦 (@nhk_kouhaku) December 31, 2020
『家族になろうよ』
ありがとうございました
見逃した方・もう一度見たい方は
NHKプラスで見られます▼https://t.co/QpADaQJ3xm#NHK紅白#福山雅治 pic.twitter.com/ctAnSlVsfD
その中の歌詞では、
いつか父さんみたいに〜
いつか母さんみたいに〜
いつかおじいちゃんみたいに〜
いつかおばあちゃんみたいに〜
と歌われ、どんなことも乗り越えていける家族になろうよ、と締められる。
結婚情報誌のゼクシィのCMソングで、2011年にリリースされた。上記の歌詞を検索して、読み込んでいただければと思うのだが、なかなかに昔ながらの家父長制が描かれた世界観。約10年の月日が流れ、この激動の社会の流れの中で聞くと、なかなかの違和感を感じる歌詞となったと私は思う。
決して、父さんは広い背中でなくても、母さんは静かで優しくなくても、おじいちゃんは無口で強くなくても、おばあちゃんは可愛い笑顔をたたえなくても、いいじゃないか!
いや、そうであってももちろんいいとは思うのだけれど、これを聞いて「家族はこうありたいね」と、皆の脳内に刷り込みがおこる社会に不安を感じると言うべきか。2020年の公共放送の最も視聴率が上がるであろう時間帯に、NHKはこの曲をあてたのだなぁ、などととしみじみと。
その対極として、星野源さんの歌詞の現代性が際立つな、と思った大晦日の夜であった。
ちなみに、『香水』の大ヒットにより初出場を果たした瑛人さんは出場が決まった時、「僕は、白組、紅組のどちらですか?」と聞いたそうである。性別で分けられている仕組みを知らなかったようだ。そういう世代が出場するし、観覧していることへの配慮を今後、NHKはどう考えていくのだろうか?
EXITの兼近さんは、以下のようにつぶやいた。
ももクロ歌合戦で歌った後は紅白歌合戦ブチ上げ!俺があらゆる合戦という争いを止めに行く🐖🍥(盛り上げます)
— EXIT 兼近 (@kanechi_monster) December 31, 2020
その後は
CDTV年越しライブ!←芸人?
明けるぞーどんな事があっても結局今年も明けるぞー🦒🍻
ジェンダーはどんどんグラデーションになっている。性別を2つに分けて、合戦することの意味は、はたして?
昨年末、ファミリーマートの「おかあさん食堂」論争でわいた。
大晦日に立ち寄ったファミレスのトイレの入り口の表示。なぜ、男子トイレには、おむつ交換台の設置がないのか?

引っ越し作業中、引越し業者から支給された段ボールの「奥様メモ」というメモ欄が気になった。なぜ、「メモ」ではいけなかったのか?
なぜ、私は元旦からこんなことを書いているのか?
なぜ? なぜ?? なぜ???
さて、2021年が始まった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
