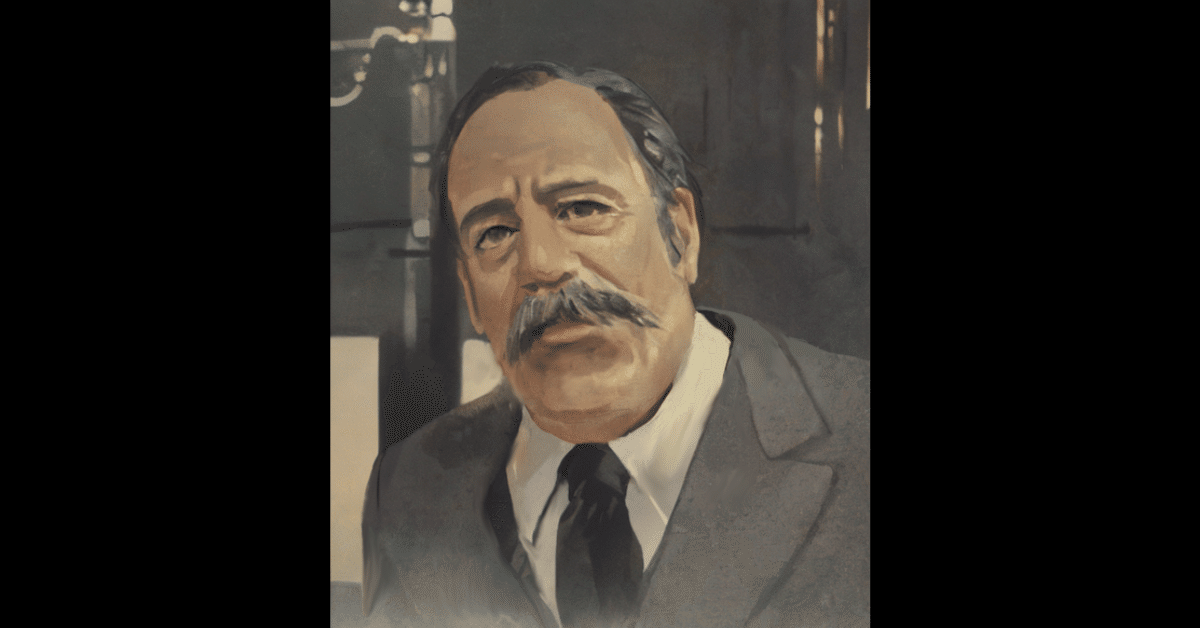
寺山修司によるサローヤンの引用――「あらゆる男は、命をもらった死である」
寺山修司が死んだのは、1983年5月4日だ。その年の2月から5月まで、寺山は『週刊読売』に「ジャズが聴こえる」という題の連載エッセイを書いた。
「ジャズが聴こえる」シリーズの最後のエッセイは「墓場まで何マイル?」という題だ。これは寺山の葬儀が行われた5月9日に発売された『週刊読売』に掲載された。寺山の「絶筆」とされる。
このエッセイは、サローヤンの次のような引用で終わる。
「あらゆる男は、命をもらった死である。もらった命に名誉を与えること。それだけが、男にとって宿命と名づけられる。」(ウィリアム・サローヤン)
う~む、カッコいい。昭和っぽさ、むんむんだ。
寺山によるこの引用のせいか、ネットのあちこちで、これがサローヤンの名言として流通している。
でも、本当にサローヤンの言葉なのか?
寺山修司は第一歌集『空には本』で、
青い種子は太陽のなかにある ジュリアン・ソレル
というエピグラフを使った。(う~む、これもカッコいい。)ジュリアン・ソレルは、フランスの作家スタンダールの小説『赤と黒』 (1830) の主人公だ。
この言葉が『赤と黒』のどこにあるのかを探してみた人がいる。でも、どこにもなかったようだ。寺山は後に堂本正樹に、「あれは、僕がコサえたんだ」と告白している(★1)。
そんな「前科」があるので、どうも信用できない。サローヤンの言葉もひょっとしたら……と思ってしまう。
サローヤンは本当にどこかで「あらゆる男は(……)」と書いているのだろうか。
気になるので調べてみた。
■エッセイ「少年のための『Home Again Blues』入門」より
「ジャズが聴こえる」シリーズには、「少年のための『Home Again Blues』入門」というエッセイもある。これは「墓場まで何マイル?」の二つ前に掲載されたものだ。
ここにも「あらゆる男は、命をもらった死」という言葉が出てくる。
「もう帰るのか?」
と、ヘイグが言った。
「ああ」と、ロックは気のない返事をした。
本当は、帰りたくなんかなかった。ブルーノの単車を借りて、六十六番の国道を一晩中でも走っていたかった。どうせ、
あらゆる男は、命をもらった死
なのだ。
エッセイの終わりでは、「サローヤンの小説の一節」として、次のような言葉が引かれる。
男はみな不安である。あらゆることに不安である。しかし、結局、あらゆることはみな彼自身が原因なのだということを知っている。男の一生は、顔や眼や口や、からだや手足をもらった死なのだ。
これも手がかりになる。
■サローヤンの『ロック・ワグラム』
いろいろ調べてみたところ、寺山がサローヤンからの引用としているのは、『ロック・ワグラム(Rock Wagram)』(1951)という小説からのもののようだ(★2)。
「少年のための『Home Again Blues』入門」に登場するロックはこの小説の主人公だし、またヘイグはロックの従弟だ。「六十六番の国道」も"Highway 66"として原文に出てくる。ただ、ブルーノは小説には登場しない。
寺山のエッセイは、エッセイといってもまるで小説の一場面のように書かれている。これはいわば寺山の二次創作だ。サローヤンの小説の登場人物の名を使って、それらしい雰囲気をかもし出しているのだ。
■原文とその訳
『ロック・ワグラム』の原文を見ていくと、次のような箇所がある。
Every man is afraid. He is afraid of many things or of everything, but in the end they are all himself, as he himself knows. A man is afraid all his life, for every man is death given a face, eyes, ears, nose, mouth, body, and limbs, and every man is death given life, as he himself knows.
どんな男も恐れている。多くのことを、あるいはすべてのことを恐れている。しかし結局、自分自身を恐れているのだ。自分でもわかっている。男は生涯にわたって恐れている。というのも、どんな男も顔や眼や耳や鼻や口や体や手足を与えられた死だからだ。どんな男も命を与えられた死だからだ。自分でもわかっている。
寺山の「あらゆる男は、命をもらった死である」が、"every man is death given life"から来ていることがわかる。
また、「男はみな不安である。あらゆることに不安である。しかし、結局、あらゆることはみな彼自身が原因なのだということを知っている。男の一生は、顔や眼や口や、からだや手足をもらった死なのだ」という文章がここから採られていることもはっきりした。
■「もらった命に名誉を与えること」以下の部分は?
では、「あらゆる男は、命をもらった死である」に続く、「もらった命に名誉を与えること。それだけが、男にとって宿命と名づけられる。」の部分は?
『ロック・ワグラム』にはそれにぴったり一致する箇所はない。
それでもぱらぱらめくっていくと、次のような一節がある。
Every man is afraid of something, but most of all he is afraid of death and disgrace. There are few moments in the life of any man in which there is no disgrace, and none in which there is no death. The nobler the man is the more aware he is of the disgrace in himself, the nagging absence of grace. The more alive the man is the more aware he is of the death in himself.
どんな男も何かを恐れている。しかし、とりわけ死と不名誉を恐れている。どんな男の人生にも、不名誉なことが起こらないことはほとんどない。そして死なない人はいない。男が高貴であればあるほど、自分の中に不名誉があることを知っており、名誉の欠落に悩まされている。生き生きとした男ほど、自分の中に死があることを知っている。
寺山の「もらった命に名誉を与えること。それだけが、男にとって宿命と名づけられる」は、この部分を自己流に書き換えたもののような気がする。
それともサローヤンの他の小説にある言葉なのだろうか。あるいはまったく別の誰かの言葉なのだろうか。
う~む、このあたりが限界だ。追求はここまでにしよう。
■おわりに
一つだけはっきりしているのは、寺山修司が「あらゆる男は、命をもらった死である」というフレーズがとても気に入っていたということだ(★3)。
いつも死を意識していたんだろうな。
■注
★1:小川太郎『寺山修司 その知られざる青春』118-120頁。
★2:清水義和の論文参照。
★3:新潮文庫の『ロック・ワグラム』の訳者・内藤誠は、「解説」で次のようなエピソードを紹介している。
あるパーティで故寺山修司とサローヤンの話をしたことがあった。/劇作家でもあるサローヤンに寺山修司が関心をもつのは当然と思ったけれど、彼のとくに好きな作品が『ロック・ワグラム』で、「男というものは……」というあの語りくちが何ともいいんだねえ、といかにも愛読者らしくいったのが、いまもあざやかに記憶にのこっている。
■参考文献
寺山修司『墓場まで何マイル?』角川春樹事務所、2000
寺山修司『寺山修司著作集1』クインテッセンス出版、2009
小川太郎『寺山修司 その知られざる青春』中公文庫、2013
清水義和「ディズニーの『白雪姫』とダリの『アンダルシアの犬』と寺山修司の『毛皮のマリー』に於ける映像詩」53-54頁と71頁、『愛知学院大学語研紀要』第34巻第1号、2009、35-72頁
清水義和「ヴァン・ゴッホと寺山修司──M. C. エッシャーによって"ひまわり"を『田園に死す』の中に読む──」27頁と51頁、『愛知学院大学教養部紀要』第59巻第1号、2011、23-57頁
William Saroyan: "Rock Wagram", Doubleday, 1951(W・サローヤン『ロック・ワグラム』内藤誠訳、新潮文庫、1990)
ヨジロー「寺山修司の詩『懐かしのわが家』―ぼくは不完全な死体として生まれ」、2024年3月1日
https://note.com/yojiroo/n/n4128e2e76aed
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
