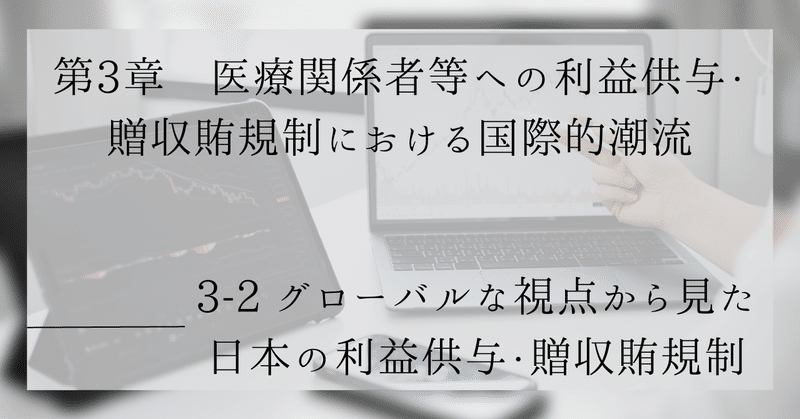
3-2 グローバルな視点から見た日本の利益供与・贈収賄規制
本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「医療関係者等への利益供与・贈収賄規制における国際的潮流」のうち、「2️⃣グローバルな視点から見た日本の利益供与・贈収賄規制」の内容をまとめたものです。
(1)公正競争規約による規制
日本における利益供与規制の基本的な特徴は,その制限の主な法源(根拠規定)が,公正競争規約に求められることである。公正競争規約は,景品表示法第31条の規定により,委任を受けた基準として消費者保護当局(消費者庁)及び競争当局(公正取引委員会)の認定を受けている一方,医薬・保健当局(厚生労働省)や製薬協による運用からは独立している。このような規制構造を有している国は例外であると言ってよい(ただし,一般用医薬品については,ある程度消費者保護当局が関与する例は多い)。
海外では,医薬・保健当局が運用する薬事基本法(日本における薬機法)において,大まかに医療関係者等への利益供与を制限する規定を置きつつ,詳細の規定(場合によっては,その解釈や執行)については,各国の製薬団体に一定程度依存している例が多い(後述するが,米国における規制は日本とは異なった意味で特異であり,必ずしもこれに当てはまらない)。
この違いは,グローバル企業においてマーケティング企画等のコミュニケーションを行う際に十分留意すべき点である。すなわち,海外においては,薬事基本法やIFPMAコードを根拠とした概念と用語(典型的なものにEvent(イベント)やSponsorship(企業による後援)がある)が用いられるのが常であり,その解釈における究極的な指針は,医薬品産業に対する社会からの「信頼」(Trust)が害されるか否かにあると言って良い。
その一方,日本の公正競争規約の場合,当然ながら医薬品産業の社会からの信頼維持も重要とはなるが,究極的には競争法の一部として建付けられている以上,「自由競争の確保」という視点も無視できず,「物品提供の一律禁止」といった制限を置くことには躊躇せざるを得ないことになる。
さらに,公正競争規約の概念や用語は,薬機法や製薬協コードとは独立して発達しているため,国際的調和は必ずしもとれていない。例えば,CMEの支援に関する規定については,IFPMAコードをはじめとして海外では一般的であるが,公正競争規約においては直接対応する規定が存在しない。また,逆に「自社医薬品の講演会の開催」という,日本ではありふれた事象一つをとってみても,その開催要件は,IFPMAコードの「EventsandMeetings(イベントおよび会議)」や「Sponsorship(企業による後援)」とは完全に一致しない。
このような背景をあらかじめ理解しておくだけでも,何が円滑なコミュニケーションを妨げているのかを把握する一助となる。
(2)公取協による運用と執行
公正競争規約の特異性に関連する事項であるが,公正競争規約を運用・執行する公取協も日本独特の組織である。日本においては過去の歴史的経緯もあり,公取協は厚生労働省や製薬協からは独立しており,その紛争予防及び解決のメカニズムも国際的に特異である。
というのも,医薬品の製造販売を行っている企業(製薬企業)は,事実上公取協への加入が強制される一方で,公取協は本部・支部体制をとっており,各社が本部及び各地の支部担当者を設置する必要がある。公取協では,製薬企業各社の公取協担当者を通じて,公正競争規約の改正を含む事務連絡が迅速に行われるほか,研修資料の提供や,公正競争規約上の解釈等に疑問がある場合における事前相談といった広範な「サービス」が提供されている。これにより,水面下における紛争予防ないし解決が図られており,結果としてコンプライアンスに関するコストが削減されているとも理解できる(「公取協モデル」)。
他方,このことは外部に対して透明性がないため,運用が「恣意的である」と捉えられるリスクは否定できない。また,各製薬企業から人員を出し合うことは,いわゆるヘッドカウント*1管理の点から,製薬企業に大きな負担をかける。このような日本の利益供与・贈収賄規制の運用は「コンプライアンス・プログラム」を中核とする海外にとっては,理解が困難であると考えられる。
*1 採用可能数のこと。各部門・部署にどれくらいの人員が配置されているのかを把握するために用いられる。ほとんどの場合,外資系企業はヘッドカウントに基づいて採用活動を行っている。
(3)国際標準としてのコンプライアンス・プログラムの考え方
公取協を通じて水面下で自主的・内部的に紛争予防及び解決を行う日本のメカニズムに対して,海外で主流なのは「コンプライアンス・プログラム」を通じた制度的な抑止と改善を繰り返すメカニズムであると言って良い。
コンプライアンス・プログラムとは,コンプライアンス推進を目的としてPDCAサイクル*2を回す体制や仕組みのことである。代表的なものに1991(平成3)年に示されたアメリカの連邦量刑ガイドラインがあり,次の手続きを履行しているかどうかが量刑に影響を与えるとされている。
*2 Plan(計画),Do(実行),Check(評価),Action(改善)を繰り返すことによって,生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法。
❶ 法令遵守の基準と手続きを規定している。
❷ 階層の上位にあるものが法令遵守を監督している。
❸ 自由裁量権を認める際に適切な注意を行う。
❹ 教育研修などで周知徹底を図る。
❺ モニタリングや監査を行い,報復の危険のない報告システムを構築する。
❻ 賞罰にあたって適切に一貫して行う。
❼ 違法行為は合理的な措置で対応し,再発を防止する。
このようにコンプライアンス・プログラムは,公取協モデルとはかなり異なっている。すなわち,公取協モデルにおいては,製薬企業各社の公取協担当者を通じてコンプライアンスに関する情報を社内に行きわたらせ,疑義事案については公取協と連携することにより紛争を予防している。その意味で,公取協モデルはどちらかというと属人性の高い紛争予防モデルであるともいえる(事実,公取協担当者は長年にわたり同一人物が務めることも実務上は多いと思われる)。
それに対して,欧米(特に米国)におけるコンプライアンス・プログラムの考え方においては,PDCAサイクルの繰り返しによる制度的な抑止と改善が重視されており,その履行の有無が法的責任の軽重に影響する。コンプライアンス・プログラムの履行方法は原則として各企業に委ねられており,基本的に業界団体が未然に水面下(非公開)で紛争解決をすることはない。
被疑事案(紛争)が発生した場合,適正手続(DueProcess)と透明性の確保(Transparency)が重視されるため,苦情(Complaint)については正式なプロセスで受け入れられるとともに,反論の機会が与えられ,被疑事案に対しての正式な見解とそれに基づく処分が公開される。制裁を受けた企業は,社内基準の見直しやモニタリングの強化,教育研修の再徹底等を行い,社内体制プロセスを改善する(この一連のPDCAサイクル過程を繰り返すこととなる)。このように,欧米におけるコンプライアンス・プログラムは,属人性よりも組織性の高い紛争予防モデルであるといえる。
(4)制裁の増大化と透明性重視の動き
コンプライアンス・プログラムの履行にも関わることであるが,海外ではPDCAサイクルの履行に対し,強いインセンティブを与えるとの観点から,結果として制裁は強くなりやすい。また,多くの場合,その制裁に至るまでの審議経過も含めて公開される(これは米国で顕著であるが,欧州各国の製薬協においても,苦情の申立てやそれに対する見解,処分は公開されることが多い)。この点は,可能な限り内部における自主的な解決を目指し,強力や処分を課すことや,その審議・意思決定の過程を公表することを避ける日本の運用とは異なっている。
(5)米国規制のグローバルにおける影響
コンプライアンス・プログラムの考え方も含め,米国における規制の考え方及びその運用は,日本を含めて国際的に大きな影響を与えている。利益供与規制に関しては,公的資金によって補助された保険プログラムの償還金の詐取を防止するという経済的側面が重視されることになり,社会からの信頼維持というIFPMAのエトスに基づく制限根拠と必ずしも一致しない。
また,基本的な発想として,米国は合衆国憲法を究極的な淵源として,「自由」を重視する社会規範・社会構造であることから,利益供与規制も含め「ルールの中では原則として自由にやって良い。ただし,ルールから外れた場合には強い制裁を課す」という紛争予防モデルに傾くことになる。当該モデルにおいては,自主団体による過度な「自主規制」や内部的な苦情処理は避けられる一方で,「違反」に対しては主に当局による強力な制裁が課されることになる。
すなわち,米国の規制は国際的にみると「標準」とは言い難い部分が多くある。しかし,その一方で米国における当局の運用は,米国市場の重要さや,違反と認定された際の制裁の強さなどから,国際的にも極めて大きな影響力を有している。そのため,米国以外の規制を議論するに当たっても,米国の規制の概要を理解しておくことは実務上有益である。
(6)民間贈賄を含めた処罰拡大の動き
米国に端を発していると考えられるが,近年の国際的な動向として,贈賄の概念が拡張しつつある。
「贈賄」とは,一般的(伝統的)には公務員への賄賂の提供であり,非公務員への利益供与は刑法上の犯罪とはみなされていなかった。日本においても,非公務員である医療関係者等への利益供与は公正競争規約によって規制されるが,刑法等の法律では直接的な制限を受けることはない。
しかし,米国の反キックバック法においては「賄賂」という建付けは採っていないものの,民間医療関係者等への利益供与も含めて刑事罰の対象となっている。また,英国,フランス,ドイツ,中国など,多くの国において贈賄の客体が公務員に限定されなくなってきており(「民間贈賄」とも言われる),刑法等による法的罰則の適用可能性が認められる。なお,米国FCPAや英国UKBAなどでは「外国公務員への贈賄」という概念も広まっており,多くの国の法律(日本においては「不正競争防止法」)が,自国民ではない海外の公務員の贈賄についても適用されることとなる。
結果として,医療関係者等への利益供与規制が,公務員や非公務員,あるいは国内,海外を問わず一元化に向かっているとも考えられる。例えばUKBAの場合,一定のコンプライアンス・プログラムを履行した際の免責が非公務員への贈賄や外国公務員への贈賄にも適用される可能性がある点をふまえると,英国法務省によるUKBAガイダンスを遵守することは,利益供与に関するグローバルなコンプライアンスリスクを低減することにつながるともいえる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
