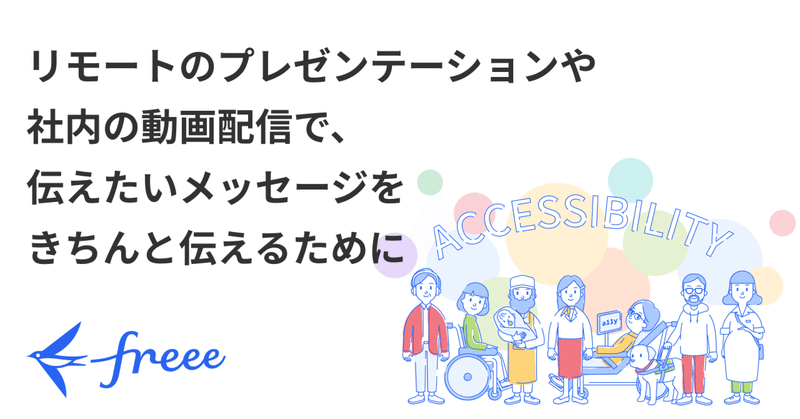
リモートのプレゼンテーションや社内の動画配信で、伝えたいメッセージをきちんと伝えるために
こんにちは。freeeでデザイナーをやっている ymrl です。社内向けに「動画やリモートプレゼンやオンラインミーティングで『伝える』ためのtips」というタイトルで投稿した内容をぜひ「あえ共freee」で投稿しませんか、というお誘いがあって、内容をすこしnote向けに書き直して投稿しています。
freeeでは初期から全社員が参加するミーティングをし続けています。リモート勤務の人が増えてからは、動画配信という形で開催されています。
動画配信にはWorkplaceという、Facebookの社内版のようなプラットフォームを使っています。Workplaceのおかげで、これ以外にも、機能のリリースの瞬間や新機能の社内説明会や社内イベントなども社内に動画配信しています。この記事を投稿する今日4月1日も、新卒社員の入社式イベントが配信される予定です。
そういう動画配信を見ていると、もうちょっと工夫すればもっと伝えたいことがきちんと伝わるのになぁ、と思うことがしばしばあります。動画配信だけでなく、Google MeetやZoomでの会議やプレゼンテーションでも、やはり同じようなところで気をつけるべきところがあります。
音声でも伝えよう
リモート勤務だと、仕事の合間に昼食を作っていたり食器を洗ったり洗濯物を取り込んだり、ちょっとした家事をしていたりします。会議や社内動画配信の時間帯は、無線イヤホンで聞きながらそういうことをするのに良いタイミングです。画面はチラチラ見てますが、常に注視しているとは限りません。
机に向かってミーティングに参加しているときも、画面共有されているドキュメントを手元でも開いて、話を聞きながらじっくり読み込んでいたり、急ぎのチャットの通知が来て返信をしようとしていたりします。
そんなとき、映像を注視していないとわからないような説明をされたり、動画コンテンツにそういう部分があったりすると、急に話についていけなくなったりします。
オンラインミーティングで画面共有しているときは、注目している場所を読み上げながら進行すると、どこの何の話をしているのか、伝わりやすくなります
動画コンテンツでは、「映像に映っているもの」や「次にやること」を口頭で説明しながら進行するようにすると、伝わりやすくなります
現在、freeeの社内には全盲のメンバーもいます。彼らは映像を一切見えてないわけで、特にここは気をつけてほしかったりします。
伝えたいことは文字でも表示しよう
音声とは逆に、映像で伝わらないことも問題だったりします。人と話しているときにうっかり聞き逃してしまったりした経験は誰にでもあるんじゃないでしょうか。あるいはオンラインミーティングだと、突然、音声が途切れてしまったりすることがあります。
そういうときに「すいません今のもう一回喋ってもらっていいですか?」と言えればいいんですが、大人数のミーティングだと言いづらい場合も多いんじゃないかと思います。
そういうことで、やっぱり、視覚的に見える形で、いま喋っていることの概要が映像に載っていると助かります。オシャレなプレゼンテーションだと、ひたすらに画像だけのスライドが連続していて、スライドだけだと何を言っているのかわからないことがあります。
プレゼンテーションのスライドを作るとき、聴く側に伝えたいことは、必ず文字にしてスライドに含めるようにしましょう
動画コンテンツでは、視聴者に馴染みのないものが出てくるときは、字幕などで補いましょう。特に固有名詞を伝える必要がある場合にはそういう工夫をしたほうがいいです
BGMには気をつけよう
大音量で音楽が流れている場所で会話がしにくくなるのは、誰しもが経験があるんじゃないかと思います。イベントや動画配信ではBGMを流したりすることがありますが、この音量が大きいと、その下で喋っている声は相対的に聞きとりづらくなります。
人間の聴覚というのは面白くて、人の声を選択的に選びとるような処理機能があって、ある程度の雑音があってもお互いの話を聞き取る力があるようです。ところがこの能力は人によってはあまり強くなく、私も苦手なのでたまに困っています。
BGMを流す側はどんな曲を流しているかを知っているので、無意識のうちにBGMの音を無視できてしまいます。流す側の人は、そういうバイアスがある前提で、聞く側が困ってしまわないか細心の注意を払わなければなりません。
動画コンテンツなどで音楽を流しながら人が喋る場合、「ちょっとBGMが小さすぎるかもな」と思うような音量までBGMを絞ったほうがいいです
ボーカル入りの楽曲を使う場合は特に注意が必要で、複数人が喋っている中で1人の話を聞き続けるような集中力が必要になります。BGMにはなるべくボーカルのない楽曲を選ぶべきです
Google MeetやZoomなどの音声通話サービスでは、人の声を伝えやすくするための加工がされて、音楽を流すとボーカルがかなり強調された状態になったり、音楽の音量が不安定になったりします。この手のサービスは人の声を伝えるための道具なので、音楽を流すのに使うべきではありません
Zoomではオリジナルサウンドを保持するオプションを使うことで、この問題は解消できるかもしれません
そもそも動画やリモート通話で伝えなければいけないんだっけ?
YouTubeなどの動画の再生時間の長さを見て、「あっ50分もある……ちょっと今見るのはやておこう……」みたいになったりしたこと、ありませんか?私はあります。
動画で説明されほうがわかりやすいというケースや、文章と動画なら動画のほうを選ぶ人というのはいると思います。ですが、全てのケースや人がそうとは限りませんし、動画はその再生時間のあいだずっと注目していなければいけなかったりします。
リモート通話も同じです。リモート通話だと会議室という物理的制約がなくなって、ついついどんどんリモートのミーティングをセットしてしまう傾向があるように思います。しかし、本当にそれは通話で伝えなければいけないことなんでしょうか?もしかしたら、ここまで説明したようなことに気をつけられていなくて、あんまりきちんと伝わってなかったりもするかもしれません。
大事なのは本当に最適な手段は何かを考えることや、いろんなやり方を許容することだと思っています。重要なことは文字情報でも伝えてほしいし、受け取る側に強いインパクトを残したいなら工夫した動画やプレゼンテーションも用意しておくと良いでしょう。
会社の生活のなかでのアクセシビリティ
ここまで書いてきたことは、実はfreee入社時に全員が履修する「アクセシビリティー研修」というプログラムで、サラッと触れているものでもあります。
この研修では、freeeが(特にプロダクトを開発していく文脈で)アクセシビリティというものに取り組んでいることを紹介した上で、「今日からできるアクセシビリティーのためのアクション」を紹介しています。
仕事としてアクセシビリティに取り組んでいますという話をすると、あまり馴染みのない人、特に開発からは離れた部署の人からすると「開発の部署の話」「障害者についての話」つまり「自分には関係のない話」のように思われてしまいがちです。しかし、今回紹介したような内容からは、あらゆる人がふとしたタイミングで困ってしまう可能性があることがわかるはずです。
いろいろな人がいろいろな状況にあることを常に考慮しながら、最適なやり方を模索したり、いろいろなやり方を並行したりすることで、それらを解消することができます。これらも「アクセシビリティに取り組む」の一端であるはずです。そして、会社の中の活動でそれをやっていくことで、働き方の多様性も、メンバーの多様性もより大きくしていけるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
