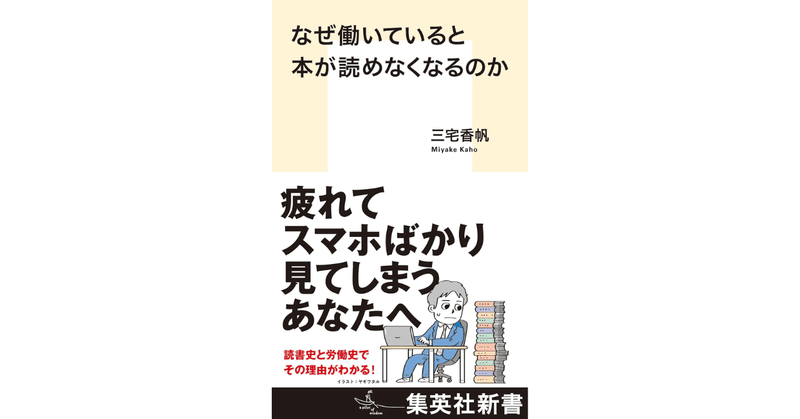
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
書籍情報
「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」……そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。
「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。
自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。
そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?
すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。
なぜ読んだか
X(Twitter)上で話題になっていて、新書で簡単に読めそうだったので読んでみた。
記憶に残ったこと
読書の立ち位置の変遷
徐々に教養を求めるものから、より実用的な情報をもとめる形に読書の使われ方が移っていくなどの変遷が見られるらしい。
というより、そもそも昔は「社会や世の中の動きを把握すること」自体が自分の立身出世(昇進)に寄与すると思われていたが、だんだんより実用ベースですぐに行動可能なレベルの情報に凝縮して不要な文脈を取り除いたような本(自己啓発書)が台頭してきたと論じられている。
また、ちょっと昔は書斎を飾りカッコつけたり、そもそも多くの本を持っているというステータス自体を目的にして、本(円本)が馬鹿売れするなどがあったらしい。(今もそういう要素はあるはあるのであろうが)
疲れているときに本が読めなくなるという原因
著者は疲れているときに本が読めなくなるのは「忙しいときには新たな文脈を取り込む余裕がないからだ」と言っている。
著者は単純に情報として効率よく得たいものと、読書的な情報の種類を分けている。前者は単に情報を得ることが目的で、自分の目的(仕事を効率的に行いたいなど)を最適化するための情報をより効率的に得ることが主眼に置かれている。(これをノイズがないという表現をしている。)
一方で、読書的なものについては、自分が予期しない情報との出会いを求める側面もあり、よりノイズがあると表現されている。
この場合に、後者は新しい文脈を取り入れることであり、これは精神的に余裕がないと難しくなるといっている。
本が読める世界へ
著者は最後の章で、本が読める社会をめざした提言をまとめている。
この中で述べられていることは結構面白かった。
今の社会で、個人を余裕がない状態に追い込んでいるのは、実は会社でも政府でもなく各個人自身であるという主張があるらしい。これは新自由主義においては各々が「もっとできる」「もっと頑張れる」といった考えをもち、かつそれが「称賛されるべきもの」といった社会の共通合意がある。そのため、自分自身で自分を追い込んでしまう構造になってしまっているということだ。
バーンアウト症候群もあるが、そもそもこの「バーンアウト」という言葉選び自体も「やりきった感」であったり「密かな自画自賛」的な感覚を思い浮かばせるようなニュアンスがでてしまっている。
そういう価値観の社会で各々が各々を追い込んでいき、自分自身を搾取するような構造になってしまっているということだ。そして場合にはよっては鬱病を患ってしまうケースもある。
著者はこの状態に問題意識をもち、全身ではなく「半身」で働けるようなことが本気で必要と考えているとの主張。
所感
ちょっと解説を雑にしてしまったところはあるが、最後の新自由主義における課題意識や主張は個人的には納得感はあった。
ちょうど最近いかのサカナクションのボーカルの山口さんのドキュメンタリーを見たばかりだったので余計に刺さるものがあった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
