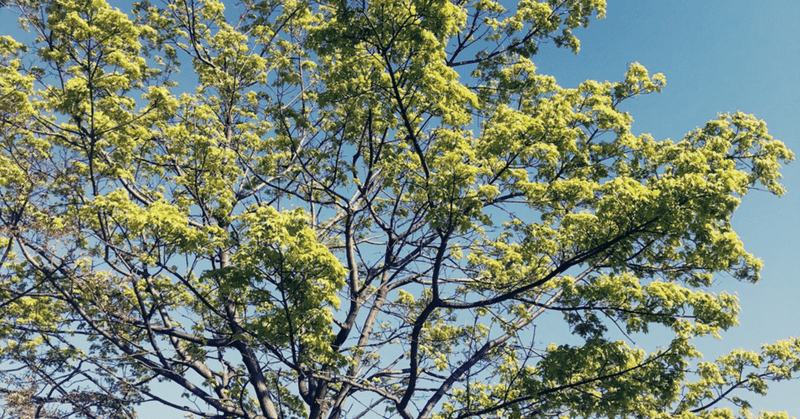
池田清彦さんの『生物にとって時間とは何か』のおもしろさを語る
#キナリ杯 の企画が立ち上がった頃に読んでいた池田清彦さんの『生物にとって時間とは何か』。この読書の時間は私にとって、「生きるってなんだろう?」ということを肩に力を入れず、それでいて知的に考えることのできる、うれしい時間でした。
これもご縁ということで、この場を借りて、この本のぐっときたポイントを、少し書いてみようと思います。
-----
1 オートポイエーシス
池田清彦さんは、生命の仕組みの理解に便利なスキームとして、「オートポイエーシス」の概念を紹介してくださっています。
曰く、生物は「物質の代謝と循環により動的平衡を保ちつつ徐々に変容することに加え、自分に必要なすべての装置を自分自身で作ってい」て、このありようを作り出している「外部と内部を区分けすることにより、自分で自分の同一性を維持し続けるシステム」のことをオートポイエーシスと言うのだと。
池田清彦さんの『初歩から学ぶ生物学』には、ポイエーシスについて、このようにも書かれています。「生物は自分を構成する物質をどんどん変えながら、なおかつ全体としては同じという奇妙な「空間」なのである。しかも、自身と外との関係を不変に定めない暫定的な状態のまま、その都度内と外を確定しつつ自分自身を保っている」。
こうしたオートポイエティックなありようを脳内でイメージした時、私は「生き物って、すっごいぐにゃぐにゃしてるなぁ、自由でおもしろいなぁ」と思ったのです。
生物というのは直線的に歩んでいるわけでも因果論的なルールでものごとを進めているわけでもなく、相当「いい加減」に、その時の自分の五感がいろんな場所から好き勝手に掴んだものを、その時の気分で内側に取り入れたり突き放したりしながら、取り入れたものからはエネルギーを得て、それを次の何かを取り入れるための動力にして生きている。
そんな自由で未来に溢れた生物のありように、個人的にかなり感動したのです。
2 世界を3つにわけてみる
池田清彦さんはその著述を進める上で、カール・ポパー(ウキペディアによれば、1902-1994に生きたイギリスの哲学者)による世界の分類フレームも活用されています。
「カール・ポパーは世界を三つに分けた。世界1、世界2、世界3である」として紹介されているそれらは、次のようなものになります。
「世界1」:物それ自体の世界、単純に言えば自然
「世界2」:意識あるいは主観的経験の世界、解釈
「世界3」:言明それ自体の世界、単純に言えば表現(の総体)
ここから進められる池田さんの著述にももちろん引き込まれたのですが、このフレームを使って世界を考えるということも、私にはとても新鮮でたのしいことでした。
池田さんが書かれている、もしも世界に「表現」がなければ「表現にわずらわされることがないかわりに、どんなことでも自分で最初から考えなければならない。これでは知識は蓄積されず、科学も進歩しない。さらには自分の考えを表現しなければ、自分の考えですらまともに進めることもできない」ということであったり、
「世界2が存在しなければ、世界3は世界1と対応するといった形での意味をもたない。世界3が意味をもつように見えるのは、様々な世界2を結ぶ媒介項として、世界2上の意味が世界3の上に投影されるからである」といったことに思いを馳せているうちに、
世界3には古の時代から今に至るまでの、ありとあらゆる場所の様々な人たちの「表現」が満ち溢れていて、私は自分の見つめる世界(世界1)を、これらのたくさんの「表現」を自由気ままに借りながら思う存分見つめることができるんだ…!となんだかものすごくワクワクしたのです。

3 ぐにゃぐにゃと、いい加減に。
この #キナリ杯 の企画が立ち上がって間もなく、「5月4日、その3日後から特定警戒都道府県以外の住人がやるべき「新しい生活様式」を発表する」という、言葉だけを見ると、「え!発表の3日後に新しい生活…」と、うっかりびっくりしてしまうような話が出ました。
そこから数日間、「3日後に新しい生活」という言葉にインスパイアされるような形で、「さて、私はこれからどう生きて行こうかな」と考えてみたのですが、考えても考えても原点に戻ってくるような感覚があったので、やはり私は、池田清彦さんの『生物にとって時間とは何か』から学んだ生き方を自分の軸にしよう、
つまり、自分の命を守ること(やばいものからはためらうことなく距離を置く)を最優先としながら、あとはその時の自分の五感がいろんな世界から好き勝手に掴んできたものを、その時の気分で取り入れたり突き放したりしながら、取り入れたものからはエネルギーを得て、それを次の何かを取り入れる動力にして、ワクワクしながらキラキラと生きようと思ったのでした。
