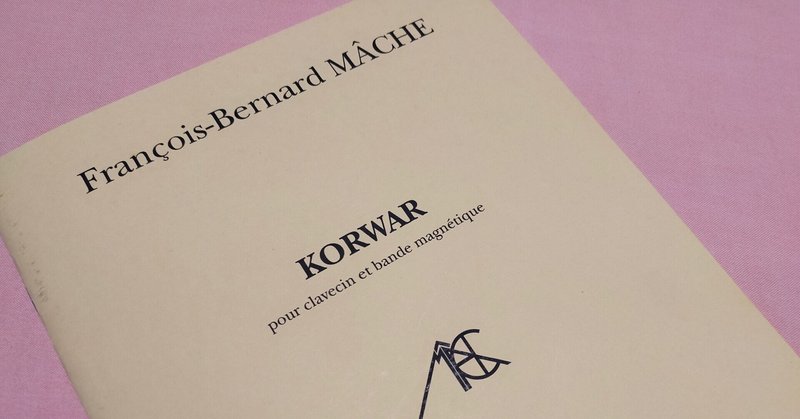
楽譜のお勉強【38】フランソワ=ベルナール・マシュ『コルワール』
フランソワ=ベルナール・マシュ(François-Bernard Mâche, b.1935)はフランスのクレルモン=フェランで3代続く音楽家一家に生まれました。ピエール・シェフェールの研究チームに参加したり、オリヴィエ・メシアンのクラスを受講したりして、作曲家として修行し、キャリアを積み始めます。マシュはヘレニズム文化に明るく、ソルボンヌ大学で古代芸術史の講義を受け持ったりもしたほどで、そのことが彼の作風には大きな影響を与えています。古代ギリシャの音律を分析し、作品に応用したりしました。『ダナエ』、『アンドロメデ』、『カサンドラ』等の作品に彼のヘレニズム文化への造詣を窺うことができます。マシュの音楽のもう一つの柱は自然の音や楽器の音の録音を用いた電子音を伴う器楽作品です。シェフェールの薫陶を受けたことが如実に現れた具体音の使用、そしてメシアンの美学の影響を見ることのできる鳥の声などの使用は、彼の音楽の特徴の一つと言えます。そういった方向の作品に、1970年代に東南アジアの国々を訪れて取材した作品群(『ナルアン』、『マラエ』、『グントゥルー・マドゥー』等)があります。今回はその方向性の作品から、電子音とチェンバロのための『コルワール』(»Korwar« pour clavecin et bande magnétique, 1972)を読んでみたいと思います。

楽譜の冒頭にはまず楽器と機材の舞台セッティングが細かく指示されています。メイン・スピーカーは1つもしくは2つで演奏可能で、舞台上、楽器のやや後方に設置されます。テープは舞台裏に置かれ、客席中央に位置する操作テーブルでコントロールされます。演奏には出版社(デュラン社)からテープのレンタルが必要ですが、今日ではデータ化されているかもしれません。また、チェンバロ・パートで必要なストップ等が書いてあります。ペダルの付いたモダン・チェンバロのために書かれた作品であることは特筆すべきです(多くのペダルを操って更に演奏声部を増やせるペダル・チェンバロとは別物です)。また、チェンバロ・パートは増幅され、電子音パートとの音量バランスを揃えるように指示されています。
『コルワール』とはニューギニア島の部族美術の像で、細かい装飾が施された木彫人物像です。この曲には様々な動物や鳥の声が録音されて登場しますが、冒頭からしばらく再生される話し言葉は何故かジンバブエのコサ語らしく、タイトルの地域からかなり離れます。登場する動物や鳥も、生息地に脈絡がないので、多様なフィールドワークの成果としてのコラージュのような作品と見るべきでしょうか。それとも私が調べたXhosaという言語以外にニューギニア地方に似たような名前の言語があるのでしょうか。とにかく、音楽は民族色溢れる開始です。チェンバロがペダルをアクセントを付けて踏むノイズで加わります。そしてレバーを引かずに無音で鍵盤をバタバタさせるノイズ。更にリズミカルな語りのフレーズに乗せて、16フィート・リュート・ストップのチェンバロがトーン・クラスター(音の塊)で言語パートのアクセント位置をなぞって強調します。少しするとシキチョウの鳴き声に似せた変なノイズがリズミカルに加わります。8フィート・リュート、16フィート・リュート、無音、ペダル・ノイズを組み合わせてチェンバロが言葉とシキチョウのやり取りに色彩を加えて行きます。開始からしばらく通常のチェンバロの音が巧みに隠されています。リュート・ストップも、クラスターだったりするので、変な雑味の強い音のする楽器という感じです。
朗読を受け継ぐのはカエルの鳴き声を模したノイズ。チェンバロは複雑なリズム・パターンを示され、クラスターを用いて抽象的なリズムの即興をするように指示されています。カエルの声のセクションが終わるに向けて次第にテープの音とリズムをシンクロさせていくようにと書かれていて、複雑なアンサンブルが徐々に正体を表す仕掛けになっています。
続いて、ムクドリ、野ブタ、再びシキチョウ、また野ブタ、グアナコ(ラマに似た動物)、イノシシ、シャチとエビ、という具合に電子音ノイズを動物の鳴き声に擬えて明確にリズムや音高を記譜して曲は続きます。特筆すべきは、シキチョウが再び現れた際には、冒頭のギロみたいなノイズと違って、かなり鳥の鳴き声に近づいたメロディーにしてある点です。同じ鳥の名前を記譜してあって、相当音質が違うので少し戸惑ってしまいました。電子音ノイズのパートの音高記譜は非常に煩雑で、微分音やグリッサンド、マルチフォニック的な混ぜ物和音を合わせて相当厳密に書いてあります。チェンバロの役目は概ね強調的色彩の付与で、ノイズ・パートで強調したいフレーズとユニゾンを行います。ノイズ・パートが複雑な箇所では、かなりの頻度で即興に任せています。音域やリズムを与えて電子音パートととの対話をさせているのです。様々な音質のノイズに合わせてチェンバロのストップも様々に変更されます。通常のチェンバロの音もよく聞かれますが、作品全体を通してリュート・ストップの多様が特徴的です。語りとクリアな鳥の鳴き声を除くと、用意された電子音パートはホワイト・ノイズ混じりのような質感を持つノイズが多く、クラスターを多様したチェンバロの音質との親和性が高く、音色のプランはこの作品の聞きどころの一つでしょう。
454小節までランダムな感の強いリズムを特徴として、具体音(に近い音)を用いているのに複雑で抽象的な音像を作り出す音楽でした。しかし454小節から最後のクライマックスを作り出すのですが、ここでは16分音符の刻みが雨音を模したノイズに乗って始まります。右手と左手をランダムに交互に組み合わせたパターンをリズム・パターンとして指示し、秒数指定で少しずつ右手と左手が弾く音を増やしていきます。最初は左がB、右がBbとCと、ごく狭い範囲で鳴っているのが、半音階的(必ずしも半音階ではありません)に少しずつ音域を広げていき、録音されたチェンバロ2台分の同様のパターンが加わって、どんどん増殖する分厚い和音パターンへと成長していきます。ミニマル・ミュージック的な方法で、とてもシンプルに、しかし効果的にクライマックスを形成しています。
チェンバロという楽器はモダン楽器との共演では音量的に難しい面がありますが、とても特徴的な音色を持っており、現代の音楽語法による使用の可能性は高いと感じています。マシュの『コルワール』では、チェンバロの音色と親和性の高い電子音をたくさん用いることで現代的で魅力的な独奏曲を作り上げました。聞いているうちになんだかリュート・ストップのチェンバロのクラスターの音色が電子音にも聞こえてきたりして、面白かったです。電子音を援用しなくても、まだまだ新しいレパートリーを増やしていく可能性を感じる楽器です。
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
