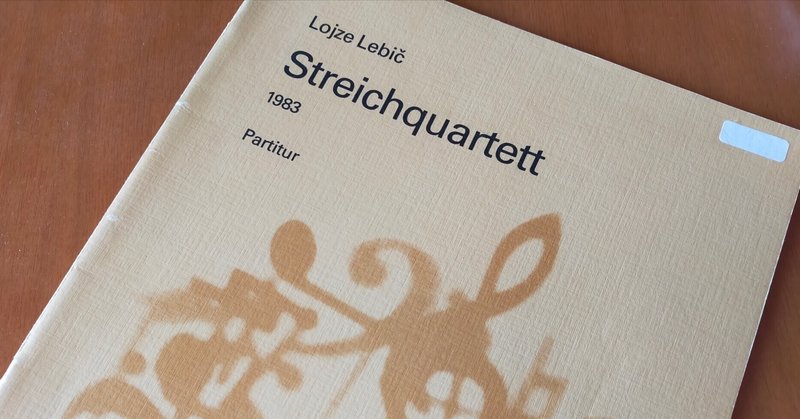
楽譜のお勉強【85】ロイジェ・レビッチ『弦楽四重奏曲』
今回はスロベニアの作曲家、ロイジェ・レビッチ(Lojze Lebič, b.1934)の『弦楽四重奏曲』(»Streichquartett«, 1983)を読んでいきます。レビッチはリュブリャナ大学で考古学を学び、その後リュブリャナ音楽院で作曲をマリヤン・コジーナに学びました。スロベニアを代表する作曲家ですが、日本ではほとんど知られていない作曲家と言って良いでしょう。スロベニアは人口も200万人ほど、面積もとても小さな国で、ヨーロッパの中でも常に色々な国々からの支配を受けてきていて、スロベニア自体が大きな影響力をもっていたことはありません。しかし、近年は合唱のレベルの高さなどから、音楽業界ではよく知られた国になってきています。今回取り上げるレビッチも、教育用の合唱曲などもいくらか作曲してきました。
レビッチの音楽は過去にはペータース社やVEBドイツ出版(現在はブライトコプフ社に吸収されています)といった大手出版社が取り扱っていたのですが、現在は廃盤です。上記2社が取り扱っていたのは、旧東ドイツ時代で、東西のドイツが併合された後、それぞれの会社が扱っていた旧社会主義国家の作曲家たちの作品の多くがカタログから廃されました。現在はレビッチの楽譜を入手するのはなかなか困難になっています。興味深い作品も多くあったのですが、致し方ありません。

レビッチの『弦楽四重奏曲』は、50歳を目前に控えた作曲家の円熟の筆で書かれた力作です。全体は、休止なく演奏される4つの楽章から成っています。第1楽章は、ソナタ形式で書かれているわけではありませんが、冒頭の大きな部分全部を繰り返す仕様になっているため、曲全体を見た時に大きなソナタの主題提示部のような趣があります。冒頭、ヴィオラのA音が伸びていく中、ヴァイオリンとチェロのピツィカートによって、和音が繰り返される序奏が演奏されます。この和音は半音トーンクラスターを開離配分で配置しなおしたような構成ですが、半音クラスターと呼ぶには少しだけ音が欠けています。音の構成は下からBb-F#-G-E-F-A-Ebです。並べ直すとEb-E-F-F#-G-A-Bbになり、G#だけが抜けていることがわかります。このような半音クラスターの一音だけが欠如したような和音はこの後も出現するので、レビッチがこの作品で意識的に素材として用いていたように見えます。
序奏の後は、フーガのストレッタのような主題提示部が聞かれます。基本的には第1ヴァイオリン主導の主題を畳み掛けるように第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロと追いかけていく構成ですが、主題は自由に変奏されており、楽器間の音程操作は厳密でないように見えます。旋律のジェスチャーのみ模倣されています。自由度はさらに増していき、線的な主題が終わった後、リズミカルな主題が現れますが、ここからはリズムも揃えないように自由にずらしながら演奏する指示があります。どんどんとズレは大きくなりますが、提示部の最後の方で、次第にテンポを合わせていくように指示があります。完全に合ったところでチェロが完全5度(F-C)を繰り返し、そこから特殊奏法のポリフォニーになって、提示部全体が繰り返されます。音高のはっきりしない擦音のノイズをさまざまな運弓で立体的に響きにしていきます。具体的な奏法、ノイズの種類はある程度奏者に任されているので、演奏によってさまざまに表情を変える音楽だと思います。繰り返しの後、短いコーダを経て第2楽章へ続きます。
動的だった第1楽章に比べ、第2楽章では小さな音程の中で蠢くニュアンスが大切にされます。一つの音高に対して、3つの楽器が当てられたりします。発音からの残響時間、グリッサンドによるイントネーションの変更などが別々に処理されて、あたかも一つの音を立体的に多方向から観察するような面白さがあります。そういった部分だけを取り出すとシェルシの音楽などを思い出しますが、実際には多声音楽的な層を諦めているわけではなく、楽器間の役割分担が複雑な音楽です。静謐な聴取に埋没すれば、多くの発見がある楽章でしょう。特にさまざまな奏法のピツィカートが多用されて、独特の浮遊感を味わう音楽です。
第3楽章は第2楽章よりもテンポが落ちます。なんとなく第2楽章が緩徐楽章かなと思って聞いていたので、その先にさらに大きな呼吸を持つ音楽が合ったことに少し驚きました。しかし、第2楽章は完全に静の音楽だったのに対し、第3楽章はそうでもありません。ゆったりはしているけれども、方向性がはっきり示され、大きな盛り上がりを見せる音楽です。低音から高音へややリズミカルなコラールが上昇していく様子が2度ほど聞かれますし、到達した超高音からの下行も特徴的です。前半で大きなうねりを作った後は、音域をほとんど動かさない静かな音楽になります。アレグロの第4楽章への予兆でしょうか。トリルで半音のような小さな音程を揺れながら進行するコラールは大変美しいです。
アレグロの第4楽章はロンド楽章のように同じ素材が何度か回帰します。冒頭のイントロは印象的で、音像を結ばないほどにアタックを弱めた運弓で疾走するフーガ的導入です。しかしこの導入は展開されることはありません。トレモロの高音ハーモニクスによる主題が薄いオーケストレーションで提示されます。その後、各楽器が異なる分割基準を持つ、ポリリズムによる音楽へと展開していきます。揃ったりズレたりを繰り返すのがこの楽章の面白さのように思います。何箇所か出てくる要素として、各楽器が異なる重音を繰り返すコラールがありますが、このコラールはリズムが2つのグループでズレるように書かれていて、リズム点が錯綜としていて興味深いです。現代の音楽でよく見かける手法なのですが、とても効果的で好きな技術です。第4楽章は途中で何度かシンクロしない自由なリズムの音楽になります。そのような箇所では基本的にグリッサンドが多用され、コル・レーニョ奏法などと共に激しい表出力を伴った音楽になります。何度かそういったセクションをロンドのように繰り返しながら、再び打点を揃えないコラールが現れ、コーダに突入します。コーダは極めて古典的な格好良い作りで、16分音符で疾走する音形をグリッサンドがなぞります。疾走句2楽器、グリッサンド・ライン2楽器で割り振られています。このうち、疾走句後半に現れる16分音符の疾走句は、第2ヴァイオリンとヴィオラによって奏されますが、16分音符ズレたユニゾンになっています。アンドリーセンなどがよく使う手法で、吟味された音型と共に使えば、とても面白いブレの効果が得られます。レビッチの『弦楽四重奏曲』での用法はBPM=160と超高速で、尚且つその輪郭をグリッサンドのラインがなぞっているのですから、とても充実した効果でした。
レビッチの作曲技術はとても手堅く、音楽を聴いた後の満足感が高いです。『弦楽四重奏曲』は彼の作品の中でも私が好んでいるものです。いつか生演奏を聴く機会がないものかと願っています。
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
