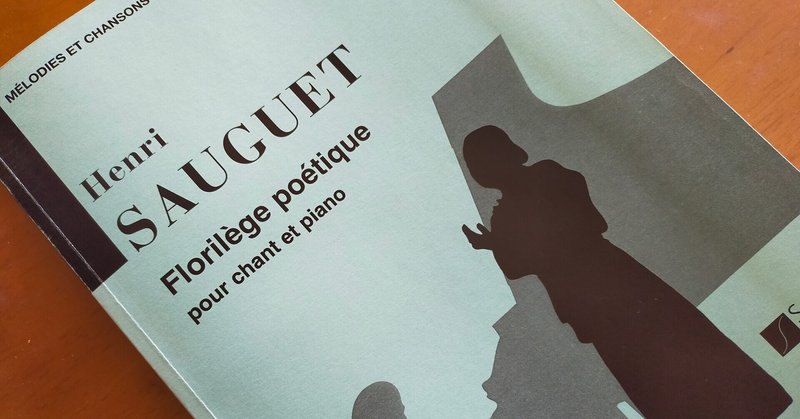
楽譜のお勉強【40】アンリ・ソーゲ『月光のように』『平和の家で』
前回の私のnoteで自作のドイツ語の歌曲について書きました。歌曲をたくさん書いてきたわけではないけれど、私は本当に歌が好きです。別の人生を歩めるとしたら、歌手になりたいとまではいかないまでも、歌の上手な人生だったらどれだけ楽しいかと思っています。日本語の他にドイツ語と英語を話す私にとって、ドイツ語の歌曲を書いたことは自然です。年の瀬もせまって一年を振り返ってみると、今年の作曲仕事は声楽曲の一年でした。春先に自分にとってのチャレンジであったスペイン語の歌曲を書きました。そして先日発表したドイツ語のリートがあり、来年初頭に能の謡のために書いた作品を発表します(こちらはもちろん日本語です)。最もハードルが高かったのはやはり自分で話さないスペイン語なのですが、過去にラテン語やイタリア語の合唱曲を書いたことがあり、発音の原理に近しいものを感じるので、なんとかなりました(と思う)。発表場所がスペイン大使館というのが緊張しましたが、喜んでいただけたので概ね大丈夫だったのでしょう。しかし私が憧れる歌の言語としてもう一つ忘れてはならないのがフランス語です。ルネッサンスの合唱曲では対位法のリズム相互補完を活かした立体的な発音遊びがフランス語ならではのポップさを放って魅力が尽きませんし、フォーレやドビュッシー、ラヴェルらの近代フランス歌曲の恍惚とした和声とフランス語の響きの相乗効果は垂涎の表現です。プーランクの歌曲のように切り込むピアノとのシュールな関係も面白いです。憧れのフランス歌曲から本日はアンリ・ソーゲの3作品について書いてみたいと思います。
アンリ・ソーゲ(Henri Sauguet, 1901-1989)はボルドーに生まれました。シャルル・ケックランに作曲を師事し、フランス6人組(オーリック、デュレ、オネゲル、タイユフェール、ミヨー、プーランク)の音楽に共感しました。ルイ・エミエ、ジャン=マルセル・リゾットと「三人組」を結成し、自作と共に6人組の音楽を紹介する演奏会を開催しました。ソーゲは6人組とほぼ同年代で、しかも長生きです。激動の20世紀の音楽界のさまざまな新しい音楽の技法を試したりもしましたが、基本的には和声的・旋法的な作風で知られます。今日最も知られるソーゲの音楽はバレエ音楽や映画音楽が中心です。しかし他のジャンルにも多くの作品を残しており、特に歌曲はたくさん書かれました。
サラベール社から出ているソーゲの歌曲集は「歌とピアノのための詩集」と題されていて、ソーゲの歌曲に合っています。フランスの出版社の歌曲集では’Chansons’という言葉が用いられているのを目にすることが多いのですが、ここでは’Florilège poétique’となっています。ドラマチックに盛り上げたり、ピアノと協奏したりすることなく、素朴な伴奏に乗せて淡々と歌うスタイルの歌曲がほとんどで、切り詰めた音使いに作曲家の自信を感じます。曲集は238ページもあり、9つの連作歌曲、14の単一歌曲が収められているので、ソーゲの歌曲の歴史を知ることができる良い楽譜です(作曲年はごく初期の1921年から最晩年の1987年)。
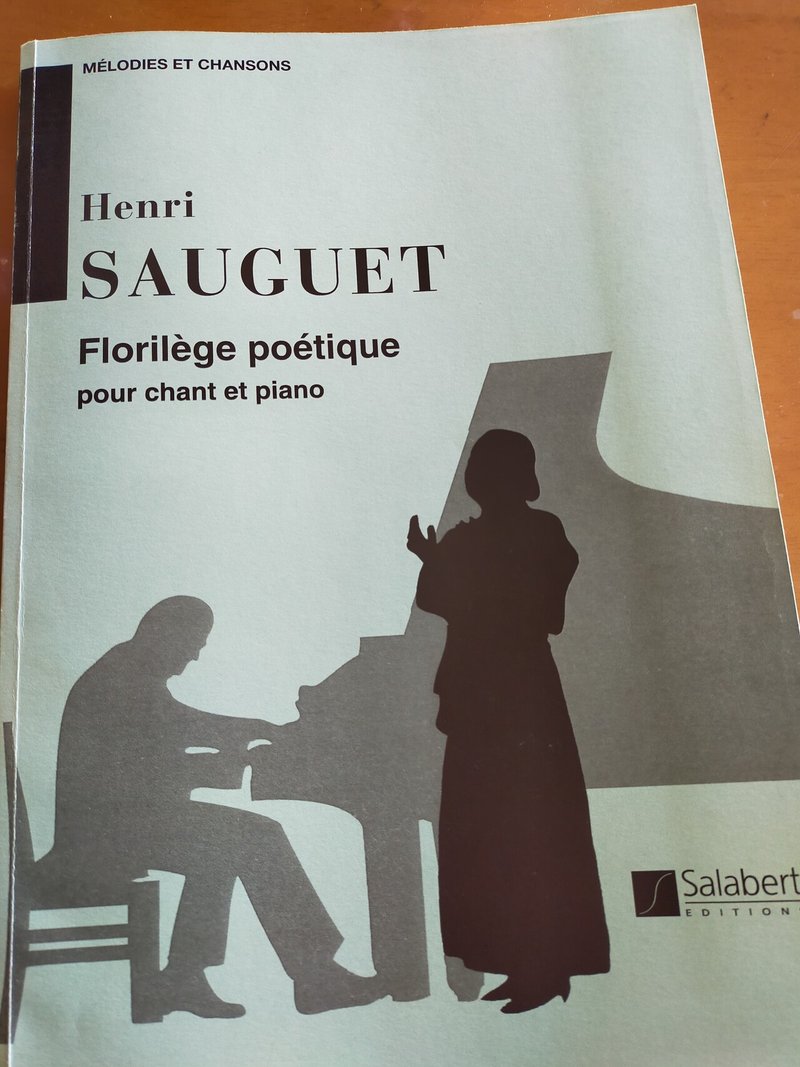
最初にご紹介するのは『月光のように』(«Comme à la lumière de la lune», 1967)です。マルセル・プルーストの詩に作曲されました。冒頭の長3度を半音階下行させたものをずらして組み合わせたピアノの単旋律(1, 2, 4番目の音が上声、3, 5, 6番目の音が下声)が神秘的でとても印象的な始まりです。柔らかく差す月光のような高音の半音階的進行が支配的な和声法で書かれていて、軸となる音があるような、ないような不思議な浮遊感が美しいです。ソーゲのピアノ書法で特に感心するのは音の少なさです。冒頭では4声体でしっかり和音が寄り添っているので、しっかりと歌を和音が支えますが、それ以外の装飾はありません。しかし彼の他の多くの歌曲にも見られることとして、2声和声の充実があります。ギリギリまで削った音数で、複雑な進行の和声を認識させてくれる音選びのセンスこそ、洗練という言葉が似合います。『月光のように』は比較的規模の大きな歌曲で、場面ごとにどんどんテンポも変わっていきます。歌は朗読のように自然に言葉を紡ぎ、そのメリスマ(歌詞一語に対し複数の音を付ける作法)的な部分はありません。実は日本の芸術歌曲もそういう作りになっている曲が多く(テンポの自由な変化と少ないメリスマ)、馴染み深い語り口だとも言える歌でした。5分以上ある歌曲はソーゲの作品の中で特に規模が大きいと言えますが、この朗読調の語り口との親和性は極めて高く、効果的です。
もう一曲、最晩年の『平和の家で』(«Dans la maison de paix», 1987)を聴きます。ラファエル・クルゼル(Raphaël Cluzel)という映画監督のテキストに作曲されました。冒頭からソーゲが得意な2声和声法が決まる前奏です。降りてきて着地する和音で厚く響かせ、彼方から(de loin)鐘の音のような連打が聞こえたら歌が始まります。低音から探るように歌い始める声をピアノは邪魔しないように、和音を響かせているだけです。これがもう一つ、ソーゲの見事な洗練の技です。よほど声量に自信のある歌い手でない限り、低音域、中音域は透過声に乏しいものです。ソーゲのピアノ書法は絶対に歌の邪魔をしません。中音域で歌っているときは大体、静謐な高音と軽めのバス音が書かれています。低音域では先ほどのように和音を響かせているだけであったり、もっと切り詰めた音数で支えていたりします。歌が盛り上がる一瞬だけ、和音を厚く弾いたり、一緒に上行したりしてピアノも同じように盛り上がるのです。しかし慎重に程よく、です。必要な音を必要な分だけ書く洗練の極み。また、こちらの作品でもメリスマは見られません。
上記のリンクでは他に『夕べの祈り』(«Prière dans le soir»)と『実装』(«Imploration»)を聴くことができます。『夕べの祈り』はサラベール社の歌曲集には収められていませんが、『実装』は収録されています。
ソーゲの歌曲のほとんどは朗読風でメリスマのない書法で、洗練されたピアノ伴奏と素朴に歌われるものです。しかし私はここで私が感じるフランス語で歌われる歌曲の魅力に気づきます。フランス語特有のじわっと音節がリエゾンで繋がる発音はとても持続的です。素朴な朗誦であっても、長い持続と広がりを感じる言語のように私には聞こえます。音節をくっきりと区切って話すドイツ語や、ほとんどの子音が母音と結合して母音がはっきり聞こえるイタリア語とは全然違った響きの世界です。私の中で歌曲の気分が高まっている今、改めてドイツ歌曲とは全然違う世界に浸ってみました。フランス語を話さない私にはとても高いハードルですが、いつかはフランス語歌曲も書いてみたいと野心を鍛えました。
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
私のドイツ語の歌曲に関する記事はこちら
スペイン語の歌曲に関する記事はこちら
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
